TRPG(テーブルトークRPG)を遊んでいるとよく耳にする人気シナリオのひとつが、「ブリュンヒルデにさよならを」です。
音楽や人間関係をテーマにしたドラマチックな内容で、プレイヤーごとに違った物語が展開されることで有名です。
最近は、このシナリオをモチーフにした「ひるならHO診断」がSNSで話題に!心理テスト感覚で答えるだけで、自分に合ったハンドアウト(HO)がわかり、「自分はSの奏者だった」「友達はGの奏者だった!」と結果をシェアして盛り上がる人が続出しています。
この記事では、初心者の方にもわかりやすく「ブリュンヒルデにさよならを」の魅力と診断の楽しみ方を紹介します。
はじめに
クトゥルフ神話TRPGとシナリオの魅力
TRPGの世界もSNSで話題になっているのをきっかけに知り、興味を持つようになりました。
ここでは、私が気になったシナリオ「ブリュンヒルデにさよならを」と関連する診断について感じたことをまとめてみます。
クトゥルフ神話TRPG(通称CoC)は、プレイヤーが探索者として未知の恐怖に立ち向かうテーブルトークRPGです。その中でも「ブリュンヒルデにさよならを」は、音楽と人間関係をテーマにした異色の人気シナリオとして知られています。
プレイヤーは「ハンドアウト(HO)」と呼ばれる役割を与えられ、才能ある奏者やそれを支える人々として物語を進めます。
たとえば、HO1では「Sの奏者」として癒しの音を奏で、HO2では「Gの奏者」として羨望や葛藤を抱える立場を担います。
プレイヤーごとに違う解釈が生まれ、同じシナリオでも卓ごとに全く異なる物語が展開される点が大きな魅力です。
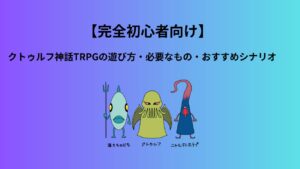
SNSで話題の「ひるならHO診断」
最近、このシナリオを題材にした「ひるならHO診断」というコンテンツがSNSで話題を集めています。
私も友人にすすめられて試してみたのですが、まるで心理テストのように楽しめるのが印象的でした。
Kuizyで公開されているこの診断は、全7問の質問に答えると自分に合ったハンドアウトが表示される仕組みです。
たとえば「好きな音楽家は?」「絶望に直面したときの行動は?」といった問いに答えていくと、HO1 Sの奏者、HO2 Gの奏者、あるいはHO3やHO4などが結果として導かれます。
実際に診断を試した人からは「自分の性格とキャラクターの雰囲気がぴったりだった」「友達と結果を比べて盛り上がった」といった声が多く見られ、TRPG経験者だけでなく未プレイ層にまで注目が広がっています。
私自身も「なるほど、自分はこの役割が似合うんだ!」とちょっとした発見がありました。
1.ひるならHO診断とは?
診断の仕組みと質問内容
「ひるならHO診断」は、7つの質問に答えるだけで自分に合ったハンドアウトがわかる簡単な診断です。
質問は「好きな色は黒か白か?」「モーツァルトとベートーヴェン、どちらが好きか?」といった直感的に答えやすいものから、「絶望に包まれたとき、希望を探すか絶望に身をゆだねるか」といった深いテーマまで幅広く用意されています。
心理テストが好きな人なら、きっと楽しめるはずです。私も「選んだ答えがどうつながるんだろう?」とワクワクしながら進めました。
適性ハンドアウトの表示
診断結果では、「HO1 Sの奏者」や「HO2 Gの奏者」といった具体的なキャラクタータイプが表示されます。
たとえば、「癒し」「純粋さ」に関する選択を多く選んだ人はHO1、「羨望」「葛藤」に近い価値観を持つ人はHO2になる傾向があります。
また、周囲を支える人間味を大事にする回答が多い人はHO3、外部から冷静に物事を見つめる選択をした人はHO4になるといった具合です。
私の場合は「支える者」としてのHO3が出て、なんだか自分の性格を言い当てられたようで妙に納得しました。
プレイヤーからの評価
実際に診断を試した人の感想では「キャラクターと自分の性格が重なって面白い」「友達と一緒にやると、それぞれの適性HOが比較できて盛り上がる」といった声が多く見られます。
TRPG経験者からは「セッション前に診断して役作りの参考にできる」と評価され、未プレイの人からは「結果をきっかけにシナリオに興味を持った」という反応も。
私も友人と同じタイミングで診断をやって「え、あなたはHO2なの?私はHO3だよ!」と盛り上がり、そこからシナリオを読んでみようという流れになりました。
診断そのものが話題作りにもなり、自然と人との距離を縮めてくれるように感じます。
2.代表的なハンドアウトの紹介
HO1 Sの奏者の特徴
HO1は「Sの奏者」と呼ばれる役割で、シナリオの中でも特に象徴的なポジションを担います。
音楽で人を癒す存在として描かれ、DEXが18固定という特殊な特徴を持つことでも知られています。
プレイヤーは多くの場合、17~18歳の高校生のような若々しいキャラクターを設定し、才能に恵まれながらもその重荷や期待とどう向き合うかが物語の焦点になります。
例えば「友人を励ますために演奏する」「観客の心を静める」といったシーンがよく登場し、プレイヤーの演技力次第で卓の雰囲気が大きく変わるのが魅力です。
私も診断結果を見ながら「もし自分がこの役を演じるならどうするかな」と想像して楽しみました。
HO2 Gの奏者との対比
HO2は「Gの奏者」として、HO1と対になる存在です。
Sの奏者が「光」や「癒し」を象徴するなら、Gの奏者は「羨望」や「葛藤」を象徴します。
例えば、Sの奏者に強い憧れを抱く一方で「自分は影に過ぎない」という劣等感に苦しむ描写が多く、物語をよりドラマチックにします。
この対比によって、二人の関係は友情として描かれる場合もあれば、恋愛的な感情や依存関係へ発展する場合もあります。
実際にSNSで「HO2が出た!」と喜んでいた人は「自分の嫉妬深いところにちょっと笑った」とコメントしていて、まさに診断がキャラクター性とリンクしていると感じました。
HO3・HO4の役割
HO3とHO4は、奏者たちを取り巻く存在として重要な役割を持ちます。
HO3は「支える者」として、友人や家族のようにSやGの奏者を現実へと引き戻す立場です。例えば「無理をするなよ」と声をかけたり、「一緒に帰ろう」と寄り添ったりすることで、演奏者の心情に深みを与えます。
一方でHO4は「観察者」として、教師や音楽関係者など外部からの冷静な視点を担います。時には「その選択は正しいのか?」と問いかけ、奏者たちに葛藤を与える存在です。
こうした役割があることで、物語は奏者二人だけの感情劇にとどまらず、周囲を巻き込んだ厚みのあるドラマへと広がっていくのです。私自身はHO3と診断されたので「やっぱり支える側が合ってるのかも」と妙にしっくりきました。
「ハンドアウト(HO)」とは
「ハンドアウト(HO)」とは、テーブルトークRPG(特にクトゥルフ神話TRPGなど)で使われる用語で、プレイヤーキャラクターごとに渡される個別の情報や役割が書かれた資料のことを指します。
ハンドアウトの役割
- キャラクターの立場や背景を伝える
例:「あなたは幼なじみの奏者を支えてきた友人だ」「あなたは天才的な音楽の才能を持つが、その影に嫉妬心を抱えている」など。 - 物語への導入をスムーズにする
参加者全員に共通のシナリオ説明だけではなく、各キャラクターがどう物語に関わっていくかを具体的に示します。 - 秘密や動機を持たせる
他のプレイヤーには知らされない「個別の目的」「秘密の情報」が書かれることもあります。これがシナリオ進行中のドラマや葛藤を生む要素になります。
ハンドアウトの具体例
シナリオ「ブリュンヒルデにさよならを」では、以下のようなハンドアウトが登場します。
- HO1 Sの奏者:音楽で人を癒す存在。純粋で特別な才能を持つ。
- HO2 Gの奏者:Sの奏者と対になる存在。羨望や嫉妬、強い絆を抱く。
- HO3 支える者:奏者を支える友人や家族の立場。
- HO4 観察者:教師や音楽関係者など、外から見守る立場。
ハンドアウトは、プレイヤーが「どんなキャラクターで、どのように物語に関わるか」を理解するための大切な手がかりです。
ゲームをよりドラマチックにする仕掛けであり、プレイヤー同士の関係性やシナリオの深みを生む重要な役割を果たしています。
🎲 初心者向け:ハンドアウトの読み方と活用のコツ
1. まずは「自分の立場」を理解しよう
ハンドアウトには、あなたがどんな役割で物語に関わるのかが書かれています。
- 「親友として支える」
- 「特別な才能を持っている」
- 「秘密を抱えている」
といった立場が明記されているので、まずはそこをしっかり確認しましょう。
👉 ポイントは「主人公になる」必要はないということ。自分に与えられた立場を意識すれば、物語に自然と絡めます。
2. 書かれている情報をそのまま使う
ハンドアウトにある情報は、シナリオを進めるためのヒントでもあります。
- 関係性(誰と親しいか、誰を警戒しているか)
- 動機(なぜこの物語に関わるのか)
- 秘密(他のプレイヤーに言っていいこと・言わないこと)
これらを意識してプレイすると、キャラクターがブレにくくなり、物語が盛り上がります。
3. 無理に「キャラ付け」しなくてOK
初心者がよく悩むのが「キャラ作りをどうすればいいの?」という点。
でも大丈夫!ハンドアウトはすでにキャラの軸を用意してくれているものです。
セリフや行動に迷ったら、ハンドアウトの一文を思い出して「この立場ならどう動くだろう?」と考えてみましょう。
4. 周りとの関係を大事にする
TRPGは「物語を一緒に作るゲーム」です。
ハンドアウトには「Aとは親友」「Bとは対立している」といった人間関係が書かれていることが多いので、それを積極的に演技に取り入れると、セッションがぐっとドラマチックになります。
5. 不安なら素直に「相談」していい
初心者だからこそ「これ言っていいのかな?」「どう演技すれば…?」と悩むもの。
そんなときはGMや他のプレイヤーに「ハンドアウトにこう書いてあるんですが、こういう解釈でいいですか?」と相談してOKです。
むしろ相談することで卓の雰囲気が和やかになり、プレイしやすくなります。
まとめ
ハンドアウトは、初心者にとって「キャラクターのガイドブック」のようなもの。
最初はそのまま読み取って演じるだけで十分楽しめます。
- 自分の立場を理解する
- 書かれている情報を大事にする
- 周囲との関係を意識する
この3つを意識すれば、TRPGのセッションをぐっと楽しめるようになりますよ!
✅ 初心者向けハンドアウト活用チェックリスト
- 自分の立場を理解する
┗ 「親友」「才能ある奏者」「秘密を抱える人」など、書かれている役割をまず確認する。 - 書かれている情報をそのまま活かす
┗ 関係性・動機・秘密はそのままプレイに使ってOK!迷ったら書かれた一文を参考にする。 - 無理にキャラを作り込まない
┗ ハンドアウト自体がキャラの芯を用意してくれているので、自然体で大丈夫。 - 他のキャラクターとの関係を意識する
┗ 「Aとは親友」「Bとは対立」といった人間関係をセリフや行動に反映すると物語が盛り上がる。 - 不安なときは相談する
┗ GM(ゲームマスター)や仲間に「こう動いて大丈夫?」と確認すれば安心してプレイできる。
このチェックリストを手元に置いておけば、TRPG初心者でもハンドアウトを上手に活用できますよ!
3.診断をやってみた人の声
SNSでの診断結果のシェア
SNSでは「#ひるならHO診断」を付けて結果を共有する人が多く見られます。
たとえば「HO2 Gの奏者が出た!確かに嫉妬深いところがあるかも(笑)」とユーモラスに書き込む人や、「HO1だった!音楽で癒す側って言われると少し誇らしい」と喜ぶ投稿も見かけます。
私も友人と一緒に診断結果を共有して「意外と当たってるかも!」と大笑いしました。診断結果をきっかけに、自分の性格や人間関係を振り返る声もあり、遊びながら共感できる点が魅力です。
TRPG経験者の反応
すでにTRPGを遊んでいる経験者からは「セッション前に診断をして、自分のキャラクター像を膨らませるのに役立つ」という実用的な感想もあります。
また「本編のシナリオで演じたHOと診断結果が一致して驚いた」という声や、「普段は選ばないHOが診断で出て、新しいキャラクター像に挑戦するきっかけになった」という意見もありました。
こうしたコメントを読んでいると、診断がプレイの準備や楽しみ方の幅を広げていることがわかります。
初心者や未プレイ層の感想
TRPGをまだ体験していない人からも「心理テスト感覚で楽しめた」「診断のおかげでシナリオに興味を持った」といった反応が多く寄せられています。
特に「友達と一緒に診断をして結果を比べ合った」というエピソードは目立ち、未プレイの人でも気軽に参加できる入り口になっているようです。
私の周りでも「TRPGは難しそう」と思っていた友人が、この診断をきっかけに「やってみたい!」と言い出したことがあり、ファン層の広がりを実感しました。
まとめ
「ひるならHO診断」は、『ブリュンヒルデにさよならを』という人気シナリオを手軽に体験できるきっかけになります。
診断の結果から自分に合ったハンドアウトを知ることで、プレイヤーはキャラクターの立場をより深く理解でき、セッションの雰囲気を一層楽しめます。
SNSでは診断結果を共有することで盛り上がり、TRPG経験者は役作りの参考に、初心者は入り口として興味を持つきっかけにしています。
心理テスト感覚で遊べる手軽さと、キャラクターの奥行きを感じられる奥深さを兼ね備えているのが、この診断の魅力です。
TRPGを知っている人も、まだ触れたことがない人も、一度試してみる価値があるでしょう。私も一視聴者として「遊びながら物語の世界を体験できるって面白い!」と実感しました。

コメント