フジテレビの元会長・日枝久氏が、10時間におよぶインタビューの中で、自らに向けられた「上納文化」「独裁体制」といった批判に初めて公の場で反論しました。
かつて“テレビの王様”とまで言われたフジテレビ。しかし、中居正広さんをめぐる性加害報道をきっかけに、過去の体質や幹部の責任を問う声が強まりました。
今回は、日枝氏の発言内容をわかりやすく整理しながら、「なぜ今、語ったのか?」という疑問や、「私たち視聴者は何を感じるべきか?」を考えてみたいと思います。
テレビ業界の“昭和的体質”に疑問を持っていた方や、フジテレビの行方が気になる方にこそ読んでいただきたい内容です。
はじめに

フジテレビ元代表・日枝久氏、沈黙を破る
2024年に起きた中居正広氏をめぐる性加害報道以降、フジテレビの過去の体質や経営陣の責任があらためて問われる中、その“象徴”とされてきた人物が口を開きました。
フジサンケイグループの前代表・日枝久氏(87)が、ノンフィクション作家・森功氏のインタビューに10時間にわたって応じ、自身に向けられた数々の批判に対して初めて本格的に反論しました。

注目すべきは、「長年沈黙してきた理由」と「あえて今、語る決意に至った背景」です。
彼の証言は、単なる“言い訳”として切り捨てるには重く、またフジテレビという巨大メディアの過去と未来を読み解く重要な材料ともなりえます。
「上納文化」「独裁体制」批判への反論とその波紋
日枝氏のインタビューで最も注目を集めたのが、「フジに上納文化なんてありません」という強い否定の言葉でした。
一部週刊誌やSNSでは、社内に“見た目の良い女性社員を特定幹部が囲う文化”があったなどの報道が相次ぎ、それが日枝体制の象徴だと指摘されてきました。しかし彼は、それらを真っ向から否定し、「上納と懇親はまったく違う」と語ります。
また、もうひとつの批判点――“独裁的な人事権の行使”についても、「相談役として意見は述べたが、最終決定は社長や会長」と釈明。
しかし、第三者委員会の報告書には、日枝氏が相談役に退いた後も人事に強い影響力を及ぼしていたとの指摘があり、その認識のずれも注目を集めました。
このインタビューは、過去のフジテレビを知る関係者や視聴者にとっても、何を信じるべきかを改めて考えさせられる機会となっています。
1.日枝久氏が語る“上納文化”の否定
「冗談じゃない」発言の背景とは?
インタビューの冒頭で、日枝久氏は「冗談じゃない、フジに上納文化なんてありません」と強い言葉で反論しました。
これは、フジテレビの内部に「若い女性社員が上層部に気に入られるために私的な付き合いをしていた」というような報道に対する直接的な否定です。
特に「港会」と呼ばれる幹部との懇親の場が、「上納」の場として語られることについて、「それは全く違う」と語り、誤解と偏見が先行していることに強い不満をあらわにしました。
日枝氏によれば、かつてのテレビ局は社員同士の距離が近く、飲みの席やイベントを通じて関係を築く文化があったとのことです。
それを「上納」と表現されるのは、あまりにも悪意に満ちているという主張です。
彼にとっては、報道の中で一人歩きした“構造的な性加害”という言葉が、フジの過去をまるごと否定するかのように映ったのかもしれません。
港会と“見た目重視”の指摘への見解
「港会」とは、社長だった港浩一氏を中心とした非公式の会合とされ、一部では「見た目の良い女性社員」が選抜されるとの噂がありました。
これについて森功氏が質問を投げかけたところ、日枝氏は「そんな会があったとしても、それを“上納”と結びつけるのは極端すぎる」とやや語気を荒らげたそうです。
実際に、港会に参加していたとされる女性社員の中には、現在もフジテレビで活躍しているプロデューサーや記者が存在し、彼女たちが「上納」されていたという見方は、当人たちのキャリアや努力を否定することにもなります。日枝氏は、そうした見方こそが女性に対する差別的なバイアスであると訴えました。
一方で、番組制作や報道の現場におけるジェンダー格差や“見た目”の影響力がゼロだったわけではないことも事実として残ります。
そのため、日枝氏の反論がどこまで説得力を持つかは、読者や視聴者の受け取り方によるでしょう。
「楽しくなければテレビじゃない」との矛盾は?
「楽しくなければテレビじゃない」──これは、日枝氏が掲げてきたフジテレビの黄金時代のキャッチコピーであり、彼自身のテレビマンとしての信条でもあります。
しかしその「楽しさ」が、結果的にセクハラやパワハラの温床だったのではないかという疑問は、SNS上でも多く見られました。
森氏はインタビューの中で、このスローガンが「放任主義」と「権力構造の曖昧さ」を生み、問題を見逃してきたのではないかと指摘しました。
日枝氏はこれに対し、「楽しさ」は自由な発想やクリエイティブな現場づくりを促すものであり、決して倫理をないがしろにするものではなかったと答えました。
ただし、世間が問うているのは“意図”ではなく“結果”です。どれだけ「上納文化ではなかった」と主張しても、それが組織内で不平等や沈黙を生んでいたなら、再考の余地があると言えるでしょう。
この点で、日枝氏の反論は一面的にすぎると受け取られる可能性もあります。
2.「独裁」と言われた人事への反論
相談役としての立場と責任
日枝氏が特に反論したのは、自身がフジテレビ内で“独裁的な人事を行ってきた”という批判です。
第三者委員会の報告書では、彼が代表を退いた後も、相談役として会長や社長人事に深く関わっていたと指摘されています。
しかし、日枝氏はこれに対し「相談を受けたことは事実だが、決定権はあくまで現職の経営陣にあった」と強調しました。
この発言は、政治の世界に例えると「影の実力者」とも言える存在への弁明に近く、確かに“相談”という言葉がどこまで影響力を持つかは、受け取り方次第です。
たとえば、後任を選ぶ際に「日枝さんがこの人を推している」となれば、それが事実上の決定打になっていた可能性は否定できません。
視聴者や社員の中には「相談役」という肩書に隠された実権に違和感を持つ声もあります。会社組織においては、肩書き以上に“誰が最後に口を挟むか”が重要だからです。
第三者委員会の報告との食い違い
第三者委員会による調査結果では、日枝氏が相談役として「人事や意思決定に影響を及ぼしていた可能性が高い」と指摘されており、これが“影響力を行使していた”と見なされている根拠になっています。
これに対し、日枝氏はインタビューで「意見は述べたが、強制はしていない」と重ねて否定しました。
また、彼は「責任から逃げるつもりはない」と述べており、自身の関与を完全に否定する姿勢ではありませんでした。
しかし「決めたのは現役の経営陣」という前提に立ち続けることで、第三者委員会との見解のズレが際立つかたちとなりました。
報告書と本人の言い分が食い違う点は、読者にとって「どちらを信じるべきか」という判断材料になります。
とくに企業不祥事やコンプライアンス問題においては、こうした食い違いが信頼の回復を遠ざけてしまうこともあります。
遠藤龍之介氏との対立と“驚愕の提案”
インタビューの終盤、日枝氏は、当時フジテレビ副会長だった遠藤龍之介氏との間で起きた衝突についても言及しました。
とりわけ印象的だったのは、遠藤氏が「取締役相談役の退任を求める」場面で、なんと「フジテレビをもう一度統括してくれませんか」と驚くような提案を持ち出したというエピソードです。
これに対して日枝氏は強く拒否したと語り、「すでに退いた人間が再び権力を握るべきではない」と答えたとのことです。
このやり取りは、第三者から見れば「じゃあなぜ相談役として影響力を行使し続けたのか?」という疑問を生む部分でもあり、彼の“反論”が時に自己矛盾を含んでいるようにも感じられます。
また、遠藤氏が局長会で行った「爆弾発言」についても触れ、「自分を追い出すための演出だった」と日枝氏は語りました。
このあたりは、組織内の主導権争いがいかに熾烈だったかをうかがわせます。単なる世代交代ではなく、価値観の断絶や、過去との訣別が社内で急速に進行していたことを示しているようです。
3.沈黙から語りへ――10時間インタビューの意味
フジテレビの「悪玉論」と日枝氏の危機感
2024年以降、世間では「日枝久=フジテレビの暗部を象徴する人物」といった見方が強まり、「上納文化」や「独裁体制」といったキーワードと結びつけて語られることが増えました。
中居正広氏の性加害問題の余波もあり、過去の経営体質に遡って責任を問う声が噴出する中で、日枝氏本人が公の場に姿を見せないことは、批判に拍車をかけていました。
今回、森功氏による10時間に及ぶインタビューに応じたことは、そのような“悪玉論”が一方的に広がることへの強い危機感からだったと見られます。
日枝氏はインタビュー内で「黙っていることが会社にとってマイナスだと感じてきた」とも語っており、フジテレビに残された後輩たちにこれ以上の悪影響を与えたくなかったのかもしれません。
メディア対応の選択と読者の受け止め方
注目すべきなのは、彼が記者会見ではなく、特定の作家とのインタビューという形式を選んだ点です。
世間の一部では「都合の良い質問しか受けない逃げの姿勢だ」と見る声もあります。実際、放送された検証番組や報道特番には一切姿を見せておらず、「なぜ沈黙を破るのが“この形”だったのか」という疑問は少なからず残ります。
一方で、森氏はテレビ局との利害関係がなく、取材対象にも容赦しないことで知られる記者です。その森氏を相手に選んだことで、日枝氏なりの誠実さや覚悟を感じたという意見もあります。
読者の多くは、情報の一部ではなく「全体像」を把握したいと願っており、このロングインタビューはその点で一定の意義があると言えるでしょう。
ただし、全体を通して感じられるのは「反省」と「弁解」の境界線が非常にあいまいだったことです。
真摯に語る姿勢の中に、自らを守ろうとする本能的な言い訳が滲んでいたことで、結果的に世間の心を完全につかむには至らなかったという見方もできます。
視聴者・読者・識者の反応と評価
ネット上では、このインタビューを巡って多くのコメントが飛び交いました。
「なぜ今さら」「口だけの釈明にしか聞こえない」といった否定的な意見の一方で、「言いたいことを言う場がようやく与えられたのでは」「批判ばかりでなく、本人の声も聞くべき」といった中立的あるいは肯定的な意見も見られます。
特に注目されたのは、同志社女子大学の影山貴彦教授のコメントです。影山氏は「今さら語ることで、逆にフジテレビの再建にブレーキをかけかねない」としながらも、「語らずに終えるよりはマシ」と一定の理解を示しました。こうした“評価のゆらぎ”そのものが、今回のインタビューの難しさを象徴しています。
一連の騒動を通して見えてきたのは、時代が変われば求められるリーダー像や説明責任のあり方も変わるという現実です。
日枝氏の発言が真実か否かではなく、それが“今の社会にどう響くのか”という観点が、今後のメディアや企業の透明性にも大きな影響を与えるでしょう。
まとめ
今回の10時間インタビューで明かされた日枝久氏の発言は、「フジテレビの長年の企業文化」や「トップによる権力の使われ方」をめぐる議論に、新たな視点と火種をもたらしました。
日枝氏は“上納文化”や“独裁的な人事”といった批判に真っ向から反論し、「楽しさ」を軸に据えたテレビ作りの理念を改めて強調しましたが、それが現在の世間感覚とズレているという印象も否めません。
記者会見ではなく、作家との対話という形式で語ることを選んだ点には慎重な戦略も感じられますが、SNSや読者コメントを見るかぎり、その意図が十分に理解されたとは言いがたい面もあります。
評価が割れるのは当然としても、少なくとも「語らなければ何も変わらない」という意思表示があったことは確かです。
フジテレビは今、過去の体質と訣別し、新たな姿勢を模索しようとしています。そこに過去の代表がどう関わるのか。
今回のインタビューは、その答えの一端を投げかけるものであり、今後も注視されるべきテーマであることに変わりはないでしょう。
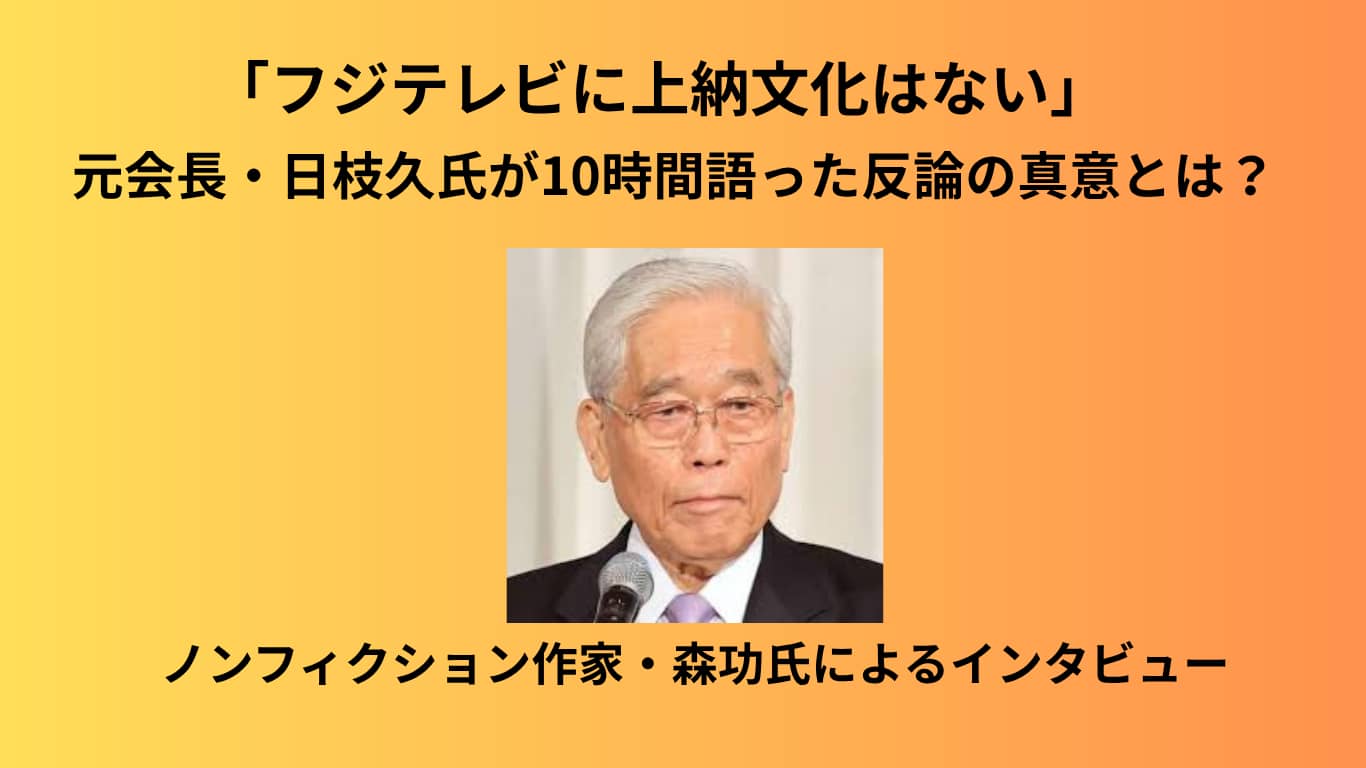
コメント