2025年9月、浜田雅功さんの深夜番組『浜ちゃんが!』が終了し、地上波から“ダウンタウン”名義の番組がすべて姿を消しました。
さらに今年春には、浜田さん自身が体調不良で一時休養していたこともあり、今後は体力的な制約からMC中心のスタイルへシフトするのではないかと注目されています。
一方で、松本人志さんは11月から独自の配信サービス「ダウンタウンチャンネル(仮称)」をスタート予定。
テレビからネット配信へ――お笑い界の象徴であるダウンタウンが描く次のステージは、業界全体の行方を占う試金石になりそうです。
はじめに
ダウンタウン深夜番組の終了が意味するもの
『浜ちゃんが!』が2025年9月24日で終了し、地上波の深夜帯から「ダウンタウン」名義の番組が姿を消しました。
これは単なる番組改編ではなく、長年“深夜=実験場”として機能してきた枠の役割が薄れていることを示します。
例えば、かつては『浜ちゃんと!』『HAMASHO』『ダウンタウンDX』など、深夜由来の自由度が新ネタや若手の露出を押し上げてきましたが、今は同じ役割をYouTube企画や配信限定番組が担う場面が増えています。
後枠に新番組『吉田と粗品と』が入るのは、放送局として“次の担い手”を前に出しながら、制作コストや編成の柔軟性を再設計していく流れの表れです。
視聴者側も、深夜にテレビ前へ“待機”するより、翌朝や通勤中にスマホで見逃し・切り抜きを追う行動が一般化し、深夜枠の存在意義が相対的に変わってきました。
ネット配信への移行が示す時代の転換点
一方で、松本人志が11月から独自の「ダウンタウンチャンネル(仮称)」を立ち上げる動きは、テレビと配信を“置き換え”ではなく“二刀流”で使い分ける時代を象徴します。
サブスクで安定収益を確保しつつ、スマホ・PC・テレビ(アプリ)で同じ番組を視聴でき、コメント機能や生配信で双方向性を作る——こうした仕組みは、深夜の自由度をそのままオンラインへ持ち込む具体策です。
吉本が既存のFANYなどで培った有料配信・イベント連動の導線を活かせば、例えば「生配信→アーカイブ→グッズ→リアルイベント」という循環が設計できます。
課題は“継続供給”と“差別化”。NetflixやAmazon、そして芸人個人のYouTubeと競合するなかで、どんな独自企画を定期的に出せるかが勝負になります。
結果として、テレビは“広く知らせる場”、配信は“濃くつながる場”という役割分担が進み、視聴者は自分の時間に合わせて自由に選ぶ——そんな転換点に私たちは立っています。
1.現状の変化と発表された動き

『浜ちゃんが!』終了で地上波から“ダウンタウン”名義番組が消滅
読売テレビ制作の長寿深夜番組『浜ちゃんが!』が、2025年9月24日で終了しました。これにより「ダウンタウン」の名前を冠した地上波番組は一時的に姿を消すことになります。
ダウンタウンDXやごぶごぶといった人気番組もすでに終了しており、ファンにとっては“時代の節目”を感じさせる出来事となりました。
特に深夜帯の番組は、芸人にとって新しい挑戦の場や若手との共演の場でもあり、それが失われることはテレビ業界全体にも影響を及ぼします。
松本人志が立ち上げる「ダウンタウンチャンネル(仮称)」
一方で、松本人志は独自の配信プラットフォーム「ダウンタウンチャンネル(仮称)」を2025年11月からスタートする予定です。
従来のテレビ番組の枠組みにとらわれず、自由度の高い企画や参加型コンテンツを展開するとされています。
サブスク方式を採用し、スマホやPCだけでなくテレビ画面でも視聴可能。ファンがコメントや投票で番組に参加できる仕組みも検討されているなど、双方向性が大きな魅力となりそうです。
吉本興業の戦略と既存プラットフォーム活用
吉本興業はすでに「FANY」などの自社配信基盤を持ち、オンラインイベントや有料配信での経験を積んできました。
さらに、関連会社を通じて「コンテンツファンド」を設立するなど、プラットフォーム運営を本格的に支える体制を整えつつあります。
テレビの影響力を維持しながら、ネットでの直課金モデルを育てる戦略が進行しており、ダウンタウンチャンネルはその象徴的な試みになるでしょう。
浜田雅功が深夜番組から姿を消すのも、
配信を見据えてとも見えますね。
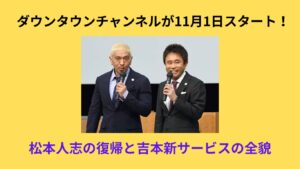
2.これから予想される影響と課題
視聴習慣・収益構造・コンテンツ形態の変化
今後は、若い世代を中心に「テレビで決まった時間に見る」よりも、「自分の好きな時間にスマホで見る」という習慣が加速していくと考えられます。
たとえば、通勤時間に切り抜き動画を見る、家事をしながら倍速で再生するなどが一般的になりつつあります。
さらに、従来の広告収入モデルだけではなく、月額課金やオンラインイベント、有料配信といった直課金の比重が高まるでしょう。
番組構成も柔軟になり、30分や1時間に縛られず、短編企画やシリーズ配信など多様な形で展開される可能性があります。
芸人・タレント活動の自由度と負担増
ネット配信に移行すると、芸人やタレントは表現の幅が広がり、テレビの放送規制に縛られない自由な企画が可能になります。
例えば、普段は放送コードで制限されがちなテーマや、視聴者との双方向的な交流も実現できるようになります。
ただし、その一方で自前でコンテンツを作り続ける責任も生じます。
配信頻度を保ちつつ企画の質を維持しなければ、視聴者はすぐに離れてしまうリスクがあるため、自由と同時に負担が大きくなるのも事実です。
テレビ局・広告業界への影響と折り合い
テレビ局にとっては、深夜番組を縮小・終了させる流れが今後さらに強まるかもしれません。
スポンサーがネットへ移行し、広告収入が分散することで、従来の「ゴールデンタイム頼み」だけでは持続が難しくなります。
一方で、すべての局が同じ道を進むわけではなく、テレビと配信のハイブリッドモデルを模索する動きも出てくるでしょう。
たとえば、テレビで特番を放送してその後ネットで完全版を配信するといった組み合わせです。広告代理店にとっても、テレビとネットをどう連動させるかが新しい課題となります。
3.国内外の類似事例と成功・失敗の示唆
新しい地図・中田敦彦・カジサックの成功例

国内では「新しい地図」が代表的な例です。
地上波を離れた後、独自の会員サイト「NAKAMA」を立ち上げ、限定コンテンツやイベントを展開することで、安定したファン基盤を築きました。

また、中田敦彦はYouTubeとオンラインサロン「PROGRESS」を組み合わせ、無料で広く届けつつ有料で深くつながる二層構造を成功させています。

さらに、カジサック(梶原雄太)は企画力と更新頻度でYouTubeにおける芸人ブランドを確立。テレビ外でも影響力を維持するモデルとなっています。
宮迫博之の再起と課題
一方で、必ずしも順風満帆ではない事例もあります。

宮迫博之はYouTubeを中心に再起を図りましたが、企画の方向性や露出の仕方によっては賛否が激しく分かれ、安定した評価につながらない難しさが浮き彫りになりました。
視聴者の期待と本人の発信スタイルがかみ合わないと、長期的な支持を得にくいという課題を示しています。つまり、ネット進出には「量」だけでなく「質」の継続が不可欠です。
ABEMAなど既存メディア×ITのモデル
国内外の大規模サービスでは、テレビ局とIT企業が連携したケースも注目に値します。
たとえば「ABEMA」はテレビ朝日とサイバーエージェントの協力で誕生し、スポーツ中継やオリジナル番組で成功例を積み上げています。
従来の放送局が培ってきた制作ノウハウと、IT企業の技術力・配信基盤が組み合わさることで、新しい視聴体験が可能になりました。
NetflixやAmazon Primeといった海外勢とも競合しながら、国内の独自ポジションを確立している点は、今後の参考モデルといえるでしょう。
まとめ
浜田雅功さんの『浜ちゃんが!』終了は、単なる番組改編以上の意味を持っています。
地上波から“ダウンタウン”名義の番組が消えたことで、テレビの存在感が少しずつ変化していることを象徴しました。
一方で、松本人志さんが新たに立ち上げる「ダウンタウンチャンネル(仮称)」は、ネット配信がこれからの主戦場になることを示しています。
今回の動きは「テレビの終わり」ではなく、「テレビと配信の共存」という新しい段階への移行です。
若年層はオンデマンドで好きな時間に視聴し、高齢層は引き続きテレビを利用するなど、視聴スタイルの多様化が進むでしょう。
芸人やタレントにとっても、テレビの制約を超えて自由に表現できる場が広がる一方、継続的に質の高いコンテンツを提供する責任が増すことになります。
また、浜田さん自身が今年春に過労で休養したことも記憶に新しく、体力面の制約が無視できない状況にあります。
そのため、今後の地上波出演ではロケや深夜の長時間収録よりも、スタジオでのMC中心の活動にシフトしていくと考えられます。
『プレバト!!』や『ジャンクSPORTS』のように司会として場を回す役割が残りやすく、これが本人にとっても負担を抑えつつ存在感を発揮できる現実的な形になるでしょう。
国内外の事例が示すように、成功するには「安定したファンとのつながり」「独自性ある企画」「柔軟な収益モデル」の3点が欠かせません。
ダウンタウンがこの新しい形を築き上げれば、後に続く芸人たちにとっても大きな道標となるでしょう。今回の変化は、エンタメ業界全体の新しい時代の始まりを告げているのです。
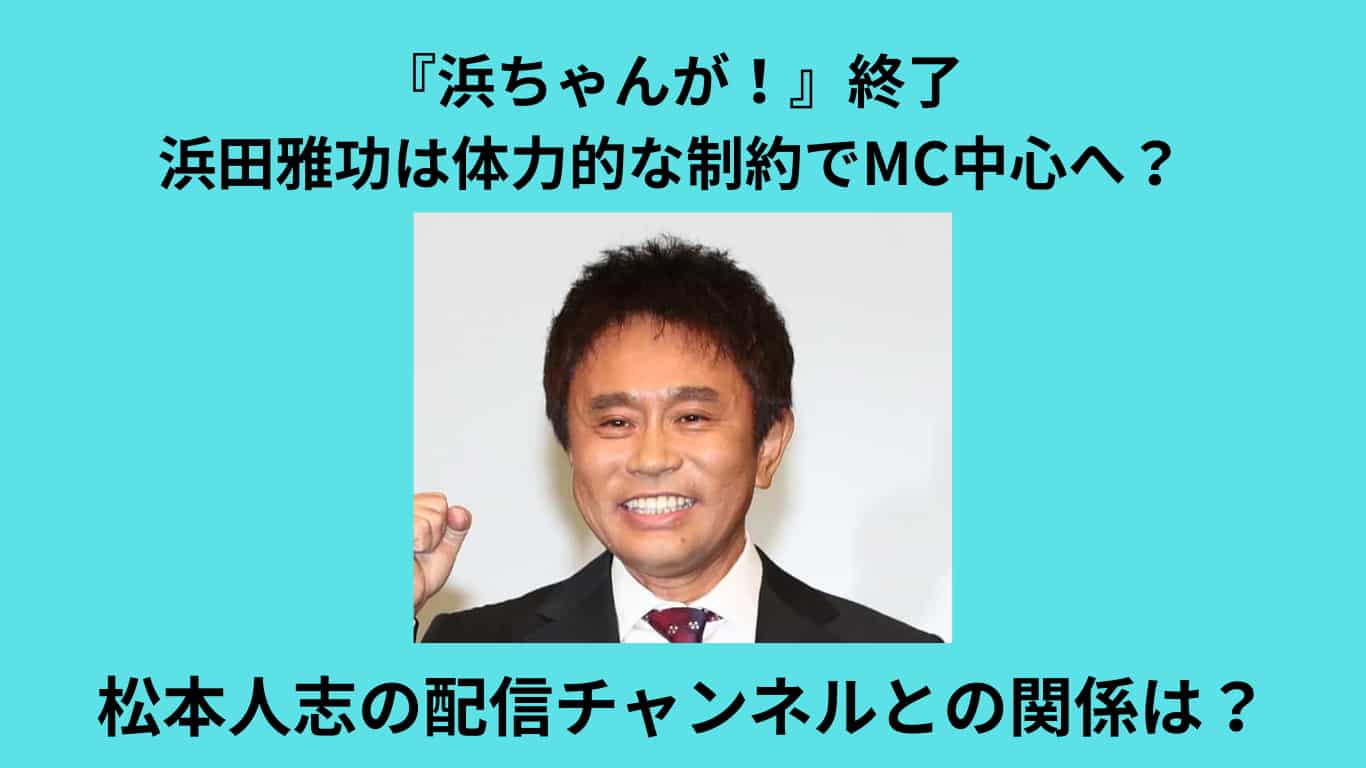
コメント