群馬県のマスコットキャラクター「ぐんまちゃん」のSNS投稿が、まさかの炎上騒動に発展した件です!
投稿されたのは一見ほのぼのとした写真とメッセージだったのですが…参政党を応援しているのでは?といった憶測が飛び交い、あっという間に炎上。
マスコットなのに、なぜ政治色を疑われたのか?
そして、なぜここまで話題になったのか?
今回の騒動を通して、公的キャラクターの“中立性”と“SNS発信の難しさ”について、私自身の視点で掘り下げてみたいと思います。
はじめまして、有権者として日々ニュースを追いかけている一市民です。このブログでは、政治や社会問題に対して、少しでも「私たち」の目線で考えられるきっかけになればと、感じたことや気になったことを綴っています。今回は、群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」のX(旧Twitter)投稿が思わぬ炎上を招いた件について、私なりの視点でまとめてみました。
はじめに
群馬県の「ぐんまちゃん」が投稿で炎上?
群馬県の人気マスコット「ぐんまちゃん」の公式Xアカウントが、ある投稿をきっかけに大きな騒動に発展しました。
投稿には「この県(くに)を愛して何が悪い!!」というメッセージと、スタッフがオレンジ色のジャケットを着て応援ポーズを取る写真が添えられていました。
これが一部の利用者に「参政党を支持しているのでは?」という印象を与え、多くの批判が寄せられる結果となりました。
普段はのんびりと県内の観光地を紹介したり、イベント出演の様子を投稿しているぐんまちゃん公式アカウント。その突然の「愛国的」なトーンと、政党のイメージカラーと重なるビジュアルが、思わぬ波紋を広げたのです。
なぜオレンジのジャケットが問題になったのか
投稿でスタッフが着ていたのは、ぐんまちゃんキャラバン隊の公式ユニフォーム。
しかし、色が参政党のイメージカラー「オレンジ」に酷似していたことから、「政党への支持表明ではないか」と疑われました。しかも、その日の投稿は選挙期間中。政治的なメッセージに敏感になるタイミングでもありました。
マスコットは本来、自治体や観光のPRに使われる中立的な存在。
そこに政治的な意図が少しでも感じられると、「政治利用では?」という批判につながります。今回の件も、誤解を招きやすい画像とメッセージの組み合わせが問題視されたわけです。
意図的だったのか偶然だったのかは運営側の説明を待つしかありませんが、公的なキャラクターが発信するメッセージの重みを、あらためて考えさせられる出来事となりました。
1.問題の投稿と炎上の経緯

「この県(くに)を愛して何が悪い!!」の真意とは
問題となった投稿には、「この県(くに)を愛して何が悪い!!」という強い語調のメッセージが添えられていました。日頃のぐんまちゃん投稿は「おはようございます!今日は〇〇に行くよ〜♪」といった和やかな口調が中心だったため、急に感情のこもった言葉が現れたことに、多くの人が違和感を覚えました。
とくに「県(くに)」というあえてふりがなを振った言葉遣いに、愛国心を強調するような意図を感じたユーザーも少なくありません。
「ぐんまちゃんがそんなメッセージを言うなんて…」「公的キャラを使って政治っぽい主張をしている」といった批判が相次いだのは、そのギャップの大きさゆえです。
オレンジ色の衣装と参政党のイメージカラーの誤解
投稿に添えられていた写真では、スタッフ2名がオレンジ色のジャケットを着用し、片手を挙げてぐんまちゃんと並んでポーズを取っていました。
この「オレンジ色」が、参政党のイメージカラーと一致していたため、「これは参政党を応援する意図では?」と受け取られてしまったのです。
実際には、このジャケットはぐんまちゃんキャラバン隊の公式衣装であり、イベントなどで着用しているものでした。しかし、投稿の文言と色の印象が重なったことで、誤解が一気に広まりました。
写真を拡大すれば「GUNMA」のロゴが確認できますが、SNSのタイムラインでは画像を流し見する人が多く、誤解が先行してしまったのです。
批判の拡散と削除までの5時間
投稿が行われたのは7月13日の午後5時ちょうど。それからわずか数分のうちに、「政治的すぎる」「ぐんまちゃんが参政党を支持してるの?」という反応がX上で広がり始めました。
地元の人だけでなく、全国のユーザーが注目する事態となり、「ぐんまちゃん」がトレンド入りするほどに。
投稿は約5時間後の夜10時過ぎに削除されましたが、その間に多数のスクリーンショットが拡散され、批判の声はおさまる気配を見せませんでした。
「なぜすぐに消さなかったのか」「担当者の暴走ではないか」といった疑問の声も上がり、説明責任を求める声が強まりました。
公的なキャラクターによる投稿は、たとえ意図しないものであっても、多くの人の注目を集め、思わぬ誤解や反発を招く可能性がある——そんな現実を改めて突きつける出来事となったのです。
2.ぐんまちゃん運営側の対応と疑問点

投稿タイミングから見える“予約投稿”の可能性
問題の投稿が行われたのは、午後5時ちょうど。ぐんまちゃん公式アカウントは、通常8時と17時に定時投稿を行っており、今回も同様のスケジュールで投稿されたと考えられます。
これにより、投稿は「予約投稿機能」を使って、あらかじめ準備されたものだった可能性が高いと指摘されています。
つまり、「誰かが勝手に投稿した」というより、あらかじめ用意され、確認の上でスケジュール設定された内容だったと推測されます。もしそうであれば、関係者内での確認プロセスが不十分だったのではないか、という疑問も浮かびます。
過去投稿との比較から見える“異質さ”
これまでのぐんまちゃんの投稿は、子ども向けのやさしい口調で、季節の話題やイベント告知が主な内容でした。
スタッフの姿が登場することもまれで、基本的にはぐんまちゃん単独で写っている写真が多く、背景も明るく穏やかなものばかりです。
ところが今回の投稿は、スタッフが主役のように前面に出ており、ぐんまちゃんが横に添えられる構図。
さらに、これまで使われたことのない強いトーンの言葉が使われ、明らかにこれまでの投稿と雰囲気が異なります。
この「投稿のテイストの急変」が、多くのユーザーに違和感や警戒感を抱かせた一因となったといえるでしょう。
スタッフが個人的に関与した可能性は?
SNS上では、「中の人(運営スタッフ)が個人的に参政党を推していて投稿したのではないか」といった憶測も飛び交いました。
しかし、前述のように投稿は17時ちょうどに行われており、通常業務の中での計画的な投稿だった可能性が高いです。
また、今回登場したスタッフのオレンジジャケットは、2025年2月の山陰放送出演時や、幼稚園訪問時にも使用されていたことが後に確認されています。
つまり、ジャケットそのものは以前から使われていたものの、あえて「今」その写真を選び、あの言葉を添えたという選択が、誤解を招いたのです。
ぐんまちゃん公式情報は後日、「政治的な意図はなかった」と明言していますが、なぜ今回のような投稿が採用され、誰が最終判断をしたのか、具体的な経緯の説明がないままでは、疑念は完全には拭えません。情報発信を担当する立場の慎重さと責任が問われる場面となりました。
3.マスコットの政治的中立性とSNSの課題
公的キャラと政治的発言の線引き
マスコットキャラクター、特にぐんまちゃんのような自治体の「顔」となる存在は、原則として政治的に中立であるべきです。
ぐんまちゃんは観光PRやイベント参加などを通して、地域の魅力を発信する立場にあります。そこに特定の政党や思想が重なると、「自治体が間接的にその政党を支援しているのでは?」という誤解を生みかねません。
たとえば、過去にも他県のご当地キャラクターが特定の市議会候補と写真を撮ったことが問題視された例があります。
キャラクターそのものに意図がなくとも、その「見え方」が問われる時代なのです。特に選挙期間中は、発信側の姿勢がより厳しく見られます。
今回のぐんまちゃん投稿が「政治的な意図はなかった」と説明されても、結果的に受け手に強い政治的メッセージを印象づけてしまった時点で、SNS発信のあり方に再考が求められるのは避けられません。
利用規約や自治体との関係
ぐんまちゃんには、公式の「使用ガイドライン」があり、営利目的や政治目的での使用は禁止されています。
今回のように、公式アカウント自らが“意図せずとも”政治的な印象を与えてしまう投稿を行った場合、それは自らの規約に反している可能性もあります。
また、ぐんまちゃんは県の広報戦略の一環として運用されており、その活動には県庁内の複数部署が関わっています。つまり、単なる「中の人」の判断で動いているわけではなく、自治体全体の信頼にも関わる問題なのです。
今回のような一見小さな投稿が、県民の信頼やイメージ戦略に大きな影響を与えうることを考えると、ガイドラインの運用や内部のチェック体制を見直す必要性があると言えるでしょう。
誤解を招かないSNS運用のあり方
SNSはスピード感が魅力であり、親しみやすい表現が求められる一方で、わずかな言葉や色味、画像の選び方が思わぬ波紋を呼ぶリスクもはらんでいます。
とくに公的キャラクターが政治や宗教、ジェンダーといったセンシティブなテーマに絡む可能性がある場合は、「誤解される余地のある表現を使わない」ことが鉄則です。
今後、ぐんまちゃんに限らず各自治体のSNS運営では、投稿前に第三者チェックを行う、政治的なキーワードやイメージカラーを避けるなど、リスク管理の徹底が求められます。
誰もが自由に意見を言えるSNSだからこそ、公的機関やキャラクターのアカウントには、より慎重なバランス感覚が求められているのです。
まとめ
ぐんまちゃんの公式アカウントによる「この県(くに)を愛して何が悪い!!」という投稿は、その文言とビジュアルの組み合わせによって、思いがけず「特定政党を応援しているのでは」と受け止められ、大きな波紋を呼びました。
発信側にはその意図がなかったとしても、選挙期間中というタイミングやオレンジ色のジャケットの視覚的印象が、誤解を拡大させる要因となってしまったのです。
今回の一件は、SNSという場が持つ影響力と、それに伴う責任の重さを改めて浮き彫りにしました。
特に、公的なキャラクターや自治体が運用するアカウントでは、たとえ一見無害な投稿であっても、「どのように見られるか」を徹底的に想定することが求められます。
ぐんまちゃんのように多くの人に愛されている存在だからこそ、政治や社会的なメッセージとの線引きはより慎重であるべきです。
今回の炎上を他山の石として、全国の自治体やキャラクター運営に携わる人々が、SNSの「伝わり方」をより深く意識した発信を行っていくことが期待されます。
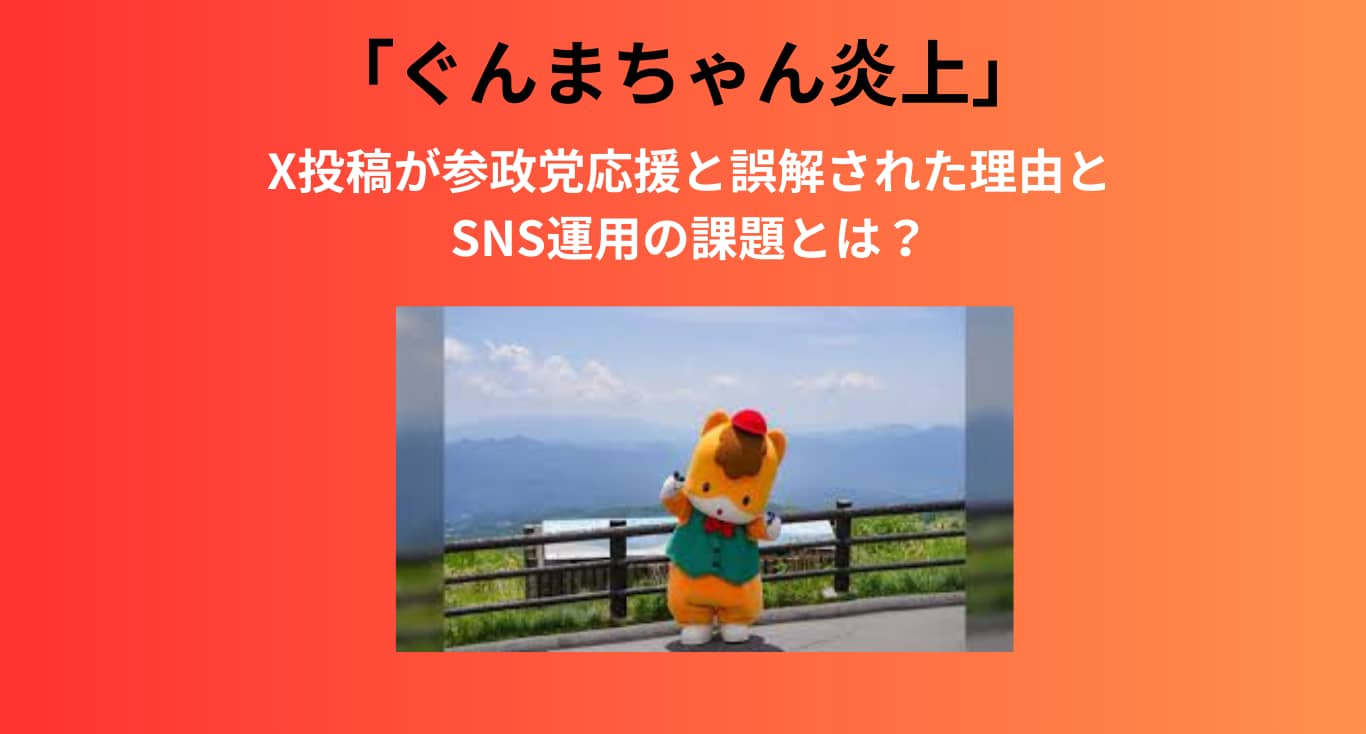
コメント