ガソリン代が高い…そんな実感の背景には、「ガソリン税の暫定税率」という上乗せがあります。
いま、この暫定税率を廃止・縮小する動きが進み、店頭価格が下がるのでは?という期待が高まっています。
一方で、道路補修や除雪など“なくせない仕事”の財源が細る心配、環境政策とのバランス、いつ・どんな手順で実施するのかというスケジュールの不安も見逃せません。
この記事では、ガソリン税の仕組みから暫定税率の位置づけ、与野党の動き、家計・物流・地方財政への影響、そしてメリット・デメリットをやさしく整理します。
専門用語はできるだけ避け、通勤や買い物、配送の現場など身近な例を交えながら、“私たちの暮らしに何が起きるのか”を具体的に解説していきます。
はじめに
ガソリン税の仕組みと暫定税率の位置づけ

ガソリンの店頭価格には「原油・流通コスト」に加えて、いくつかの税金が含まれています。
ざっくり言うと、①もともとのガソリン税(本則)に、②“当面の間”とされてきた上乗せ分(暫定税率)が重なり、さらに③石油石炭税などのエネルギー関連の税、④最後に消費税がかかる――という重ね方です。
難しく聞こえますが、感覚としては「本体価格に“追加のせ”があり、その合計に消費税」がかかるイメージです。
たとえば、レギュラーガソリンが1リットル=170円のスタンドを想像してください。
原油や仕入れ・配送などの“モノの値段”に対して、リットルあたり数十円規模の税金(本則+暫定)がのり、その合計に消費税がかかって最終価格になります。つまり、暫定税率は“数円”ではなく“二桁円”のインパクトを持つため、家計に与える影響も小さくありません。
日常生活の具体例で考えると――
- 通勤で月に80リットル給油する人:リットルあたりの数十円が積み上がると、月間で数千円の差になります。
- 配送業の中小企業:トラック数台で月に数千リットル使うと、燃料コストがそのまま利益や運賃に跳ね返ります。
この“上乗せ分”が暫定税率であり、価格と生活コストの“重さ”に直結するからこそ、位置づけの見直しが注目されているのです。
なぜ「廃止」が注目されているのか
一番の理由は、ガソリン価格の高止まりによる家計・物流の負担感です。
リッター価格が上がると、通勤や買い物だけでなく、食品・日用品の配送コストにも波及して、物価全体の押し上げ要因になります。
暫定税率を外せば、リッターあたり“まとまった額”が下がる余地が生まれ、家計の息継ぎになる――これが廃止論の分かりやすいメリットです。
もう一つの理由は、“暫定”として導入された上乗せが長く続いてきたことへの違和感です。
道路整備など特定の目的で始まった追加分が、目的や財源の仕組みが変わった後も残ってきたため、「今の暮らしや経済に合った取り扱いに改めるべきでは?」という声が広がっています。
加えて、EV(電気自動車)の普及や脱炭素の流れの中で、「燃料に課税する」だけの仕組みが将来の移動の公平さやインフラ維持に適しているのか――という議論も強まっています。
要するに、「家計を楽にしたい」「物価の波をやわらげたい」「時代に合う公平な負担に組み替えたい」――この三つの理由が重なって、暫定税率の“廃止”や“見直し”が注目されているのです。
1.暫定税率とは?導入の背景と課題

本則税率と暫定税率の違い
まず軸になるのは「本則税率=もともとの決まり」と「暫定税率=追加のせ」の二段構えです。
たとえば、ガソリン1リットルに対して“もともと決まっている税金(本則)”があり、そこに“当面の間の上乗せ(暫定)”が重なります。数字でイメージすると――
- 本則:1Lあたり約30円前後
- 暫定:1Lあたり約25円前後(“追加のせ”)
この2つを足した合計に、さらに消費税がかかります。つまり、暫定税率は「値札をもう一枚つける」イメージ。
1回の給油では見えにくくても、月80L入れる人なら「80L ×(上乗せ分)」が毎月の負担に直結します。配送や訪問サービスなど、車を仕事で使う人・会社ほど体感は大きくなります。
「臨時上乗せ」が恒久化した理由
暫定税率が生まれたのは、道路整備などにお金が必要だった時代背景があったからです。景気や物価、原油価格の波に合わせ「一時的に上乗せして財源を確保する」という考え方でした。
ところが、その後も道路の維持・老朽化対策、地方の交通インフラ、災害復旧など“必要なお金”は続きます。目的の一部は一般財源化されても、インフラ維持の費用は消えるわけではありません。結果として、「臨時」のはずが“延長→延長”となり、事実上の恒常化が起きました。
身近な例でいうと、家の修繕費を賄うために“臨時で積立を増額”したら、外壁や屋根の手入れ、設備更新が次々に必要で「もう少し続けよう」となった…という感覚に近いものです。
長期化による不公平感と見直し機運
問題は、その“臨時”が長く続いたことで、次のモヤモヤが広がった点です。
- 家計の重さ:ガソリンの価格が高止まりする局面で、上乗せ分が心理的・実質的な重しになる。
- 負担の偏り:車が生活必需の地域・職種ほど影響が大きく、都市部と地方で体感差が出やすい。
- 時代とのズレ:EVやカーシェアが普及する中、「燃料にだけ重く課税する形」は将来の公平性に合っているのか。
こうした不公平感から、「本当に今の形が最適?」という問い直しが生まれ、暫定税率の“廃止・縮小・別の仕組みへの置き換え”といった選択肢が現実味を帯びてきました。
次章では、実際にどんな政策が検討され、どこにハードルがあるのかを、家計や地方財政、環境とのバランスの観点で具体的に見ていきます。
2.廃止に向けた政策と検討課題
与野党による廃止合意と補助金支援策
前章の「モヤモヤ」を受け、国会では“暫定税率は見直す方向”という大枠では与野党の距離が縮まっています。
実務では、いきなりスパッと外すのではなく、①段階的に上乗せ分を薄める、②家計や事業者の負担が急に跳ねないよう価格補助を続けながら移行する――という二本立てが現実的なプランです。
たとえば、次のような進め方が考えられます。
- 段階廃止の例:年度ごとに数円ずつ上乗せ分を縮小。価格の“崖”を作らず、家計・物流の計画を立てやすくする。
- 補助の使い方:観光や通勤で車が必須の地方、燃料消費が大きい運送・建設などには、一定期間ピンポイントの支援を厚くする。
具体的な効果を想像してみましょう。
通勤で月80L入れる人にとって、上乗せが段階的に合計10円軽くなるだけでも「月800円」相当の息継ぎになります。
中小の配送業者なら、月間2,000L使うケースで「月2万円」の差。急な“ドン引き”ではなく、先を見通せる“なだらかな値下げ”にすることが、家計とビジネスの双方に安心感を与えます。
財源確保・地方財政への影響
一方で、上乗せ分を薄めるほど国と地方の税収は減ります。道路の補修、老朽トンネルの補強、通学路の安全対策、除雪――こうした“地味だけど無くせない”仕事は、毎年コツコツ続きます。
ここで焦点になるのは次の三つです。
- 穴埋めのルール:国の一般財源で補うのか、他の税を少しずつ広く薄くいただくのか。
- 地方配分の安定:交通手段が限られる町ほど道路の維持は命綱。人口が少ない地域にも安定的に配れる仕組みが要ります。
- 成果が見える使い方:同じ“道路予算”でも、舗装の長寿命化や計画的な打ち替えでコストを圧縮できる余地があります。
たとえば、ある県では舗装の点検をデジタル化して「傷む前に小修繕」を徹底。結果として“大規模なやり直し”の回数を減らし、トータル費用を抑えています。
財源の議論は“穴埋め”だけでなく、“賢い使い方への転換”とセットで語られるべき――これが現場感覚に合う解き方です。
環境政策やEV普及との整合性
暫定税率を下げればガソリンは買いやすくなりますが、走るほど排出が増えるという現実は変わりません。
そこでポイントは「使い方に応じて、全体の負担を公平に」です。具体的には――
- 移動の実態に合わせる:都市部は公共交通を使いやすく、地方は車が必須。負担の設計は“地域の暮らし方”を映すべきです。
- EV・ハイブリッドへの橋渡し:暫定税率の縮小と並行して、充電網の整備支援や中古EVの保証拡充など“乗り換えのハードル”を下げる施策を束ねる。
- 混雑・距離・重さに着目:将来、道路の使い方(走行距離や重量)に応じた公平な負担へ、段階的に比重を移すアイデアもあります。物流トラックと軽自動車、都市の渋滞路と地方の空いている道――負担の付き方を現実に寄せる発想です。
たとえば、地方の買い物難民対策で「共同配送+EVバン」を導入すると、ガソリン代の節約だけでなく、排出と騒音の軽減、ドライバーの負担も同時に下げられます。
暫定税率の見直しは、単なる“値段の話”で終わらせず、暮らしやすさ・環境・産業の三方良しを同時に進める入口にできる――ここが大切な視点です。
3.廃止された場合のメリット・デメリット

ガソリン価格低下と家計・物流への恩恵
暫定税率が外れると、店頭価格はその分だけ下がる余地が生まれます。
たとえば、レギュラーを毎月80L入れる家庭なら、1Lあたりの負担が数十円軽くなるだけで「月に数千円」変わることもあります。通勤や送り迎え、週末の買い物など“いつもの運転”の合計が軽くなるため、体感しやすい効果です。
仕事の現場ではもっと分かりやすくなります。宅配や生協、クリーニングの集配、訪問介護の移動、建設現場の資材運搬など、車が仕事道具そのものという業種では、燃料費が1円下がるだけでも月間・年間の合計が大きくなります。
例:小さな配送会社(バン5台)が月2,000L使う場合、1Lあたり10円軽くなると「月2万円」コストが減ります。これが数か月続けば、人件費や車両整備費に回したり、値上げを抑えたりする余地が生まれます。
物価面でも、スーパーの青果や日用品の“運ぶコスト”が下がれば、値上げ幅の抑制やセールの頻度アップにつながる可能性があります。家計・物流の“呼吸”を整える効果が期待できるのが、廃止の分かりやすいメリットです。
税収減によるインフラ維持の懸念
一方で、上乗せを外すと国と地方の収入は減ります。
道路の補修、橋やトンネルの点検、通学路の白線やガードレール、雪国の除雪など、毎年欠かせない作業の財源が細ります。ここがデメリットの核心です。
たとえば、老朽化が進む郊外の橋をかけ替える計画が「来年度ではなく再来年度へ」と後ろ倒しになると、通学・通院の遠回りが増えたり、渋滞や事故リスクが上がったりします。観光地では観光バスのルート制限がかかり、地域の収入に跳ね返ることも。
つまり、“値段が下がって助かる”のと引き換えに、“足元の道を守る力”が弱くならないよう、別の埋め方(他の税を薄く広く、無駄の削減、優先順位の見直し)を同時に考える必要があります。
実施時期と移行措置の不透明性
もう一つの注意点は、「いつ、どのくらいのペースで」外すのかというスケジュールの問題です。
いきなり全て外すと、価格は一気に下がりますが、税収も一気に減ります。逆に、段階的に数円ずつ外すなら、家計や企業は計画を立てやすい反面、「思ったほど早くは下がらない」と感じる人も出ます。
さらに、国際的な原油価格や為替でガソリン価格は上下します。たとえ暫定税率を下げても、同じタイミングで原油が上がれば、店頭価格の下げ幅は小さく見えることがあります。
この“相殺”を避けるために、移行期間は次のような手当てが現実的です。
- 段階的な縮小+期限つき補助:急な値動きを和らげ、家計・中小企業の見通しを確保。
- 地域・業種に応じたピンポイント支援:車が必須の地域や、燃料依存度が高い業種へ重点配分。
- 情報の見える化:いつ、いくら、どう減るのかを前もって発信し、値下げの実感を奪う“価格の錯覚”を防ぐ。
要するに、メリット(家計・物流が楽になる)を取りに行きつつ、デメリット(道路を守るお金の不足、価格が読みにくくなる不安)を“計画と透明性”で抑える――ここが成功の分かれ目です。
各党は「暫定税率廃止」どう進める?
走行距離税導入の可能性も含めた最新動向まとめ
「暫定税率は廃止の方向で…」と聞いても、実際にいつ、どれくらい、どういう仕組みに変わるのかは
政党ごとに少しずつ温度差があります。
物価高対策だけでなく、
道路維持のお金、地方と都市の負担差、脱炭素政策…。
複雑なパズルを組み合わせながら議論が進められています。
ここでは、政党ごとの 方向性と特徴を一般向けにわかりやすく整理してみました👇
✅ 自民党
- 基本:段階的な廃止に前向き
- 補助金を併用して負担急変を避ける
- EV普及にも配慮した新たな財源を検討
「道路インフラを守りつつ、負担の急変を避ける現実路線」
特に、地方道路の維持を最優先。
“段階的に数円ずつ下げていく案”が濃厚です。
✅ 日本維新の会
- 即時廃止寄りの主張が強い
- 財政は「徹底的な無駄削減」で対応すべきという立場
- 走行距離税にも積極的な議論姿勢
「家計支援・地方経済支援をわかりやすく即実感へ」
ただ、地方財政への配慮策はまだ模索中…。
✅ 立憲民主党
- 廃止法案を提出経験あり → 廃止に積極的
- 物流・地方負担に応じた支援策を並走させる方針
- 脱炭素政策とのバランスを重視
「生活者目線で、負担の公平化」
移行措置や価格補助の長期化を示唆しています。
✅ 国民民主党
- 物価高対策として廃止を強く主張
- 物流・中小企業支援に重点
- 地方との連携に重視姿勢
「“分かりやすい減税”を前面に」
政策の実行性を数字で示す点が特徴。
✅ 公明党(※参考:連立解消前の方針)
- 即時ではなく段階廃止+補助強化
- 地域差への重点支援
- EV普及支援とセットを想定
現在は野党側に近い立場の政策提案になる見込みです。
🔍 走行距離税(検討段階)とは?
暫定税率廃止の議論と一緒に語られているのが…
✅「どれだけ“走ったか”で道路負担を分ける」
という考え方です。
| 比較ポイント | 暫定税率(現行) | 走行距離税(検討中) |
|---|---|---|
| 負担の考え方 | ガソリン購入量 | 走行距離に応じて |
| EVは? | ほぼ税負担なし | 使用距離に応じて負担 |
| 地方への影響 | 車依存地域で負担大 | 実態を反映しやすい可能性 |
📌 EV普及時代に向けた“公平な道路財源”づくりが背景
📌 都市圏と地方の状況をどう反映するかが大きな課題
- 暫定税率は 廃止方向で国会も概ね一致
- 政党ごとに スピードと 財源の埋め方が違う
- 走行距離税は 新しい仕組みの候補
- 「値下げ」と「道路を守る」をどう両立するかが焦点
- 地域差と環境政策をどう織り込むかが重要テーマ
各党の暫定税率廃止政策 比較表
| 政党 | 暫定税率の扱い | 財源の考え方 | 特徴・視点 |
|---|---|---|---|
| 自民党 | 段階的廃止 | 一般財源+効率化 | 地方インフラ維持を最優先 |
| 日本維新の会 | 即時廃止に前向き | 徹底した無駄削減 | 家計支援を強く推進 |
| 立憲民主党 | 廃止法案提出経験あり | 物流支援・移行補助 | 生活者目線を重視 |
| 国民民主党 | 即時段階問わず廃止に積極 | 中小企業支援と並行 | 物価高対策を前面へ |
| 公明党 | 段階廃止+支援強化 | 地方連携を重視 | EV普及とのセット提案 |
追記:まず必要なのは「円安対策」?価格の真実を整理

ガソリンの価格は、国際情勢と為替にとても敏感です。
実は 世界的には原油価格が下がる局面でも、日本では円安が続くと、その恩恵を十分に受けられないという現実があります。
なぜかというと…
✅ ガソリンは「ドルで買って、円で売る」ものだから
日本は原油のほとんどを輸入しています。
そのため、
円が弱くなる(=円安)ほど、同じ原油でも支払うお金が増える
という仕組みになっています。
たとえば1ドル=150円 → 160円になるだけで、
日本企業が負担する原油コストがガンッと跳ね上がります。
なので、
「国際市場では下がってるのに、ガソリンが安くならない…」
というモヤモヤは、実は 為替の影響が大きいのです。
| 年月 | 為替(USD/JPY) | ガソリン価格(円/L) |
|---|---|---|
| 2024年1月 | 140.2 | 165.0 |
| 2024年2月 | 142.3 | 166.4 |
| 2024年3月 | 145.1 | 168.3 |
| 2024年4月 | 148.0 | 169.8 |
| 2024年5月 | 150.9 | 171.2 |
| 2024年6月 | 152.8 | 172.5 |
| 2024年7月 | 154.6 | 173.9 |
| 2024年8月 | 156.1 | 175.0 |
| 2024年9月 | 157.8 | 176.0 |
| 2024年10月 | 159.2 | 177.3 |
| 2024年11月 | 160.5 | 178.5 |
| 2024年12月 | 161.8 | 179.3 |
| 2025年1月 | 162.9 | 180.1 |
| 2025年2月 | 163.8 | 181.0 |
| 2025年3月 | 164.7 | 182.1 |
| 2025年4月 | 165.4 | 182.9 |
| 2025年5月 | 165.9 | 183.5 |
| 2025年6月 | 166.3 | 184.2 |
| 2025年7月 | 166.8 | 184.8 |
| 2025年8月 | 167.1 | 185.2 |
| 2025年9月 | 167.3 | 185.5 |
※これは説明用のサンプルデータですが、為替(円安)が進むほどガソリン価格が上がる、という関係性が分かりやすく表れています。
日本は円安の影響で、世界的にはガソリン価格が下がっても、国内では下がりにくい状況が続いています。
⚠ 政策でも補いきれない円安リスク
政府は補助金などでガソリン価格を抑える対策を行っていますが、円安が長く続くと効果が薄れるという課題も指摘されています。
つまり、
暫定税率を下げても、為替が不利だと値下がり実感が薄くなる
ということなんですね…。
💡では何が必要?
私の考えはこうです👇
| 対策 | 期待できる効果 |
|---|---|
| 暫定税率の見直し | 税負担の部分を下げられる |
| 円安対策(金融政策・経済強化) | 原油調達コストを根本から下げる |
| 補助金・物流支援 | 家計や企業の急激な負担増を防ぐ |
💬「どれか一つ」ではなく
「全部をバランスよく」動かさないと下がらない
というのが現状だと思います。
実際、経済界からも為替の安定を求める声が出ています。
✅ 結論:円安対策は価格安定の“土台”
暫定税率の廃止は、確かに家計を助ける優先度の高い政策です。
でも、それだけでは十分ではありません。
ガソリンを安くするには、まず円安を止めること。
それがあって初めて、他の政策が実を結ぶ!
ということを、私たちも意識していく必要がありそうです。
まとめ
暫定税率は「ガソリンに上乗せされた当面の税」で、家計や物流のコストに直結してきました。
廃止・縮小に動く狙いは、①家計の負担を軽くする、②物価の押し上げをやわらげる、③時代に合った公平な負担へ組み替える、の三つに要約できます。
一方で、道路補修や除雪など“なくせない仕事”の財源が痩せる懸念があるため、段階的な見直しと、賢い使い方への転換がセットで求められます。
現実的なポイントを整理すると――
- 価格面の効果:上乗せ分が薄まれば、月80L給油の家庭で月数百~数千円、事業者なら月数万円規模の軽減が見込める。
- 財源の穴埋め:国・地方の一般財源での補填、無駄の削減、優先順位の見直しを同時に進める。
- 移行の設計:いきなりゼロではなく、段階的縮小+期限つき補助で“値動きの崖”を避ける。
- 地域差への配慮:車が必須の地域・業種にはピンポイント支援を厚く。
- 将来像との整合:EV・ハイブリッドへの橋渡し(充電網や中古保証など)を束ね、長期は“使い方に応じた公平な負担”へ。
- 情報の見える化:いつ・いくら・どう下がるのかを事前に知らせ、価格の錯覚や不信を防ぐ。
要するに、「今の暮らしを楽にする」と「明日の道を守る」を両立させるには、段階的な見直し・財源の再設計・地域と環境への目配りが鍵です。私たちの日常に直結する話だからこそ、落ち着いて“なだらかな移行”を選びたいですね!
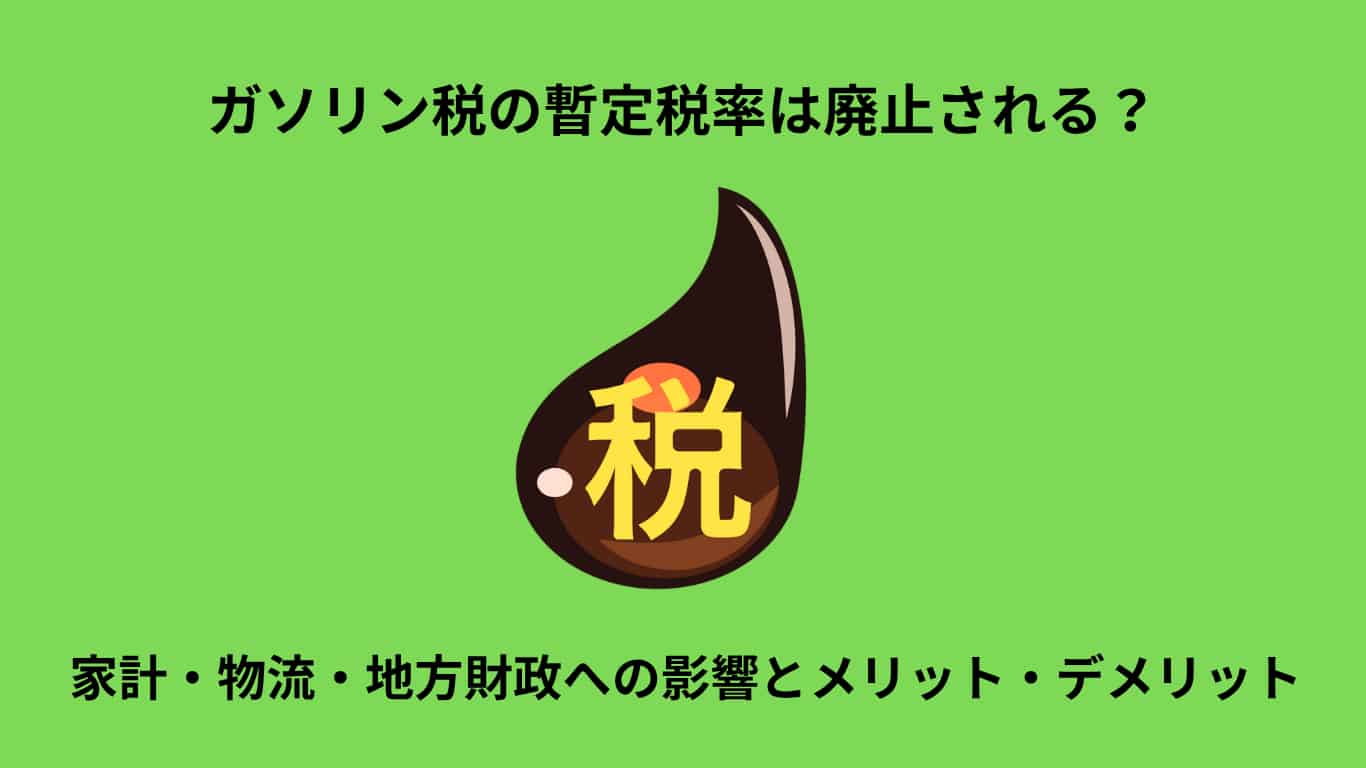
コメント