「外国人が増えると日本人の給料が上がらない」──そんな言葉を聞いたことはありませんか?
参院選でも注目されたこのテーマは、SNSや政治家の発言を通じて広く議論されています。中には「外国人労働者は日本人の7割の賃金で働く」「安い労働力が賃金を押し下げる」といった主張も見られますが、実際のところはどうなのでしょうか?
この記事では、厚生労働省の統計データや識者のコメントをもとに、「外国人労働者の増加が日本人の賃金に与える影響」についてわかりやすく解説します。誤解や先入観にとらわれず、データと事実に基づいて一緒に考えていきましょう。
はじめに
外国人労働者の増加と賃金低下の因果関係とは?
最近の選挙やSNSで、「外国人労働者が増えると日本人の賃金が上がらない」といった主張が目立つようになっています。実際、ある政党の代表者は「外国人は日本人の7割の給料で働いている。そんな安い労働力が入ってくれば、日本人の給料は上がらない」と述べています。これだけを聞くと、「なるほど」と思ってしまいがちですが、本当にそんな単純な話なのでしょうか?
実際には、賃金の変動にはさまざまな要因が関わっています。たとえば、会社の規模、働いている人の年齢や経験年数、業界全体の景気動向などです。外国人が増えたことだけで、日本人の給料が必ずしも下がるとは限らないのです。
選挙で注目される「外国人政策」の論点整理
2024年の参院選では、「外国人政策」が大きな争点のひとつとなっています。「安い労働力としての外国人受け入れ」が是か非か。中には「外国人が増えることで、日本人の雇用や賃金が脅かされる」という不安を煽るような意見も見受けられます。
けれども、こうした主張はデータに基づいているのでしょうか?厚生労働省の統計や専門家の意見を見てみると、必ずしもそうとは言い切れないことがわかってきます。この記事では、「外国人労働者が日本人の賃金に与える影響」について、できるだけやさしく、事実に基づいて整理していきます。
1.外国人労働者の平均給与は本当に安いのか
厚労省統計が示す外国人の月給「約24万円」
まず注目したいのは、厚生労働省が公表している「賃金構造基本統計調査」(2024年)です。この調査によると、日本国内で働く外国人労働者の平均月給は約24万円。これは、同じ調査で示された日本人一般労働者の平均月給約33万円と比べて、約7割程度の水準です。
この数字だけを見ると、「やっぱり安い賃金で働かされている」と感じるかもしれません。しかし、この差にはさまざまな背景があることを忘れてはいけません。単に「外国人だから安い」と決めつけるのではなく、その理由を丁寧に見ていく必要があります。
日本人の平均賃金との比較とその背景
日本人の平均月給が33万円とされている一方で、外国人は約24万円。確かに差はありますが、実は日本人の賃金も長期的には少しずつ上がっています。たとえば2014年時点では30万円ほどだった平均賃金が、10年で3万円ほど上昇しているのです。
それに対して、「外国人が増えたから日本人の賃金が上がらない」という主張は、統計の流れとは矛盾しています。つまり、外国人労働者が増えている一方で、日本人の給料も上がっているのです。
この点から見ても、外国人労働者の存在が日本人の賃金にブレーキをかけている、というシンプルな見方には無理があります。
勤続年数・企業規模・年齢による要因とは
賃金の違いには、年齢や勤続年数、企業の規模など、個別の事情が大きく関わっています。外国人労働者は、日本に来て間もない若い世代が多く、勤続年数も短めです。さらに、大企業ではなく中小企業や現場仕事に従事していることが多いため、どうしても平均賃金が低くなりがちです。
これは、たとえば新卒で入社した20代前半の日本人と、40代で長く勤めた社員とで給料が違うのと同じ理屈です。外国人だからという理由ではなく、働いている環境や条件の違いがそのまま数字に現れているだけとも言えます。
つまり、「外国人の給料が安い=日本人の給料が下がる」という短絡的な構図は、統計や現実の就労状況を見れば、成立しないことが分かります。
2.「外国人が増えると賃金が下がる」は本当か?
百田尚樹氏・神谷宗幣氏の主張と根拠
「外国人が増えると日本人の賃金が上がらない」と主張する代表的な政治家が、日本保守党の百田尚樹氏と参政党の神谷宗幣氏です。
百田氏は「外国人労働者の給与は日本人の約7割」とし、「安い労働力が増えれば日本人の給料が上がらないのは当然」と述べました。神谷氏も「人手が不足していれば賃金は上がるが、供給が増えれば下がる」とし、外国人が“安く働く存在”として日本人の賃金に影響を与えているとの見方を示しています。
たしかに市場の需給関係からすれば、労働力の供給が増えれば、単純に価格=賃金が下がる、という理屈にはなります。ただし、これはあくまで理論上の話であり、実際の労働市場はもっと複雑です。
実務的には、外国人と日本人は同じ職場であっても異なる職種や雇用形態で働いていることも多く、一律に「外国人が増えれば日本人の給料が減る」と断言するのは早計です。
是川夕氏の見解:直接的な因果関係は証明されていない
国立社会保障・人口問題研究所の是川夕氏は、「外国人労働者の増加が日本人の賃金に直接影響を与えているという証拠はない」と指摘しています。むしろ、外国人の賃金が低いのは、年齢が若く、勤続年数が短く、小規模な企業で働くケースが多いためであり、「外国人だから安い」というのは誤解であるという立場です。
また、同じ現場で働く外国人と日本人の間に、大きな賃金格差があるわけではないという点も重要です。つまり、「見かけ上の平均賃金の差」はあっても、同じ仕事内容での支払いに明確な差があるとは言えないのです。
こうした視点は、平均値だけで判断するのではなく、背景や構造を理解することの大切さを教えてくれます。
労働市場の需給構造と少子高齢化の現実
実は、日本の労働市場は「人が余っている」どころか、「人手が足りない」状態が続いています。少子高齢化により、働き手である生産年齢人口(15〜64歳)は今後も減り続ける見込みです。
内閣府の「高齢社会白書」によると、2024年時点で約7373万人だった生産年齢人口は、2050年には約5540万人にまで減少するという予測もあります。つまり、年に数十万人単位で働き手が減っていく状況が続くのです。
このような中で、たとえ年間30万人の外国人を受け入れたとしても、慢性的な人手不足を完全に補えるわけではありません。むしろ、外国人労働者の存在があってこそ、医療や介護、建設、外食など、人材が集まりにくい現場がまわっているという側面もあります。
現実の労働市場では、「外国人労働者が日本人の給料を奪っている」というよりも、「外国人がいなければ回らない現場がある」というのが実態なのです。
3.賃金を決める要因は何か?
友原章典教授の指摘:賃金は複合的な構造の中で決まる
外国人労働者の受け入れが賃金に与える影響について、青山学院大学の友原章典教授は「外国人はあくまで一つの要因にすぎない」と語っています。つまり、賃金はもっと多くの要素が重なり合って決まるということです。
たとえば、ある企業が賃金を上げるかどうかは、売上の見通し、経営陣の方針、同業他社との競争関係などにも大きく左右されます。労働者の供給量が多少増えたからといって、すぐに給料が下がるとは限りません。
また、外国人労働者が多く働く職場でも、日本人と同じ条件で働いているケースは多く、賃金決定の仕組み自体が外国人と日本人で分かれているわけではないのです。
外国人労働者は「一因」にすぎない
世の中の賃金が変動する要因として、外国人労働者の増加が取り上げられることはありますが、それが決定的な要因になることは稀です。実際、企業が賃上げを見送る理由としてよく挙げられるのは「利益が伸びていない」「人件費の余裕がない」といった内部事情です。
たとえば、地方のスーパーが人手不足で時給を上げたいと考えても、経営が苦しければ賃上げには踏み切れません。このような場面で外国人労働者を雇っても、もともと上げられなかった賃金が「さらに下がる」という因果関係は成立しにくいのです。
つまり、外国人の増加と日本人の賃金の間には、直接的なリンクではなく、複数の変数が絡んでいるということです。
海外経済・企業の内部留保・業界構造との関係
さらに視野を広げると、日本の賃金がなかなか上がらない背景には、海外経済の動向や企業の内部留保の増加も関係しています。
たとえば、円安で原材料費が高騰しても価格転嫁できない企業は、コストを人件費で調整しようとします。また、日本の企業は利益が出ても内部に資金をため込み、賃金に反映させにくい傾向があるとも言われています。
こうした構造的な問題に目を向けず、「外国人が増えると給料が下がる」という単純な見方をするのは、本質を見誤ることになります。
労働市場を正しく理解するためには、「誰が働くか」だけでなく、「どう働き、どんな仕組みの中で賃金が決まっているのか」を見つめることが重要です。
まとめ
「外国人が増えると日本人の賃金が上がらない」という主張は、一見すると納得感がありますが、実際には多くの前提や背景を無視した単純化された議論だということがわかってきました。
厚生労働省の統計では、外国人労働者の給与は日本人の約7割とされていますが、その理由は年齢、勤続年数、企業規模といった条件の違いによるものが大半です。また、近年のデータでは、日本人の平均賃金も少しずつ上昇しており、「外国人がいるせいで日本人の賃金が上がらない」とは言い切れません。
さらに、専門家の見解では、賃金はさまざまな要因が複雑に絡み合って決まるものであり、外国人労働者の増加はその中の一要素に過ぎないとされています。企業の経営方針や業界の構造、海外経済の動向など、もっと大きな力が賃金に影響を与えているのが実態です。
人手不足が深刻化する中で、外国人労働者の存在はむしろ日本の産業を支える大切な力になっている現場も多くあります。だからこそ、誰かを悪者にするのではなく、現実に即したデータと事実に基づいて、私たちは冷静に考える必要があります。
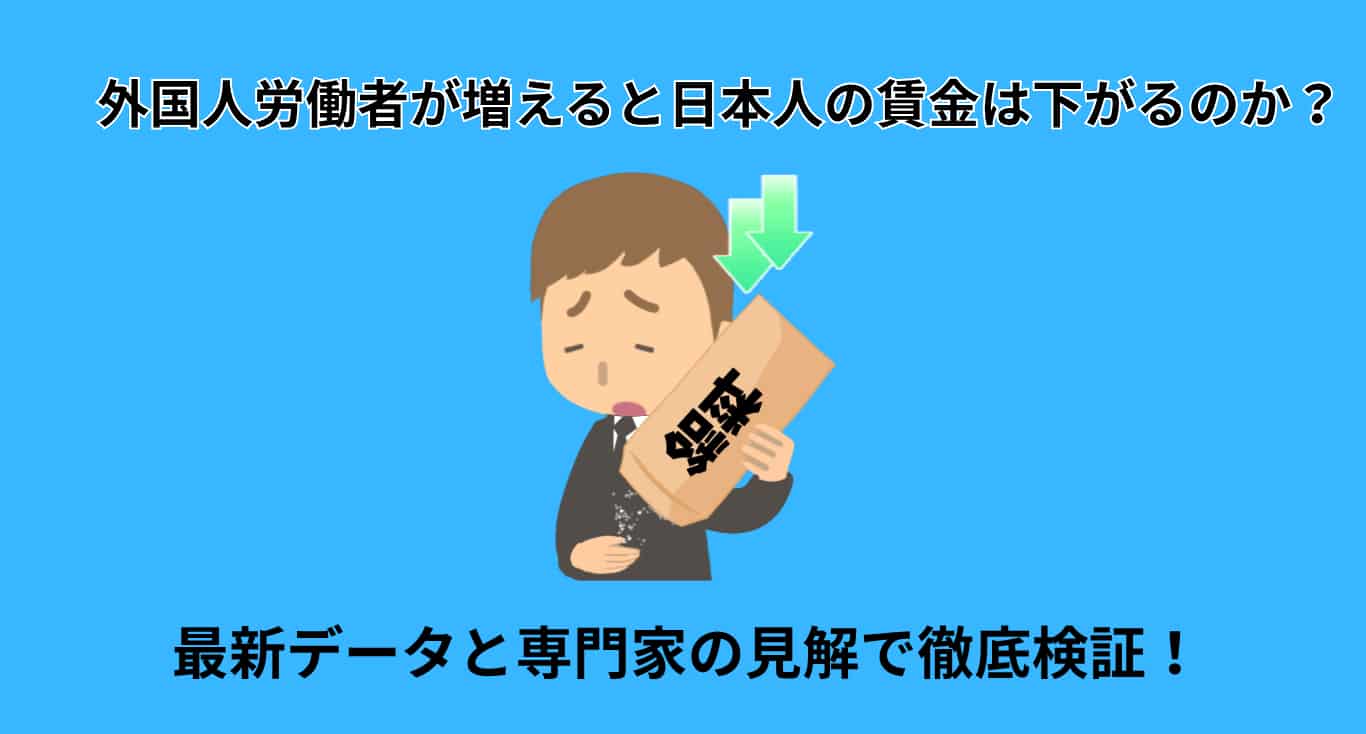
コメント