「逃げてもいい」――その言葉が多くの人の胸を打ちました。
2025年8月、横浜市で開催された「不登校生動画甲子園2025」で、全国から集まった432本の応募作品の中から最優秀賞に選ばれたのは、新潟県の中学3年生・ひなさんの動画でした。
不登校を経験した彼女が伝えたメッセージは、単なる個人の体験を超えて、「不登校とは何か」「どう受け止めるべきか」という社会全体への問いかけでもあります。
この記事では、受賞作品の内容や大会の特徴、そして専門家の見解を交えながら、不登校と向き合う上で大切な視点を整理していきます。
はじめに
不登校生動画甲子園とは?
今回は「不登校生動画甲子園」というコンテストについてご紹介したいと思います。
不登校を経験した全国の若者たちが、自らの思いや体験を短い動画に込めて発表する場なんです。
TikTokなどが主催し、対象は13歳から19歳の中高生。2025年で3回目を迎えたこの大会は、「不登校で見つけたこと」をテーマに、1分以内のショート動画を募集しました。
表彰式は横浜市の歴史ある開港記念会館で行われ、応募総数は432本にものぼりました。
会場では、ファイナリストの動画上映に加え、本人たちが直接自分の言葉で語るスピーチもあり、とても心を動かされました。

大会が注目される背景
この大会がこれほど注目を集める理由は、不登校というテーマ自体に社会的な関心が高まっているからです。
文部科学省の調査によれば、不登校の児童生徒数は年々増加し、全国で34万人を超えるそうです。
不登校と聞くと「後ろ向き」や「問題」というイメージがまだ強いですが、実際には命を守るための選択であることも少なくありません。
今回の大会では、「周りと違っても恥じることじゃない」「逃げても生きる意味を見つけたい」といった言葉が多く語られ、観客の心に強く響きました。
専門家や保護者も審査に加わり、不登校の現実を多角的に捉えようとする姿勢も、この大会ならではの大きな特色だと感じました。
1.中学3年生「ひな」さんの最優秀作品
@momo_nox 私の見つけたことは逃げ道です#不登校生動画甲子園 #不登校 #不登校生 #おすすめのりたい #不登校生動画選手権 ♬ オリジナル楽曲 – 解剖 – ひな
受賞作品の内容と表現
最優秀作品賞に選ばれたのは、新潟県に住む中学3年生の「ひな」さん(15)の動画でした。
小学生のころ、容姿に関する悪口を言われ、しかも先生たちに見て見ぬふりをされた経験から不登校になったそうです。
ベッドから起き上がれず、スマートフォンで動画を見続ける日々もあったといいます。そんな彼女を救ったのは「絵を描くこと」でした。
動画では、自分が描いたイラストと日常の風景を巧みに組み合わせ、テンポよく切り替わる映像の中に「何げない一言で人は飛び降りるかもしれない」「逃げ道を作った。幸せになれるように」といった強い言葉を重ねていました。
観る人に深い印象を残す内容で、私自身も胸が締め付けられる思いがしました。
「逃げていい」というメッセージ
受賞後のスピーチで、ひなさんは「逃げていいんだ、というメッセージを伝えたかった」と語っていました。
逃げることは「弱さ」と考えられがちですが、彼女にとっては命を守るために欠かせない選択でした。
動画には「逃げることは恥ずかしくない」「人生の一部であり、やがて楽になれる」という強い想いが込められていて、同じような経験を抱える人たちにとって大きな励ましになったと思います。
実際に会場では、多くの人が涙を流し、共感の拍手を送っていたのがとても印象的でした。
審査委員からの評価と感想
審査委員長のロバート・キャンベルさんは「完成度が高く、小説の原作のように心を揺さぶられる作品だった。私自身も励まされた」とコメントしていました。
他の審査員からも「映像の表現力が素晴らしい」「メッセージがまっすぐに伝わってきた」と高い評価が寄せられていました。
映像の技術だけでなく、自分のつらい経験を真摯に表現したことが評価されたのだと思います。こうして、ひなさんの作品は「不登校生動画甲子園2025」を象徴する存在となりました。

投稿者: ひな(@momo_nox)
受賞作品: https://www.tiktok.com/@momo_nox/video/7539761319432424705
受賞コメント:
最優秀賞に選んでいただきありがとうございます。
気持ちを伝えるために頑張って作った動画なので本当に嬉しいです。
ロバート キャンベルさんより:
絵が作ってくれた逃げ道が、新たな自信の入り口になったことが印象的でした。ご自身の不安を音楽や映像、言葉に乗せて、重ね塗りするようなタッチで作っています。ひなさん自身の辛かったこと、絵を描いて自信を持てたことが伝わってきました。また、動画としての完成度が非常に高かったことも評価されました。
2.大会全体の取り組みと特徴

応募総数と選考の流れ
今回の「不登校生動画甲子園2025」には、全国から432本もの動画が寄せられました。応募者は、不登校を経験した13歳から19歳までの中高生たちです。
動画の長さは1分以内と限られているのに、そこに込められた思いはどれも濃く、多様な表現があふれていました。
審査は一次選考を経て、最終的に8本のファイナリスト作品が選ばれ、表彰式で上映されました。
こうした流れは「自分の声を社会に届ける」という大切なプロセスであり、参加者にとって挑戦と発信の両方を経験できる場になっていました。
ファイナリストのスピーチと多様な声
表彰式では、上映後にファイナリスト本人が登壇し、自分の言葉で思いを語りました。
「周りと違うことは恥じることじゃない」「まだ見つけられていないけれど、生きる理由を探したい」といった言葉は、会場全体を包み込みました。
ある参加者は、不登校で得た時間を「自己理解を深める大切な期間」と話し、別の参加者は「逃げたからこそ見つけた趣味や仲間がある」と語っていました。
その一つひとつの声が、不登校という言葉の裏にある多様な現実を映し出していたのだと感じました。
審査体制と新たな試み(当事者・保護者参加)
今回特に印象的だったのは、審査に不登校経験者や保護者が参加したことです。
これまで専門家中心だった審査に、実際の経験を持つ人たちが加わることで、よりリアルな視点が反映されました。
たとえば、高校生の娘が不登校を経験したお母さんは「不登校は“良かったこと”だけではなく、苦しみや葛藤もある。その姿を動画にする勇気に心を打たれた」と話していました。
この試みは、当事者の声を真正面から受け止めようとする大会の姿勢を示しており、信頼性や意義をさらに深めるものになったと思います。
3.社会的意義と専門家の見解
不登校は生存戦略としての側面
不登校というと「逃げ」と思われがちですが、不登校ジャーナリストの石井しこうさんは「命をつなぐための選択」と強調していました。
学校に行くことが苦痛で心身に影響が出るとき、距離を取ることは自己防衛であり、生き延びるための手段だといえます。
実際、参加した若者の中には「逃げたからこそ生きられた」「その時間に趣味や居場所を見つけられた」と話す人もいて、不登校の意味を新たに考えるきっかけを与えていました。
「逃げた後」の社会的自立の課題
一方で、逃げることは一時的な解決にすぎず、その後の自立につなげる支援が必要だという声も多くありました。
ネット上の意見でも「逃げ続けることはできない」「逃げた経験を活かし、立ち向かう力を育てることが大切」といったコメントが目立ちました。
実際に、不登校から回復した人の中には通信制高校で学び直したり、アルバイトを通して社会と再びつながっていく例もあります。
逃げることで“終わり”ではなく、“次の一歩”へ進む環境を整えることが、今後の大きな課題なのだと感じます。
当事者の声を社会に届ける新しい形
今回の大会が大きな意義を持つのは、当事者の声をダイレクトに社会へ届ける新しい形を示したからです。
認定NPO法人「育て上げネット」の工藤啓さんは「動画という形で一人ひとりの言葉を発信できること自体が『子どもがまんなかの社会』を示すもの」と話していました。
政府のパブリックコメントのような形式ばったものではなく、自由で率直な表現だからこそ、同じ悩みを抱える人や社会全体に届くのだと思います。
誰かに見てもらえるか分からない不安を和らげ、「自分の存在を知ってほしい」という思いを託せる場所になったことは、この大会の大きな成果だと感じました。
まとめ
「不登校生動画甲子園2025」は、432本もの応募作品とともに、「逃げ」とされがちだった不登校の姿を新しい角度から見せてくれました。最優秀賞を受賞したひなさんの動画は、「逃げてもいい」という言葉を力強く伝え、多くの人の心を動かしました。
大会全体では、ファイナリストのスピーチが共感を呼び、当事者や保護者を審査に加える新しい試みも行われました。これは社会全体で不登校と向き合う姿勢を示す大きな一歩だと思います。
専門家は「不登校は生存戦略である」と強調しつつ、「その後の自立を支える環境づくりが欠かせない」と課題を提示していました。また、動画という身近な手段で声を社会に届けられることが、この大会の特筆すべき成果です。
「逃げることは悪くない」というメッセージを広く伝えた今回の大会。若者たちの声や映像は、同じ境遇で悩む人々に寄り添うだけでなく、社会全体に「不登校をどう受け止めるか」という問いを投げかけました。これからも、こうした声に耳を傾け、支援と理解の輪を広げていく必要があると強く感じました。
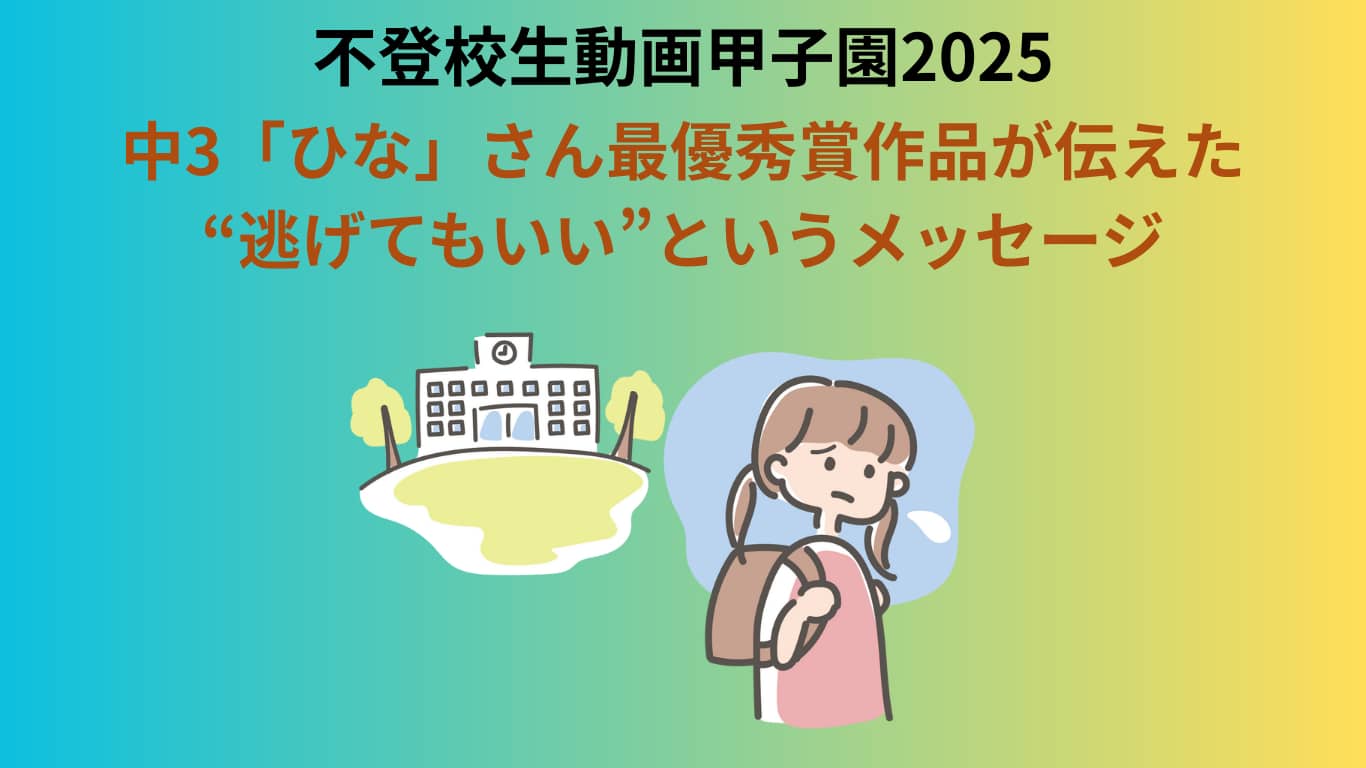
コメント