北海道・羅臼岳で2025年8月に発生したヒグマ襲撃事件は、多くの登山者や地域住民に大きな衝撃を与えました。
実は事故の2週間前、同じ地域で「餌付け」が疑われる事案が報告されており、野生動物への安易な関わりが悲劇を招いた可能性が指摘されています。
本記事では、この事件をもとに 「野生動物への餌付けがなぜ危険なのか」 を解説し、全国で実際に起きた事例や、私たちができる防止策について分かりやすく紹介します。
はじめに
羅臼岳で起きたヒグマ襲撃事件
2025年8月、北海道の羅臼岳で登山をしていた男性がヒグマに襲われ、命を落とすという痛ましい事故が起きました。
実はそのわずか2週間前、同じ地域でヒグマへの餌付けが疑われる事案が確認されており、今回の事故に関わった個体との関連性が指摘されています。
「山で野生動物に出会えたら特別な体験になる」と感じる人もいるかもしれませんが、食べ物を与える行為はヒグマの警戒心を失わせ、人間を餌の供給源と誤解させる危険があります。
その結果、このような悲しい事故が現実に起きてしまったのです…。
餌付けが引き金となる人獣衝突の実態
「かわいそうだから少しだけ…」「観光客を喜ばせたいから」といった軽い気持ちでの餌付けが、野生動物にとっても人間にとっても大きなリスクを生みます。
ヒグマが人里に現れるようになれば、農作物の被害や住宅地への侵入が増え、最悪の場合は駆除されることになります。
実際に、知床では「RT」と呼ばれるヒグマがゴミを漁るようになり、犬を襲う事件が続発しました。
また秋田県では、スーパーにヒグマが侵入し、ハチミツやパンに誘われて異常事態が発生しました。
こうした事例はすべて、人間が与えた食べ物や残飯に動物が依存してしまった結果 です。
羅臼岳の事件は氷山の一角にすぎません。野生動物への餌付けがどれほど危険な行為かを、私たちは真剣に考える必要があります。

1.野生動物への餌付けが人間に及ぼすリスク

襲撃事故のリスク増大
餌付けによって野生動物が人間に慣れると、「人間=餌をくれる存在」と学習してしまいます。
ヒグマは特に学習能力が高く、一度でも食べ物を得ると、繰り返し人の生活圏に現れるようになります。
羅臼岳の事故でも、登山中の男性が突然襲われましたが、その背景には過去の餌付けが警戒心を失わせた可能性があると考えられています。
一度こうした習慣が身につくと、人のリュックや食料を狙って襲撃に発展してしまうこともあるのです。
観光や地域社会への影響
「野生動物が近くで見られる」と期待して餌を与える人は少なくありません。
しかし、その結果、地域が「危険な場所」とみなされ、観光客が減少するケースもあります。
例えば、知床半島ではヒグマの頻繁な出没により観光バスの運行に影響が出たり、キャンプ場が一時閉鎖された例もあります。
観光収入の減少だけでなく、住民の安心した暮らしも脅かされてしまうのです。
日常生活に潜む危険性
餌付けの問題は山や観光地に限られません。住宅地周辺でも、放置されたゴミ袋や庭先の生ゴミが餌付けと同じ役割を果たしてしまいます。
北海道のある地域では、夜になるとクマがゴミをあさるのが常態化し、住民が夜間外出を控えるようになった例もあります。
表面的には「少しの油断」でも、実際には人と動物の境界を崩し、生活全体を危険にさらしているのです…。
2.野生動物にとってのリスク
野生性を失い依存化する危険
人間から餌をもらうことに慣れた動物は、本来の生き方を忘れてしまいます。
ヒグマは秋になるとドングリやサケを食べて冬眠に備えますが、餌付けによって人間の食べ物を求めるようになると、自分で餌を探す力を失ってしまうのです。
実際に知床では、ゴミ置き場や民家に出没するクマが増え、野生で生き抜く力を奪われてしまっている現状があります。
問題個体として処分対象になる現実
人里に繰り返し現れるようになった動物は「問題個体」とされ、最終的には駆除されることが少なくありません。
北海道では毎年、餌付けによって人に慣れすぎたヒグマが「危険」と判断され、やむを得ず射殺される事例が報告されています。
これは、私たちの軽率な行動が動物の命を奪ってしまう現実を示しています。
人間の食べ物がもたらす健康被害
人間の食べ物は野生動物にとって不向きです。塩分や油分の多い加工食品は消化不良を引き起こし、病気の原因にもなります。
例えば、野鳥にパンを与えると栄養バランスを崩し、成長不良や病気を引き起こすことが知られています。
ヒグマにとっても、お菓子やチョコレートは内臓に負担をかけ、命に関わる健康被害につながるのです。
「少しだけなら大丈夫」という気持ちが、実は動物に深刻なダメージを与えてしまいます。
3.餌付けが原因とされる国内の事故事例
羅臼岳・知床でのヒグマ事例
羅臼岳での死亡事故は、餌付けがいかに危険かを物語っています。事故の約2週間前、同じ場所でヒグマに食べ物を与えた疑いがあり、人=食べ物という結びつきを学習してしまった可能性があります。
知床では、キャンプ場や駐車場のゴミ、釣り人が捨てた魚の内臓などが「無自覚の餌付け」となり、クマが人に近づく行動を強めています。
車のドアやテントに鼻を突っ込んだり、リュックを狙って接近する姿も観察されており、最終的には人身事故や駆除につながってしまうのです。
秋田県スーパー立てこもり事件
秋田県では、ヒグマが市街地のスーパーに侵入し、長時間徘徊する異常事態が起きました。パンくずや甘い食品、生ゴミが誘因になったと考えられています。
この騒動で営業が停止されただけでなく、周辺の学校や保育施設では登下校ルートが変更され、集団下校が行われました。
被害がなかったとしても、売上の減少、従業員の不安、地域全体の恐怖感など「見えない損失」が大きく残りました。
原因は、日常の「ちょっとくらい」「あとで片づければいい」という油断にあります。
全国的に増加するクマ被害の背景
クマの出没や被害が全国で増えているのにはいくつか理由があります。
①山の実りの不作といった自然条件の変化、②人間活動の拡大(観光や宅地開発)、③ゴミの管理不足や観光客の餌やりなど、人間の行動が大きく関わっています。
特に③は私たち自身が改善できる部分です。ゴミ箱のフタを必ず閉める、キャンプ場で食べ残しを放置しない、釣り場で魚の内臓を捨てない、民家の果樹を収穫するなど、日常の心がけで出没を防ぐことができます。
逆に一度でも簡単に食べ物を得た経験をクマに与えてしまうと、何度も繰り返されます。被害を減らすためには、地域全体で「餌をゼロにする」努力が必要です。
まとめ
羅臼岳の事故は、「少しだけなら」という軽い気持ちが、動物の命と人の安全を同時に危険にさらすことを示しています。
餌付けは動物の警戒心を奪い、人を“餌の出どころ”と学習させてしまいます。
その結果、人身事故、地域社会の不安、そして最終的には駆除という悲しい結末につながってしまうのです。さらに、人間の食べ物は動物の健康にも悪影響を与えます。
私たちができることはとてもシンプルです。
①餌を与えない、②ゴミをきちんと管理する、③観察や撮影でも距離を保つ、④ルールを守る、⑤子どもや観光客に伝える――この基本を徹底すれば、事故や出没のリスクは確実に減らせます。
「野生は野生のままに」。一般市民として日々の暮らしの中で意識したいのは、小さな行動の積み重ねが動物の命を守り、地域の安心につながるということです。皆さんと一緒に、この大切なことを共有していければ嬉しいです!
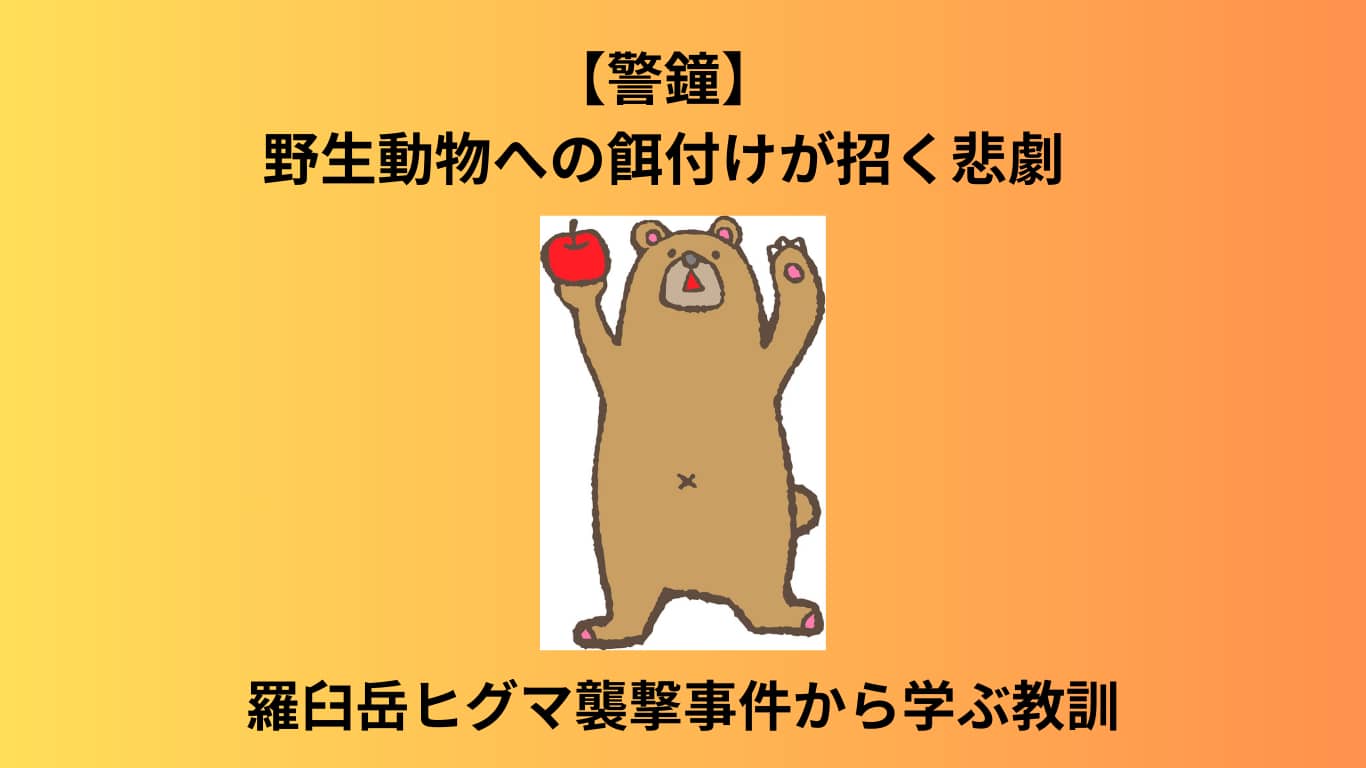
コメント