「サナエちゃん」と呼ばれる高市早苗首相が、ひそかに“エンちゃん”と呼んでいる人物がいます。
その名は遠藤敬(えんどう・たかし)議員。
報道では「泉州のおっちゃん」とも称され、自民党と日本維新の会の連立を影で支えた“調整役”といわれています。
では、なぜ首相があえてこの呼び名を使うのか?そして“エンちゃん”と呼ばれる遠藤氏は実際どんな人物なのか?
この記事では、テレビ番組の発言や地元でのエピソードをもとに、遠藤氏の実像と、首相との“あだ名”に込められた意味を探っていきます!
はじめに
自維連立の裏側にいた「エンちゃん」とは
2025年10月に発足した高市早苗内閣。政治の世界では「自民党と日本維新の会が手を組んだ」と大きなニュースになりましたが、その背景には、あまり表に出ない1人の政治家の存在がありました。
それが、日本維新の会の遠藤敬(えんどう・たかし)氏です。テレビ番組では「エンちゃん」や「泉州のおっちゃん」と呼ばれ、どこにでもいそうな気さくな雰囲気の人物として紹介されましたが、実は政局を動かす大きな役割を担っていました。
遠藤氏は、派手な発言や強い主張で注目を集めるタイプではありません。しかし、関係者の間では「誰とでも仲良くなる懐の深さ」を持ち、人をつなぎ、動かす力に長けていると言われています。
この「人たらし」のような資質が、政権の枠組みを変えるほどの結果につながったのです。
政局を動かした泉州の調整力に注目
遠藤氏の地元は大阪・泉州エリア。岸和田の「だんじり祭り」で有名な地域です。例えば祭りの場では、与党・野党を超えた政治家たちが一堂に集まり、笑顔で語り合う姿が見られることもあるそうです。
その中心にいるのが遠藤氏で、「あの人が呼んだから来た」という関係者の声が多いのだとか。
こうした地道な信頼関係の積み重ねが、政府と維新の間に橋をかけました。
「表舞台の主役」というよりは、裏方として動き、周囲が動きやすくなる環境を整える調整役。それが、エンちゃんこと遠藤敬氏です。
彼がどのようにして連立を実現へ導いたのか。本記事では、その実力と舞台裏に迫っていきます。
1.エンちゃん=遠藤敬氏とは?

維新の国対委員長から首相補佐官へ
遠藤敬氏は、日本維新の会で国会対策委員長を担っていた人物です。
国会対策委員長というのは、テレビや新聞に頻繁に登場する目立つ役職ではありませんが、政党間の連絡や調整を行う「縁の下の力持ち」です。
遠藤氏はそこで力を発揮し、与野党のあらゆる政治家と話をまとめてきました。
そんな遠藤氏は、高市内閣の発足にあわせて「連立合意政策推進担当」の首相補佐官に就任します。
閣僚ではなく、官邸の中に入り込むポジション。まさに、政権と維新の“連絡役”として欠かせない存在であることがわかります。
テレビ番組で専門家が「この人がいなければ連立は成立しなかった」と語るほど、裏側で大きな役割を果たしていたとされています。
泉州エリアを地盤とする小選挙区連勝議員
遠藤氏の地元は、大阪・泉州エリア。岸和田市、泉大津市、和泉市、高石市、そして泉北郡といった街が含まれます。いわゆる「港町らしい義理と人情」の地域で、地元とのつながりの深さが政治的な強みになっていると言えます。
注目すべきは、衆議院選挙で比例復活なしの“小選挙区5連勝”。これは、毎回しっかりと地元有権者から信頼を勝ち取っている証です。
大声で政策を語るよりも、日々の人付き合いや、地元行事に顔を出し続けることで支持を積み重ねてきたタイプの政治家といえます。
たとえば、だんじり祭りでは主役級の動きを見せる政治家として知られ、地元の人からは「遠藤さんは気さくで話しやすい」と評判。こうした地道な取り組みが、国政でも活きる人脈に発展していったのでしょう。
高市首相より8学年下の57歳
遠藤氏は1967年生まれの57歳。高市首相より少し若く、普通に考えれば「先輩を立てる調整役」に回りやすい世代です。実際、番組でも高市首相のことを親しみを込めて「サナエちゃん」と呼んでいると明かされました。
先輩たちに対して物怖じしない一方で、きちんと敬意も示す。そのバランス感覚が、政治の世界ではとても大切です。
「上下関係に縛られすぎず、でも失礼にならない距離感」。この絶妙な人付き合いが、多くの政治家から信頼される理由なのかもしれません。
――ここまで見てきたように、遠藤敬氏は決して派手さはないものの、地元と国会の双方で強い信頼を獲得してきた人物です。
次の章では、そんな彼がなぜ「泉州のおっちゃん」と呼ばれるのか、その背景に迫ります。
かつては飲食店を経営していた経験も
遠藤氏の経歴には「飲食店経営」という記載があり、政界に入る前は地元でお店を切り盛りしていたことがわかっています(衆議院公式プロフィールより)。
店舗名や所在地などの詳細は公表資料では確認されていませんが、人が集まる現場で培ったコミュニケーション力や段取り力は、今につながる大きな強みになっていると感じます。
商店街や地元イベントなど、人と人が触れ合う場を大切にしてきたからこそ、現在の「誰とでも仲良くなれる政治家」という評価にもつながっているのではないでしょうか。
まさに現場で身につけた力が、国政の調整役として発揮されていると言えます。
2.なぜ「泉州のおっちゃん」と呼ばれるのか
誰とでも仲良くできる懐の深さ
遠藤氏が「泉州のおっちゃん」と呼ばれる理由は、肩書きよりもまず人として相手に近づく姿勢にあります。
たとえば、地元の食堂で相手の陣営や立場に関係なく声をかけ、まず近況を聞く——そんな日常の積み重ねです。
選挙の時期だけ顔を出すのではなく、地域の行事や商店街の集まり、学校や福祉施設の催しにも足を運び、名前ではなく顔で覚えてもらう関係づくりを続けてきました。
会議では意見が対立しても、「今日は結論を急がず、まず困っている人を先に助けよう」と、誰も反対しづらい“小さな合意”から話を前に進めます。
相手の得意分野や趣味を覚えておき、次の話題の糸口にするのも得意です。堅い言葉よりも、冗談や世間話で空気をほぐす——この“距離の詰め方”が、年齢も党派も超えて人をつなぐ力になっています。
だんじり祭りで見せた超党派ネットワークと現場力
泉州を代表する「だんじり祭り」は、遠藤氏のネットワークがもっともわかりやすく表れる舞台です。
与党・野党の議員、地方の首長、専門家、さらには経済人やメディア関係者まで、普段なら席を同じくしにくい人たちが同じ場に集まります。
祭りという“肩書きを外せる空間”で顔を合わせると、対立していた相手とも不思議と会話が生まれます。「まずは地域の安全対策だけ一緒にやろう」「次は防災訓練で協力しよう」と、具体的な小さな約束に落とし込めるのです。
現場での段取り力も光ります。
急に来賓が増えれば、席や導線を即座に組み替え、関係者に短い言葉で要点だけ伝える。トラブルが起きれば、電話一本で関係者をつなぎ、役割を決め、時間を決める。難しい専門用語は使わず、「明日までにここ」「今日はここまで」とわかりやすく区切る。
こうした“その場で動かす力”が、保守もリベラルも巻き込んで物事を前へ進める原動力になっています。
3.“自維連立”のキーパーソンだった理由
小泉総理構想から高市内閣へ即座に転換
当初、維新の中では「次の総理は小泉氏かもしれない」という空気がありました。ところが、ふたを開けると総裁選を制したのは高市氏。
多くが様子見に入る中で、遠藤氏は立ち止まりませんでした。連絡帳をめくるように関係者へ次々に連絡し、「まずは今日、共通で進められることを確認しよう」と話を切り替えます。
たとえば、対立が起きにくい子育てや防災といった分野から接点を作り、相手の「今、やれること」を引き出す。方向転換の初日にやるべきことを細かく並べ、1つずつ片づける——その“スピードの出し方”が、空気を一気に変えました。
唯一の交渉窓口としてゼロから連立を再構築
高市内閣の誕生で前提が変わった以上、これまでの積み上げは一度白紙に戻ります。
遠藤氏は、相手ごとに“関心のツボ”を押さえながら、短い面談や電話で合意の芯を探りました。
たとえば、A氏には地域インフラ、B氏には教育、C氏には規制の見直し——という具合に、相手が前向きに動ける入口から話を立ち上げます。
会議の資料は分厚くせず、紙1~2枚に「目的・いつまでに・誰が」をシンプルに記すだけ。
こうすることで、担当者が上司へ説明しやすくなり、ゴーサインが出やすくなる。結果として、「まずは政策の一致点で組む」という実務的な合意が積み重なり、ゼロからの再構築が現実の形になっていきました。
官邸との橋渡し役としての首相補佐官就任
最終的に遠藤氏は「連立合意政策推進担当」の首相補佐官に就きます。
ここで大事なのは“肩書”より“動線”です。官邸側の担当者が誰に相談すれば早いのか、維新側の誰に伝えれば現場が動くのか——その連絡線を1本に束ねる役割を担いました。
たとえば、法案の方針が固まる前に、現場の懸念(費用、人員、スケジュール)を先回りして共有し、無理のない実施案に手直しする。
また、対立が起きそうな論点は“言い換え”で衝突を避け、「まずは試行」「期限付きで検証」という落としどころに誘導する。
官邸のスピード感と、維新の実務志向をつなぐ“翻訳者”として動くことで、机上の合意を現場が回せる計画に変えていったのです。
遠藤 敬(えんどう たかし)氏のプロフィールまとめ

■基本情報
・名前:遠藤 敬(えんどう たかし)
・生年:1967年(57歳)
・出身:大阪府高石市
・学歴:大阪産業大学附属高校 卒業
・所属政党:日本維新の会
・役職:
└ 元 国会対策委員長
└ 高市内閣「連立合意政策推進担当」首相補佐官(閣外協力)
■選挙区
・衆議院 大阪18区
(岸和田市/泉大津市/和泉市/高石市/泉北郡)
➡ 小選挙区 比例復活なしの5連勝中
※地元支持の厚さを示すポイント!
■人物像・評価
・「泉州のおっちゃん」と呼ばれる親しみやすい人柄
・高市首相からは「サナエちゃん」と呼ばれる関係(距離感の近さが話題)
・派手さより調整力で評価
・だんじり祭りでも存在感(与野党が集まる場を自然に作る)
➡ 要するに
『誰とでも仲良くなれる橋渡し役』タイプの政治家
■連立のキーマンといわれる理由
・自民-維新の“自維連立”を裏でまとめた中心人物と報じられる
・総裁選後、高市首相との間を最速でつないだと番組でも解説
・官邸のスピード感と維新の実務をつなぐ“翻訳者”
➡ 政局を動かす 縁の下の真の実務家
遠藤敬氏に報じられた「利益供与」疑惑とは?公選法の視点から整理
遠藤敬氏の名前を検索すると、「公職選挙法違反の疑い」という言葉が目に入る方もいるかもしれません。
では、その内容とは一体どのようなものなのか?そして、法律上どこが問題とされるのか?報道内容と法制度を整理しながら、冷静に見ていきたいと思います。
公職選挙法が禁止する「利益供与」とは?
公職選挙法の目的は、簡単に言うと“お金や物で票を買う行為を防ぐこと”です。
禁止されている主な例は以下の通りです。
- 有権者に金銭を配る
- 欲しがりそうな物品を贈る
- 特別なサービスを無料で提供する
→ これらは「買収」や「寄附の禁止」に当たります。
特に選挙区内の人々に対して政治家が何かを提供することは、選挙と関係がなくても原則NGとされています。
「タダで何かをあげる」「特別に安く提供する」
= お金と同じ効果がある“利益”とみなされる可能性がある
ここが大きなポイントです。
報じられた疑い:「秋田犬の無償譲渡」は利益になるのか?
遠藤氏について報道されたのは、
子犬(秋田犬)を無償で譲渡したことが利益供与ではないか?
という指摘です。
秋田犬は数十万円以上の価格がつくことも多く、「単なる贈り物」とは言えません。
そのため一部では「公選法上の寄附行為に当たる可能性」が議論されました。
しかし、ここで重要なのは——
✅ この行為が 選挙と結びついていたのか?
✅ 受け取った相手が 有権者に当たるのか?
✅ 対価(保護犬活動など)があったのか?
これらが明確にならなければ 違法性は確定しない ということです。
現時点では、
捜査機関による立件に至った事実は公表されていない
= 法的に決着がついた話ではない
という整理が最も正確です。
争点は「政治家の慈善活動との線引き」
実のところ、動物保護やボランティアを行っている政治家は少なくありません。
ですが、
- “善意の支援”が
- “特定有権者への特別な便宜”に見えてしまうと
法律上の問題が発生します。
政治家にとっては、
「助けたい気持ち」と
「利益供与と言われるリスク」
が常に隣り合わせなのです。
今回の件はまさにこの線引きが問われるテーマであり、遠藤氏自身から、今後改めて説明が行われる可能性もあります。
大切なのは「事実が確定していない段階で断定しないこと」
SNSでは「違法だ」と断じる投稿も見られますが、公職選挙法の判断は専門家でも難しいものです。
政治家への疑念が生じたときこそ:
- 冷静に情報源を確認する
- 公式な判断が出るまで様子を見る
そんな姿勢が求められるのではないでしょうか?
今後の報道やご本人の説明に注目しながら、見えてきた事実を踏まえて判断する必要がありますね。
まとめ
「エンちゃん」こと遠藤敬氏は、派手な発信よりも“人をつなぎ、物事を動かす”実務力で評価されるタイプでした。
泉州の地元行事――たとえば岸和田のだんじり祭り――を“肩書きを外せる場”として活用し、与野党のキーパーソンを同じテーブルに座らせる。
そこで「まずは防災訓練だけ一緒に」「次は地域インフラの安全対策」といった小さな合意を積み重ね、対立を越える糸口をつくる。
この積み重ねが、総裁選の結果が変わった瞬間でも、関係者へ即時に連絡網を回し、実務から合意を再構築する“スピード”につながりました。
高市内閣下では、首相補佐官(連立合意政策推進担当)として、官邸と維新の“動線”を一本化。
法案の方針が固まる前に現場の懸念(費用・人員・期日)を洗い出し、衝突しやすい論点は「試行」「期限付き検証」へと着地させる“翻訳役”を担います。
要するに、遠藤氏の強みは「誰とでも話せる懐の深さ」×「現場で段取りを切る力」×「言葉を言い換えて衝突を避ける技術」。
今後は、子育て・防災・規制見直しなど“争いになりにくい政策領域”から成果を積み、官邸のスピードと現場の実務を噛み合わせられるかが、政局の行方を左右する重要ポイントになるでしょう。
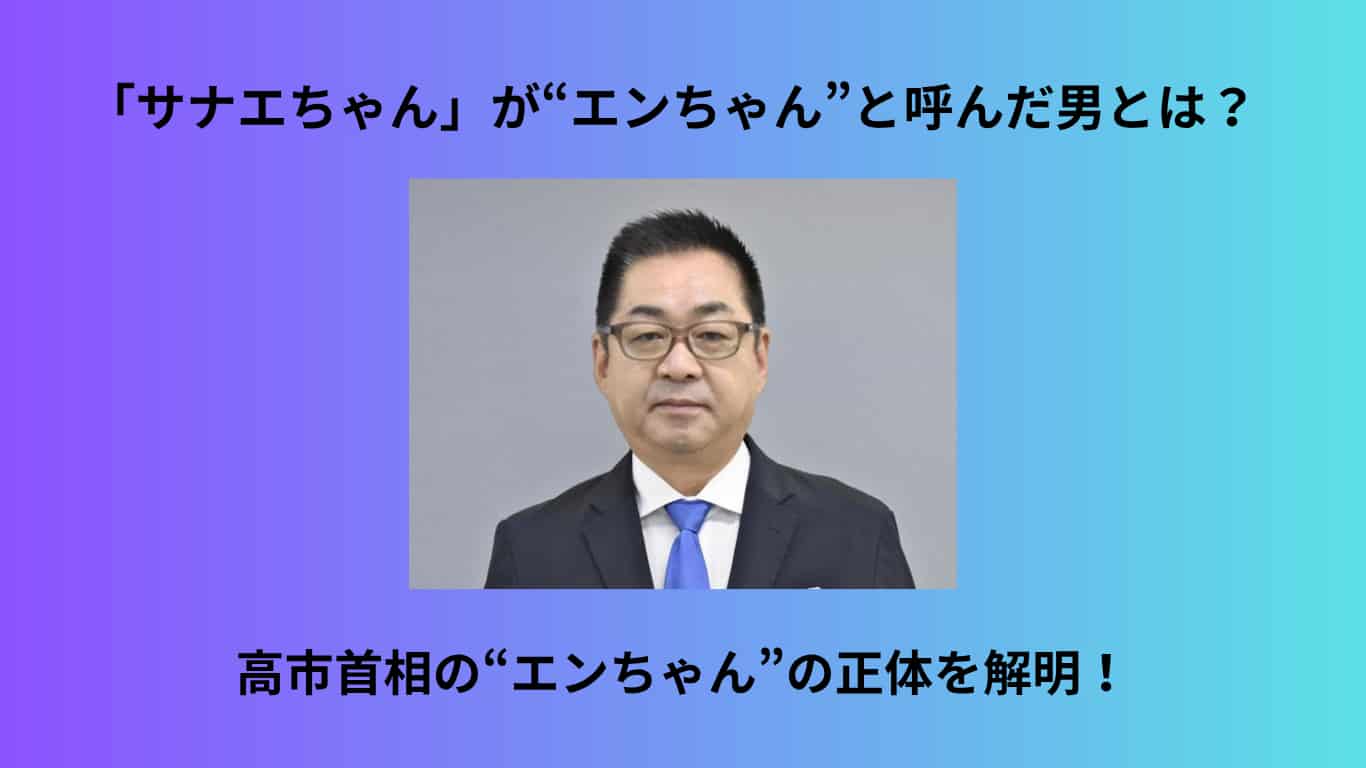
コメント