「水ダウ」で話題を呼んだ“スピード解散選手権”の出演コンビが、ついに全組消滅しました。
最後まで活動を続けていた「コンピューター宇宙」が、2025年10月5日放送の『オールスター後夜祭’25秋』で「本日をもって解散します」と電撃発表。
不仲の経緯や当日のスタジオの空気、Xに寄せられたコメント、さらにクイズ演出中のシステムトラブルと藤井健太郎プロデューサーの謝罪まで、時系列でやさしく解説します。
はじめに
「水曜日のダウンタウン」発“スピード解散選手権”とは?
TBS系バラエティ番組『水曜日のダウンタウン』の中でも、特に強烈なインパクトを残したのが「スピード解散選手権」です。
これは、芸人コンビの一方が“ドッキリ”として相方に突然「解散しよう」と切り出し、実際に解散が決まるまでのスピードを競うという過激な企画でした。
2022年1月に放送され、アルコ&ピースの推薦で出演した「コンピューター宇宙」をはじめ、竹内ズ・スタンダップコーギー・バビロンといった若手芸人たちが参加。
笑いの裏にはリアルな人間関係の機微や、芸人としての葛藤が垣間見える内容で、視聴者の間でも「笑っていいのか迷う」「リアルすぎて怖い」と話題になりました。
この企画で注目されたのが、普段から“不仲コンビ”と呼ばれていたコンピューター宇宙。
仕掛け人のブティックあゆみが「解散しよう」と切り出すと、相方のはっしーはっぴーが次第に怒りをあらわにし、わずか7分13秒で「もういい、解散!」と決着。
その生々しさが逆に笑いを呼び、視聴者の印象に強く残りました。
「コンピューター宇宙」生放送での突然の発表に注目集まる
あれから3年、2025年10月5日深夜放送の『オールスター後夜祭’25秋』の生放送で、まさかの“現実の解散発表”が起きました。
番組中のクイズコーナーで「本日をもって解散するコンビは?」という問題が出され、正解として発表されたのがコンピューター宇宙。
スタジオ中が一瞬静まり返り、有吉弘行が「不仲ということで」とまとめると、ブティックあゆみが「不仲です」と即答。
“あのドッキリが現実になった”と、放送直後からSNSでは「ついに現実に…」「スピード解散選手権、全滅した…」といった驚きと寂しさの声が相次ぎました。
さらに、番組を手がける藤井健太郎プロデューサーがX(旧Twitter)でクイズ中のシステムトラブルを謝罪する投稿を行い、話題はさらに拡散。
“ドッキリの神様”と呼ばれる藤井氏の番組らしい皮肉な展開として、多くの視聴者の関心を集めました。
この「水ダウ」発の解散劇は、笑いと現実の境界をあらためて問い直す出来事となったのです。
1.生放送中に突然の発表「本日をもって解散します」
「オールスター後夜祭’25秋」で起きた衝撃の瞬間
2025年10月5日深夜に放送された『オールスター後夜祭’25秋』。
番組後半、恒例のクイズコーナーで「本日をもって解散するコンビは?」という一問が出題されました。
普段はバラエティらしい笑いに包まれるこのコーナーですが、この夜ばかりは空気が一変。
正解発表とともに「コンピューター宇宙」という名前が映し出されると、スタジオ内がざわつき、観客席からも小さな悲鳴のような声が漏れました。
司会の有吉弘行が半信半疑で「本当に解散するの?」と尋ねると、はっしーはっぴーがマイクを握り、「本日をもって解散します!」とハッキリと宣言。
その言葉に場の空気は完全に変わり、笑いよりも驚きと静寂が支配しました。
多くの共演芸人が「え?ドッキリじゃないの?」と困惑する中、番組は予定通り進行。
まさかの“生放送での解散発表”という事態に、視聴者のSNSも瞬く間に騒然となりました。
クイズ形式で明かされた異例の演出とスタジオの反応
「クイズの正解発表=解散発表」という構成は、まさに『オールスター後夜祭』らしい皮肉な演出でした。
通常なら笑いに包まれるはずの場面で、リアルすぎる“現実の結末”が明かされることになったのです。
クイズの選択肢には他の芸人コンビの名前も並び、解散発表がどの組かを当てる形式だったため、観客も出演者も一様に混乱。
さらに放送中、システムトラブルによって選択肢が正しく表示されず、番組は一時中断。
仕切り直しの後に改めて問題が出題され、再び「コンピューター宇宙」が正解として映し出されました。
この一連の流れが“藤井健太郎プロデューサーらしい混沌の演出”として、放送直後からネット上でも大きな話題となりました。
中には「藤井P、この状況すら演出にしてる説」「これぞ後夜祭の真骨頂」と称賛する声もあれば、「現実すぎて笑えなかった」と心配する投稿も見られました。
有吉弘行や共演芸人のリアクション
有吉弘行は冷静に「不仲ということで」とコメントをまとめながらも、少し複雑そうな表情を見せました。
それに対してブティックあゆみが即座に「不仲です」と認めると、スタジオ中が一瞬静まり返り、笑いが追いつかない空気に。
横で見ていたお笑いコンビ・アルコ&ピースの酒井健太は「え、マジで?」と驚き、平子祐希も「まさか本当に解散とは…」と呆然とした様子でした。
放送後、SNSでは「有吉さんもリアクションに困ってた」「笑いよりも人間ドラマ」「後夜祭で涙出るとは」といった感想が相次ぎました。
視聴者にとっても、芸人が笑いを届ける“舞台”で現実の別れを告げる瞬間を見せられたことは衝撃的で、バラエティ番組の“限界”を考えさせられる出来事になったのです。
2.「不仲コンビ」として知られた2人の関係

はっしーはっぴーとブティックあゆみのやり取り
「コンピューター宇宙」は、ネタ中のツッコミの強さや、楽屋トークでの“噛み合わなさ”がむしろ笑いになるタイプのコンビでした。
たとえば、打ち合わせではブティックあゆみが細かく段取りを決めたがる一方、はっしーはっぴーは本番で“場の空気”を優先して変えてしまう——そんな価値観のズレが日常的に起きていたと言われます。
『水曜日のダウンタウン』の「スピード解散選手権」でも、あゆみが理詰めで解散を切り出したのに対し、はっしーは感情を抑えきれずヒートアップ。
お互いの“良さ”が裏目に出るときは衝突に変わる、その関係性がテレビを通しても見えていました。
「怒りっぽいから耐えられなかった」と語った本音
生放送のスタジオで、有吉弘行に理由を問われたはっしーはっぴーは「(相方が)すぐ怒るんで耐えられなくて」と率直に吐露。
これは単なる一度きりの口論ではなく、日々の積み重ねでしんどさが増していたことを示しています。
現場での小さな意見の違い、移動中の会話の温度差、ライブの打ち上げでの反省会の長さ——どれも芸人にとっては当たり前の風景ですが、ストレスが重なると「相方の癖」が自分の活動意欲を削る要因にもなります。
コンビは“二人三脚”だからこそ、歩幅が合わない期間が続くと、次第に前に進めなくなるのです。
SNSで明かされた解散理由とファンのコメント
放送後、はっしーはっぴーはXに「これでコンピューター宇宙解散します!最後に後夜祭に出られて嬉しかったです」と投稿。
ブティックあゆみも「大きな出来事があったわけではなく、コンビ活動への漠然とした不安が膨らんで心が折れた」と、静かな口調で理由を補足しました。
コメント欄には「最後まで笑わせてくれてありがとう」「不仲も含めて“芸”だった」「いつかまた並ぶ日を待ってる」といった温かい声が並ぶ一方で、「無理に続けるより正解」「個々の方が伸びるタイプ」という現実的な意見も目立ちました。
“ドッキリの結末が現実になった”という重さを受け止めつつ、二人の次のステージを後押しするムードが広がっています。
3.「水ダウ」スピード解散選手権の呪い?全組が“消滅”
2022年の「スピード解散選手権」出演コンビたちのその後
“解散を切り出してから決着までの速さ”を競う前代未聞の企画に名を連ねたのは、コンピューター宇宙/竹内ズ/スタンダップコーギー/バビロンの計4組。
放送当時は「さすがに本当に解散まではいかないだろう」という空気もありましたが、3年の時間がその楽観を覆します。
2023年、まず竹内ズとスタンダップコーギーが相次いで解散。2025年には、3人組のバビロンからおーちゃんが脱退し、残る2人はコンビ「パピヨン」へ転じました。
そして最後まで存続していたコンピューター宇宙も、2025年10月に生放送で解散を発表。結果として“当時のメンバー構成のまま”の継続はゼロに——視聴者の間で「水ダウの呪い」と半ば冗談めかして語られる流れが現実になりました。
竹内ズ・スタンダップコーギー・バビロンの解散経緯
竹内ズは、作風の方向性や活動の優先順位をめぐるズレが少しずつ表面化。賞レースの結果やライブの手応えをきっかけに“次の一歩”を別々に選ぶ決断に至りました。

スタンダップコーギーは、ネタ作りのテンポや舞台での役割配分など、日々の細部での不一致が積み重なったとされ、円満ながらも実務的な判断として解散を選択。

バビロンは3人体制ならではの掛け合いとコント構成が魅力でしたが、2025年初頭におーちゃんが離脱。トリオならではの“3点バランス”が崩れたことで、残る2人は名義を改めて再スタートを切りました。

いずれも“ケンカ別れ”というより、活動の設計図を引き直すための決断——そんなニュアンスが共通しています。
3年越しで全組が消えた“企画の因縁”とは
「スピード解散選手権」は、笑いのために“解散”という最終カードを一度テーブルに乗せた企画でした。
実際の活動では、ライブ本数の増減、賞レースの結果、SNSでの反応、収入の上下、相方との時間配分など、目に見えにくいストレス要因が積み上がります。
一度“解散”という言葉が可視化されると、以降の議論で選択肢として出しやすくなってしまう——それが“因縁”です。
もちろん、全てを企画のせいにするのは乱暴ですが、「解散」というタブーを一度口にした記憶は、後の現実判断に小さく影を落とす。
結果として3年のうちに全組が形を変えた事実は、ドッキリのお題が“笑い話”にとどまらないことを示しています。
芸人にとって解散は終点でありリスタートでもある——今回の連鎖は、その二面性を痛烈に浮かび上がらせました。
まとめ
“ドッキリで出た言葉”だったはずの「解散」が、3年かけて現実の選択肢に育っていった——今回の連鎖は、その事実をはっきり示しました。
笑いのために一度テーブルに乗せたカードは、活動の壁にぶつかったとき、再び最有力の選択肢として戻ってくることがあるのです。
コンピューター宇宙のケースでは、「怒りっぽい」「歩幅が合わない」といった日常レベルの違和感が、ライブや収録、移動の一コマごとに積み重なり、最終的な決断につながりました。大事件があったわけではなくても、摩耗は確実に進みます。
一方で、竹内ズやスタンダップコーギー、バビロン(→パピヨン)に見られるように、「解散=終わり」ではありません。作風の刷新、組み合わせの再設計、ピンでの表現の追求など、解散後の“再出発”に活路を見いだす流れもはっきりしています。
視聴者側の反応にも変化が見られました。昔なら「ケンカ別れ」の一言で片づけられがちだったものが、いまは「無理に続けるより健全」「個々で伸びるなら応援したい」という声が中心です。
コンプライアンスやSNSが可視化するこの時代、芸人の働き方そのものに理解が広がっているとも言えます。
今回の出来事は、バラエティが“笑い”だけで成立していないことを思い出させました。企画、現場運営、SNSの熱量、本人たちの生活——それらが複雑に絡み合う中で、コンビが形を変えることは不自然ではありません。
解散は終点であり、同時に表現者としての新しい入口でもあります。
コンピューター宇宙の二人にとっても、今日がゴールではなくスタートライン。ネタの作り方やメディアの出方が変わっても、“人を笑顔にする”という軸がブレなければ、舞台は必ず見つかります。次にどんなステージで笑いを届けてくれるのか——静かに、でもワクワクしながら待ちたいところです。
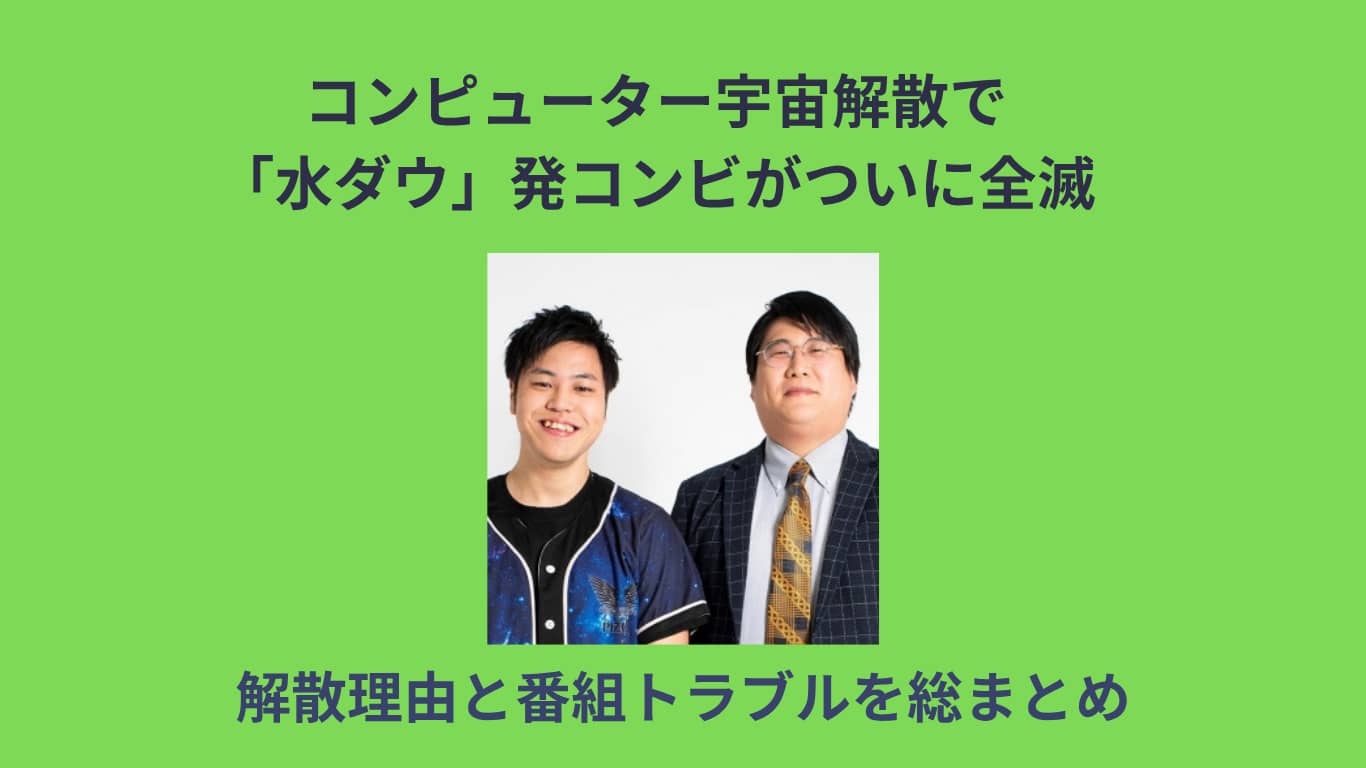
コメント