中国でアステラス製薬の日本人社員がスパイ罪で有罪になったというニュースに衝撃を受けました。
「まさか自分には関係ない」と思っていませんか?でも、中国では反スパイ法が改正されてから、外国人が“知らないうちに”逮捕されるケースが相次いでいます。観光での写真撮影、研究目的の調査、出張中の会話──それが突然「スパイ行為」とされてしまうかもしれないのです。
この記事では、アステラス社員の事例を通じて、中国でスパイ罪とされる行為の実態や、現地で活動する日本人が抱えるリスクを、できるだけわかりやすくまとめました。ニュースの奥にある“本当に怖い話”、ぜひ最後まで読んでみてください。
はじめに
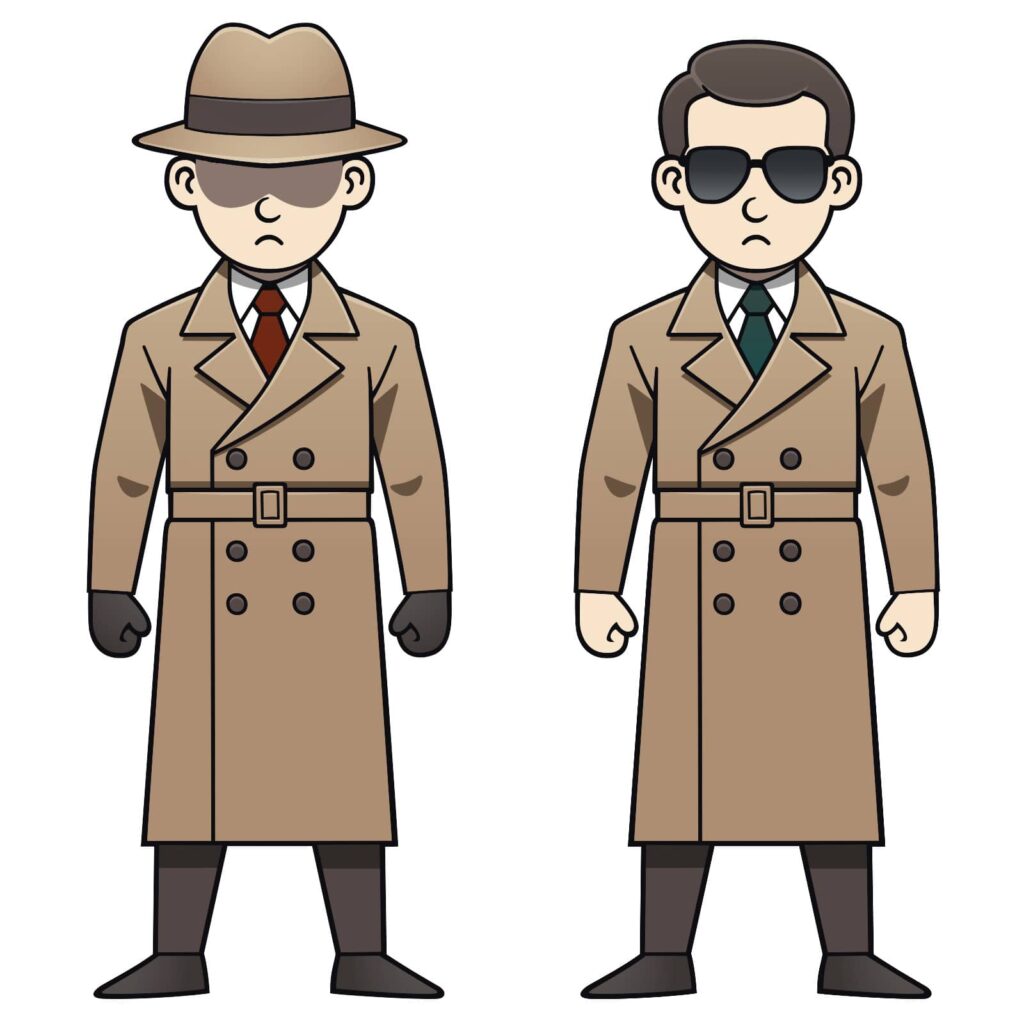
中国での邦人拘束が相次ぐ背景とは
ここ数年、中国では日本人を含む外国人が「スパイ行為」の疑いで拘束されるケースが増えています。
2023年には、製薬大手アステラス製薬の60代の日本人社員が北京市で拘束され、2025年7月に懲役3年6月の有罪判決を受けました。
しかし、その行為の詳細は明かされず、「何が違法だったのか」が分からないままという状況です。
背景には、中国が国家安全を重視し、情報管理を厳格化しているという事情があります。
特に2023年の反スパイ法の改正以降、国家機密だけでなく「国家の安全や利益」に関わるあらゆる情報が処罰の対象となり、その範囲が非常に広く、しかもあいまいになっています。
そのため、「何気ない行動」が当局によりスパイと見なされるリスクが高まっているのです。
スパイ罪とされる行為の不透明性が与える影響
中国での「スパイ罪」は、具体的な定義や基準が公にされていないため、どこまでがセーフでどこからがアウトなのかが非常に分かりづらいのが特徴です。
たとえば、出会い系アプリで知り合った相手に頼まれて軍艦の写真を撮った、自然保護区で昆虫や植物を採取した、GPSを使って測量を行った――こうした行為も、場合によってはスパイとされる可能性があります。
この不透明さは、中国で生活やビジネスを行う外国人、特に日本人の間に強い不安を与えています。
実際に何が「スパイ」とされるか分からないため、無意識のうちにリスクを背負ってしまうこともありえます。
在中国日本大使館も「安全の手引き」で注意喚起を行っていますが、根本的な不透明さが払拭されない限り、緊張感は続くといえるでしょう。
1.アステラス製薬社員に下された有罪判決

判決の概要と懲役3年6月の背景
2025年7月、中国・北京市の第2中級人民法院は、アステラス製薬の60代の日本人社員に対し、「スパイ行為」に該当する罪で懲役3年6月の有罪判決を言い渡しました。
この男性は2023年3月に当局に拘束され、以降、長期間にわたり勾留されていました。起訴内容は非公開で、裁判も一部非公開で行われたとされています。
日本政府は「スパイ行為に関与したとは認識していない」として、繰り返し早期解放を求めてきましたが、受け入れられませんでした。
この判決は、単にひとつの事件にとどまらず、中国の司法制度や外交姿勢を反映した象徴的な出来事といえます。背景には、日中間の安全保障上の緊張や、外国人に対する監視の強化があるとみられています。
何がスパイ行為と見なされたのか
今回の事件で最も問題視されているのは、「具体的に何をしたのか」が明らかにされていない点です。
判決では「国家の安全に危害を及ぼす行為」があったとされていますが、どのような情報を収集したのか、どこで、誰から、どのような方法で行ったのかは不透明です。
関係者によれば、この社員は業務の一環として中国各地を出張し、現地の大学関係者や研究者との接点もあったとされますが、それが何らかの「国家機密」に接触したと解釈された可能性があります。
中国の反スパイ法では、たとえば公的な施設の外観を写真に撮ったり、地元の研究者から公開情報として入手した資料であっても、それが「国家利益に関わる」と当局が判断すればスパイ行為と見なされる可能性があります。
このように、一般的なビジネス活動や学術交流さえも、摘発の対象になりうるという現実があるのです。
裁判手続きの不透明さと国際的懸念
さらに問題視されているのが、中国の裁判手続きの不透明さです。被告側の主張がどのように審理されたのか、弁護人が自由に活動できたのかも明確ではなく、判決文の全文も公開されていません。
外交ルートを通じて日本側が情報収集を試みたものの、詳細は伏せられたままでした。
こうした対応に対して、国際社会からは「恣意的な司法運用ではないか」との批判も上がっています。
実際、アメリカやカナダの市民も過去に似たような事例で拘束・起訴されており、政治的圧力や外交カードとして利用されているとの見方も根強くあります。
日本企業の中国駐在員や長期滞在者にとっては、「明日は我が身」という緊張が常につきまとう状況です。
今回のアステラス製薬社員の判決は、その象徴であり、今後の中日関係に影を落とす一因ともなりかねません。
2.反スパイ法が拡大適用される実態
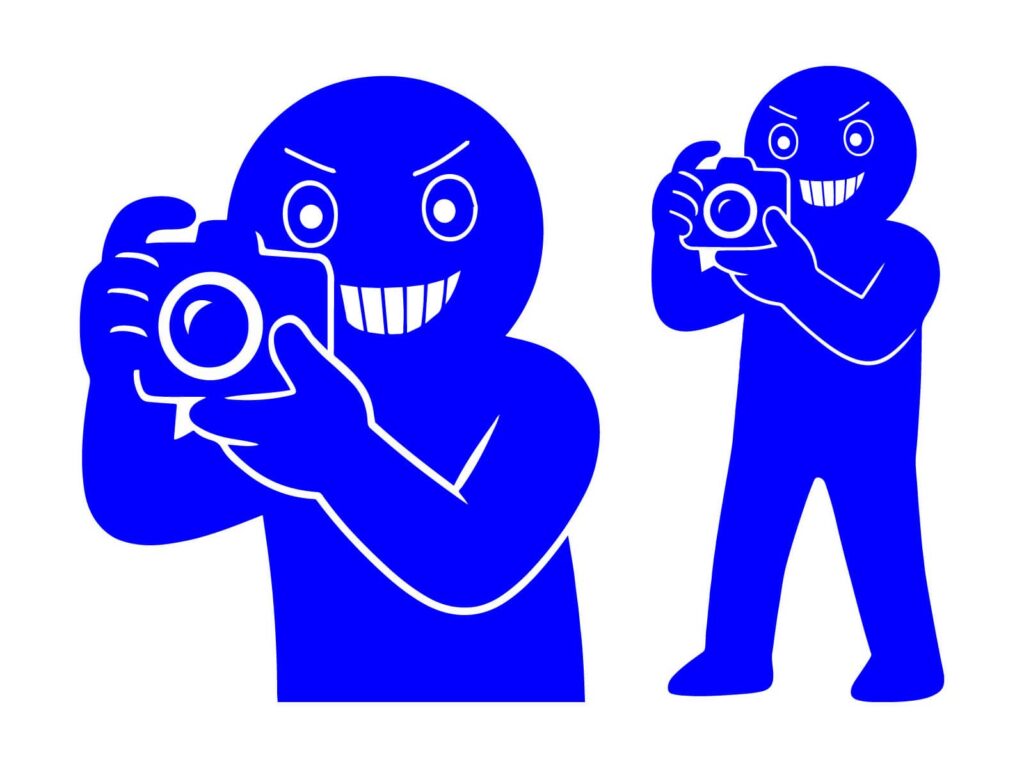
出会い系アプリを通じた軍事情報の撮影事例
在中国日本大使館が作成した「安全の手引き」によれば、近年摘発された事例の中には、日常的な行動がスパイ行為と見なされたケースも含まれています。
たとえば、出会い系アプリで知り合った中国人女性からの依頼で、港に停泊中の中国軍艦やその動きを写真に撮った外国人が、「軍事情報の収集」とされ拘束されたという例があります。
このような行為は一見すると単なる好奇心や個人間のやりとりに思えますが、中国当局の見方では「軍事施設の監視・記録」に該当するおそれがあり、国家安全に直結する重大な違反とされるのです。
SNSやネット上に画像を公開しただけでも、「外国勢力への情報提供」と判断されるリスクがあるとされ、外国人にとっては予想外の落とし穴となっています。
自然保護区での採取行為が摘発対象に
さらに意外なのは、自然環境や生物に関する調査・採取行為もスパイ行為とみなされることがある点です。
実際に、中国の自然保護区に観光目的で複数回足を運び、野生の昆虫や植物のサンプルを採取していた外国人が、「国外機関からの指示を受けて情報や資源を収集していた」として処罰された例も報告されています。
とくに植物の種子や貴重な昆虫標本などが国外に持ち出された場合、「生物資源の流出」として国家の利益に反するとされることがあり、中国ではこれらが国家資源と見なされるケースが増えています。
こうした基準は外国人にはなじみが薄く、注意喚起がされていない場所での活動でも処罰対象となる危険性があります。
学術調査・測量も国家安全に関わるとされる例
学術目的で行われた調査活動さえも、摘発の対象になることがあります。
たとえば、大学の研究機関などが行うアンケート調査が、「統計法違反」や「社会秩序の撹乱」として問題視されたり、地質調査やGPSによる測量が「国家の地理情報の漏洩」とされることがあります。
中国では、温泉掘削や地下資源調査を目的に行われた活動が、国家安全に関連する情報の収集と判断され、厳しく取り締まられるケースも出ています。
調査データそのものが問題ではなく、「その意図や用途」が当局にとって危険と映るかどうかが判断基準になっているのです。
このように、純粋な学術活動や事業調査であっても、「外国との関係性」や「使用目的」によってスパイ罪に問われるおそれがあり、現地での活動には細心の注意が必要です。
3.中国の反スパイ法改正とそのリスク
「国家安全と利益」の定義のあいまいさ
中国は2023年に反スパイ法を改正し、それまでの「国家機密」の保護に加えて、「国家の安全や利益に関わる文書、データ、資料、物品」などの提供や取得も処罰の対象としました。
一見して幅広い保護を目指しているように思えますが、最大の問題はこの「国家の安全と利益」という言葉の意味が極めてあいまいで、どこまでが違法行為なのかが明確にされていない点です。
たとえば、ある外国人が現地企業との会話を通じて入手した資料が、外部から見ればただの市場調査のデータであっても、中国当局が「国家の利益に関わる」と解釈すれば、スパイ罪に問われる可能性があります。
また、科学的な測定機器を使用しただけで、「不正な地理情報収集」とされるケースも報告されています。つまり、法律の解釈次第で“無意識の違反者”が簡単に生まれてしまうという不安が常につきまとうのです。
知らぬ間に罪に問われるリスクの拡大
反スパイ法の改正後、中国で活動する日本人や外国人にとって、「自分の行動が法律に触れるかどうか判断がつかない」という事態が現実のものとなっています。
実際、出張中に公共施設の周辺を撮影しただけで、「軍事施設に関わる情報の収集」とされかねません。
また、現地の研究者との共同調査や、地方の鉱物資源に関する視察でさえも、当局が「国家安全への脅威」と見なせば、摘発される可能性が出てきます。
これにより、一般のビジネスパーソンや研究者、観光客であっても、知らないうちにスパイ行為に問われる危険性が高まっており、事前に十分な情報やガイドラインがないままに活動すること自体がリスクになっています。こうした状況は、「法を犯さないために何を避けるべきか」が極めて見えにくい社会構造を生み出しています。
恣意的な運用と在中邦人の不安
最も深刻なのは、こうした法律が恣意的に運用される可能性があるという点です。
たとえば、外交関係の悪化や国内の政治的緊張を背景に、外国人が「見せしめ」として拘束されるケースも疑われています。
今回のアステラス製薬社員の件でも、判決の内容が公開されず、どのような証拠があったのかが不明なまま刑が確定したことで、「誰でも同じような状況になり得るのではないか」という懸念が広がっています。
実際に在中邦人の中には、「どこまでが安全な行動なのか分からない」「写真を撮るのもためらうようになった」といった声が多く聞かれます。
さらに、日本国内でも中国出張や赴任を避ける動きが企業内で強まりつつあり、経済や人的交流の停滞にもつながりかねません。
こうした不安定な環境下で生活する日本人にとって、反スパイ法の影響は単なる法制度上の問題ではなく、日々の安心や自由に直結する深刻な課題となっています。
まとめ
アステラス製薬の日本人社員に下された有罪判決は、単なる一企業の問題にとどまらず、中国における「スパイ罪」の運用実態とそのリスクを浮き彫りにしました。
中国の反スパイ法は、2023年の改正以降、適用範囲が大きく広がり、「国家の安全や利益」に関わるとみなされる行為であれば、外国人であっても処罰の対象となりうるようになりました。
問題は、その「基準」が極めてあいまいで、写真撮影や資料の持ち出しといった、日常的で無害に見える行為さえも、当局の判断ひとつでスパイ行為とされてしまう点にあります。
軍港の写真、昆虫の採取、地質調査、アンケート調査──こうした事例のいずれもが、中国では摘発対象になっているのです。
そのため、在中日本人だけでなく、出張や観光、留学などで中国を訪れるすべての人が、無意識のうちにリスクに晒されているとも言えます。
法律の不透明さに加えて、裁判手続きの閉鎖性、外交的背景による恣意的な拘束など、「いつ、誰が」巻き込まれてもおかしくない状況が続いています。
中国で活動する際には、従来以上に慎重な行動が求められます。同時に、国としても企業としても、現地の法制度や安全情報を正しく理解し、万一の事態に備える体制を整える必要があります。
この問題は「対岸の火事」ではなく、私たちひとりひとりにとっても無関係ではないのです。
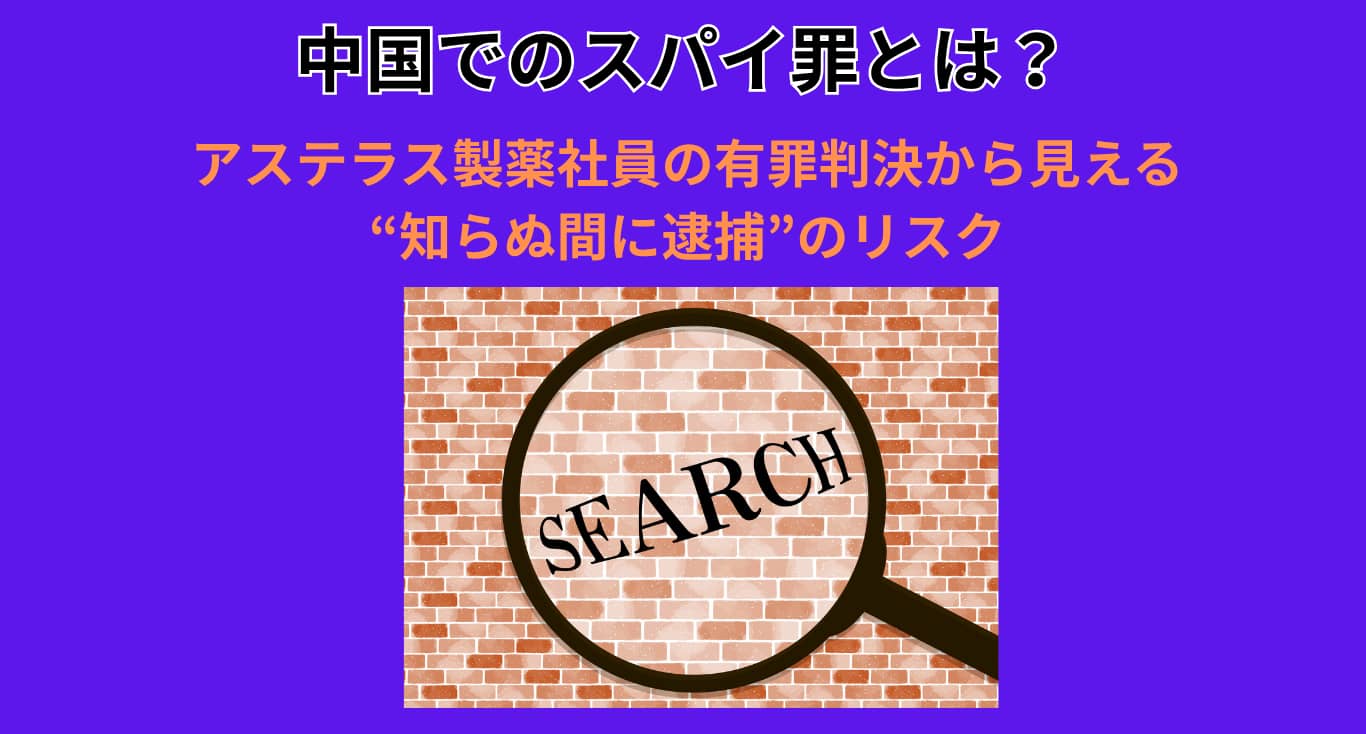
コメント