かつて日本の部活動では、「愛のムチ」という言葉のもとに体罰やしごきが当たり前のように行われていました。
殴る・蹴るといった暴力だけでなく、人格否定や理不尽な上下関係、常軌を逸した命令によって、多くの子どもたちが心身に深い傷を負ってきました。
本記事では、当時の証言や体験談をもとに、部活動に潜む暴力の実態とその社会的背景を振り返りながら、いま私たち大人が考えるべき課題を探っていきます。
はじめに

部活動に潜む「愛のムチ」という名の暴力
かつて日本の学校や地域のクラブ活動では、「愛のムチ」という言葉が指導の名のもとに使われてきました。
殴る、蹴るといった直接的な体罰や、ケツバットのような行為は「しごき」と呼ばれ、当然のように受け止められていた時代もありました。
実際に「退部を申し出た生徒が顧問に殴られ、顔面に3カ月の重傷を負った」といった証言や、「水分補給を禁止され、竹刀や靴底で太ももを叩かれた」という声は、その異常さを如実に物語っています。
こうした体験は単なる過去の出来事ではなく、いまなお多くの人の心に深い傷を残しています。
トラウマとして残る体験談と社会的背景
体罰や理不尽なしごきは、身体的な痛みだけでなく、心に消えないトラウマを刻み込みました。
「同じミスをしても怒鳴られるのは自分だけ」「泣く暇もなかった」という証言からは、人格を否定され続ける苦しさが伝わってきます。
さらに「先輩に死んだハトを埋めさせられた」「体調不良を訴えると生理かどうかを確認されそうになった」といった常軌を逸した体験も寄せられています。
こうした背景には、勝利至上主義や旧態依然とした上下関係がありました。部活動は仲間と共に成長できる場である一方、その裏側には「伝統」や「指導」という言葉で正当化された暴力と支配が存在していたのです。
1.暴力が支配したグラウンドの現実

殴る・蹴るが当たり前だった時代の証言
かつての部活動では、殴る・蹴るといった暴力は「当たり前」のように行われていました。
千葉県の30代男性は「ケツバットがあったが愛のムチだと思っていた」と振り返りますが、多くの声はそうした行為を「しごき」ではなく「暴力」として記憶しています。
埼玉県の70代男性は「退部を申し出た生徒が顧問に殴られ、顔面に3カ月の重傷を負った」と証言し、福岡県の女性は「水分補給を禁止され、竹刀で太ももを叩かれ出血した」と振り返っています。
これらは日常的に繰り返され、恐怖が練習や試合の一部となっていたのです。
顧問による体罰と事件化されたケース
暴力は一部で事件として取り上げられることもありました。
愛知県の50代女性は「グラウンドの掃除中、少しの汚れを理由に顧問から何度も殴られた」と語り、「怖くて何も言えなかった」と当時の空気を振り返ります。
さらに東京都の男性は、兄弟が通っていた高校で「野球部員が体育教師2名にリンチを受け、鼓膜を破られた」と証言しています。
これほどの暴力があっても、大きな問題として扱われず、被害者の恐怖や痛みだけが残されました。
軽すぎる処分と記憶の風化
驚くべきは、加害者となった教員への処分が極めて軽かったことです。
先述の東京都の証言では、暴力をふるった教師は軽い処分を受けただけで、その後は大学教授にまでなったといいます。
「暴力犯罪があったにもかかわらず制裁が異常に軽く、今では忘れられつつある」との声は、社会全体がこうした出来事を曖昧に済ませてきたことを示しています。
被害者にとっては忘れられない記憶でも、時間とともに「仕方のない時代のこと」として片付けられていく現実があるのです。
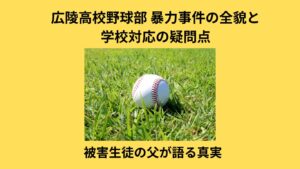
2.逃げ場のない精神的追い込み

人格否定や理不尽な怒鳴り声
暴力は殴る・蹴るといった身体的なものだけではありません。多くの部員が、顧問や指導者から浴びせられる言葉の暴力に苦しんでいました。
千葉県の50代女性は「みんなが同じミスをしても、怒鳴られるのは私だけだった」と語ります。
指揮棒で頭を叩かれたり、顔を平手打ちされたりする日々の中で、自分の存在を否定され続ける感覚に押し潰されていったといいます。
こうした理不尽な叱責は、心を委縮させ、部活を続ける気力を奪いました。
精神的な圧力で追い詰められた部員たち
一部の部活動では「強化合宿」と称し、人権を無視した練習が行われていました。
愛知県の30代女性は、山奥の小屋に閉じ込められ、過酷な練習を強いられたと証言しています。
また、中国地方の父親は「監督の罵声や意味のない人格否定により、2人の息子が退部に追い込まれた」と明かしました。
身体的な暴力がなくとも、逃げ場のない精神的圧力が部員の心をむしばみ、将来にわたって自信や人間関係に影を落とすことも少なくありませんでした。
家族や周囲にも及んだ影響
このような精神的追い込みは、本人だけでなく家族や周囲にも影響を及ぼしました。
「部活を辞めたい」と相談されても、家族は「根性が足りない」と突き放してしまったケースもあれば、逆に子どもが壊れていく姿を見て深く後悔する親もいました。
部活動の指導が子どもの人生を左右し、時には家庭にまで重い影を落とす現実は、多くの証言に共通して表れています。逃げ場のない空気の中で、子どもたちはただ耐えるしかなかったのです。
3.歪んだ上下関係と異常なルール
先輩からの理不尽な命令と屈辱
部活動の世界では、先輩・後輩の関係が絶対的なものとして存在していました。
岐阜県の30代女性は「高校2年生のとき、3年生の先輩に死んだハトを埋めてこいと命じられた」と証言しています。
単なる命令ではなく、恐怖や羞恥を伴う屈辱的な行為を強制されることが、上下関係を守るための“儀式”のように繰り返されていたのです。このような理不尽な命令は、部活を辞める自由すら奪い、子どもたちを縛りつけました。
「死んだハトを埋めろ」「生理の確認」などの異常行為
理不尽さは時に常軌を逸し、人格や尊厳を踏みにじる行為へと発展しました。
埼玉県の40代女性は「体調不良を訴えると、生理かどうかを確認するためにパンツを脱がされそうになった」と語ります。
また、練習中の水分補給を許されず、目の前で麦茶を砂場に捨てられ「飲みたかったら飲め」と砂まみれの液体を口に入れさせられる屈辱もあったといいます。
これらは指導とは無関係で、支配欲や集団内の歪んだ秩序によって生み出された異常な行為でした。
校則以上に強い先輩支配の構図
こうした上下関係は「校則」や「教師の指導」よりも強力で、部員の生活すべてを支配しました。
札幌の50代女性は「校則よりも、先生よりも、先輩の言うことが最強だった」と振り返ります。
閉ざされた部活動という小さな社会の中で、先輩の権威は絶対的で、声を上げることは許されませんでした。
その結果、理不尽なルールがまかり通り、誰もが沈黙することでその構造を維持してきたのです。
子どもたちにとっては「仲間と過ごす時間」であるはずの部活動が、むしろ恐怖と屈辱を植え付ける場となってしまいました。
まとめ
部活動は本来、仲間とともに努力し、喜びや達成感を共有する貴重な経験の場であるはずです。
しかし現実には、「愛のムチ」という言葉のもとで暴力やしごきが正当化され、心身を深く傷つけられた人々が数多く存在してきました。
殴る・蹴るといった身体的暴力だけでなく、人格を否定する言葉や逃げ場のない精神的追い込み、さらには先輩による異常な命令や屈辱的なルールがまかり通ってきたことは、社会全体が直視すべき問題です。
一方で、部活動を「楽しかった思い出」と語る人がいるのも事実です。
だからこそ、部活動そのものを否定するのではなく、子どもたちが安心して活動できる環境をどう作るかが求められています。
勝利至上主義や古い慣習に縛られるのではなく、子どもたち一人ひとりの成長や尊厳を大切にする指導体制が必要です。
寄せられた声の中には「社会に出るための上下関係を学べた」という肯定的な意見もありましたが、それが暴力や理不尽を正当化する理由になってはいけません。
部活動は、未来を担う子どもたちにとって安全で豊かな学びの場であるべきです。今回の証言や事例を通じて、私たち大人が問い直すべきなのは、「伝統」という名の暴力を許すのか、それとも子どもたちの笑顔と健やかな成長を守るのかという点に尽きるでしょう。
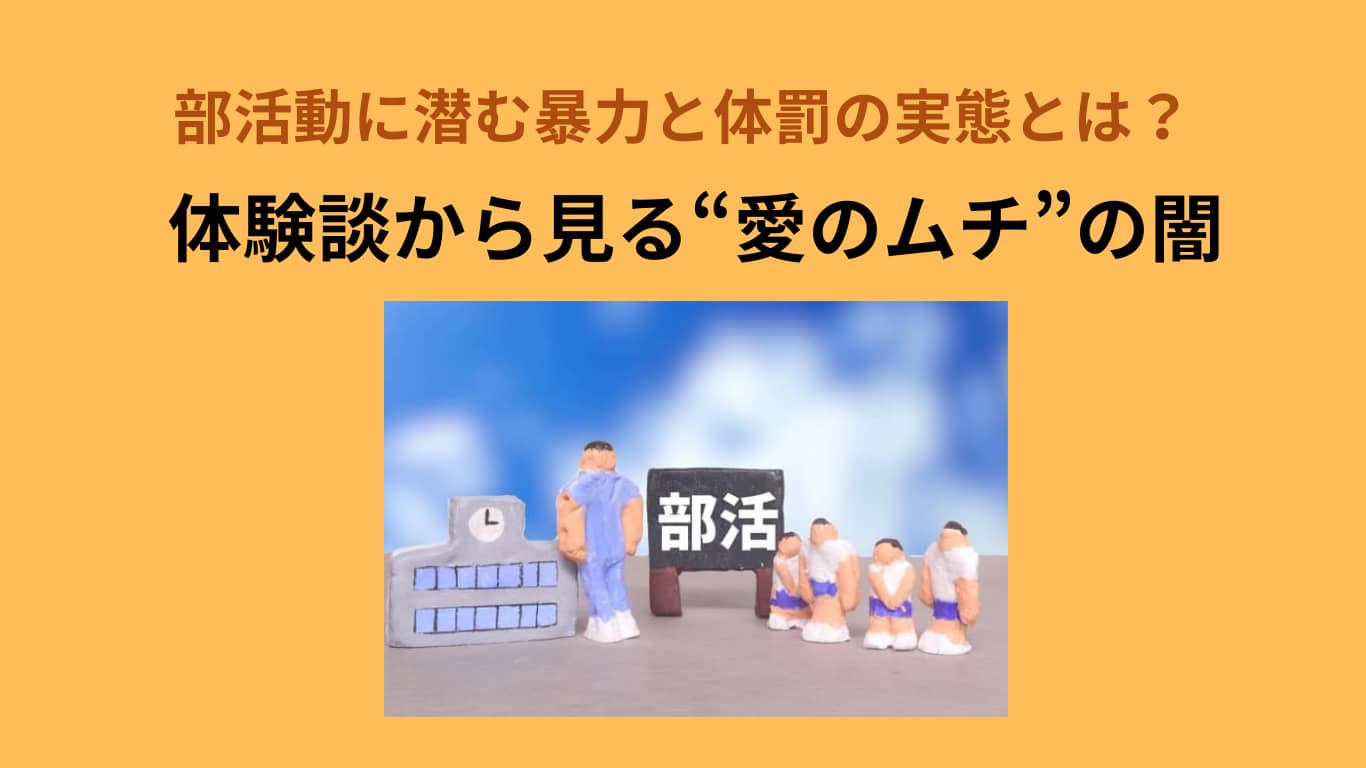
コメント