NHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第16回で突如登場した謎の男「丈右衛門」。
その不気味な存在感と静かな登場シーンは、前作『鎌倉殿の13人』の“善児”を思い出した方も多いのではないでしょうか?SNSでは「善児の再来か?」「また出てきそうで怖い…」と話題沸騰中です。
本記事では、丈右衛門の正体や平賀源内との関係、さらには背後に見える一橋治済の影まで、視聴者目線で深掘りしていきます!
はじめに

江戸の闇に浮かぶ「丈右衛門」という謎の存在
NHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第16回で突如として姿を現し、血のにおいを残して姿を消した謎の男「丈右衛門」。
平賀源内の獄死に深く関わったと思しきこの男は、源内の家に現れた際、すでに不気味な雰囲気をまとっていました。
特に蔦屋重三郎とすれ違うシーンで流れた“鳥の鳴き声”の演出は、視聴者の背筋をぞっとさせるのに十分なもの。しかもその後、源内に罪を着せるかたちで共謀者を斬ったとされ、真相が見えぬまま闇に消えていきました。
ドラマ内では「松本秀持に仕えていた丈右衛門」として紹介されましたが、源内のセリフからは「名前を騙った別人」であることが示唆されます。
さらに、源内の物語が書かれた血塗れの書面が、一橋治済の庭で焼かれていたことから、「丈右衛門」が政治的陰謀に関与している可能性も浮かび上がってきました。
SNSで囁かれる「善児再来説」とその根拠とは

放送直後からSNSでは「丈右衛門=善児説」が急浮上。「忍び寄る足音がなかった」「クレジットが“丈右衛門だった男”って何!?」「これって“鎌倉殿の13人”の善児(梶原善)じゃん」といった声が数多く投稿されました。
善児とは、前作『鎌倉殿の13人』で梶原善が演じた寡黙で冷酷な刺客であり、視聴者に強烈な印象を残した存在です。
今回の丈右衛門も、名前を隠し、静かに獲物に近づき、証拠を残さず去るというまさに「名もなき暗殺者」像にピタリと重なる存在です。
特にオープニングクレジットで「丈右衛門だった男」と意味深に表記されたことは、多くのファンにとって“今後また登場する”という不穏な期待を抱かせました。
丈右衛門は単なる一話限りの登場人物なのか、それとも幕府の裏側を動かす「影の存在」なのか──物語の進行とともに、その正体に迫っていく必要があります。
1.丈右衛門とは何者だったのか
初登場シーンと不気味な鳥の鳴き声の演出
丈右衛門が初めて姿を現したのは、蔦重が平賀源内のもとを訪ねた場面。不吉な空気が漂う中、先客として現れた丈右衛門は、旗本の屋敷普請の図面を依頼するという名目で源内の家に入り込んでいました。
注目すべきは、彼が廊下で蔦重とすれ違った瞬間に流れた不気味な鳥の鳴き声。
セリフもなく、ただ目を光らせて通り過ぎるだけの演出にもかかわらず、視聴者の間には「恐怖を感じた」「音楽の使い方が不穏すぎる」といった感想が多数上がりました。
演出としての“音”が、丈右衛門の異質さをより際立たせており、まさに「人ではない何かが来た」とすら感じさせるシーンでした。
姿や所作に派手な特徴はないにもかかわらず、ただそこに「いるだけ」で場の空気を支配する存在感。それこそが、丈右衛門という人物の“恐ろしさ”の始まりだったのかもしれません。
平賀源内に罪を着せた真の目的
その後、源内が気を失っている間に使用人が殺され、罪を着せられたことが明らかになります。
源内は獄中で、自身を陥れたのは「丈右衛門」だと証言しましたが、この丈右衛門、実は松本秀持に仕えていた人物の名を騙った“別人”である可能性が示唆されています。
つまり、最初から“なりすまし”で近づいていたわけで、単なる通り魔的な犯行ではなく、計画性のある行動だったと考えられます。
さらに、源内のもとに謎の人物が差し入れた「湯」があったことも、視聴者の間で話題に。毒や薬が仕込まれていた可能性が否定できず、丈右衛門が命を奪うために送り込まれた暗殺者だったという推測に拍車をかけました。
使用人殺しから罪のなすりつけ、証拠隠滅に至るまで、すべてが精密に設計された一連の動きに見えてきます。
クレジットに現れた「丈右衛門だった男」の意味
そして視聴者をさらに混乱させたのが、第27回のオープニングクレジット。
「丈右衛門」ではなく、「丈右衛門だった男」(矢野聖人)と表記された矢野聖人の名前。この“だった”という言葉に込められた意味は何なのか?──名前を捨てたのか、あるいは他人に押し付けたのか、あるいは正体そのものが別物だったのか…。
この表記が「正体不明性」をあえて強調した演出であると考えれば、彼が単なる登場人物ではなく、物語の中で形を変えながら何度でも現れる“影”のような存在である可能性も。
まさに、視聴者の中に「また出てくる」という不安と予感を残すための仕掛けだったのです。
2.一橋治済との関係性を探る
血染めの書面が一橋家の庭で燃やされる意味
平賀源内の家から消えた「血のついた物語の書面」。この重要な証拠が、その後なんと一橋治済の庭先で燃やされていたという衝撃の展開。
無言で焚かれるその様子に、視聴者は戦慄しました。「なぜ一橋家が関わっているのか?」という疑問が一気に浮上し、丈右衛門が単独で動いている存在ではなく、もっと大きな力の手先なのではないかという見方が強まりました。
書面は源内が生前に書き綴った物語、あるいは政敵にとって不都合な情報が含まれていた可能性があります。
あえて「燃やす」という行動に出たということは、誰かに見られるリスクを冒してでも証拠を消す必要があったということ。
つまり、治済側が“情報を消す”必要があるほど、この一件は政治的にも重要だったという証左でしょう。
丈右衛門の背後に見える治済の影
もうひとつの注目点は、丈右衛門と治済の関係性です。丈右衛門が現れてから後の展開を注意深く追うと、その背後には常に一橋治済の存在がちらつきます。
例えば、源内が逮捕された背景に政治的な陰謀があったことを示すように、田沼意次が丈右衛門の素性を探ろうとした際、息子の意知がその調査を抑え込もうとする場面が描かれました。
その意知を“罠”にはめるような形で仕立てられたのが、家治との「狩り」のエピソード。
佐野を引き立てたい意知に同行させられた一件は、一見すると穏やかなシーンですが、その後に丈右衛門だった男が佐野のもとを訪れ、「意知が証拠を隠した」と嘘の証言をする流れへと続きます。
ここで意知の信用を落とす工作が進められていることがわかり、治済の意向が強く反映されていると考えざるを得ません。
意知を陥れる「狩り」の真相とその策略
「獲物が見つからない」――それだけなら単なる失敗にすぎなかったはずの狩りの場面。
しかし、この小さな違和感が、後に大きな陰謀の一部だったことが判明します。丈右衛門だった男が佐野に「意知が獲物を隠した」と告げる場面は、その前の狩りシーンと対になって描かれ、意図的な仕込みだったことがはっきりします。
意知の失墜は、田沼家の影響力を削ぎたい一橋治済にとって都合の良い展開。丈右衛門=治済の刺客説がより濃厚になっていく瞬間です。
さらに“名を名乗らない男”として再登場した丈右衛門だった男が、佐野のもとに再び接触するなど、彼の動きは治済の意向を代弁するかのようでもあります。
つまり、丈右衛門は「一橋治済が陰で動かす存在」としての役割を担っており、表舞台では描かれない幕府内部の権力争いを示す“影の使者”なのです。
3.善児との共通点と視聴者の考察
音もなく近づき、正体を隠す暗殺者像
丈右衛門が視聴者に強烈な印象を与えた最大の理由は、その“静けさ”にありました。
登場シーンでは足音ひとつ立てず、まるで影のように現れては消える。声を荒げることもなく、しかし確実に相手を追い詰めていく。これは『鎌倉殿の13人』に登場した暗殺者・善児のスタイルと酷似しています。
善児もまた、無表情で任務を遂行し、語ることは少なく、しかしその一挙手一投足に血の匂いが漂っていました。
丈右衛門が源内に近づくとき、そして佐野に獲物を差し出し嘘を吹き込むとき、その目の奥には善児と同じような冷徹さが光ります。
決して目立たず、しかし誰よりも影響力を持つ、そんな“裏の仕事人”の姿が、視聴者の記憶を善児に重ねさせたのでしょう。
「鎌倉殿の善児」へのオマージュか
制作側が意図的に「善児」を思い出させるような演出を行っているのではないか、という声も多く見られます。
特に、「丈右衛門だった男」という謎めいたクレジット表記は、視聴者の好奇心を強く刺激しました。
『鎌倉殿』では、善児が語らず、語らせず、最後までミステリアスな存在だったことから、同じように丈右衛門も“名もなき暗殺者”として描かれているのでは?という考察がSNS上を飛び交いました。
NHK大河が過去作とのリンクを匂わせるケースは珍しくありません。「べらぼう」では物語上の繋がりはないものの、“善児的存在”を配置することで、現代の視聴者が持つ“記憶”や“イメージ”を活用して緊張感を生み出しているとも考えられます。これは演出として非常に巧みで、過去作品のファンをもう一度引き込む狙いがあったのかもしれません。
「また出てきそう」──ネットの反応まとめ
丈右衛門が姿を消したあとも、ネット上では「絶対また出てくる」「善児も最初はあっさりだったし」「こういうヤツが最終話で要人を暗殺するんだよ…」といったコメントが相次ぎました。
中には「一橋治済の手駒として何度も顔を変えて登場するのでは?」という、スパイ的存在としての再登場を予想する声も。
また、蔦重とすれ違った時の“目”の演技が「本当に怖かった」「人の目じゃない」「まばたきひとつしなかった」と注目されており、視覚的な恐怖が強く印象づけられていることがわかります。
こうした細かな演出の積み重ねが、丈右衛門というキャラクターを“ただの殺し屋”では終わらせない深みある存在へと昇華させています。
丈右衛門が次に姿を現すとき、それは物語が大きく動く合図かもしれません。視聴者の「また出てきそう」という直感は、決して見当違いではないでしょう。
まとめ
謎の刺客「丈右衛門」は、ただの登場人物ではなく、『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』の物語そのものを陰で揺るがす存在として描かれています。
音もなく近づき、目だけで圧をかけるその姿に、視聴者は『鎌倉殿の13人』の善児を重ねざるを得ませんでした。
平賀源内に罪を着せた巧妙な罠、血の付いた証拠を焼く治済の庭、そして田沼意知を陥れる「狩り」のシナリオ。
そのすべてに丈右衛門の影がちらつきます。彼は一橋治済の手先として動いている可能性が高く、まさに“江戸の闇”を象徴する暗殺者です。
クレジットで「丈右衛門だった男」と名付けられた演出が示すように、彼の正体は依然として霧の中。
しかし、視聴者の多くが感じている「また出てくる気がする」という予感こそが、このキャラクターの真の恐ろしさを物語っています。
蔦重、そして物語全体の命運を握る「影の存在」──丈右衛門が再び姿を見せるとき、『べらぼう』は決定的な転機を迎えるかもしれません。
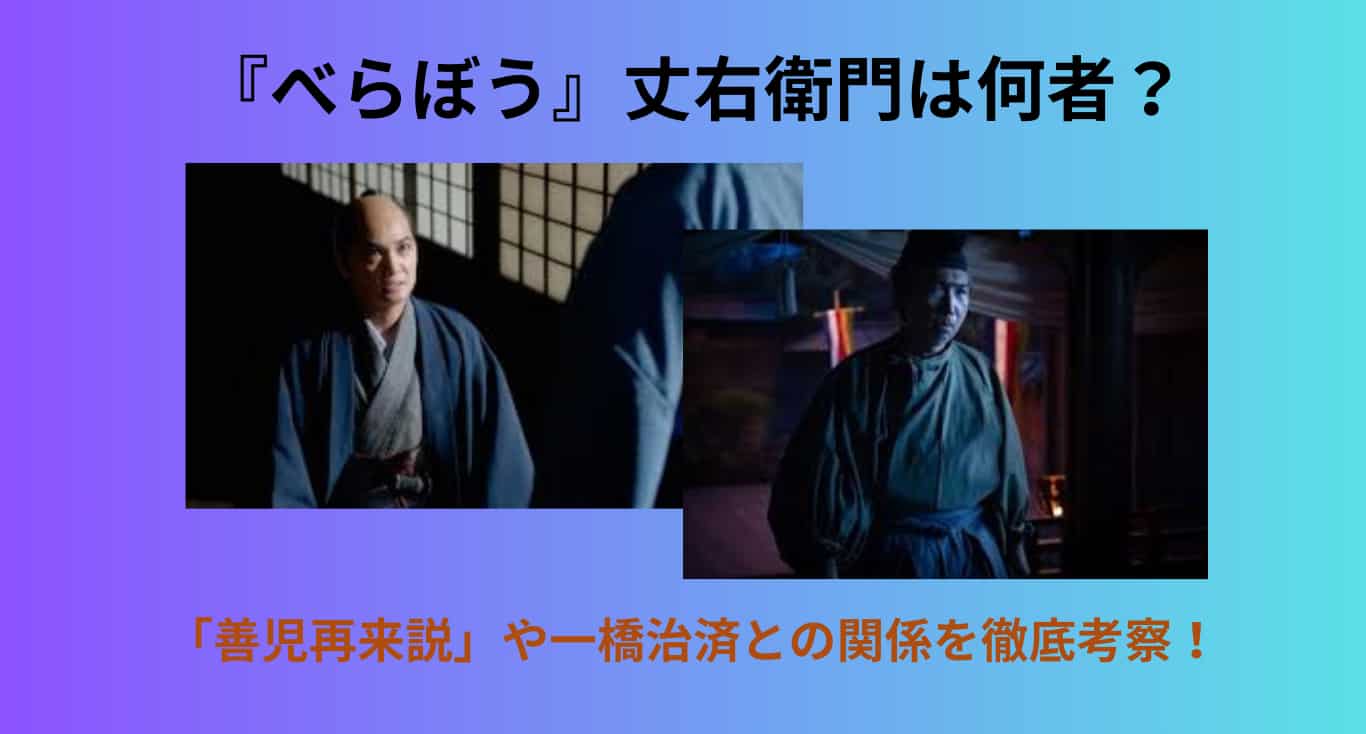
コメント