ブドウの高級品種「シャインマスカット」をめぐり、農林水産省がニュージーランドへのライセンス供与を検討していることが明らかになりました。
「また海外に売り渡すの?」──SNSで非難が飛び交っています。
小泉進次郎農水相は「産地の理解なく進めることはない」と発言しましたが、「後手に回っている」との声が殺到。なぜここまで炎上したのか、産地の抗議と政策の背景を整理してお伝えします。
はい、背景を整理します。
シャインマスカットのニュージーランドへのライセンス供与は、ニュースが出た直後から X(旧Twitter)で強い批判が集まっています。その主な理由は次の通りです。
1.ライセンス供与検討の発端
農水省は、海外で違法に栽培される日本の果樹品種を抑止するため、「正規のライセンス供与」という新たな政策を推進し始めました。対象の第一号として浮上したのが「シャインマスカット」。
ニュージーランド企業からの相談を受け、供与を前向きに検討していることが明らかになりました。
この動きは「流出防止策」としては理にかなっている面もありますが、国内農家にとっては大きな不安要素を孕んでいました。
2.山梨県知事の抗議
9月25日、山梨県の長崎幸太郎知事が国会内で小泉農水相と面会。
「輸出ができない中でライセンスが供与されれば、生産者が大きな打撃を受ける。せめて同じ土俵で対等な競争をさせてほしい」
と強調し、まずは国産シャインマスカットの輸出体制を整備することが先決だと訴えました。
この発言はX上で「当然だ」「順序が逆だ」と多くの共感を呼び、農水省への不信感が高まりました。
3.小泉農水相の発言と反発
翌26日の会見で小泉農水相は、
「産地の理解が得られない状況の中では、海外許諾を進めることはない」
と説明。表向きには「産地合意を重視する」姿勢を示しました。
しかしSNSでは、
- 「そもそもなぜ産地と十分に相談する前に海外供与を検討したのか」
- 「火の手が上がってから『理解なしでは進めない』と言うのは後追い対応」
- 「ブランドを守ると言いつつ、また海外に売り渡そうとしている」
といった批判が殺到。小泉氏の発言は火消しどころか「後手に回った」と受け止められました。
🔥 非難が殺到している理由
1. 「また国外に売り渡すのか」という感情的反発
- すでに過去、日本が海外登録を怠ったことで中国・韓国などに流出し、安価なシャインマスカットが世界に出回ってしまった経緯があります。
- 消費者や農業関係者から「同じ失敗を繰り返すのでは」「国のブランドを守る気があるのか」という怒りが噴出しました。
2. 産地の不利益に対する懸念
- 日本の生産者は輸出の際に植物検疫などの制約で不利な立場に置かれています。
- 「自国産は輸出が難しいのに、外国企業にはライセンス供与するのはおかしい」という不公平感が非難の的になっています。
- 山梨県知事が小泉進次郎農相に「輸出体制整備が先」と訴えた点が、そのままSNSで共感を呼びました。
3. 「産地軽視」「農家を犠牲にする政策」との perception
- 農水省は「国際的な監視体制整備」「海外での質の保証」を目的に説明しましたが、
Xでは「結局、農家を守るよりも外資に道を開くのか」「農政の犠牲になるのはいつも農家」といった声が目立ちます。
4. タイミングの悪さ
- 国民感情として「円安・物価高」「農家の収益難」など国内課題が大きい中で、海外企業への供与を検討する報道が出たことが火に油を注ぎました。
- 「国産ブランドを育てるより、外国にいい顔をしている」という印象が批判に直結しました。
📌 まとめ
非難の核心は、
- 「海外流出で損をしたのに、なぜさらに海外に譲るのか」
- 「輸出できない国内農家が不利になるのに、順序が逆だ」
という 不公平感・不信感 にあります。
| 立場 | 典型的な意見・投稿例 |
|---|---|
| ポジティブ | 「海外で正規ライセンスを与えることで違法流出を防げるなら前進だと思う」 「市場拡大や周年供給でブランド価値を維持できるのでは?」 「日本産と輸出先が競合しないなら共存も可能かも」 |
| ネガティブ | 「また海外に売り渡すのか。ブランドを守る気があるのか」 「国内農家は輸出できないのに、外国に供与するのは不公平」 「農家を守らず外資に譲る農政なんて本末転倒」 「過去の流出で苦労したのに、なぜ同じことを繰り返す?」 |
| 中立・様子見 | 「農水省の説明どおり、日本向け輸出と競合しないなら検討の余地あり?」 「ただし輸出体制が整っていないのは確か。順序の問題だと思う」 「産地合意なしに進めないと言っているので、まだ決定ではない」 |
シャインマスカット出来事年表
| 年月 | 出来事 | 内容・背景 |
|---|---|---|
| 1980年代後半〜 | 開発開始 | 農研機構が約30年かけてシャインマスカットを育成。 |
| 1988年 | 交配 | 「安芸津21号」×「白南」の交配を実施。 |
| 2006年 | 品種登録(国内) | 日本で品種登録。ただし海外登録は行わず、国際的保護は期限切れに。 |
| 2010年代〜 | 海外流出 | 中国・韓国で無断栽培・輸出が拡大。日本産の競争力低下が深刻化。 |
| 2020年12月〜2022年4月 | 改正種苗法 施行 | 海外持ち出し制限・自家増殖の許諾制を導入。違法流出防止を強化。 |
| 2025年4月 | 基本計画 更新 | 政府の「食料・農業・農村基本計画」に「海外ライセンス供与」を初めて明記。 |
| 2025年9月上旬 | 農水省が山梨県へ説明 | ニュージーランド企業からの相談を受け、ライセンス供与を前向きに検討していると報告。「日本向け輸出は想定せず」と説明。 |
| 2025年9月25日 | 山梨県知事 抗議※1 | 長崎幸太郎知事が国会内で小泉進次郎農相に要請書を提出。「輸出体制の整備が先」と抗議。 |
| 2025年9月25日 | ロイター報道 | ライセンス供与を農水省が検討中と国際的に報じられる。初の供与案件となる可能性に注目が集まる。 |
| 2025年9月26日 | 農相 会見 | 小泉農相が「産地の理解が得られない状況では進めない」と表明。供与は未決定。 |
💡
※1 誤解されやすいポイント
山梨県の抗議はライセンス供与そのものへの反対ではなく、
輸出体制が整わない状況で海外に供与すれば、日本産だけが不利になるという点への反発でした。
「輸出ができない中でライセンスが供与されれば生産者が大きな打撃を受ける。
せめて同じ土俵で対等な競争させてほしい」
― 山梨県・長崎幸太郎知事(ロイター報道より)
知事は「まず輸出環境の整備を優先すべき」と求めています。
現時点(2025年9月26日): ライセンス供与は検討段階。産地(山梨県など)は強く反発しており、農相は「合意なく進めない」と明言。実現には時間がかかる見通し。
シャインマスカット違法流出の経緯(時系列)
そもそも農水省が「海外ライセンス供与」を打ち出すことになった経緯を見てみました。
現在の「シャインマスカット違法流出」の状況を整理しますね。
1. 海外登録されなかった経緯
- シャインマスカットは2006年に日本国内で品種登録されましたが、
海外での品種登録(UPOV条約に基づく国際登録)を6年以内に行わなかったため、
国際的な知的財産の保護が切れてしまいました。
| 年代 | 出来事 | 影響 |
|---|---|---|
| 2006年 | 日本で品種登録(国内のみ)。 | 海外登録せず → 国際保護は6年で切れる。 |
| 2010年代 | 苗木・種苗が流出し、中国・韓国で無断栽培。 | 現地で大規模生産 → 東南アジアへ輸出開始。 |
| 2020年代 | 「陽光玫瑰(中国産)」などが市場を席巻。 | 日本産より安価で販売 → ブランド毀損、価格下落。 |
2. 海外での無断栽培
- その後、中国や韓国を中心に苗木や種苗が流出し、無断で大規模栽培されるようになりました。
- 中国では「陽光玫瑰(Yangguang Meigui)」という名称で市場に出回り、アジア各国へ輸出されています。
- 韓国でも無断増殖が進み、香港・東南アジア市場で「韓国産シャインマスカット」として販売されるケースが確認されています。
| 国・地域 | 現状 | 日本への影響 |
|---|---|---|
| 中国 | 「陽光玫瑰」としてブランド化。東南アジアへ大量輸出。 | 日本産の高級イメージが薄れる。価格競争で不利に。 |
| 韓国 | 無断増殖が広がり、香港・東南アジアへ輸出。 | 「韓国産シャインマスカット」が日本産と競合。 |
| その他(東南アジア等) | 現地市場で「安価なシャインマスカット」として流通。 | 高級ブドウの位置づけが揺らぐリスク。 |
3. 日本農家への影響
- アジア市場に出回る「中国産」「韓国産」が日本産よりも安価なため、
ブランド価値の希薄化・価格下落につながっています。 - 農水省はこれによる損失を 年間100億円以上 と試算しています。
4. 品質とブランドの問題
- 無断栽培品は品質基準がバラバラで、糖度や粒の大きさに差があるため、
「シャインマスカット=必ず高品質」という信頼が揺らぐリスクがあります。 - 日本産を指名買いする富裕層もいますが、市場全体のブランド力低下は避けられません。
| 項目 | 日本国内 | 中国・韓国など海外 |
|---|---|---|
| 品種保護 | 国内登録あり(2006年〜) | 国際登録なし → 保護切れ |
| 栽培 | 許諾制(改正種苗法で厳格化) | 無断栽培・大規模生産 |
| 輸出 | 植物検疫で制約あり | アジアへ大量輸出 |
| 価格 | 高級品(数千円〜1万円/房) | 日本産より安価で流通 |
| 日本への影響 | 輸出拡大に壁 | ブランド毀損・市場競合 |
🔹 現状への対応
- 日本は 改正種苗法(2020〜2022年施行) で新たな品種の流出を防ぐ仕組みを整備しました。
- しかし「シャインマスカット」はすでに保護切れのため、
正規ライセンス供与による“後追い対策” が模索されています。
ポイント: 農水省は違法流出による損失を年間100億円以上と試算。
このため「正規ライセンス供与」による管理体制の整備が急務とされています。
🔹 正規のライセンス供与とは?
- 農水省が品種育成権者(今回は農研機構など)と調整し、海外の事業者に対して正式に栽培権を与えることです。
- ライセンス契約に基づき、対象国の生産者は合法的にシャインマスカットを栽培できるようになります。
- この仕組みを通じて、
- 違法に持ち出されて無秩序に栽培される事態を抑止
- 品質・ブランドの基準を維持
- 日本側にライセンス料(知的財産収益)が入る
といった効果が期待されます。
正規ライセンス」と「違法流出」の違い
| 項目 | 正規ライセンス供与 | 違法流出(現状多い) |
|---|---|---|
| 栽培 | 政府・育成者が許可 | 無断持ち出し |
| 品質管理 | 基準に沿った監視あり | バラバラ(品質劣化の恐れ) |
| 収益 | ライセンス料が日本に還元 | 日本には還元されない |
| 輸出 | 日本産と競合しない市場を想定 | 競合し、日本産の価格を押し下げる |
🔹 なぜ批判されるのか?
- 国内農家は輸出に必要な植物検疫の壁があり、不利な条件下にある
- そんな中で「海外にだけ正規ライセンスを与えるのは不公平」と見られる
- 「国内の輸出体制を整備してからにすべき」という産地の声が強い
👉 まとめると、「正規のライセンス供与」とは “日本政府が公式に許可して管理する海外栽培権” のことです。
メリットはブランド保護と収益還元、デメリットは国内産地との利害衝突。
シャインマスカットの場合は?
- シャインマスカットは 海外での権利保護が切れている(国際登録なし)ため、
→ 中国や韓国などでの無断栽培は 「違法」ではなく“合法”扱い になってしまっています。 - つまり、現地での取り締まり・罰則は事実上できないのが現状です。
🔹 日本国内での対策・罰則
1. 改正種苗法(2020〜2022年施行)
- 登録品種の 無断海外持ち出しは禁止
- 違反すると 10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下) が科されます。
- ただしこれは「これからの流出」を防ぐためのもの。
- シャインマスカットはすでに海外保護切れなので「適用外」です。
2. 水際での取り締まり
- 種苗や苗木の 輸出検査・持ち出し規制 を強化。
- 農水省・税関が連携し、違反品を摘発する体制を整えました。
3. 海外での正規ライセンス供与
- 違法に流出した国(中国・韓国など)には手を出せませんが、
- 新たに別の国で無秩序に広がるのを防ぐため、正規ライセンス供与という「後追い対策」を実施。
- これにより、「勝手に作られる」状況を少しでもコントロール下に置く狙いがあります。
🔹 海外での罰則は?
- 中国や韓国では、すでに知的財産権が保護されていないため、無断栽培は現地法で“合法”扱い。
- 日本からの訴訟も 権利失効のため成立しません。
- そのため「取り戻す」ことは不可能で、事実上「失敗の教訓」として位置づけられています。
📌 まとめ
- 日本国内:改正種苗法で新たな流出を厳罰化(懲役・罰金あり)
- 海外既存流出:権利切れのため取り締まり不可 → 有効な罰則なし
- 今後の対策:正規ライセンス供与で後追い管理、新品種は必ず国際登録
👉 つまり、「これからは守れるが、シャインマスカットは後追いしかできない」という状況です。
山梨県知事が指摘した「輸出体制」とは?
1. 植物検疫の壁
- 日本産シャインマスカットを海外に輸出する際、輸入国ごとに厳しい植物検疫(害虫・病気チェック)が課されます。
- そのため輸出に時間とコストがかかり、出荷時期がずれる・品質が落ちるといった問題が発生。
- 知事は「この検疫制度を緩和・改善しない限り、海外市場で日本産が不利になる」と訴えています。
2. 物流・輸送の整備
- ブドウは生鮮品のため、鮮度維持のための 低温物流(コールドチェーン) が不可欠。
- 輸送費が高騰している中で、海外に安定的に出荷できる輸送インフラが十分ではありません。
- 知事は「輸送ルートの拡充」「輸送コスト補助」といった政策的支援を求めています。
3. 輸出市場の開拓と販促
- 中国・韓国産の安価な「偽シャインマスカット」が市場に広がっているため、
「日本産である」ことを差別化してブランド力を高める販促活動 が必要。 - 政府の輸出促進施策(クールジャパン戦略・JETRO支援など)をさらに強化することを求めています。
4. 価格競争力の確保
- 日本産は高品質ですがコストも高く、輸出先での価格競争に弱い。
- 農家への補助やコスト削減策がなければ、「海外産に太刀打ちできない」という懸念があります。
🔹 知事の主張の核心
- 「国内の農家が輸出できない状況で、外国にライセンスを与えるのは不公平」
- まずは
- 植物検疫の調整
- 輸送・物流インフラの整備
- 販促・ブランド強化
を進めて、日本産シャインマスカットが輸出で戦える体制を作るべき、という立場です。
ポイント:山梨県知事の抗議は「ライセンス供与に絶対反対」ではなく、
輸出体制が整わないまま海外供与を進めると不公平という順序の問題を指摘しています。
5.まとめ
- Xでの批判の根っこ
→ 「日本の技術を海外にまた流出させるのか」「ブランドを守る気があるのか」という不信感。 - シャインマスカットの法的な現状
→ 海外ライセンス登録を怠ったため、すでに 国際的な保護は失効。
→ 中国や韓国での栽培は「違法」ではなく、現地では合法・公式に栽培されている状態。 - 政府の方針
→ この失敗を繰り返さないため、今後の品種は 正規の海外ライセンス供与で管理しようと方針転換。
→ 今回、ニュージーランドから申し出があり、第1号案件として検討している。 - 国内の課題
→ 日本産の輸出は植物検疫や物流体制の壁があり、まだ十分に整っていない。
→ そのため「市場に出たときに日本産が不利になるのでは」という懸念がある。 - 山梨県知事の抗議の本質
→ 「ライセンス供与そのものに反対」ではなく、
→ 「輸出体制が整わないうちに供与を進めると国内農家が負ける」という順序の問題を指摘している。
つまり、
- 過去の失敗(シャインマスカット流出)は取り返せない
- 今後は正規ライセンスで守ろうという政策転換
- しかし 国内輸出の準備が整わないまま供与すると、また日本の農家が損をする
- だから 山梨県知事は「順序を正せ」と抗議している
という構図です。
また。小泉農水相の発言が非難されたのは、
- 産地合意前に海外供与を検討したこと
- 国内輸出体制が整っていない中で海外に道を開こうとしたこと
- 説明が「後追い」に見えたこと
が原因です。
ライセンス供与は「違法流出防止」と「国際ブランド保護」の両面を持つ施策ですが、産地や消費者の不信を払拭することが不可欠です。
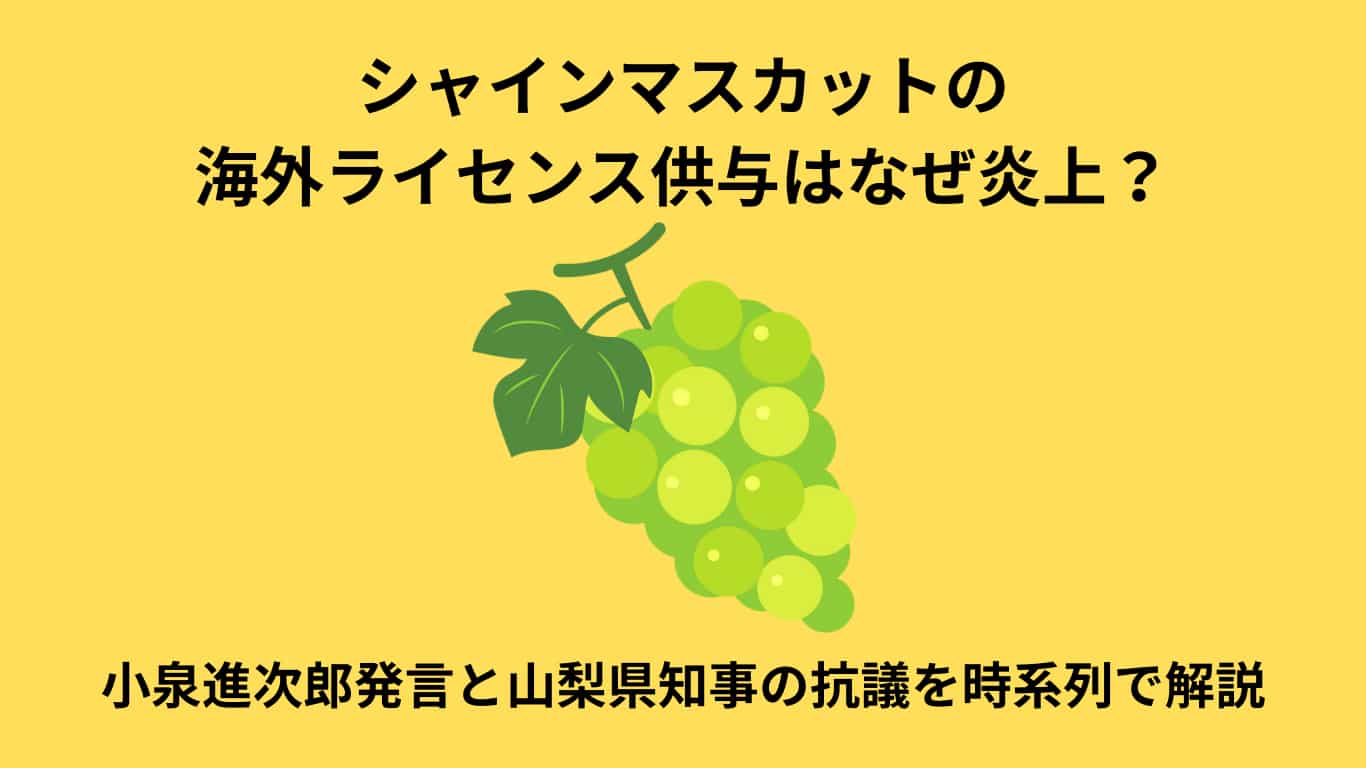
コメント