ワクチン後遺症で「元の体に戻りたい」と願いながら、救済に届かない人がいます。
めまいや強いだるさで家事も仕事も難しく、診断書や書類の費用はどんどん膨らむのに、申請は「評価不能」や“症状固定”の壁で止まってしまう——。
本記事では、現場で起きている負担の実態と、申請でつまずかないための記録・整理のコツ、周囲ができる具体的な支え方まで、生活の目線でお伝えします。
はじめに
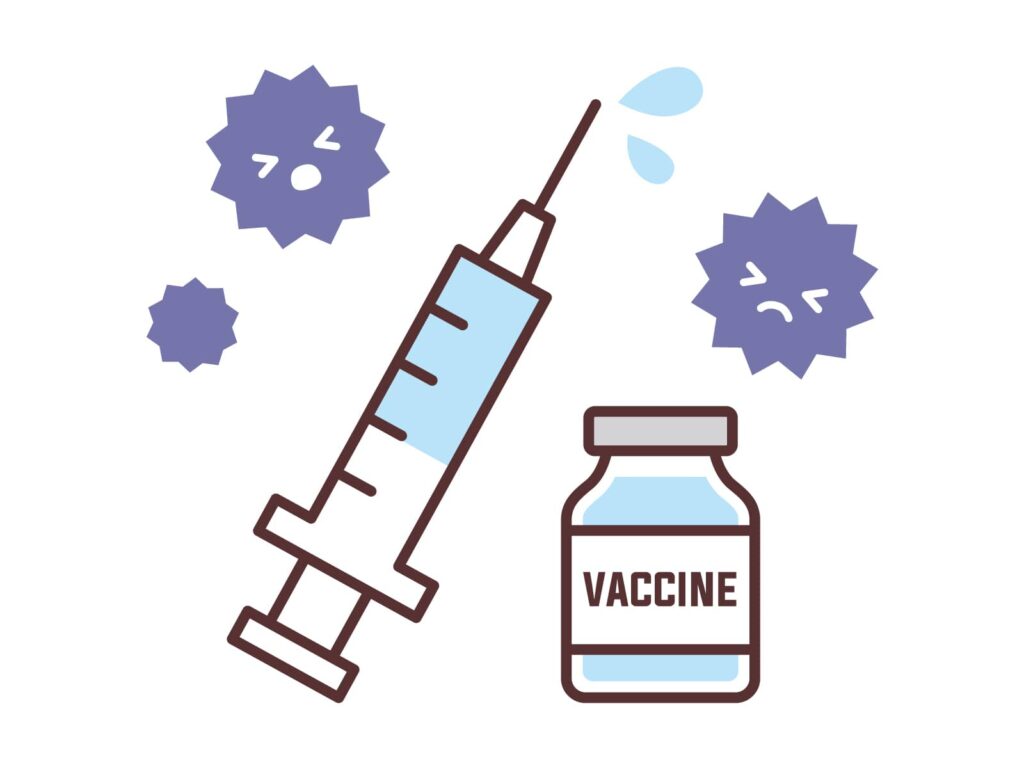
新型コロナワクチン後遺症をめぐる現状
新型コロナワクチンの接種が広く進められた結果、重症化を防ぐ効果があった一方で、一部の人々は接種後に長引く体調不良に悩まされています。
倦怠感やめまい、強い頭痛や動悸など、日常生活に大きな支障をきたす症状が続くケースが報告されています。
例えば、50代の元高校教諭の女性は、接種後に寝たきりとなり、自宅での生活もままならなくなりました。ご飯や洗濯などの家事ができず、トイレに行くのもはって進むほどの状態に陥り、仕事を続けることができなくなったといいます。
このように、生活そのものを奪うほど深刻な後遺症は、本人だけでなく家族にも大きな負担を与えています。
国の救済制度の課題と社会的関心
こうした人々を支えるために国には救済制度が存在しますが、実際に利用しようとすると数々の壁に直面します。
診断書を1通ごとに医療機関から発行してもらう必要があり、その費用は数千円から1万円にのぼります。通院歴が多い場合、診断書だけで数十万円規模の出費が必要になることもあります。
さらに、膨大な書類を提出しても「症状が固定していない」などの理由で申請が認められないケースも少なくありません。
自治体レベルでは「救済に値する」と判断されても、国が最終的に覆すこともあります。
この制度上の矛盾や対応の遅れは社会的にも注目され、SNSやニュースのコメント欄では「迅速な救済を求める声」や「副反応を軽視すべきでない」という意見が多く寄せられています。
ワクチン接種が国策として進められた以上、被害を訴える人々の声を無視できない状況になっているのです。
1.患者たちが直面する後遺症の実態

倦怠感やめまいに苦しむ日常生活の制約
はじめにで触れたように、最も多いのは「とにかく体が動かない」という強い倦怠感と、立ち上がった瞬間に視界がぐらつくめまいです。
朝、目覚ましは聞こえるのに体がベッドから起き上がれない。洗面所まで歩く間に息が上がり、途中で座り込む。買い物に出ても、店内を1周できずに引き返す──そんな“生活の細部”でつまずきが生まれます。
元高校教諭の女性は、炊事や洗濯を分割して行う「こま切れ家事」に切り替え、トイレまでは壁づたい、外出は車いすと杖を併用するといった工夫でしのいでいました。
調子の良い日は10分だけ散歩、悪い日は浴室へ行くのも難しい。症状の波に合わせて予定を変えざるを得ず、仕事復帰どころか「今日できること」を選ぶだけで精一杯という日々が続きます。
障害年金や救済制度で認められない現実
「なんとか働けるようになりたい」と申請しても、「症状が固定していない」「客観的な証拠が不足」などの理由で否認されるケースが目立ちます。
たとえば、寝たきり中心の生活でも、医師の勧めで“調子が良い日に短時間の散歩を試みた”という記録があると、「日常動作は可能」と評価されることがあります。
また、自治体が「認定に値する」と整理して国へ意見を送っても、最終判断で覆ることもあります。
本人からすると、良い日と悪い日の差が激しい“ゆらぐ障害”なのに、制度側は“いつも同じ状態”であることを前提に線引きしてしまう。そのズレが、救済までの距離をさらに広げています。
膨大な診断書・証明書取得の経済的負担
救済を申請するためには、通院した医療機関ごとに診断書や受診証明を集める必要があります。1通あたり数千円から1万円。複数科を回っていれば、合計はすぐに数万円、ケースによっては二桁万円に達します。
元教諭の女性は、本来40軒ほど受診したものの、「費用も体力も持たない」ため、特に支出の大きかった24軒分に絞って提出しました。
書類は段ボール1箱分に膨れ上がり、整理や郵送にも時間とお金がかかります。つまり「症状で働けない」→「収入が減る」→「申請のための費用が払えない」→「救済に届かない」という悪循環が生じやすいのです。
こうした現実は、単なる“書類の多さ”ではなく、患者にとって日々の生活費を削ってまで挑む重いハードルとして立ちはだかっています。
2.国と自治体の判断の違い
自治体が「認定すべき」と判断したケース
現場を担当する自治体は、患者の生活実態に近いところで情報を集めます。
たとえば、通院履歴や家族からの聞き取り、主治医の所見だけでなく、介護認定の記録、休職・退職の経緯、日常動作の困難さ(入浴・トイレ・移動の可否)まで重ね合わせ、「実質的に生活が成り立っていない」と評価すれば“認定すべき”と国へ意見を付します。
元高校教諭の女性のように、家事が「こま切れ家事」になり、トイレまで壁づたい・車いす・杖を併用してようやく移動できる、といった具体的事実は、自治体の担当者にとっては強い材料になります。
地域の支援制度(移動支援や見守り)へつないだ記録が残っている場合は、「日常生活能力の著しい低下」として、自治体判断は前向きになりやすいのが実態です。
国が「症状固定していない」と否認する仕組み
一方、最終判断を担う国は「医学的に状態が一定か(固定しているか)」を重視します。
良い日と悪い日の“ゆらぎ”が大きい後遺症では、リハビリの一環として短時間散歩を勧められることもあり、その記録が「日常動作は可能」と解釈されることがあります。
また、提出書類の中で医師の記載に差がある(初診と再診で所見の表現が異なる、診療科ごとに評価がずれる)と、「因果関係や重症度の評価が安定しない」と判断されがちです。
つまり、生活上の困難さが明白でも、「症状が固定していない=将来の変化余地がある」と見なされると、否認に傾く構造があるのです。
患者側から見れば“努力した証拠”(短時間の散歩や復職トライ)が、制度側では“できる日の証拠”として不利に働くというねじれが生じています。
書類審査の実態と7000枚超の負担
申請書類は、カルテ写し、検査結果、薬歴、診断書、受診証明、紹介状、リハビリ記録、生活状況の申述書など多岐にわたります。
複数の医療機関を回れば文書は雪だるま式に増え、1人分で段ボール1箱、総枚数が7000~8000枚というケースもあります。
費用負担も重く、診断書1通あたり数千円~1万円。神経内科、循環器内科、耳鼻科、心療内科、リハビリ科…と横断的に受診していれば、文書代だけで二桁万円に届くことも珍しくありません。
体調が不安定な中でコピー、製本、郵送、追加照会への回答といった“事務作業”を自前でこなすのは大きな消耗です。
さらに、書類の“粒度”をそろえる作業も難関です。日付が抜けている、単位が異なる、検査機器が別規格――こうした「形式の揺れ」を後から指摘され、再提出になるたびに時間と費用が増えます。
結果として「働けないから収入が減る→申請費用を捻出できない→提出が遅れ、救済も遅れる」という悪循環に陥りやすくなっています。
3.「薬害」としての認識と社会的影響
患者団体の訴えと厚労省の対応
後遺症を訴える当事者たちは、「元の体に戻りたい」「生活を取り戻したい」という切実な願いを掲げて集まり、厚労省前で声を上げました。中には、歩行が難しく車いすで参加した人、家族に支えられて短時間だけ現場に立ち会った人もいます。
訴えの中心は、(1)原因の丁寧な検証、(2)スピード感のある救済、(3)生活再建まで見据えた支援の3点です。
一方で、面会や要望提出の場は形式的になりがちで、「聞いてはくれたが、何が変わるのかが見えない」という受け止めも目立ちます。
たとえば、患者側が「家事や移動ができない」と生活実態を話しても、返ってくるのは「今後の検討課題とする」「追加資料の提出を」といった事務的な回答。
現場の生活の重さと、制度側の言葉の軽さとの間に、深い溝が残っているのが実情です。
「評価不能」とされる副反応報告の現状
審査の資料に「評価不能」と記されるケースが多いのは、当事者にとって大きな壁です。
これは「嘘」と断定しているわけではなく、「提出された情報だけでは因果関係を判断できない」という意味合いです。
たとえば、接種から症状出現までの時間が記録上ばらついている、複数の診療科で病名や所見が統一されていない、症状が日によって大きく揺れる、といった“書類の穴”や“医学的グレー”が重なると、結論は「わからない」に流れやすくなります。
しかし当事者にとっては、その「わからない」が生活費・治療費の自己負担につながります。
めまいで転倒し、在宅でも見守りが必要になったのに、評価不能のままでは介護やリハビリの支援につながりにくい。つまり「判断保留=実質的な不支給」という結果を生み、生活をさらに追い詰めてしまいます。
ワクチン接種をめぐる社会的圧力と分断
接種の有無をめぐる“空気”も、後遺症問題を複雑にしています。
接種した人が不調を訴えると、「気のせい」「もうコロナは落ち着いたのに」と周囲に受け止められず、職場での配置転換や欠勤の説明が通らないことがあります。
逆に、接種を控えた人は「協力しない人」と見られ、学校行事や職場の飲み会で気まずい思いをしたという声もあります。
こうした圧力や偏見は、当事者の“助けを求める力”を奪いがちです。
体調の波が激しい人ほど、通院の同伴や買い物の代行など、身近な支えが必要になりますが、「責められるかもしれない」という不安から、症状や困りごとを言い出せない。結果として、医療にも制度にも届きにくくなり、孤立が深まります。
後遺症の有無や接種の選択に関わらず、まず目の前の困りごと(移動・家事・就労・学業)を具体的に支えること。たとえば、勤務シフトの柔軟化、通院日程に合わせた在宅勤務、学校での提出期限の延長、地域の見守りサービスとの連携など、現実的な工夫が分断を和らげる第一歩になります。
コロナ後遺症とワクチン後遺症、どちらも見逃せない問題
ワクチン後遺症とコロナ後遺症は、実際には異なるものですが、症状が似ているために混同されることが多いです。
特に、ワクチン接種後にコロナに感染し、その後遺症が悪化した場合、原因を明確に区別するのは難しいことがあります。これが「ワクチンを悪者にしている」という意見につながる原因となることもあるでしょう。
コロナ後遺症は見過ごされがち?
一方で、コロナ後遺症は、現在も社会で広く認識されているわけではなく、医療機関や社会からの支援が遅れているという声もあります。
これに対して「ワクチンの副作用にばかり注目し、感染症による後遺症を軽視している」といった反論も存在します。
ワクチン接種を進める政府の立場からすると、ワクチン接種による後遺症が注目される一方で、感染による後遺症が見過ごされることに対する不満が表面化することもあります。
両者の影響を適切に理解する必要がある
ワクチン後遺症とコロナ後遺症、それぞれが持つ影響は明確に異なりますが、同じように長引く症状に苦しむ人々にとっては、どちらも生活に深刻な支障をきたしています。
そのため、どちらか一方を責めることなく、両者の症状や影響を十分に理解することが非常に重要です。
特に、ワクチン接種をした結果として後遺症が発生した場合、政府や医療機関に対してはより積極的な支援と情報提供が求められます。
ワクチンを悪者にするのではなく、透明性を持って副反応や後遺症に対する適切な対応策を整備することが、社会的信頼を築くために不可欠です。
まとめ
社会的に注目されるべきは、ワクチンやコロナ自体による後遺症を含むすべての影響をしっかりと理解し、支援体制を強化していくことです。ワクチン接種に関する議論も重要ですが、それだけではなくコロナによる後遺症にも平等な対応が必要です。患者の立場からすれば、治療や救済を求めて声を上げることが重要であり、その声が実際に社会全体で受け入れられ、具体的な支援につながることを望んでいます。
まとめ
ワクチン後遺症をめぐる現実は、体の不調だけではありません。家事や移動すら難しい日がある、仕事や学業を続けられない、申請のための書類や費用が重くのしかかる――そうした“生活の困りごと”が積み重なっていました。
自治体は生活実態を丁寧に拾い上げ「認定すべき」とする一方で、国の最終判断では「症状が固定していない」「評価不能」とされ、結果的に救済へ届きにくい構図も浮かび上がりました。
加えて、接種の有無をめぐる社会的圧力や偏見が、当事者の声をさらに届きにくくしています。
だからこそ、当事者と周囲の人が今すぐできる“小さな実務”が大切です。
体調の波や生活の困難を日誌に残す(起床・家事・移動・休憩の時間、できた/できなかった理由をメモ)、通院の記録や検査結果のコピーを月ごとにファイル分けする、診断書は費用や負担を見ながら優先度の高い医療機関から順に集める――といった積み重ねは、申請の“穴”を減らし、否認理由につながりやすい「情報のばらつき」を小さくします。
支えを広げる工夫も現実的です。勤務先には在宅勤務や短時間シフト、学校には提出期限の延長や席替えなど、具体的な配慮を例示して相談する。地域の見守りサービスや買い物代行、家事サポートといった公的・民間の支援をリスト化し、良い日・悪い日で使い分ける。
同じ悩みを持つ当事者会に参加し、申請書の書き方や“つまずきポイント”を共有することは、孤立の解消にもつながります。
制度側には、生活実態を反映した迅速な救済と、原因のていねいな検証が求められます。
私たちにできるのは、当事者の声を事実に基づいて可視化し続けること、そして目の前の困りごと――移動・家事・就労・学業――を具体的に支えることです。
「元の体に戻りたい」「元の生活を取り戻したい」という願いに一歩ずつ近づくために、記録、整理、共有、そして周囲の理解づくりという現実的な行動を積み上げていきましょう。
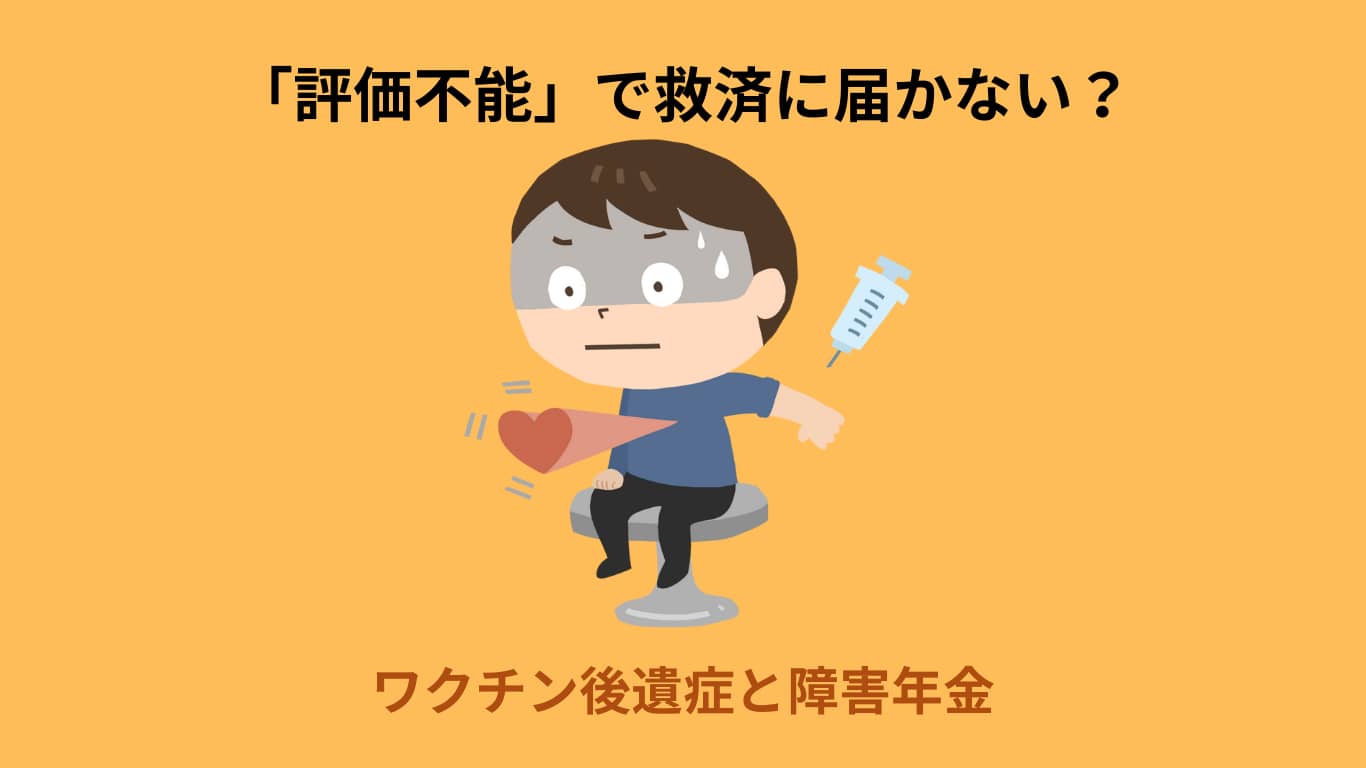
コメント