2025年8月、千葉県木更津市が「JICAアフリカ・ホームタウン」に認定されたことをきっかけに、SNS上では「ナイジェリアから移民を受け入れるのでは?」といった誤情報が拡散しました。
しかし木更津市は、市長名義の公式声明で「移住・移民政策とは無関係」と強く否定しています。
本記事では、木更津市の見解やJICA事業の本来の目的、そして誤解が広がった背景について分かりやすく整理しました。
はじめに
木更津市の声明発表の背景
2025年8月21日に横浜で開催された「第9回アフリカ開発会議(TICAD9)」において、千葉県木更津市がナイジェリア連邦共和国の「JICAアフリカ・ホームタウン」として認定されました。
これを受けて木更津市は25日、市長名義で声明を発表しました。声明の主な目的は、SNS上で広がった「ナイジェリアからの移民受け入れ」などの誤情報を否定し、市民に正しい情報を伝えることでした。
木更津市とナイジェリアのつながりは「東京2020オリンピック・パラリンピック」でのホストタウン事業にさかのぼります。当時の交流がきっかけとなり、今回の認定に至った背景があります。
SNSで拡散した誤情報の概要
一方で、認定の発表後にSNSでは「特別就労ビザが緩和されるのでは」「大量の移民受け入れにつながるのでは」といった情報が急速に広まりました。
さらに、山形県長井市に関しては「日本が長井市をタンザニアに捧げた」とも取れる海外報道の見出しが拡散し、混乱が大きくなりました。
著名人や地方議員までもがSNS上で疑問を呈したことで話題はさらに拡大し、市民の間には「国が勝手に決めたのではないか」という不安が広がったのです。
木更津市が公式声明を出したのは、こうした誤解を払拭し、事業の趣旨が国際交流や人材教育にあることを強調するためでした。
1.JICAアフリカ・ホームタウン事業とは
TICAD9での発表経緯
「JICAアフリカ・ホームタウン」事業は、2025年8月21日に横浜で開かれた第9回アフリカ開発会議(TICAD9)の関連イベントとして発表されました。
TICADは日本政府と国際機関が共同で進めるアフリカ支援の国際会議であり、今回は地域レベルでの交流強化に焦点が当てられました。
サミットでは、日本の地方自治体とアフリカ各国を結びつけ、持続的な国際交流を育てていくことが大きなテーマとなりました。
認定を受けた4自治体と相手国
このとき認定を受けたのは全国で4つの自治体です。
千葉県木更津市はナイジェリア連邦共和国、新潟県三条市はガーナ共和国、山形県長井市はタンザニア連合共和国、そして愛媛県今治市はモザンビーク共和国と、それぞれペアを組む形で発表されました。
いずれの都市も過去にオリンピックや文化交流を通じて縁があり、そこから国際協力や人材育成へと関係を広げていく狙いが示されています。
事業の本来の目的と狙い
本来の目的は「移住政策」ではなく、地域と地域を結ぶ国際交流にあります。
具体的には、スポーツや教育、文化を通じて若者の人材育成を支援すること、そして地方都市が国際的なつながりを持つことで地域活性化につなげることが掲げられています。
木更津市の場合は、ナイジェリアでの野球やソフトボールの普及を通じて「規律」を大切にする教育に協力する予定です。
このように、事業の狙いは地域間交流を通じた相互理解の深化であり、SNSで広がった「移民受け入れ」や「ビザ緩和」といった話題とはまったく別の次元にあるものです。
2.SNS上での誤解と批判
JICA批判が出た理由
- SNSでの誤解拡散
「ナイジェリア移民の大量受け入れにつながるのではないか」「特別就労ビザの発給要件が緩和されるのではないか」といった根拠不明の情報がSNSで拡散しました。
こうした話は実際には木更津市もJICAも要請・承知していないにもかかわらず、「移住政策と直結する」と誤認されたことが批判の火種になりました。 - 国際交流と移民政策の混同
「ホームタウン認定」はあくまで地域交流・人材育成・文化スポーツを通じた国際協力の枠組みですが、世論の一部では「国際協力=移民受け入れ拡大」と短絡的に結び付けられ、批判的に捉えられました。 - JICAへの不信感
国際協力機構(JICA)はODAや海外研修で知られていますが、一部では「外務省や国際機関に近すぎる」「地域住民の声を十分反映していない」といった不満が常に存在します。今回も「市民に十分説明されないまま国際的な枠組みに巻き込まれているのでは」という疑念が表に出ました。
「移民受け入れ」への誤解
事業の発表直後から、SNSでは「ナイジェリアからの移民を大量に受け入れるのではないか」という憶測が飛び交いました。
根拠のない情報ながら「特別就労ビザが緩和される」という具体的な言葉が添えられたため、不安は一気に広がりました。
実際には、木更津市もJICAもそうした計画は持っていませんでしたが、「国際交流」と「移民政策」が短絡的に結び付けられてしまったのです。
海外報道の誤訳が与えた影響
さらに誤解を深めたのが、海外メディアの報道でした。
山形県長井市について「Japan dedicates Nagai City to Tanzania(日本が長井市をタンザニアに捧げる)」という見出しが出回り、「日本の自治体が外国に譲渡された」と受け取られる形でSNSに拡散しました。
このような誤訳は、国境を越えて情報が伝わる際にニュアンスが変わってしまう典型例であり、結果的に「日本の自治体が切り売りされている」という極端な批判を呼び込むことになりました。
批判の拡散と著名人の反応
誤情報は市民の間だけでなく、地方議員や著名人の発信によってさらに広まりました。
奈良市議選で当選したへずまりゅう氏や、参政党の小柳彩子市議、さらには漫画家の倉田真由美氏までがSNS上で「これは本当に大丈夫なのか」と懸念を表明したのです。
影響力のある人物が発言すると、一般ユーザーも「やはり問題があるのでは」と感じ、話題は加速度的に拡大していきました。
こうした状況は、市民に「自分たちの暮らしに直接関わるのではないか」という不安を与え、批判の声が一層強まる要因となりました。
3.木更津市の公式見解と対応
移住・移民政策とは無関係との説明
木更津市は、市長名義で発表した声明の中で「移住・移民の受け入れや特別就労ビザの発給要件の緩和といった事実は一切ない」と強調しました。
SNS上で広がった憶測については、同市も承知しておらず要請もしていないと明確に否定しています。
あくまで事業の目的は国際交流と人材育成にあり、市民生活や移民政策に直結するものではないことを繰り返し伝えました。
JICAへの説明要請と市民への安心メッセージ
さらに木更津市は、主催者であるJICAに対して「事業の趣旨を正確に説明するように」と強く要請しました。
これは、海外報道の誤訳やSNSの誤解が広がる中で、市民が不安を感じないようにするための措置です。
声明では「国際交流や多文化共生は重要だが、事実とは異なる情報が出回らないよう、今後は丁寧な説明を続ける」と述べ、市民に向けて「安心してほしい」というメッセージを発信しました。
今後の具体的な取組(野球・ソフトによる人材教育)
木更津市が具体的に掲げている取り組みは、スポーツを通じた教育支援です。
JICAの「草の根技術協力事業(地域活性型)」の採択を受け、ナイジェリアで野球やソフトボールを広めることで、若者に「規律」を基礎とした人材教育を行う計画です。
例えば、日本からコーチを派遣して現地の子どもたちに指導したり、交流試合を通じてお互いの文化を学び合うといった活動が想定されています。
このように、実際の事業は移民やビザ制度とは無関係であり、スポーツをきっかけに人と人との信頼を育むことに焦点が当てられています。
日本とナイジェリアの認識の違い
今回の「JICAアフリカ・ホームタウン」事業をめぐる混乱は、日本・木更津市とナイジェリア政府側での“伝え方の違い”が大きな要因になっています。
どちらも同じ枠組みを指しているのですが、焦点の置き方が異なるため、市民には真逆のイメージが広がってしまいました。
日本、木更津市をナイジェリア人の故郷に指定August 22, 2025 カテゴリ: 最新ニュース、プレスリリース
日本政府は木曜日、文化外交を深化させ、経済成長を促進し、労働力の生産性を向上させるための戦略的取り組みの一環として、同国に住み、働くことをいとわないナイジェリア人の故郷として木更津市を指名した。
第9回アフリカ開発のための東京国際会議の傍らで発表されたこの新しいパートナーシップの下で、日本政府は、木更津に住み、働くために木更津に移住したい、高度なスキル、革新的、才能のあるナイジェリアの若者のための特別なビザカテゴリーを創設します。
スキルアップの準備ができているナイジェリアの職人やその他のブルーカラー労働者も、日本で働くための特別免除ビザの恩恵を受けることができます。
国際協力機構も式典で、山形県の永井市をタンザニアの故郷、新潟県の三条市をガーナの故郷、愛媛県の今治市をモザンビークの故郷に指名しました。
この協定を通じて、日本は、アフリカ4カ国との既存の関係を持つ自治体を公式に結びつけることで、アフリカ4カ国との交流を強化したいと考えています。
ナイジェリア臨時代理大使のフローレンス・アキニエミ・アデセケ駐日大使代理と渡辺義邦市長は、日本政府から木更津をナイジェリア人の故郷と名付けた証明書を受け取りました。
4都市は、日本、ナイジェリア、その他アフリカ3カ国の経済成長に付加価値をもたらす人材育成のための双方向交流の基盤を育成します。
地方自治体は、この指定により都市の人口が増加し、地域活性化の取り組みに貢献することを期待しています。
木更津は、2020年東京オリンピックのナイジェリア代表団の公式開催地でした。チームは、COVID-19の影響でオリンピックが延期されたため、オリンピック村に移動する前に、市内で試合前のトレーニングキャンプと順応を実施した。
石破茂首相は、TICAD9の開会の挨拶で、アフリカへの新規投資に55億ドルを表明し、アフリカ開発のための相互理解、現地解決、協力の重要性を強調しました。総理大臣は、民間セクター主導の持続可能な成長、若者と女性のエンパワーメント、地域統合に日本が注力していることを概説した。
石破総理大臣は、日本の高齢化の課題を認識しながらも、アフリカの発展には地域に根ざした解決策が不可欠であると強調した。
「日本はアフリカに対して様々な協力や支援を行っています。しかし、まず第一に、日本はアフリカについてもっと知る必要があります。したがって、TICAD 9でのこの共創を共に解決策を創出するにあたり、私たちは3つの重要な分野、つまり民間部門主導の持続可能な成長、若者と女性、アフリカ内外の地域統合と連結性に焦点を当てます。」
同氏は、人口減少と農地縮小という課題に取り組む日本を支援するようアフリカ諸国に訴えた。
アビオドゥン・オラドゥンジョエ
州議会議事堂
情報
局長 2025 年 8 月 22 日
比較表:両国の認識の違い
| 視点 | 日本・木更津市の説明 | ナイジェリア政府リリースの表現 |
|---|---|---|
| 事業の位置づけ | 国際交流・教育支援の一環 | 経済・労働力確保の戦略的取り組み |
| 主な目的 | 野球・ソフトボールを通じた若者教育(規律の育成) | ナイジェリアの若者や職人の移住・就労機会拡大 |
| ビザ制度 | 一切関与していない、要請も承知もしていない | 「特別ビザカテゴリー創設」「免除ビザの恩恵」と明記 |
| 木更津市の役割 | ホストタウンの縁を生かした国際交流 | 「ナイジェリア人の故郷」として生活・就労の場を提供するかのように説明 |
| 市民へのメッセージ | 「移民政策とは無関係、ご安心ください」 | 「都市の人口増加・地域活性化につながる」と期待を強調 |
なぜ認識がずれたのか?
- 翻訳・言葉の違い:「hometown」という言葉が、日本では「交流の象徴」なのに対し、ナイジェリアでは「居住地」と直訳的に解釈された可能性があります。
- 外交的リップサービス:式典では大きな期待を込めて「働きに来る若者に道を開く」と強調することが多く、それが政策的事実と混同されました。
- 報道姿勢の違い:日本側は「教育・交流」に重点、ナイジェリア側は「経済・労働力」に重点を置いた発信をしたことで、認識がすれ違いました。
信頼回復のために必要なこと
- JICA・外務省・木更津市が協力して「事業の趣旨」を多言語で統一的に説明する。
- 「何をするのか」「何をしないのか」をFAQ形式で整理し、SNSや報道に迅速に共有する。
- 相手国メディアにも訂正や補足説明を依頼し、誤解が拡散しないようにする。
このように、日本は「教育交流」だと説明しているのに、ナイジェリア側は「移住・ビザ優遇」だと受け止めて発信してしまったことが、市民に大きな不安を生む原因になっているのです。

JICAとは?
JICA(国際協力機構)は、日本の政府が中心となって設立された独立行政法人で、発展途上国との国際協力を推進する役割を担っています。
学校や病院の建設、技術指導、人材育成などを通じて「日本と世界をつなぐ懸け橋」として活動しています。また、国の大きなプロジェクトだけでなく、地方自治体やNPOとも協力し、地域に根差した国際交流を後押ししています。
今回の「アフリカ・ホームタウン」事業では、木更津市だけでなく、全国の3つの自治体も認定を受けています。
- 愛媛県今治市 × モザンビーク共和国
造船業やスポーツを通じた交流が背景にあり、人材育成や地域産業のつながりを強める取り組みが予定されています。 - 新潟県三条市 × ガーナ共和国
金属加工や燕三条地域のものづくり文化を生かし、技術や教育面での協力を展開していくことが期待されています。 - 山形県長井市 × タンザニア連合共和国
長井市は以前からタンザニアとの交流があり、農業や教育の分野で地域連携を進めることを目指しています。
木更津市とナイジェリアのスポーツ交流を含め、4都市はそれぞれの強みを生かした協力関係を築きながら、相手国との「地域レベルでの国際協力」を進めていくのです。これが、JICAが重視する「草の根の国際協力」の具体例といえるでしょう。
JICA(ジャイカ)とは、 独立行政法人 国際協力機構(Japan International Cooperation Agency) のことです。日本のODA(政府開発援助)を実施する中核的な機関で、開発途上国の支援や国際協力を担っています。
基本情報
- 正式名称:独立行政法人 国際協力機構(Japan International Cooperation Agency)
- 設立:2003年(現在の形は2008年、旧海外経済協力基金や国際協力銀行の一部機能を統合)
- 所管官庁:外務省
- 本部:東京都千代田区二番町
主な役割
- 技術協力
- 日本の専門家を途上国に派遣し、教育・医療・農業・防災などの分野で人材育成や技術移転を行う。
- 逆に、開発途上国の研修員を日本に招いて学んでもらう事業もあります。
- 有償資金協力(円借款)
- 開発途上国に対して、返済義務のある低金利の長期融資を行い、インフラ整備や経済開発を支援。
- 無償資金協力
- 医療機材や学校建設など、途上国に返済不要の支援を実施。
- 青年海外協力隊(JOCV)派遣
- 若者が途上国に派遣され、現地で教育・医療・スポーツなどの活動を行う。国際交流の象徴的な事業の一つ。
最近の特徴
- SDGs(持続可能な開発目標)達成支援
教育、気候変動、ジェンダー平等などの課題に積極的に取り組んでいます。 - 災害支援
地震や洪水などの緊急時には国際緊急援助隊を派遣し、人命救助や復興を支援。 - 地域活性化事業
国内自治体と連携し、国際交流を通じて地方創生につなげる試み(今回の「アフリカ・ホームタウン」事業もその一環)。
👉 つまりJICAは「日本の知識や技術、人材を世界に活かす公的な国際協力の窓口」です。
まとめ
木更津市が「ナイジェリアからの移民受け入れ」といった誤情報を公式に否定した背景には、SNSや海外報道で広まった誤解がありました。
実際の事業は、東京五輪のホストタウンを契機とした国際交流の延長線上にあり、ナイジェリアの若者へのスポーツ教育支援が中心です。移民政策やビザ制度の変更とは一切関係がありません。
今回の騒動では、木更津市だけでなく長井市や他の自治体も、事実誤認への迅速な説明を求められました。
誤訳や断片的な情報が拡散する時代において、自治体が公式見解を即座に発信し、市民へ丁寧に説明することの重要性が改めて浮き彫りになったといえます。
今後も、国際交流を前向きに進めるためには、透明性のある情報発信と市民との信頼関係づくりが欠かせないでしょう。
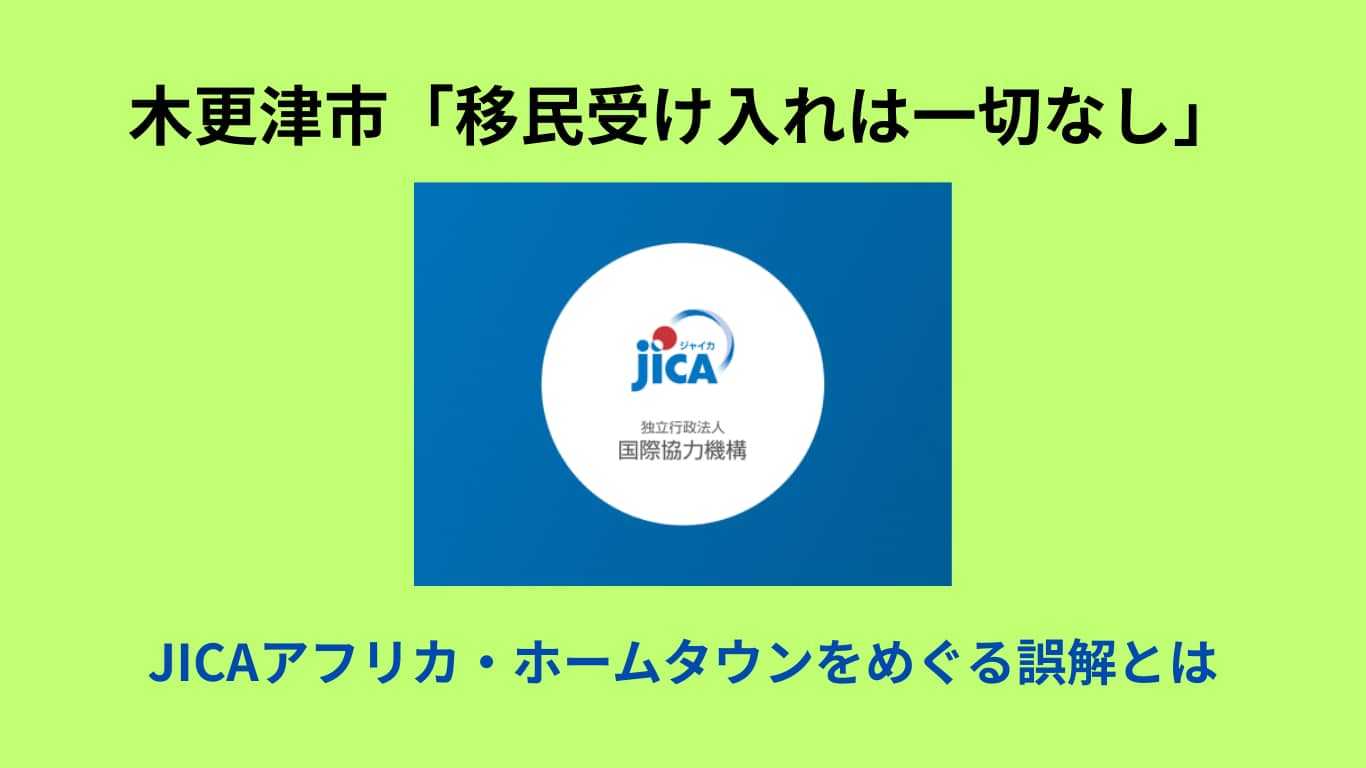
コメント