物価が高い今、「新税」で家計は増えるの?減るの?
本記事は燃料・所有・距離課金の違いを、月の走行距離や給油量の例でわかりやすく比較します。
地方や子育て・介護世帯、仕事で車が欠かせない人への配慮も一緒にチェックしましょう。
はじめに
背景:ガソリン暫定税率の廃止と「新税」検討の経緯
2025年8月24日の報道では、老朽化した道路・橋・上下水道などの維持費をまかなうため、政府が自動車の利用者から新たに税を徴収する案を検討していると伝えられました。
与野党で「年内にガソリン税の旧暫定税率を廃止する」方針が合意された一方で、その穴埋め財源が必要になっているのが出発点です。
背景には、埼玉県八潮市で起きた下水道管破損の死亡事故のように、高度経済成長期に整備されたインフラの老朽化が全国で表面化している現実があります。
現行の暫定税率は、ガソリン1リットル当たり国の揮発油税24.3円、地方揮発油税0.8円が上乗せされてきました。
軽油でも地方税の軽油引取税に暫定分17.1円が含まれます。
たとえば家族で月に80L給油する家庭なら、ガソリンの暫定分だけで約2,000円の負担(80L×約25円)でした。
物流会社のディーゼルトラックが月1,000L使うと、軽油の暫定分だけで約1万7千円に達します。
こうした負担を軽くするための「減税」方針と、インフラ維持費を確保するための「新税」検討が同時に進んでいるのが現在地です。
論点整理:物価高対策とインフラ維持財源の両立
論点は大きく二つあります。第一に、物価高で家計が苦しいなか、暫定税率を廃止しても同じ規模の新税を上乗せすれば、実質的に負担が変わらないのではないか、という点です。
ガソリン価格が数円上下するだけでも、通勤や子どもの送迎、買い物に車が欠かせない家庭には直撃します。地方では「車が生活の足」という世帯が多く、負担感は都市部より大きくなりがちです。
第二に、老朽インフラの安全を守るための安定財源をどう確保し、どう配分・公開していくかです。
新税を設けるなら、①何にどれだけ必要か(橋や水道の優先順位)、②どの税方式が公平か(燃料に上乗せ・所有に課税・走行距離で負担など)、③集めたお金を地方にどう手厚く回すか、を具体的に見える化することが欠かせません。
たとえば「通勤で毎日20km走る地方の利用者」と「週末だけ車に乗る都市部の利用者」で負担が逆転しないか、物流や農業のコスト転嫁で物価に跳ねないか、といった生活目線の検証も必要です。
こうした論点を整理しつつ、本稿では次章以降で課税方式の選択肢、家計・産業への影響、財源設計の要件を具体的に見ていきます。
1.新税は何をどう課すのか

方式① 燃料課税の継続・上書き(炭素色/旧暫定の置換)
最もわかりやすいのは、ガソリンや軽油など「入れた分だけ払う」やり方を続ける案です。
これまで上乗せされてきた暫定分(ガソリンなら24.3円/L+地方0.8円、軽油なら17.1円/L)を、名前や中身を変えて置き換えるイメージです。給油のたびに広く薄く集められるため、徴収の仕組みを大きく変える必要がありません。
- 生活への影響例:月80L給油する家庭なら、1円/Lの新税で月+80円、5円/Lなら月+400円。
- 事業への影響例:月1,000L使う中小運送なら、1円/Lで月+1,000円、5円/Lで月+5,000円。原価にのせれば配送料や商品の値段に波及します。
長所は「使うほど負担」を徹底できること、観光や休日ドライブなど混み合う時期に価格で抑制が働きやすいことです。
短所は、価格が高止まりの時期に家計へ直撃しやすいこと、地方や通勤で車が必須の人に負担が偏りがちなことです。
価格が急に跳ねたときの「上限」「還付」「子育て・低所得世帯の上乗せ給付」などの緩和策とセットで設計するのが現実的です。
方式② 車体課税の再編(自動車税+重量税の統合新税)
次に、車を「持っていること」に対して年に一度などで負担する案です。
現在の自動車税と重量税を一本化し、車重や環境性能(燃費・電動化)、年式(古くなるほど安全・環境コストが高い)などで段階づけるイメージです。インフラ維持費のように毎年かかるお金に、毎年安定して充てやすいのが強みです。
- 生活への影響例:年5,000円の上乗せなら、月あたり約420円。走行距離が少ない人でも同じ額になるため、「あまり乗らないのに…」という不公平感が出やすい側面があります。
- 事業への影響例:複数台を保有する会社は台数分の固定費が増えます。逆に、繁忙期だけレンタカーやカーシェアに切り替えるなど「保有を減らす工夫」で負担を抑えやすい面もあります。
長所は、価格変動に左右されにくく、家計の見通しが立ちやすいこと。
短所は、「走らない人も同額」の固定的な負担になりやすいことです。
公平性を高めるには、走行距離が極端に少ない人向けの軽減や、子育て・介護用途への割引、商用車の控除など、細かな配慮が鍵になります。
方式③ 走行距離課金・ロードプライシングの導入可否
三つ目は「走った距離に比例して払う」考え方です。車検時のメーター申告や車載機での記録、都市部の混雑エリアだけ時間帯料金をかけるやり方など、いくつか手段があります。
道路の傷みは走行距離や車重に左右されるため、理屈としては道路の使い方に沿った負担になりやすい方式です。
- 生活への影響例:平日通勤で片道15km(往復30km)×月20日=月600km。1円/kmなら月600円、2円/kmなら月1,200円の負担。
- 事業への影響例:年10万km走る長距離トラックは、1円/kmで年10万円、2円/kmで年20万円。物流コストに直結するため、食料品や日用品の価格にも影響が及びます。
長所は、走るほど負担という公平性と、都市の渋滞対策(混雑時間だけ高くする等)にも使えること。
短所は、機器導入や運用コスト、プライバシーへの不安、不正対策の難しさです。
まずは「車検ごとの自己申告+無作為抽査」「都市の一部エリアのみ時間帯料金」など、限定的な試行から段階的に広げる現実路線が考えられます。
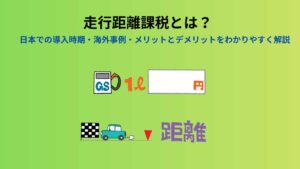
2.家計・産業・地域への影響

家計負担の変化(ガソリン車・ディーゼル・EV/PHV)
前章で方式を見たので、ここでは暮らし目線の「いくら増えるの?」を具体的に想像します。
- ガソリン車(例①:月600km・燃費15km/L→40L消費)
- 燃料に1円/Lの新税で月+40円、5円/Lで月+200円、10円/Lで月+400円。
- ガソリン車(例②:郊外・買い物や送迎多めで月80L給油)
- 1円/Lで月+80円、5円/Lで月+400円、10円/Lで月+800円。
- ディーゼル乗用・小型商用(例:月600km・12km/L→約50L)
- 1円/Lで月+50円、5円/Lで月+250円。
EV/PHVの場合
- 燃料(L)に課す方式なら、EVは負担ゼロ。一方、統合新税(所有に年額で課税)なら、たとえば年+5,000円の上乗せで月約+420円。
- 走行距離課金なら、月600kmで1円/km→月+600円、2円/km→月+1,200円。
- PHVは「電気+ガソリン」。たとえば月600kmのうち400kmを電気で、残り200kmをガソリン(20km/L→10L)なら、5円/Lで月+50円にとどまります。
ポイントは、燃料課税=「給油するほど、すぐ増える」、所有課税=「毎月一定で読みやすい」、距離課金=「走るほど比例」という性格の違いです。通勤距離が長い家庭ほど、距離課金や燃料課税の影響が大きくなります。
物流・農業・公共交通への波及と物価転嫁
- 長距離トラック(年間10万km・燃費3km/L→約33,333L/年)
- 3円/Lで年+約10万円、5円/Lで年+約16.7万円。月あたり約+8,300〜+13,900円。輸送原価にのれば、食品・日用品の店頭価格にじわり波及します。
- 地域の路線バス(年間6万km・3km/L→約20,000L/年)
- 3円/Lで年+約6万円、5円/Lで年+約10万円。赤字路線の維持には、運賃改定や自治体支援の議論が避けられません。
- 農業(軽油利用)
- トラクター等で500〜1,000L/シーズン使う農家なら、3円/Lで+1,500〜+3,000円/年、5円/Lで+2,500〜+5,000円/年。
- 既存の軽油引取税の農業用免除(時限措置)の扱いを新税にどう引き継ぐかで、負担は大きく変わります。
- 公共交通・宅配・生協便
- 走行距離課金を導入すると、運行距離が長いほど影響が直撃。時間帯別料金(混雑時だけ上乗せ)を採るなら、オフピーク配送や深夜便の活用など運行計画の見直しが進む可能性があります。
物価転嫁の道筋は、燃料・距離ベースのコスト→物流→小売価格という順でじわじわ広がるのが一般的。負担を和らげるには、中小事業者への一時的な負担軽減や省燃費車・タイヤ・運転研修への投資支援が効果的です。
都市部と地方の公平性/低所得層・子育て世帯の配慮
- 都市 vs. 地方の差
- 都市部:通勤5km×往復×月20日=月200km。距離課金1円/kmなら月+200円。
- 地方部:通勤30km×往復×月20日=月1,200km。同条件で月+1,200円。
同じ働き方でも地方ほど負担が重くなりやすいため、人口密度や公共交通の有無に応じた地域係数や上限設定が必要です。 - 低所得層・子育て・介護世帯
- 子どもの送迎や通院は「削れない移動」。月○kmまで非課税(ベーシック走行枠)や、児童扶養手当・介護認定連動の還付など、“必要な移動”を守る設計が現実的です。
- 仕事で車が必須な人への配慮
- 訪問介護・保守点検・営業などは、走行が業務そのもの。職務用走行の控除や車両台数の多い事業者向けの段階的負担で、雇用とサービスを守れます。
- 使途の納得感を高める仕掛け
- 「あなたの地域の橋・水道に今年いくら投資されたか」を地図で公開、老朽化度合いと工事予定を見える化。負担の痛みを“見える改善”で納得に変えることが、受容性を左右します。
3.財源設計と使途の透明性
必要額の試算と代替案(補助金整理・無駄削減)
まず「いくら必要か」を家計簿のように見える化します。必要額=(老朽化インフラの維持・更新に必要な総額)−(既存の国・地方の予算確保分)。報道や専門家の言及で議論のたたき台とされる年1.5兆円規模を仮置きすると、次のような組み合わせが現実味を帯びます。
- ① 既存支出の整理・転用
2022年開始のガソリン補助金は累計8兆円超が投入されてきました。暫定税率廃止のタイミングで補助金を段階終了し、その一部を恒常財源に振り替える設計(例:補助金▲7,000億円→インフラ枠+7,000億円)。 - ② 小幅・段階的な課税の組み合わせ
いきなり大きく乗せず、燃料にごく小幅(例:1〜3円/L)+所有側で年額わずか(例:年3,000〜5,000円)などを2〜3年かけて段階導入。物価・賃上げ動向を見ながら微調整します。 - ③ 使い方に応じたメリハリ
走行距離課金の限定導入(都市の混雑時間帯や高速長距離)で一部を賄い、通勤や生活必需の走行には月○kmまで非課税(ベーシック走行枠)を設定。 - ④ 歳出の無駄の削減
指名停止や予定価格見直し、包括発注からの分割・競争入札化、維持管理の予防保全シフト(壊れる前に小修繕)で、同じ1円でも長持ちさせる工夫を積み上げます。
「増やす前に減らす」原則で①④を先行し、足りない分を②③で最小限に埋める。これが家計への衝撃を抑えつつ、持続可能な財源をつくる順序です。
配分ルール:地方自治体への重点配分と劣化インフラ優先
集めたお金を「どこに、どれだけ」回すかで納得感は大きく変わります。おすすめはスコア方式による客観配分と地域公開のセットです。
- 客観スコア(例)
- 老朽度:築年数・劣化度(点検結果)
- 重要度:交通量・代替路の有無・医療/防災アクセス
- リスク:腐食・地震/豪雨脆弱性・通学路/バス路線係数
→「老朽度×重要度×リスク」を合成したスコア上位から優先的に予算配分。 - 地方への重点配分
維持管理費の多くを担う自治体に基礎枠+スコア連動枠で二段配分。人口や道路延長、豪雪・離島といった地域係数も織り込みます。 - 透明化の仕掛け
地図ダッシュボードで「今年この橋にいくら」「水道管の更新距離は何m」を見える化。入札結果、工期、進捗、写真を誰でも閲覧できる形にし、未執行残の理由まで明記します。
政策決定のロードマップ(税調~年末大綱~国会審議)
制度は段取りが命です。生活や物価への影響を抑えつつ、試して、測って、直す流れを計画に組み込みます。
- ① 秋:制度設計の骨子
与党税制調査会で財源ミックス(補助金整理+小幅課税)と軽減・還付メニュー(低所得・子育て・介護・業務走行)を明文化。自治体向けの配分スコア案も同時提示。 - ② 年末:税制改正大綱
段階導入(例:初年度は0.5〜1円/L+年額1,000円程度)、都市限定の距離/時間帯実証、家計影響の四半期レビューを大綱に明記。 - ③ 通常国会:法案審議・可決
経過措置(既存車の据え置き期間、事業者の猶予・設備投資減税)をセット。使途特定(インフラ限定)条項と公開義務を法律本文に書き込みます。 - ④ 施行準備:情報基盤の整備
ダッシュボード、自治体の点検/申請様式の標準化、監査と第三者評価の仕組みを整備。住民説明会や料金シミュレーターで影響を事前に提示。 - ⑤ 実施・検証:PDCA
初年度は小規模で開始し、物価・賃上げ・地方の交通事情を見ながら翌年度係数を調整。「5年で総点検・見直し」のサンセット条項で、制度を硬直化させません。
まとめ
ガソリンの暫定税率をやめるなら、その穴をどう埋めるかは「私たちの生活」と直結します。
燃料に少しずつ上乗せするのか、車を持っていることに年額で負担するのか、走った距離に応じて払うのか——方式が変われば、毎月の家計の感じ方も変わります。
たとえば月80L給油する家庭は、1円/Lで月+80円、5円/Lで月+400円。通勤で月600km走る人は、距離課金1円/kmなら月+600円。所有に一定額を足す方式なら、年+5,000円で月+約420円。どれが自分に合うかは、暮らし方で大きく違います。
大切なのは「負担の重さ」よりも「納得感」があるかどうかです。地方で車が必須の人、子育て・介護で車に頼る人、仕事で長距離を走る人——必要な移動には上限や還付、割引などの“守り”を用意する。
集めたお金は、危険度の高い橋や水道から優先して、どこにいくら投じたかを地図で公開する。こうした当たり前の工夫が、不信感を減らします。
これから議論が進む中で、読者が今できることはシンプルです。
- 自分の走行パターンを把握:月の走行距離、給油量、車の燃費をメモする。
- 影響をざっくり試算:〈燃料案〉は「給油量×想定上乗せ額」、〈距離案〉は「月のkm×想定単価」、〈所有案〉は「年額÷12」。
- 必要な配慮を書き出す:通院・送迎・業務走行など“削れない移動”をリスト化し、どんな軽減があれば助かるか考えておく。
制度づくりは、一度決めて終わりではありません。小さく始めて、影響を確かめ、必要に応じて直す——その過程を「見える形」で進められるかが、家計と安全の両立を左右します。
私たち一人ひとりが数字で自分ごと化し、必要な配慮や優先順位を具体的に伝えることが、より良い落としどころにつながります。
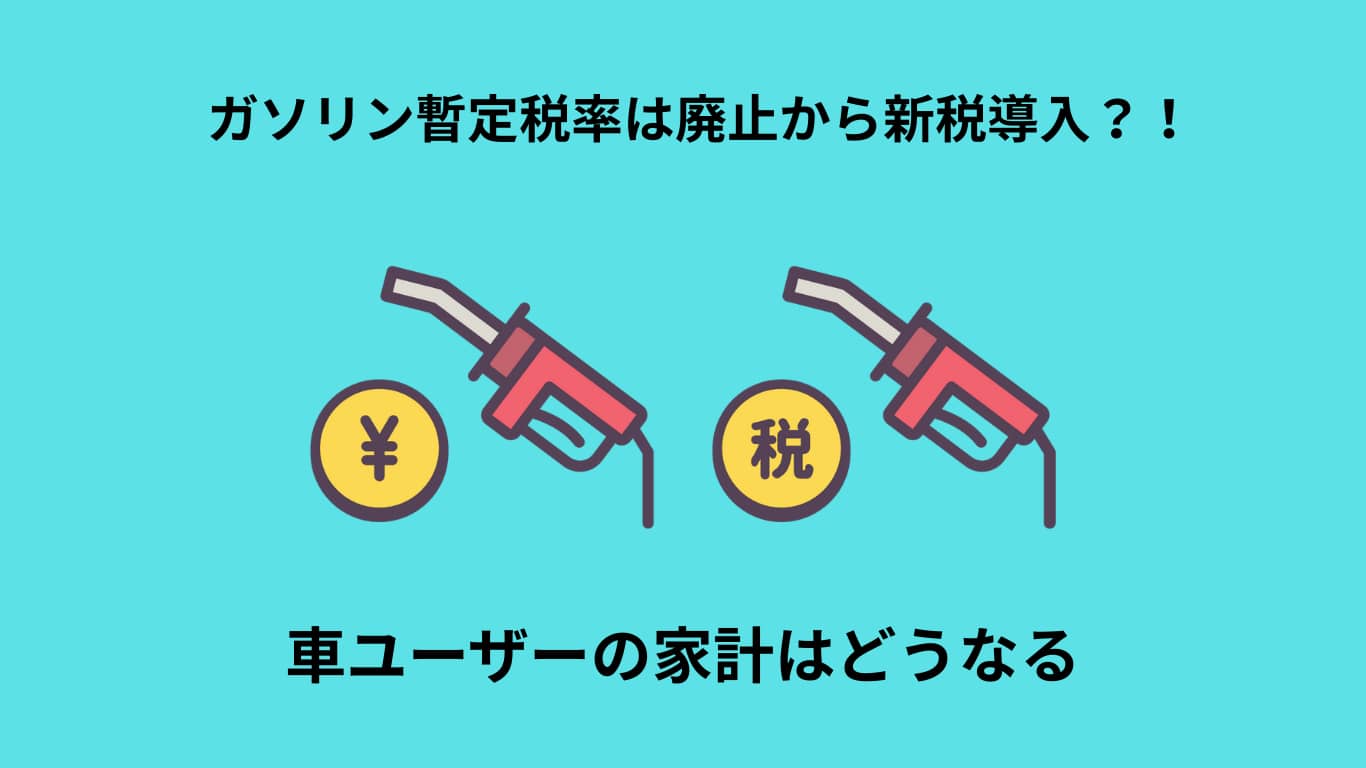
コメント