櫻井よしこ氏が「南京大虐殺はなかったことが証明済み」と語ったことで、大きな議論が起きています。
本記事では、外務省の公式説明や、研究者たちが積み上げてきた事実、そして多くの人が気になる「犠牲者数」を、むずかしい言葉を使わずに整理します。
結論を急がず、何がわかっていて、どこに幅があるのかを一つずつたどります。
はじめに
事件の概説と発言の波紋(櫻井よしこ氏コラムを起点に)
8月4日付の産経新聞に掲載された櫻井よしこ氏のコラムは、「南京大虐殺はわが国の研究者らによって“なかったことが証明済み”」とする強い表現で注目を集めました。
直前には、8月6日の広島平和記念式典で石破茂首相が「記憶の継承」を呼びかけ、また中国では7月25日公開の映画『南京写真館』が大きな興行収入を記録した、といった出来事が続いていました。
櫻井氏は、こうした流れが「反日宣伝」を強めると指摘し、7月末の蘇州での日本人親子への暴行報道も挙げています。
このコラムを受け、SNSやニュースサイトのコメント欄では批判と支持が一気に噴出。
「政府も“事件そのものは否定できない”としているのに、なぜ『なかった』と言い切るのか」といった疑問や、「中国側の人数主張は多すぎるのでは」という指摘など、論点が多方面に広がりました。
本記事では、感情的な応酬に流されず、公開情報と研究の到達点、そして読者が抱きがちな素朴な疑問を、具体例を交えながら丁寧にたどります。
論争の焦点整理:存在認定と犠牲者数・表現の適切性
論点は大きく二つあります。
第一に「事件があったのか」という存在認定です。
外務省は、日本軍の南京入城後に非戦闘員の殺害や略奪があったことは否定できないと明記しています。
たとえば、当時の目撃証言や埋葬記録、人口動態の推計など、複数の手がかりが積み重ねられてきました。
第二に「犠牲者数はいくらか」。中国側の「30万人」から、日本側研究の「数万~20万人」まで幅があり、数字の根拠の取り扱いが最大の争点です。
コメント欄でも「30万人は物理的に不可能では」「証言は尊重しつつも検証が必要」といった声が目立ちます。
言い切りの強い表現は、事実認定と人数推計という別次元の問題を混同させやすく、議論を硬直化させがちです。
本稿では、(1)事件の存在に関する合意点、(2)人数推計の幅と根拠、(3)言葉の選び方が議論に与える影響――を順に整理していきます。
1.発言の経緯とメディア/世論の反応
コラム掲載の背景と主張の要点(「なかったことが証明済み」発言)
8月4日朝刊の産経新聞1面に載った櫻井よしこ氏のコラムは、石破首相が「戦後80年」の個人メッセージを秋以降に出すという報道に触れつつ、「それは中国の反日宣伝に手を貸す」と警鐘を鳴らす内容でした。
本文では、中国で公開中の映画『南京写真館』が公開4日で約5億元の興行収入に達したこと、江蘇省蘇州で日本人の母親が石で殴られたとされる出来事を例に、「反日感情の過熱」を主張。
クライマックスで「『南京大虐殺』は、わが国の研究者らによって“なかったことが証明済み”」と書き切った点が最大の争点になりました。
強い断定表現と、映画や事件の具体例を並べて“現在の日本への影響”へと結びつけた構成が、読者の受け止めを大きく二分させました。
同時期の時事文脈(戦後80年・平和式典・関連映画・治安事案)
コラムの前後には、感情が動きやすい出来事が続きました。
8月6日の広島平和記念式典で首相が「記憶の継承」を誓ったこと、7月25日に中国で『南京写真館』が公開され短期間で大ヒットしたこと、7月31日に報じられた蘇州での暴行事案、さらに9月3日の「抗日戦争勝利」軍事パレードという予定――。
戦争から80年という節目と、中国国内の出来事が連鎖的に並ぶ中での主張だったため、読者は「歴史認識」と「現在の安全・外交」を同時に考えざるを得ない状況に置かれました。
たとえば、「式典での追悼メッセージ」と「映画のヒット」を同じ時間軸で見たとき、歴史の語り方が今の社会や世論にどう跳ね返るのか、という問いが一気に具体化したのです。
SNSと主要メディアの初期反応:批判点と支持意見の分類(主なヤフコメの傾向含む)
初期反応は大きく三つに分かれました。
- 批判派:
・「外務省は“非戦闘員の殺害や略奪は否定できない”としている。『なかった』と言い切るのは政府見解とズレる」
・「“存在の有無”と“犠牲者数の多寡”を混同している。議論を乱暴にしてしまう」
・「大手紙の1面コラムとしては、根拠提示が薄い」 - 条件付き支持派:
・「中国側の『30万人』は多すぎるのでは。数字の根拠を検証すべき」
・「映画や国内報道が感情を煽っている面もある」 - 慎重派(様子見):
・「戦争体験者の証言は尊重しつつ、記憶と事実の区別、証言の偏りを考慮した検証が必要」
・「言い切り表現は対立を深める。事実の層を一つずつ確認したい」
コメント欄の実例としては、「事件の存在は認めるが、30万人は物理的に不可能では」「証言は大切だが、数字は記録で確かめたい」といった声が目立ちました。
要するに、世論の関心は“事件の有無”よりも“どのくらいの規模だったのか”“どうやって数を確かめるのか”に移っており、ここから先は、数字の根拠や史料の読み方を具体例でたどる段階に入ります。
2.研究史と公式見解の整理
日本政府・外務省の立場:存在は否定できず、人数は確定困難
政府は公式サイトで、「日本軍の南京入城後に、非戦闘員の殺害や略奪があったことは否定できない」と明記しています。
一方で、犠牲者の具体的な数は「諸説あり、どれが正しいかを認定することは困難」としています。
人数が定まらない理由は、当時の状況に即して考えるとわかりやすいです。たとえば――
- 市内の人口が短期間で大きく移動し、住民登録や名簿が機能していなかった。
- 埋葬や遺体収容を担った団体が複数あり、重複計上や未計上が生じた。
- 戦闘による死亡と、戦闘の後に起きた処刑・略奪・暴行による死亡が混ざり、線引きが難しい。
こうした事情から、「事件の存在認定」と「正確な人数の特定」は別の課題として扱われています。
学術的到達点:共同研究と主要研究者の結論(「あった」が前提)
研究の世界では、「南京事件があった」こと自体は前提になっています。
安倍元首相の下で始まった日中の共同研究(『日中歴史共同研究』)でも、日本側・中国側ともに「事件の存在」を前に進め、
- 日本側は「なぜ暴行が起きたのか」(命令系統の乱れ、捕虜の扱い、住民保護の欠落など)を分析、
- 中国側は「現地で何が起きたのか」(市街地や近郊での殺害・略奪の実態)を記録や証言から復元、
という役割分担で検証を進めました。
具体的に使われる史料の例としては、当時の裁判記録、海外記者や宣教師の日記、軍や警察の文書、埋葬団体の記録、写真類などがあります。写真のキャプション違い、証言の記憶違い、数字の重複といった「つまずきやすい点」を一つずつ点検しながら、全体像を組み立てていくやり方が一般的です。笠原十九司氏らの研究も、この積み上げに基づいており、「存在は前提、規模や経緯は引き続き検討」という整理で一致点が広がっています。
国際的な位置づけ:追悼日・ユネスコ登録・国際社会の評価
中国では、南京占領の日にあたる12月13日が「南京大虐殺犠牲者国家追悼日」とされ、国家行事として追悼式が行われています。
事件関連の文書群は2015年、ユネスコの記憶遺産(Memory of the World)にも登録されました。日本政府は当時、登録に抗議し、分担金の扱いをめぐって強い不満を表明しましたが、最終的には拠出を再開しています。
国際的には、「出来事そのものを否定する立場」は支持を得にくく、研究や教育の場では、被害の実態を資料で確認しつつ、数字の幅や評価の違いを併記するのが一般的です。つまり、世界の場では「存在は認める」「規模の見積もりは幅を持って示す」という扱いが主流になっています。
3.最大の争点「犠牲者数」をどう読むか

推計の幅と根拠資料(公判記録・埋葬統計・人口推計・一次史料)
犠牲者数は、使う資料と数え方で数字が動きます。代表的な根拠は次のとおりです。
- 公判記録:東京裁判や各軍事法廷の判決・証拠書類。規模感を示す数字が出ますが、当時の証拠収集の質や、定義(戦闘と処刑の線引き)に注意が要ります。
- 埋葬統計:市内・近郊で遺体収容を担った団体の記録。例として、団体別の「○日〜○日に××体を収容」のような日誌が残り、合算すると“何万”というオーダーになります。ただし、重複計上(同じ遺体を別団体が記録)や未収容(川流し、焼却)が生じます。
- 人口推計:占領前後の人口や難民数、避難の出入りを基に「差分」を見る方法。住民登録が機能していない期間があり、市内のみか近郊を含むかで結果が変わります。
- 一次史料(その場で書かれた記録):宣教師・医師・記者・市民の日記、写真、救護所の台帳、国際安全区委員会の報告など。場所・時間が具体的で、出来事の積み上げに役立ちますが、見える範囲が局地的である点を織り込む必要があります。
実務的には、①埋葬統計をベースに、②同日に近接地点での重複を除き、③未収容の可能性と郊外分を補正し、④一次史料で場所・時刻をクロスチェック――という手順で「幅」を示すのが堅実です。ここから、数万〜20万人といったレンジ表示が生まれます。
「30万人説」への検討:物理的可能性・反証・反論の整理
「30万人」はしばしば議論の的です。考え方の土台をそろえると、感情論を避けやすくなります。
- 物理的可能性の検討
- 期間:主な暴行が集中したのは占領直後の数週間という見立てが多い。仮に6週間で30万人とすると、日平均で約7,000人規模。これは「市内のみ」では説明しにくく、近郊や郊外(城外の農村や河川敷)を含める前提が必要です。
- 能力:大量処刑ができる兵力・弾薬・拘束場所の有無、遺体処理の方法(埋葬・焼却・河川投入)を併せて考えます。
- 反証側が挙げる論点(例)
- 占領直後の市内人口規模を踏まえると、市内だけで30万は過大。
- 埋葬統計の合算は“数万”台に収れんすることが多い。
- 同期の救護・配給記録と突き合わせると、30万規模の欠落は説明が難しい。
- 反論側が挙げる論点(例)
- 「南京市内」だけでなく広い作戦圏(城外・周辺県境)を含めれば、母数が拡大する。
- 未収容遺体(焼却・河川)や、記録喪失(混乱期の破棄・散逸)を補正すべき。
- 短期集中の大量処刑(河川敷や壕での集団射殺)では、埋葬統計に反映されにくいケースがある。
実務的には、①地理的範囲(城内/城外/近郊)、②時間幅(何週間を対象にするか)、③「誰を数えるか」(戦闘死か、戦闘後の処刑・暴行死か)を明確にし、それぞれの前提ごとに幅を提示するのが、読者にとっても理解しやすい出し方です。
証言の扱い方:尊重と検証の両立(バイアス・方法論・史料批判)
証言は、出来事の「質感」や「場面の連なり」を伝える重要な材料です。ただし、数字に落とす際は次の工夫で精度を高めます。
- 同地点・同時刻の相互参照:住民の証言と、救護所の台帳、宣教師の日記、写真・地図を地名・地物(門、橋、寺)で突き合わせる。
- 数え方の明確化:「見た人数」か「推測」か、「翌日に戻ったら増えていた」などの再目撃を切り分ける。
- 記憶のゆらぎへの配慮:年月を経た証言では、日付の前後や人数の丸めが起きやすい。当時に書かれた記録があれば優先して裏づけに使う。
- 翻訳・要約の誤差:外国語の日記・報告は訳語でニュアンスが変わることがあるため、原文語の用語(executed/killed in battle など)を確認する。
まとめると、証言は「場面の確定」に強く、数字は「複数資料の合成」に強い――この得意分野を組み合わせるのがコツです。読者が議論に参加しやすいよう、記事では(1)どの範囲を対象に、(2)どの資料を主に使い、(3)どの前提で補正したのか――を明記し、レンジで示すことを心がけます。これが、感情的な対立を避けつつ、実像に近づくためのいちばんの近道です。
まとめ
本稿では、(1)事件の存在認定、(2)犠牲者数の幅と根拠、(3)言葉の選び方という三つの柱で見てきました。まず、「あったのか/なかったのか」という問いについては、政府の公式説明や主要研究の積み上げから、存在を否定しない立場が共有されています。一方で、「どれだけの規模だったのか」は、資料の種類や地理的範囲、対象期間の取り方で数字が動き、確定困難であることも確認しました。
数字をめぐる議論で大切なのは、前提をそろえることです。たとえば、(A)城内だけか近郊を含むか、(B)占領直後の何週間を対象にするか、(C)戦闘による死亡を数えるのか、その後の処刑・暴行死も含めるのか――。この三点を示したうえで、幅(レンジ)で提示するのが、読者にも伝わりやすい出し方です。
資料の使い方にもコツがあります。埋葬統計は全体像のたたき台に、一次史料(日記・台帳・写真)は場所と時刻の特定に、公判記録は出来事の法的評価と規模感の確認に向きます。さらに、証言は場面の連なりを描くのに強い一方、人数化には慎重さが要る――こうした役割分担の理解が、感情的な対立を避ける助けになります。
現代の私たちができるのは、言い切りを避け、重ねられた資料を丁寧に読む姿勢を持つことです。たとえばニュースやコラムを読む際、①どの範囲・期間・対象を数えているか、②どの資料に基づく主張か、③反対の資料や弱点に触れているか――この三つを確認するだけで、受け止めは大きく変わります。
そして、記憶の継承は「過去の出来事を正確に伝えること」と同時に、言葉が現在の社会に与える影響を自覚することでもあります。
存在認定と人数推計を混同しない、相手の前提を確かめる――その基本を守ることが、事実に近づく最短ルートです。今回の議論が、歴史を語る言葉と向き合うための実用的な視点として、読者一人ひとりの判断の助けになれば幸いです。
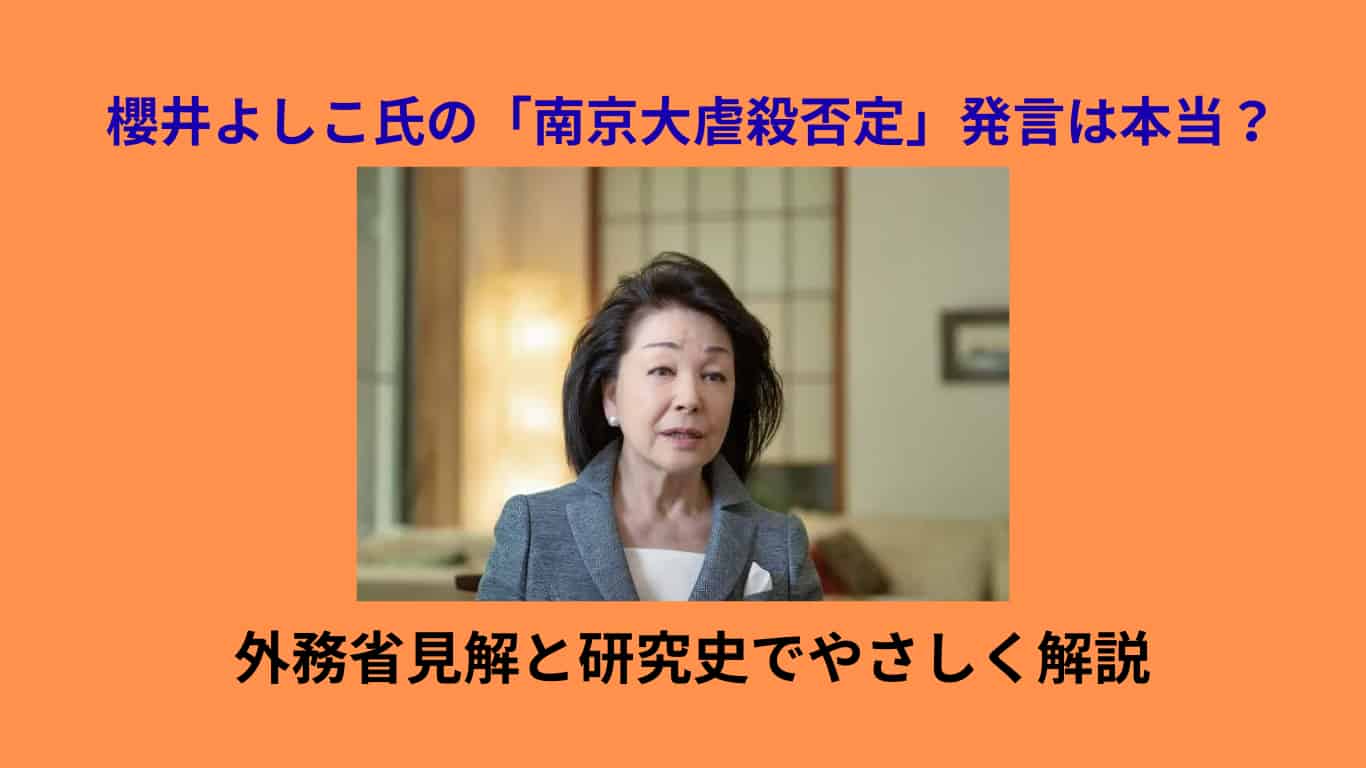
コメント