最近ニュースでも大きく取り上げられている「クマの市街地出没」。北海道では特に深刻で、農作物被害や人身事故のリスクが増えています。
こうした状況に対応するため、2025年9月から「緊急銃猟制度」が始まりますが、その運用をめぐって北海道猟友会が「場合によっては発砲を拒否しても良い」と支部に通知したことが話題になっています。
なぜ猟友会がこうした判断を下したのか?背景には、発砲後の責任や補償制度の欠如といった大きな課題があるのです。
本記事では、緊急銃猟制度の仕組み、猟友会の苦悩、そして行政の責任について、わかりやすく整理してお伝えします。
はじめに
クマやイノシシの市街地出没とその問題
こんにちは!一般市民の私が今回お伝えしたいのは、北海道をはじめとする地域で急増しているクマやイノシシの市街地出没の問題です。
これらの動物が人間の生活圏に侵入する原因として、森林の減少や食物の不足が挙げられます。
特に、クマが農作物やゴミを漁るために集落近くに現れることが多くなり、これが人身事故や物的損害を引き起こしています。
2022年には斜里町で撮影されたヒグマの映像が話題になり、この問題がさらに注目を集めました。北海道猟友会などが積極的に対応していますが、問題解決にはまだ多くの課題が残されています。
新たな「緊急銃猟」制度の導入と猟友会の対応
2025年9月1日から導入される「緊急銃猟」制度では、これまで発砲が制限されていた市街地や夜間でも、クマやイノシシを銃で駆除できるようになります。
この制度が導入される背景には、動物による被害の増加と住民の不安があります。
しかし、この新制度に対する懸念の声も多いのが現実です。
北海道猟友会は、発砲に対する責任が個々のハンターに重くのしかかることを懸念しており、発砲後に人身被害が発生した場合、ハンターがその責任を負う可能性があることが問題視されています。
猟友会は、発砲の判断を慎重に行うように支部に通知し、環境省からの適切な対応を求めています。
1.「緊急銃猟」制度の概要
制度の背景と目的
「緊急銃猟」制度は、増加するクマやイノシシの市街地での出没に対応するため、2025年9月1日から導入される新しい規則です。
これまでは、都市部や夜間の発砲は警察官の許可を得る必要があり、発砲する条件が厳格でした。
しかし、動物の被害が深刻化する中で、市町村の判断で発砲を認めることで迅速に駆除できるようになります。特に農作物や住民の安全を守るために、法律が改正され、より柔軟な対応が可能となりました。
この制度により、クマやイノシシによる人身事故が防げることが期待されています。
発砲に関する新しいルール
新しい「緊急銃猟」制度では、動物が市街地に現れた場合、地方自治体の判断で発砲が認められます。
ただし、猟友会が懸念しているのは、発砲後のリスクです。銃弾が人に当たる可能性が残るため、現場のハンターにとっては非常に大きな責任が伴います。
猟友会は、発砲による事故が発生した場合に補償がないことを問題視しており、そのリスクを軽減するために慎重な判断を求めています。
また、環境省への対応を求めており、制度運営に対する不安の声が上がっています。
市町村の役割と避難指示
「緊急銃猟」制度の実施において、市町村の役割は非常に重要です。
発砲を行う前に、周辺住民に避難指示を出すことが義務づけられています。これにより、無関係な市民が銃弾に巻き込まれるリスクを減らすことができます。
市町村が迅速に避難指示を出すことが求められる一方で、猟友会は発砲のタイミングや場所を慎重に選ばなければなりません。
猟友会の判断が住民の安全に直結するため、その責任は非常に重いのです。
2.猟友会の立場と課題
発砲判断の責任とリスク
「緊急銃猟」制度の導入により、クマやイノシシへの銃撃がより迅速に行えるようになりますが、その判断には大きなリスクが伴います。
特に、発砲後に人身事故が発生した場合、ハンターがその責任を負わなければならないため、猟友会のメンバーには非常に大きなプレッシャーがかかっています。
銃を発砲するタイミングが非常に重要であり、周囲に市民がいないかを常に確認しなければならないため、慎重な判断が求められます。
万が一、誤って発砲してしまった場合の法的責任を考慮すると、ハンターには非常に大きなリスクが伴います。
環境省からの回答を待つ猟友会
北海道猟友会は、環境省に対して発砲時のハンターの身分保障について明確な対応を求めています。
現在、発砲後に事故が起きた場合、ハンターが責任を負う可能性が高いため、猟友会としては不安を抱えたまま運用を開始することに懸念を示しています。
環境省から十分な回答が得られない中で、猟友会のメンバーたちは、この制度が現場に与える影響に不安を感じています。今後の環境省からの回答が、制度の運用に大きな影響を与えることでしょう。
ハンターの不安と補償制度の欠如
「緊急銃猟」制度の進展の中で最も大きな課題となっているのは、発砲による事故が発生した場合の補償制度がないことです。
現在、猟友会のメンバーは、万が一事故が起きた場合に個人の責任として対応しなければならない状況です。
猟友会は補償制度の整備を強く求めており、特に予期せぬ事態が発生する可能性があるため、ハンターがリスクを回避することは難しいと感じています。
制度運用の開始前に補償制度が整備されることを期待しています。
3.行政の責任と猟友会の今後
猟友会の重要性と行政の対応
北海道の猟友会は、クマやイノシシの駆除を行う上で非常に重要な役割を担っています。
これらの動物が市街地に出没することで住民の安全が脅かされる中、猟友会の活動は必要不可欠です。
しかし、現場で活動するハンターたちはそのリスクを一手に背負っており、行政の支援が不可欠です。
特に、ハンターが発砲に伴う責任を一人で負うのではなく、行政が適切な補償や支援を行うことが求められています。
猟友会は法的な保護や補償制度の整備を行政に強く要望しており、今後の制度運営には行政の積極的な関与が欠かせません。
自衛隊や警察OBの活用案
猟友会が抱える人手不足やクマ駆除の際の緊急対応力の不足を解消するために、自衛隊や警察OBの活用案が提案されています。
これらの人々は過去に危機的状況での対応経験が豊富で、銃の取り扱いにも慣れており、猟友会の活動を支援するための有力な人材となります。
過去の訓練や経験を活かして、市街地での銃駆除における精度を高めることができるため、こうした人材を予備職員として活用することは猟友会の負担軽減につながります。
市民への安全保障と猟友会支援
市街地でのクマやイノシシの出没を防ぐため、猟友会の活動を支援することは市民の安全にも直結します。
行政は猟友会を支援するために、財政的な支援や補償制度を整備する必要があります。
また、市民も猟友会の重要性を認識し、協力的な姿勢を持つことが求められます。
地域住民が猟友会の活動に協力することで、より効果的に動物による被害を減らすことができます。このように、猟友会の支援は地域社会全体の安全保障に繋がる重要な要素となるのです。
4.砂川ハンター事件と今回の制度への影響
事件の経緯
北海道砂川市では2018年、市の依頼を受けた猟友会の支部長が、市職員や警察官の立ち会いのもとで仔ヒグマを駆除しました。
しかしその後、跳弾で同行者の銃が壊れたという証言があり、ハンターは書類送検されました。結果的に不起訴となったものの、北海道公安委員会は「建物に弾が届く恐れがあった」として銃の所持許可を取り消しました。
裁判の流れ
この処分を不服として裁判が行われ、2021年の一審(札幌地裁)では「市の要請に基づく駆除であり、警察官も抑止しなかった」ことなどから、処分は違法とされ許可取り消しは覆されました。
しかし、2024年の控訴審(札幌高裁)では逆に「建物に弾が届く可能性があった」と判断され、一審判決が取り消されました。
制度への影響
この砂川ハンター事件は、猟友会のメンバーに大きな不安を残しました。「行政の要請で駆除しても、事故があれば全て自分の責任になる」という状況が明らかになったからです。
今回の「緊急銃猟」制度を前に、北海道猟友会が「発砲を断ってもよい」と通知した背景には、この事件の教訓が色濃く影響しています。
猟友会の現場感覚からすれば、命がけで対応しても行政から守られない可能性がある以上、慎重にならざるを得ないのです。
事件の発端と概要
- 発端(2018年)
北海道砂川市でヒグマの出没に対応するため、猟友会の砂川支部長である池上治男さんが、市職員・警察官が立ち会う中、ライフルで仔ヒグマを駆除しました。これは市からの依頼によるものでした。 - 書類送検と行政処分
2か月後、跳弾によって同行のハンターの銃が破損したとの証言を受け、警察に書類送検されましたが不起訴に。その後、北海道公安委員会は「建物に弾が届く恐れがあった」として猟銃所持許可を取り消しました。
1審判決とその理由
- 裁判所の判断(2021年)
札幌地裁は、市の要請に基づく駆除であり、警察官が発砲を抑止しなかったこと、安全に配慮した判断だったことなどを踏まえ、「処分は裁量権の濫用で違法」と判断し、許可取り消しを取り消しました。
控訴審の判決
- 高裁による判断(2024年10月)
札幌高裁は、たとえヒグマに命中しても跳弾によって住宅などに弾が届く可能性があるとの認定から、「建物に向けた銃行為に当たる」として、ハンターの訴えを棄却し、一審判決を取り消しました。
なぜ今でも語られるのか?
この事件は、公益目的でクマ駆除に尽力したハンターが処分を受けたという事実が、他の猟友会員に強い不安をもたらしました。特に、「緊急時でも行政の保護がない」という事実は、今回の「発砲を断ってよい」という通知の背景の一つでもあり、制度運用に不信感を残す大きな要因となっています。
事件のポイントをまとめると:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆除の背景 | 市からの要請 → 駆除実施 |
| 争点 | 安全確認の不備 → 許可取り消し |
| 判決の流れ | 1審:許可取り消しは違法→ 2審:取り消しは妥当と判断 |
| 社会的影響 | 他のハンターにも不安拡大 → 制度運用への慎重姿勢へ |
まとめ
「緊急銃猟」制度の導入は、クマやイノシシの市街地への出没に対応するための重要なステップですが、現場で活動する猟友会のメンバーには多くの責任が伴います。
特に、発砲後のリスクや補償制度の欠如が課題となっており、猟友会はその運用に慎重な立場を取っています。
行政の支援が不可欠であり、補償制度の整備や猟友会の活動支援が急務です。
また、自衛隊や警察OBなどの経験豊富な人材の活用は、今後の課題解決に向けての一つの解決策となるでしょう。
市民の安全を守るためには、猟友会と行政が協力し、共により安全で効果的な対応を進めることが求められています。
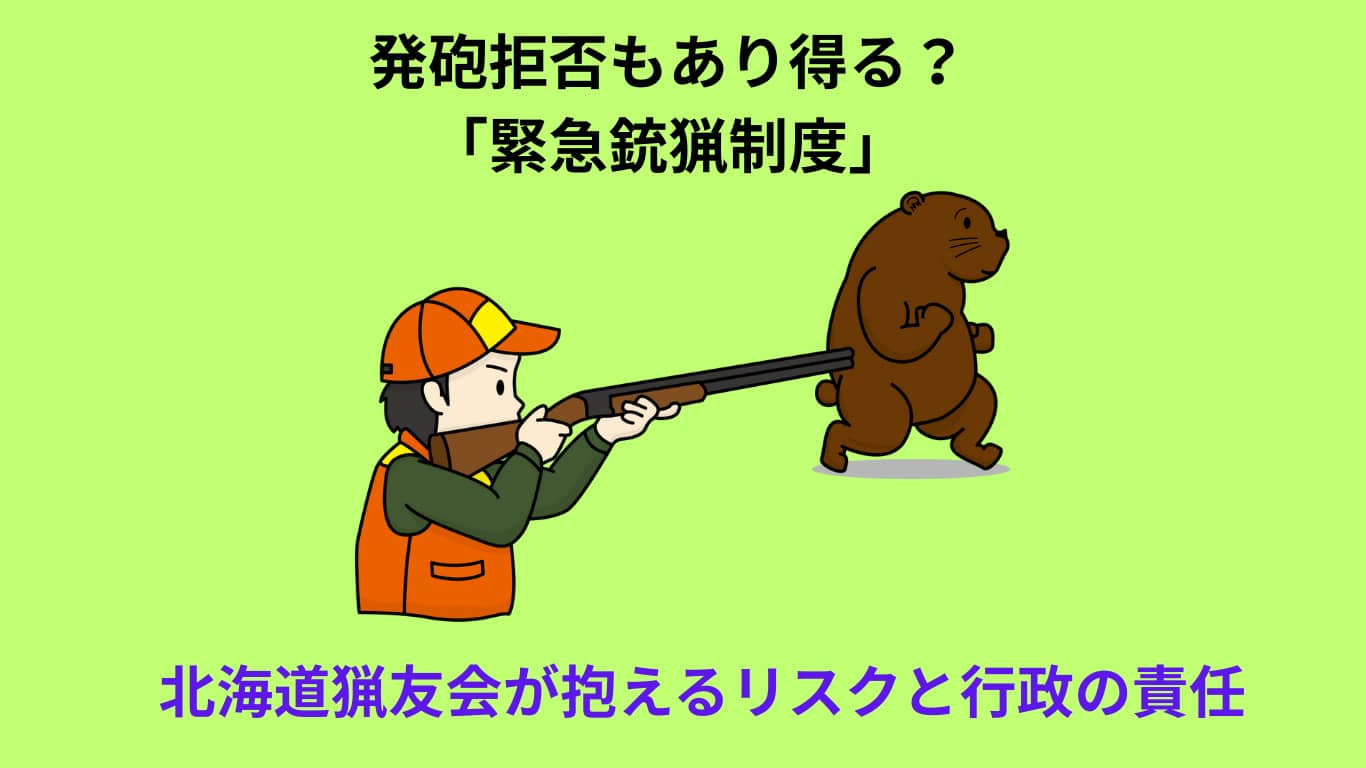
コメント