「キャンプ用品は防災にも使える」とよく言われますが、果たして本当にそうでしょうか?
寝袋やバーナーは便利でも、災害直後に街中で焚き火をするのは現実的ではありません。
ソロキャンプの達人・ヒロシさんは「キャンプと防災を一緒にするのは危うい」と警鐘を鳴らします。
本記事では、ヒロシさんが実際に取り入れている在宅避難の考え方や、本当に役立つ防災グッズを詳しく紹介します。家族やペットを守るための現実的な備えを、ぜひ一緒に考えてみましょう。
はじめに
芸人でありソロキャンプの達人でもあるヒロシさんの言葉を通して、防災の現実を一緒に見ていきたいと思います!
キャンプと防災をめぐる誤解
「キャンプ用品は防災に役立つ」とよく言われます。確かに、寝袋やマットがあれば避難所の固い床でも体を休めやすく、バーナーやガス缶があれば調理に困りません。
しかし、芸人でありソロキャンプの達人でもあるヒロシさんは、この考え方に疑問を投げかけます。
たとえば災害直後に街中で焚き火をするのは現実的ではありませんし、釣り針を持っていても池の鯉を釣って食べることはできません。
キャンプと防災は似ているようでいて、実際には大きく異なる場面が多いのです。
ヒロシさんは「こじつけのように防災と結びつけるよりも、現実に即した備えを考えるべきだ」と語ります。
ヒロシが語る「現実的な備え」とは
ヒロシさんが重視しているのは「在宅避難」という視点です。
自宅が安全であれば、避難所に行くよりも自宅で過ごす方が落ち着き、必要なものも手元にあります。そこで本当に大切になるのは、水や食料、そして防犯対策です。
彼が特にすすめるのは「携帯浄水器」。川やため水をろ過すれば、飲み水の確保が容易になります。
また、非常時には争いが起きることを前提に考えるべきだとし、防犯用にクマ撃退スプレーまで用意しています。
さらに、氷砂糖や羊羹のような「心を支える甘味」を備えておくことも重要だと語ります。
つまりヒロシさんの防災観は「教科書的なマニュアル」ではなく、「自分の生活や家族、ペットを守るために何が本当に役立つのか」を突き詰めたものなのです。
1.サバイバルとキャンプの違い

災害時に焚き火はできない
キャンプでは焚き火が楽しみのひとつですが、災害時には現実的ではありません。
街中で火をおこすことは危険であり、煙や匂いが周囲の人々を不安にさせる可能性もあります。
ヒロシさん自身も、キャンプを始めた当初は「火おこし道具さえあれば何とかなる」と思っていたそうですが、都会での災害を想像するとそれは不可能だと気づいたと語ります。
むしろ、カセットコンロやガスバーナーのように安全に火を扱える道具こそ役立ちます。焚き火が象徴する“サバイバル”は、実際の災害とは結びつかないのです。
在宅避難が現実的な理由
多くの人が「避難所に行くのが当然」と思いがちですが、ヒロシさんは「家が無事なら自宅にとどまるのが最も安心」と考えています。
体育館などの避難所は、プライバシーの確保が難しく、大人数が集まることで精神的なストレスも増します。見知らぬ人との共同生活に不安を抱く人は少なくありません。
一方、自宅にいれば布団で眠ることができ、慣れた環境で過ごせます。
食器や生活用品もそろっているため、最低限の備蓄さえあれば生活の質を大きく落とさずに済みます。こうした現実的な視点から、ヒロシさんは「在宅避難こそ最優先」と強調します。
避難所生活と個人の適応力
もちろん、自宅が倒壊するような被害を受けた場合には避難所に行かざるを得ません。
しかし、その環境はキャンプとはまったく違います。キャンプは「好きな仲間」と「十分な装備」が前提のレジャーであり、互いに助け合う余裕があります。
一方、避難所では状況が異なります。物資は限られ、知らない人々と狭い空間を分け合わなければなりません。
例えば寝袋やマットを持参すれば多少快適になりますが、それすら持っていない人も多いのです。
ヒロシさんは「サバイバル気分で防災を語るのは危うい」と警鐘を鳴らし、避難所での生活には個人の適応力が試されると指摘します。
つまり、キャンプのスキルをそのまま防災に結びつけるのではなく、状況ごとに現実的な備えを考えることが大切なのです。
2.本当に役立つ防災グッズ

命を守る携帯浄水器の重要性
ヒロシさんが「一番大事」と語るのは、水の確保です。食べ物が数日なくても人は生きられますが、水がなければ命に直結します。そこで役立つのが「携帯浄水器」です。
川やため池の水をろ過して飲めるようにする小型の道具で、1万円前後で手に入るものも多くあります。
実際に川の水をくんで、フィルターを通すと安全な飲み水になる仕組みです。
都市部に住む人は「給水車が来るから大丈夫」と思いがちですが、実際には赤ちゃんや高齢者が優先され、大人がすぐに水を得られる保証はありません。そんな時、この浄水器があれば安心につながります。
防犯意識とクマ撃退スプレーの発想
災害時に見落とされがちなのが「防犯」です。
物資が不足すれば、争いや奪い合いが起こる可能性は十分にあります。
ヒロシさんは「平常時でさえ電車で席を譲らない人が多い。非常時に助け合いが自然に生まれるとは思わない」と厳しい現実を指摘します。
そのため、防犯対策として携帯しているのが「クマ撃退スプレー」。北海道でのヒグマ対策用ですが、人に向けて噴射するのではなく、威嚇のために持っているそうです。
実際に使わずとも、手にしているだけで「守る準備がある」という意思表示になり、抑止力として働きます。これは、防災の一環として「自分と家族をどう守るか」を真剣に考えた結果の発想です。
備蓄品の選び方と実例(水・食料・甘味)
水と防犯以外に、具体的な備蓄品も重要です。ヒロシさんの自宅には20リットル以上入るウォータータンクや10年保存水が備えられています。
食料としては、水を加えるだけで食べられる登山用のアルファ米や、茹でて簡単に食べられるパスタを常備。加えて、乾パンや塩、氷砂糖、羊羹といった長期保存できる食品もストックしています。
特に氷砂糖や羊羹のような「甘味」は、エネルギー補給だけでなく心の支えになります。疲れ切った時に一口の甘いものが気持ちを落ち着ける効果は大きく、精神的な備えとしても役立つのです。
ヒロシさんは「欲しい時に手に入らないのが非常時。だからこそ、普段から自分で用意しておくことが大切」と強調します。
3.ペットや家族を守るために
車での避難と移動手段の確保
災害が大規模で自宅が住めなくなった場合、避難所に行く以外の選択肢として「車での避難」があります。
ヒロシさんはジムニーと軽トラックの2台を所有し、緊急時にはジムニーに必要な荷物を積んで移動する計画を立てています。
車があれば、一時的に寝泊まりすることもでき、電気やガスが復旧している地域へ移動することも可能です。
都市部に住む人にとっては、マイカーの有無が避難行動の自由度を大きく左右します。
燃料を常に半分以上入れておく、車内に毛布や水を置いておくなど、小さな工夫が大きな安心につながります。
猫との避難シミュレーション
ヒロシさんにとって大きな課題は「愛猫との避難」です。
普段からケージに慣れていない猫は、災害時に突然閉じ込めると強いストレスを感じてしまいます。
実際に地震が起きた際には、恐怖で家のどこかに隠れてしまい、すぐに連れ出せない可能性もあります。
そのため、平常時からケージに慣れさせる練習をしておくことが大切です。
猫や犬を飼っている家庭は、ペット用の餌や水、トイレ用品を数日分まとめておくことも必須です。
「自分だけ逃げる」のではなく「一緒に逃げられるか」を考えることが、家族同然のペットを守るために欠かせません。
家族構成に応じた必需品(オムツ・生理用品など)
防災の備えは世帯によって大きく異なります。
小さな子どもがいる家庭ではオムツや粉ミルクが必需品となり、女性にとっては生理用品が欠かせません。
しかし、非常時に他人から分けてもらえる保証はなく、むしろ人に見られることでトラブルになることもあります。ヒロシさんは「必要なものは自分で用意しておくしかない」と強調します。
例えば3日分のオムツや、1週間分の生理用品を防災袋に入れておく、さらに使い慣れた日用品や薬を備えておくことで、緊急時の負担を大きく減らせます。
非常時には「最低限の衣食住」だけでなく、「普段と変わらない生活を少しでも維持できるか」が心身の安定につながります。家族構成に合わせた現実的な備えこそが、防災の要といえるのです。
まとめ
キャンプと防災は似ているように見えて、その本質はまったく異なります。
災害時に必要なのは「非日常を楽しむ技術」ではなく、「現実を生き抜く備え」です。
ヒロシさんが語るように、焚き火や釣り道具ではなく、携帯浄水器や水の備蓄、防犯の意識が命を守ります。そして、氷砂糖や羊羹といった小さな甘味が、非常時の心を支える力になります。
また、自宅で安全に過ごせるなら在宅避難が最も現実的であり、車での移動やペットとの避難シミュレーションなど、家族の状況に合わせた具体的な準備も不可欠です。
オムツや生理用品など、他人に頼れないものは特に「自分で備える」姿勢が求められます。
「枕元に靴は置いていない」というヒロシさんの言葉には、形だけのマニュアルに縛られるのではなく、自分や家族に合った防災を考えるべきだという現実的な視点が込められています。
防災とは、正解がひとつではない世界です。自分自身の暮らしに寄り添った備えを積み重ねることこそ、真に役立つ防災への第一歩なのです。
私自身もこの記事を書きながら「自分の家族や暮らしに合った備えをもっと見直そう」と強く感じました。皆さんも、ぜひ自分なりの防災を考えてみてくださいね!
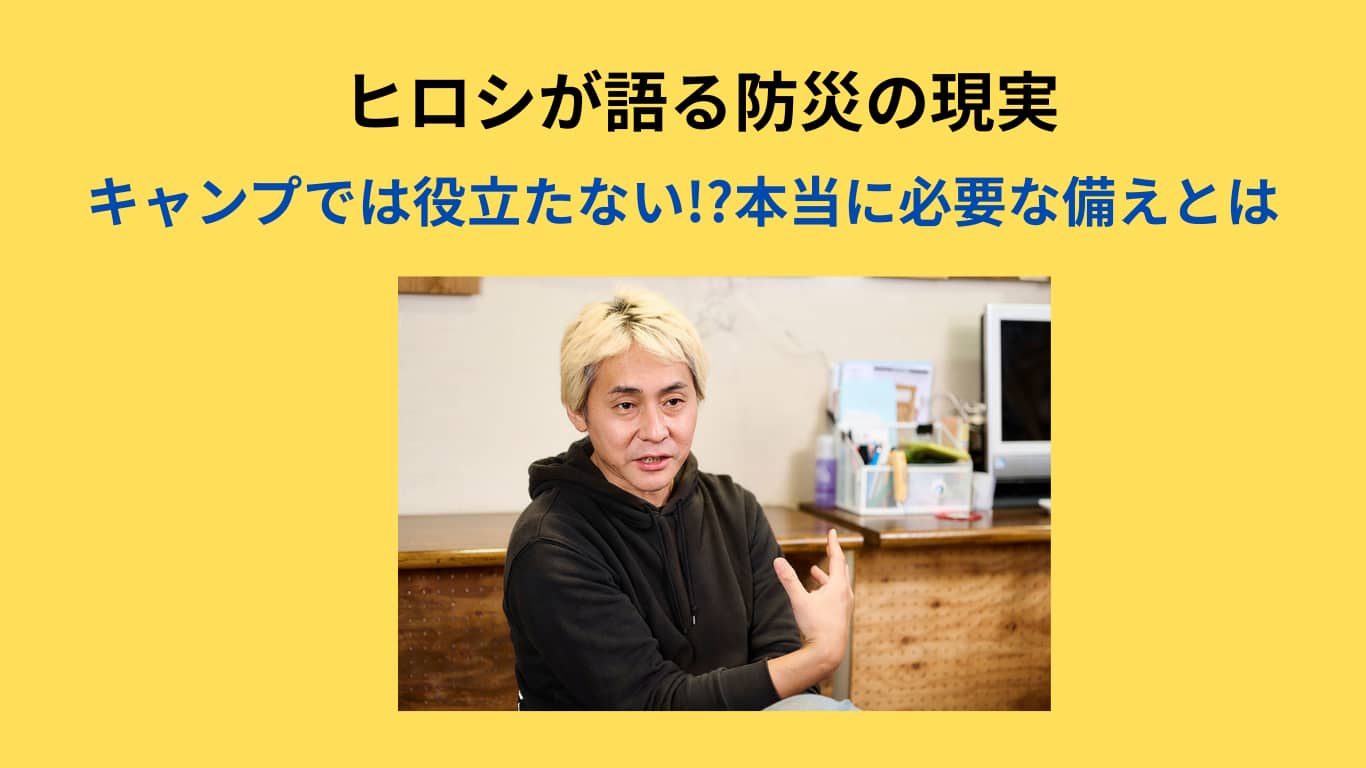
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3e5d48fb.c54a9181.3e5d48fc.24ea18fd/?me_id=1423813&item_id=10000030&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkeynice%2Fcabinet%2F10959095%2Fimgrc0090740488.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b6b2c89.f346f8f2.4b6b2c8a.bba488e8/?me_id=1346464&item_id=10000282&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcubicsense%2Fcabinet%2F10571347%2F10650530%2F10650554%2Fimgrc0136624339.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
コメント