『火垂るの墓』に登場するおばさんは、子どもの頃に観ると「意地悪な人」という印象が強く残りますが、大人になってからは違う背景が見えてきます。
高畑勲監督は「おばさんは特別冷酷ではなかった」と語り、時代によって“正義”の形が変わる恐ろしさを指摘しました。
このテーマは、NHK朝ドラ『あんぱん』の「逆転しない正義を探して」という物語とも響き合います。
本記事では、監督のコメントや戦時下の背景を踏まえ、時代を超えて考えるべき“正義”の在り方を掘り下げます。
はじめに
中川翔子が語った「火垂るの墓」感想と反響
2025年8月15日、日本テレビ「金曜ロードショー」で約7年ぶりに地上波ノーカット放送された高畑勲監督の名作『火垂るの墓』。
放送後、タレントの中川翔子さんが自身のX(旧Twitter)で「節子がかわいくてかわいそうでつらい」「やっぱり火垂るの墓のおばさん意地悪すぎる」と率直な感想を投稿しました。
この言葉は瞬く間に拡散され、「本当にひどい」「わかる!」という共感の声から、「年を取って見るとおばさんの言動も理解できる」という大人目線の意見まで、幅広い反応が寄せられました。
コメント欄には、戦時中の厳しい生活事情や、疎開を受け入れる側の複雑な心情を踏まえた意見も目立ち、作品が世代や立場によって全く違った受け止め方をされていることが浮き彫りになりました。
高畑監督は過去のインタビューで、「当時の社会は非常に抑圧的な全体主義で、おばさんの言動も特に冷酷ではなかった」「清太の失敗は、その時代に抗い純粋な二人きりの家庭を築こうとしたこと」と語っています。
そして「いつかまた時代が逆転すれば、おばさん以上に清太を批判する時代が来るかもしれず、それが恐ろしい」とも述べています。
この“時代によって変わる正義”という視点は、今の私たちがこの作品をどう見るかに大きく関わります。
視聴者が抱くおばさん像の変化
『火垂るの墓』のおばさん像は、視聴者の年齢や経験によって大きく変化します。
子どもの頃に観たときは、清太と節子をいじめる「意地悪な大人」として強く印象に残る一方、大人になってからは「家族を守るために必死だった人」として見えることもあります。
特に戦時下の日本では、働き盛りの男性が戦地に行き、残された女性や高齢者は軍需工場や農作業に追われ、物資不足の中で暮らしていました。
そんな状況で、都会からやってきた疎開児童を受け入れるのは、経済的にも精神的にも大きな負担だったはずです。こうした背景を知ることで、「意地悪」という単純なラベルでは語れない、多面的なおばさん像が見えてきます。
このテーマは、NHKの朝ドラ『あんぱん』にも通じます。
やなせたかしさんをモデルにしたこの作品では、「逆転しない正義を探して」というメッセージが物語の軸になっています。
戦中・戦後という価値観が揺れ動く時代においても、自分が信じる正義を持ち続けられるのか──その問いは、『火垂るの墓』が投げかける「時代が変われば正義も変わる」というテーマと深く響き合います。
1.おばさんは本当に意地悪なのか?
子ども目線で見たおばさんの印象
子ども時代に『火垂るの墓』を初めて観たとき、多くの人にとっておばさんは「清太と節子をいじめる意地悪な人」という強い印象で残ります。
食事を減らす場面や、冷たい言葉を浴びせる姿は、兄妹を応援する側としては耐えがたいものです。
節子がしょんぼりする表情、清太が悔しさをこらえる顔…あのシーンを見たら、「この人さえいなければ」と思わずにはいられません。当時の私もそうでした。
大人になると見えてくるおばさんの背景
ところが、大人になってから見直すと、違う側面が見えてきます。戦時中は食べ物も物資も不足し、自分の家族を守るだけで精一杯。
そこに突然、親を亡くした兄妹がやって来れば、家計も気力も圧迫されます。
おばさんもまた、夫や息子を戦地に送り出していたかもしれません。高畑監督は「おばさんの言動は特別に冷酷ではなかった」と語っています。
時代の価値観を踏まえると、あれが“普通”の反応だった可能性は高いのです。
戦時下の生活苦と疎開受け入れの現実
当時の農村は、若い男性がほぼ全員戦地に行き、残った人たちは農作業と軍需工場の仕事を掛け持ちしていました。
食料は配給制で、芋や雑穀ばかり。そんな中で疎開児童を迎えるのは、助け合いというより「食い扶持が増える」という切実な負担でした。
おばさんの厳しさは、単なる意地悪ではなく、生きるための必死さだった──そう思うようになりました。
2.清太と節子の選択とその結果

純粋な兄妹の生活を守ろうとした清太
清太は、母を亡くしてから節子を守ることに全力を注ぎます。
おばさんの家で肩身の狭い思いをし、やがて「二人だけで生きる」と決意。
蛍を集めたり、川で遊んだりする姿は微笑ましい反面、生活基盤を失う危険な選択でもありました。
社会的役割や勤労奉仕を果たさなかったことへの批判
当時の社会では、年齢に関係なく働くのが当然とされていました。
清太が勤労奉仕や農作業に積極的に参加しない姿は、おばさんにとって苛立ちの種だったはずです。
監督は「清太の失敗は、全体主義の時代に抗って純粋な家庭を築こうとしたこと」と指摘しています。
その美しい理想が、時代の現実とはあまりにもかけ離れていたのです。
家を飛び出す決断がもたらした悲劇
防空壕での暮らしは、自由でありながらも過酷でした。食料は尽き、節子は衰弱。清太は盗みや物々交換で必死に食べ物を探しましたが、戦争末期の飢餓の中ではどうにもなりません。
結果として、愛する妹を失うという最悪の結末を迎えます。
3.時代背景から考えるおばさん像
戦局悪化と農村の労働力不足
1945年、日本の戦局は極限まで悪化していました。農村では労働力が不足し、畑を耕す手も足りない中で軍需生産も同時にこなす必要がありました。
この状況で疎開児童は「手伝い手」にならない限り、家族の負担を増やす存在となってしまいます。
疎開される側の心理と受け入れ負担
都会から来た子どもたちは、農作業や家事に不慣れで、教える手間もかかります。
おばさんの苛立ちは、こうした現実的な負担からも来ていました。「意地悪」という一言では片付けられない事情が、そこにはあったのです。
戦争がもたらす価値観の対立と変化
戦時下では、個人より共同体が優先される価値観が当たり前でした。
高畑監督は、「いつか時代が再び逆転したら、おばさん以上に清太を批判する時代が来るかもしれない」と警鐘を鳴らしています。
この視点は、NHK朝ドラ『あんぱん』のテーマ「逆転しない正義を探して」ともつながります。
戦争や混乱の中でも、揺らがない正義を持ち続けることが、いかに難しいか──二つの作品は時代やジャンルを超えて、その問いを私たちに投げかけているのです。
まとめ
『火垂るの墓』は、年齢や立場によって見え方が変わる作品です。
子どもの頃はおばさんを憎み、大人になるとその背景を理解し始める。清太の行動は愛情から出たものでしたが、時代の現実にはあまりにも脆かった。
おばさんも清太も、どちらも生き抜こうとしていた──その事実を忘れてはいけないと思います。
そして、このテーマは『あんぱん』が描く「揺るがない正義」の探求とも響き合います。
時代がどう変わろうと、私たちは何を守り、何を手放すのか──この問いは、今を生きる私たちにも突きつけられているのです。
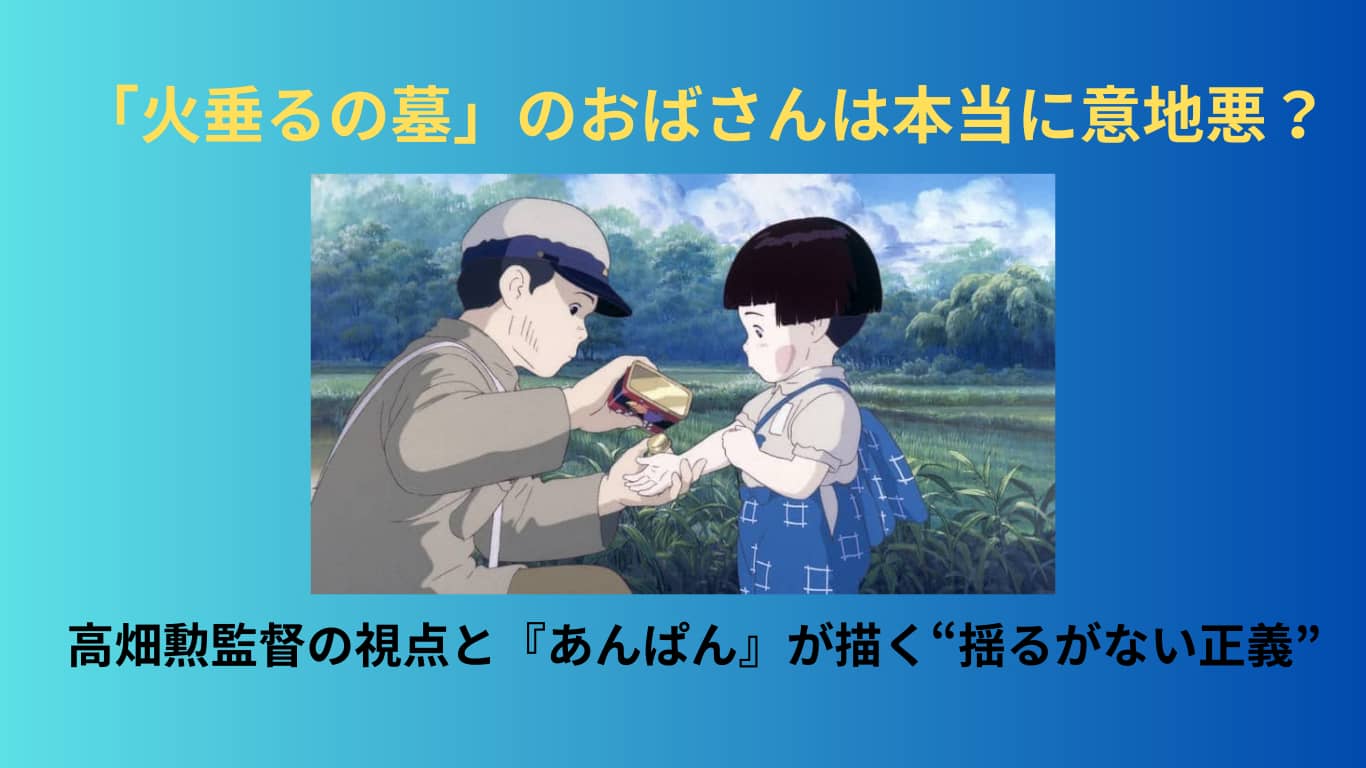
コメント