猫と暮らしている方や猫好きのお子さんがいる家庭では、日常的に猫と触れ合う機会が多いですよね。
ですが、猫にひっかかれたあとに発熱やリンパ節の腫れが続く場合は「猫ひっかき病」の可能性があります。
特に5〜14歳の子どもに多く発症し、全身倦怠感が長引くこともあるため注意が必要です。
この記事では、猫ひっかき病の原因や症状、子どもに多い理由、予防方法、そしてひっかかれたときの応急処置や医療機関を受診する目安についてわかりやすく解説します。
はじめに
猫ひっかき病が注目される理由
猫ひっかき病は、猫にひっかかれたり、かまれたりしたことがきっかけで起こる感染症です。
特に、野良猫との接触や屋外に出る機会の多い猫が感染源となることが知られています。
症状は軽い発熱やリンパ節の腫れだけで終わる場合もあれば、全身倦怠感や視力障害など思わぬ重症化につながることもあります。
近年はペットブームにより猫と触れ合う機会が増えており、この病気に関する知識の必要性が高まっています。
知らずに過ごしてしまうと「ただの疲れや風邪」と見誤り、受診が遅れるケースも報告されています。
子どもに多い発症リスクと背景
猫ひっかき病は、特に5歳から14歳の子どもに多く見られます。
子どもは動物への好奇心が強く、無防備に野良猫に触れたり、興奮した猫を抱こうとしてひっかかれる場面が多いからです。
また、傷の処置が不十分なまま遊びを続けてしまうことも、感染のリスクを高めます。
さらに西日本では猫ひっかき病の発症が比較的多く、これはネコノミの数や地域の気候条件が影響していると考えられています。
子どもが猫に触れるときの注意点や、ひっかかれた後の正しい対応を知っておくことは、家庭や学校での予防に直結する重要なポイントです。
1.猫ひっかき病とは?

原因となる細菌と感染経路
猫ひっかき病は、猫の体内にいる「バルトネラ・ヘンセレ」という細菌が原因で起こります。
この細菌は猫自身にとってはほとんど害がありませんが、人に感染すると発熱やリンパ節の腫れといった症状を引き起こします。
細菌はネコノミという寄生虫を介して猫に広がり、その猫が人をひっかいたり、かんだりすることで人の体内に入ります。
さらに、猫の毛に付着したノミの糞を触った手で目や傷口をこすると感染することもあります。
飼い猫であっても10%程度はこの細菌を持っているとされ、特に屋外に出る猫は注意が必要です。
発症までの流れと症状の特徴
猫にひっかかれたりかまれたりすると、数日以内に小さな赤いブツブツ(丘疹)が出てくることがあります。
その後1〜2週間ほどで、ひっかかれた場所に近いリンパ節が腫れてきます。
例えば腕をひっかかれた場合は脇の下のリンパ節が腫れ、足の場合は足の付け根のリンパ節が大きくなるケースが多いです。
この腫れは痛みを伴うこともあり、微熱や体のだるさ、頭痛、食欲不振などが同時に現れることも少なくありません。
多くは数週間から数カ月で自然に治りますが、子どもや体力が低下している人は症状が長引くことがあります。
重症化や非定型例のリスク
ほとんどの場合は自然に治る病気ですが、まれに重症化することがあります。
例えば、目の奥に炎症が起こり視力が低下する「視神経網膜炎」や、肝臓や脾臓にしこりのような炎症(肉芽腫)ができることがあります。
こうした非定型例では、リンパ節が腫れないこともあり、「原因不明の熱が続く」という症状だけで長期間苦しむケースもあります。
特に1カ月以上発熱や倦怠感が続く場合は、猫ひっかき病を疑って検査を受けることが早期発見につながります。
2.発症リスクと感染しやすい人

子どもに多い理由と行動特性
猫ひっかき病の発症者の約7割は子どもです。特に5歳から14歳の子どもは、動物への興味が強く、無防備に猫を抱き上げたり、顔を近づけたりすることが多い傾向があります。
遊びの最中に猫を驚かせてしまい、ひっかかれるケースも少なくありません。
さらに、子どもは小さな傷を軽視しがちで、洗浄や消毒をせずにそのまま遊び続けてしまうこともあります。これが感染のリスクを高める大きな要因となっています。
飼い猫・野良猫での感染状況
野良猫はネコノミが寄生している可能性が高く、細菌を保有している割合が高いといわれています。
そのため、野良猫との接触が猫ひっかき病の主な感染源となっています。
しかし、屋外に出る機会のある飼い猫や、複数の猫と接触する機会がある猫も感染している可能性があります。
調査によると、飼い猫でも約10%がバルトネラ・ヘンセレを保有しているとされ、完全に室内飼いをしていても感染を完全に避けられるわけではありません。
季節や地域による発症傾向
猫ひっかき病は秋から冬にかけて発症が多くなります。
これは夏にネコノミが活発に繁殖し、猫に感染が広がるためと考えられています。
その後、寒くなって猫が屋内で過ごす時間が増えることで、人との接触機会が増えるためです。
また、地域別では西日本での発症例が多く、これは気候が温暖でネコノミが生息しやすいことが関係しています。
北海道のように寒冷な地域ではネコノミが少ないため、発症例も比較的少ない傾向があります。
3.予防と発症後の対応
感染を防ぐための日常習慣
猫ひっかき病を防ぐには、日常的なちょっとした心がけが大切です。
まず、野良猫にはむやみに近づかないことが基本です。
特に子どもは猫を見るとつい触りたくなりますが、外で暮らす猫は細菌を持っている可能性が高いため、触れないよう教えておきましょう。
飼い猫の場合も、できるだけ屋外に出さず、体を清潔に保つことが大切です。爪を短く切ることも予防になります。
さらに、猫に触れた後は必ず石けんで手を洗うことを習慣にすると、万が一の感染リスクを大きく減らせます。
猫にひっかかれたときの応急処置
もし猫にひっかかれたりかまれたりしたら、すぐに流水で傷口をしっかり洗い流してください。
水道が近くにない場合は、ペットボトルの飲料水でも構いません。洗った後は消毒液を塗り、必要に応じて清潔なパッドで覆います。
小さな傷でも油断せず、その日のうちに処置をしておくことが大切です。
特に深い傷や出血が多い場合は、自己処置に頼らず外科を受診してください。これらの対応を怠ると、感染のリスクが高まり、後で熱や腫れが出てしまうことがあります。
医療機関を受診する目安と治療法
ひっかかれたあと2週間ほどは、体調の変化を注意深く観察しましょう。
特にリンパ節の腫れや発熱、だるさなどが出てきた場合は、早めに小児科や内科を受診することが重要です。
その際、必ず「猫にひっかかれた」または「かまれた」という事実を伝えてください。
猫ひっかき病は血液検査で診断できます。治療は抗生物質が中心で、これにより症状は比較的早く改善します。
まれに視力障害や内臓への炎症など重い症状が出る場合もあり、その際は専門的な治療が必要になります。早めに医療機関を受診することが、重症化を防ぐ第一歩です。
まとめ
猫ひっかき病は、猫にひっかかれたりかまれたりしたことがきっかけで発症する感染症で、特に5歳から14歳の子どもに多く見られます。
軽い発熱やリンパ節の腫れで済むことが多い一方、視力障害や内臓への炎症など重い症状につながるケースもあります。
感染を防ぐためには、野良猫にむやみに触れないこと、飼い猫を清潔に保ち爪を短く切ること、そして猫に触れたら必ず手を洗うことが重要です。
ひっかかれてしまった場合は、すぐに傷を洗い消毒し、その後2週間ほど体調を観察しましょう。
発熱やリンパ節の腫れが続くときは、早めに医療機関を受診し「猫にひっかかれたこと」を伝えることが大切です。日常のちょっとした注意と早めの対応が、重症化を防ぎ、安心して猫と暮らすための第一歩になります。
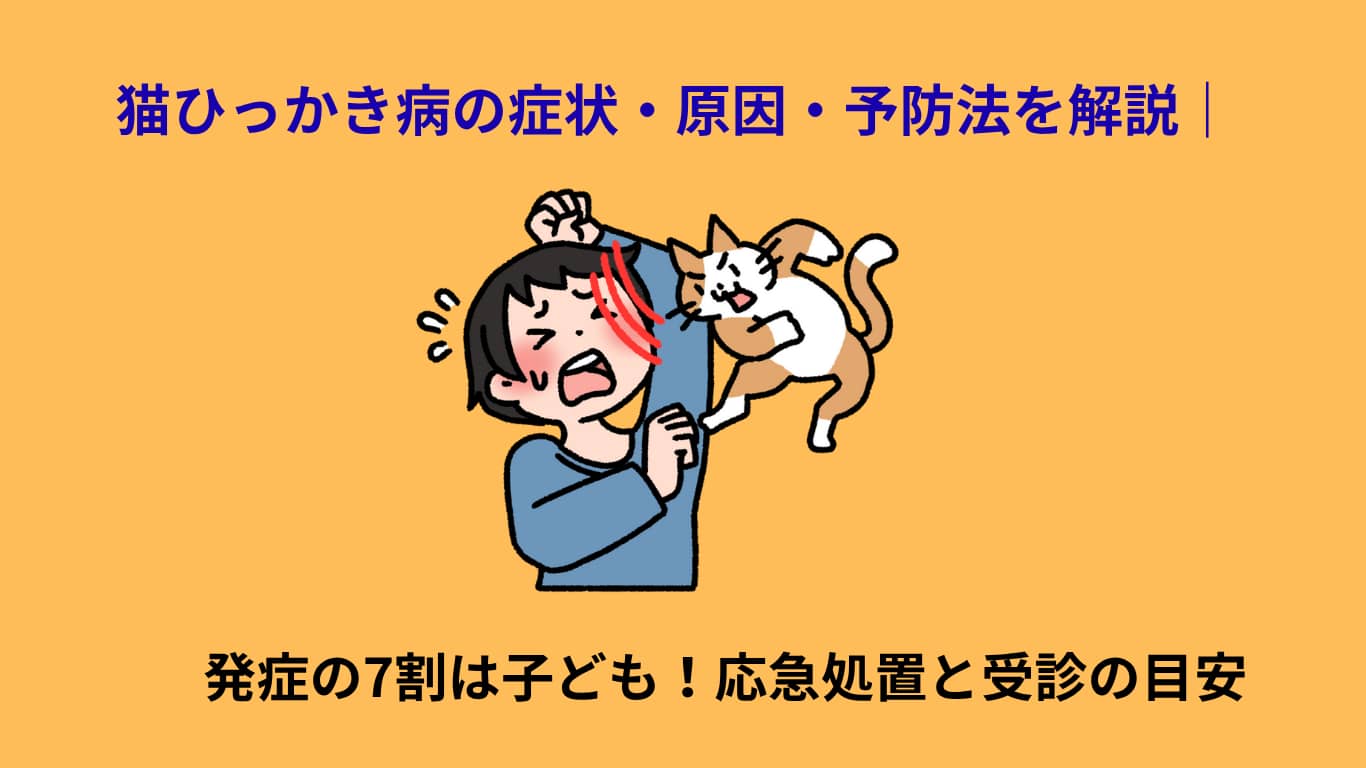
コメント