子どもを望んでも授かれない現実は、多くの夫婦にとって深刻な悩みです。
特に、男性の無精子症と診断された場合、「どうすれば自分たちの子を持てるのか」という大きな壁に直面します。
本記事では、無精子症と診断された夫婦が選んだ第三者からの精子提供(AID)の実情や、その後に続く家族の暮らし、そして社会的課題について、実体験をもとに詳しく解説します
はじめに
不妊治療と「無精子症」という現実
結婚して間もない夫婦にとって、子どもを授かることは自然な願いです。
しかし、現実は時に厳しく立ちはだかります。兵庫県に暮らす田中さん夫婦もその一組でした。
妻の体に軽い子宮内膜症があったため、不妊治療専門のクリニックに通い始めたものの、なかなか結果が出ません。そんな中、夫の精液検査で「無精子症」という診断が下されたのです。
無精子症とは、精液中に精子がまったく存在しない状態のことを指し、男性の100人に1人が該当するといわれています。
「どうして自分が…」という衝撃と同時に、「妻に申し訳ない」という罪悪感も伴いました。
精巣から直接精子を取り出す手術も試みましたが、結果は変わらず。遺伝的に自分の子を授かることは難しいという現実を突きつけられたのです。
夫婦が直面した葛藤と選択の重さ
夫婦の間に深い沈黙が続く日々。子どもを諦めるのか、それとも養子縁組に進むのか──選択肢はいくつかありました。
しかし、妻には「どうしても自分で産みたい」という強い願いがありました。悩みに悩んだ末、2人が出した答えは「第三者からの精子提供」でした。
これは、日本では約80年前から行われている非配偶者間人工授精(AID)という方法で、提供者は匿名であるケースがほとんどです。
匿名性ゆえの葛藤はありましたが、それでも夫婦は前に進むことを決意しました。時間が経てば経つほど、子どもを望む気持ちは強くなり、迷っている余裕はなかったのです。
1.夫の「無精子症」と妻の強い願い
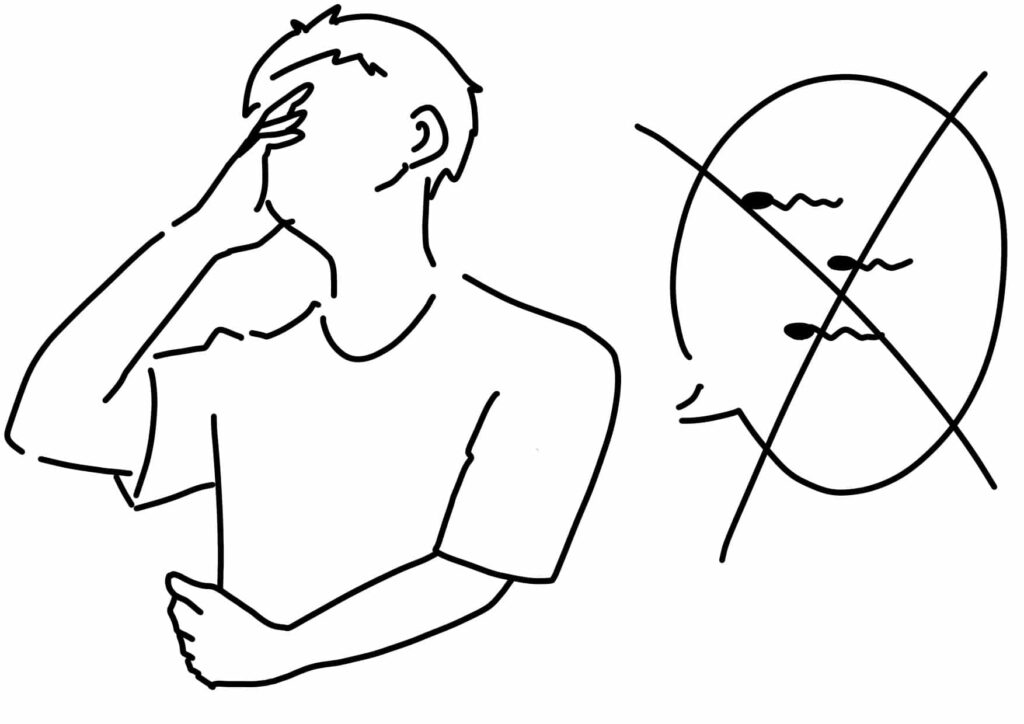
発覚した無精子症と心理的ショック
田中さん夫婦が不妊治療を始めて1年ほど経った頃、医師の勧めで夫の優さんも検査を受けることになりました。
結果は想像もしなかった「無精子症」。精子がまったく確認できないという現実に、2人は大きな衝撃を受けました。
優さんは「まさか自分が」と頭が真っ白になり、同時に「1年間も頑張ってくれた妻に申し訳ない」という思いでいっぱいになったそうです。
その後、精巣から直接精子を採取する手術にも挑戦しましたが、結果は変わらず。遺伝的に自分の子どもを授かる道は閉ざされていると告げられました。
その夜、2人は長時間話し合い、泣きながらも「これからどうするか」を真剣に考え始めました。頭をよぎったのは養子縁組の選択肢。しかし、すぐに答えを出せるものではありませんでした。
「自分で産みたい」という妻の思い
そんな中で妻のゆりこさんが口にした言葉は、「どうしても自分で産みたい」という強い願いでした。
子どもを育てるだけでなく、妊娠・出産という体験そのものをあきらめきれなかったのです。
「ただ子どもが欲しいという気持ちだけじゃなくて、自分でお腹で育てて産みたい」という思いは、養子縁組では満たされないものでした。
夫の優さんは、その強い気持ちを受け止め、「自分にできることを探そう」と決意。ネットでの情報収集や不妊治療の体験談を読み漁り、さまざまな可能性を検討しました。
養子縁組ではなく精子提供を選ぶまで
情報収集の中で出会ったのが「第三者からの精子提供(AID)」という方法でした。
国内で実施しているクリニックは限られていましたが、自宅から通える範囲にも対応可能な病院がありました。
提供者は匿名という条件でしたが、それでも「自分で産める」道があることは大きな希望になりました。
もちろん迷いもありました。「子どもが成長したとき、出自を知りたいと言ったらどうするのか」「本当にこれでいいのか」。答えの出ない問いを抱えつつも、2人は時間をかけて話し合いを重ねました。
最終的に夫婦が出した結論は、「一度きりの人生、悔いのない選択をしよう」というものでした。こうして田中さん夫婦は、第三者からの精子提供という道を選んだのです。

2.第三者からの精子提供(AID)の現状と課題

AIDの仕組みと国内での歴史
AID(非配偶者間人工授精)は、精子を持たない男性とその配偶者が子どもを授かるために行われる医療です。
第三者から提供された精子を使って女性の体内に人工的に受精を行い、妊娠を目指す方法です。
日本では約80年前にこの方法が導入され、戦後間もない時期から実施されてきました。
当初は医師が自ら提供者を探し、大学の医学生などの協力を得て行われていたといいます。
現在では日本産婦人科学会に登録された16の医療機関などで実施され、これまでに1万人以上の子どもが誕生したとされています。
一方で、AIDを行うクリニックは全国的に限られており、夫婦が治療を受けたくても物理的な距離や経済的な負担で断念するケースもあります。
田中さん夫婦も、通いやすいクリニックが近くにあったことを「恵まれていた」と振り返っていました。
提供者が匿名であることへの葛藤
AIDの特徴のひとつは、提供者の情報が原則として匿名であることです。
田中さん夫婦が通ったクリニックも、匿名で凍結保存された医学部生の精子を使用する仕組みでした。血液型は合わせられるものの、顔立ちや体格といった外見的な要素は調整できません。
匿名性には、提供者のプライバシーを守る目的がありますが、その一方で親になる夫婦や生まれてくる子どもにとって葛藤を生む要因ともなります。
ゆりこさんは、「子どもが大きくなって『自分は誰の子どもなのか』と知りたくなったときに答えられないのがつらい」と語りました。
優さんもまた、「父親に似ているね」と言えない現実を想像すると、言葉を失うことがあるといいます。
この匿名性をどう受け止めるかは、AIDを選ぶ夫婦にとって大きな決断のひとつとなっています。
出自を知る権利と法制化の遅れ
生まれてきた子どもが「自分の出自を知る権利」を持つべきだという声は年々高まっています。
欧米の一部の国では、ドナーの氏名や連絡先などを子どもが成人後に知ることができる仕組みが導入されています。
日本でも今年、初めて「出自を知る権利」に関する法案が国会に提出されました。
法案では、提供ドナーの情報を国が100年間保存し、成人後の子どもが希望すれば開示するという内容でした。
しかし、名前など個人を特定できる情報はドナーの同意がある場合のみの開示にとどまり、当事者団体からは「これでは匿名と変わらない」という批判の声が上がりました。
結局、この法案は審議されることなく廃案となり、AIDに関する包括的な法律は依然として存在していません。
田中さん夫婦もこの法制化の動きを注視しており、「通れば第一歩になるはずだった」と悔しさを口にしています。
出自を知る権利とドナーのプライバシー保護、この二つのバランスをどう取るかは、今もなお答えが出ていない大きな課題なのです。
3.生まれた我が子と家族のこれから
精子提供で誕生した息子との暮らし
田中さん夫婦にとって、息子・全(ぜん)くんの誕生は長い苦悩の先に訪れた喜びでした。
「待ち望んで生まれてきてくれたんだよ」と何度も語りかけたという2人。全くんは6歳になった今も、お父さんの優さんにべったりで、取材中も肩に乗ったりひざに寝転んだりと、とにかく仲の良さが印象的でした。
家族で公園に出かけることが休日の定番で、キャッチボールやお弁当を囲む時間は、田中さん夫婦にとってかけがえのない日常になっています。
血のつながりはなくても、日々一緒に過ごす中で自然と似てくる仕草や笑顔に、ゆりこさんは「やっぱり家族だな」と感じる瞬間が増えたと話します。
出自を伝える工夫と子どもの理解
田中さん夫婦は、息子が2歳のころからAIDで生まれたことを伝えるようにしてきました。そのために選んだのが絵本でした。
絵本には「お父さんには精子がなかったけど、親切な人からもらって君が生まれたんだよ」とやさしい言葉で描かれており、全くんはそれを何度も読み返すうちに自然と理解するようになったそうです。
ゆりこさんは「隠すことの方が重たいものになる」と考え、繰り返し小さなうちから伝えることを心がけてきました。
今では全くん自身が「お父さんには精子がなかったけど、もらって僕ができたんだよ」と自分の言葉で話すことができるまでになっています。
将来への不安と「寄り添う」覚悟
ただし、これで終わりではありません。全くんが成長するにつれ、提供者が誰なのかを知りたいと思う時期が来るかもしれません。
匿名提供である以上、その答えを用意することは簡単ではありません。
優さんは「将来、息子がどんな思いを抱いても、まずは受け止めて寄り添いたい」と語ります。
ゆりこさんも「本人がどうしたいと思うかを尊重したい。否定するのではなく、一緒に考えていきたい」と覚悟を示しました。
田中さん夫婦の思いは、「その時にできる最善の選択をする」というもの。血のつながりの有無にとらわれず、家族としてどう寄り添い、支え合うかを大切にしているのです。
まとめ
夫の無精子症という現実に直面しながらも、「自分で産みたい」という妻の強い思いを大切にした田中さん夫婦。
悩み抜いた末に選んだ第三者からの精子提供(AID)という選択は、匿名性や出自を知る権利といった課題を伴うものでした。
しかし、その選択の先に生まれた息子・全くんの存在は、2人にとってかけがえのない喜びとなりました。
家族での日常は、血のつながり以上に深い絆で支えられています。そして田中さん夫婦は、息子が将来どのような思いを抱いたとしても、まずは受け止めて寄り添う覚悟を持っています。
AIDをめぐる社会的な議論はまだ続いており、出自を知る権利や法整備の課題は残されたままです。
しかし、ひとつの家族の姿として、この体験は「親になる」ということの本質を問いかけています。
子どもを持ちたいと願う夫婦にとって、どの方法を選ぶかに正解はありません。大切なのは、悩み、話し合い、そして「その時にできる最善の選択」をすること。
その先に生まれる家族の形を、社会全体で温かく見守ることが求められているのではないでしょうか。
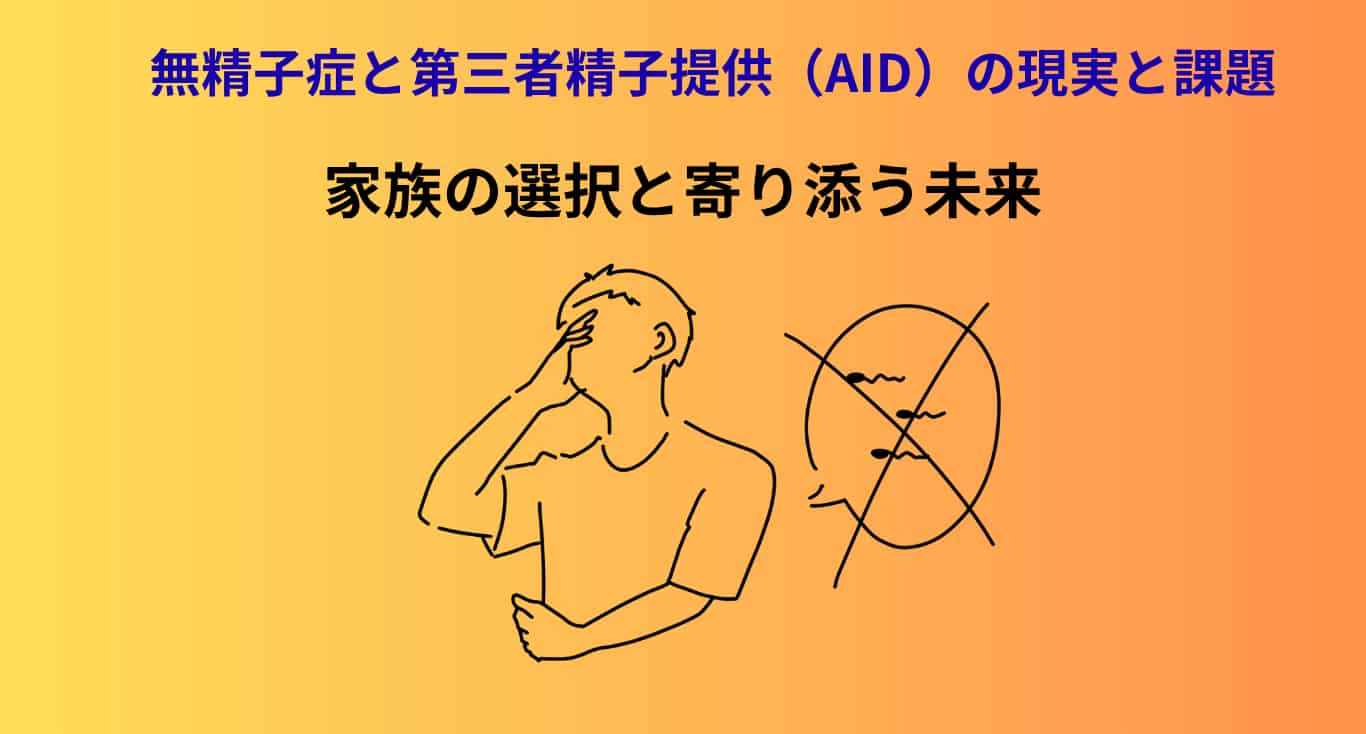
コメント