近年、不妊に悩む夫婦や、子どもを望む同性カップル、シングル女性の増加により、医療機関だけでなくSNSを通じた個人間での精子提供が広がっています。
中には善意で活動する提供者もいますが、性被害や詐欺、感染症リスクといった深刻な問題も存在します。
本記事では、精子提供を始めた男性の体験談をもとに、個人間精子提供の現状、SNS活用の背景、そして法的課題について詳しく解説します。
はじめに
個人間精子提供の現状と課題
日本では不妊に悩む夫婦や、子どもを望む同性カップル、シングル女性が増えており、従来の医療機関だけでなく、SNSを介した個人間での精子提供が広がっています。
特に、精子バンクなどの公的な仕組みが限られている中、個人が善意で精子を提供するケースも少なくありません。
しかし、こうした方法には感染症リスクや契約トラブル、金銭目的の詐欺といった問題が伴います。
法律で明確に規制されていない現状では、誰でも「精子提供者」を名乗れるため、安全性や倫理面で大きな課題が残されています。
ハジメさんが精子提供を始めた背景
大阪府に住む会社員のハジメさん(仮名・38歳)は、5年前に大学時代の友人から「無精子症で子どもができない」と告白されました。
そして友人から「妻と性交渉して子どもを作ってほしい」という衝撃的な依頼を受けます。
戸惑いながらも無精子症に悩む夫婦が多いことを知り、最終的に依頼を受け入れました。その経験をきっかけに、同じように悩む人の助けになりたいという思いから、SNSで精子提供を呼びかける活動を始めます。
ハジメさんは交通費以外の金銭は受け取らず、これまで20件以上の依頼に応じ、7人の妊娠に成功しました。
彼は「社会貢献としての達成感がある」と語りますが、同時に個人間精子提供にはリスクも多いことを強調しています。
1.友人からの依頼で始まった精子提供
無精子症を告白された友人からの驚きの依頼
ハジメさんが精子提供に関わるきっかけとなったのは、大学時代からの友人からの突然の相談でした。
ある日、友人は「無精子症で子どもを授かることができない」と打ち明け、続けて「妻と性交渉して子どもを作ってほしい」と頼んできたのです。
あまりにも想像外のお願いに、ハジメさんは最初、言葉を失いました。
「最初は何を言っているのか理解できなかった」と当時を振り返ります。
友人の切実な表情と、「このままでは家族を築けない」という思いに触れ、ハジメさんは深く考え込むことになります。
出産までの経緯と複雑な心境
最終的にハジメさんは友人の依頼を受け入れることにしました。
数日間悩み、無精子症について調べる中で、多くの夫婦が同じ悩みを抱えていることを知ったからです。
性交渉による提供という方法は決して軽い決断ではありませんでしたが、友人夫妻の「どうしても子どもを」という気持ちを尊重しました。
その結果、翌年に友人の妻が無事に出産し、元気な赤ちゃんが誕生しました。「友人の笑顔を見たとき、正直複雑な気持ちもあったけれど、同時にホッとしました」とハジメさんは語ります。
親権を主張しないという口約束の取り決め
この精子提供で特に重視されたのは、法的なトラブルを避けるための取り決めでした。
生まれた子どもに対してハジメさんは親権を一切主張しないことを明言し、養育費なども発生しないことを確認しました。
書面での契約は交わさず、あくまで信頼に基づく口約束でした。
子どもは友人夫妻の子として育てられ、ハジメさんも年に一度だけ会う関係にとどまっています。
この一件を通じて、ハジメさんは「誰かの人生を大きく左右する行為」への責任を強く意識するようになったといいます。
2.SNSを活用した精子提供の広がり

SNSアカウント開設と依頼急増
友人の依頼をきっかけに精子提供の経験をしたハジメさんは、「同じように悩んでいる人がもっといるかもしれない」と考えるようになりました。
そこで、自分が精子を提供できることを告知するためにSNSアカウントを開設。
プロフィールには学歴や感染症検査の結果を掲載し、信頼性を高める工夫をしました。感染症の有無を確認する簡易検査は毎月受け、陰性証明書の画像を投稿。
すると、想像以上の反応が寄せられ、1年ほどで20件以上の依頼が舞い込むようになりました。
多くの依頼者は匿名でやり取りし、実際に会う際には喫茶店や駅前など人通りのある場所を選びました。
SNSという手軽さもあり、これまで接点のなかった地域や立場の人たちからの相談が増えたのです。
提供方法と無償提供の理由
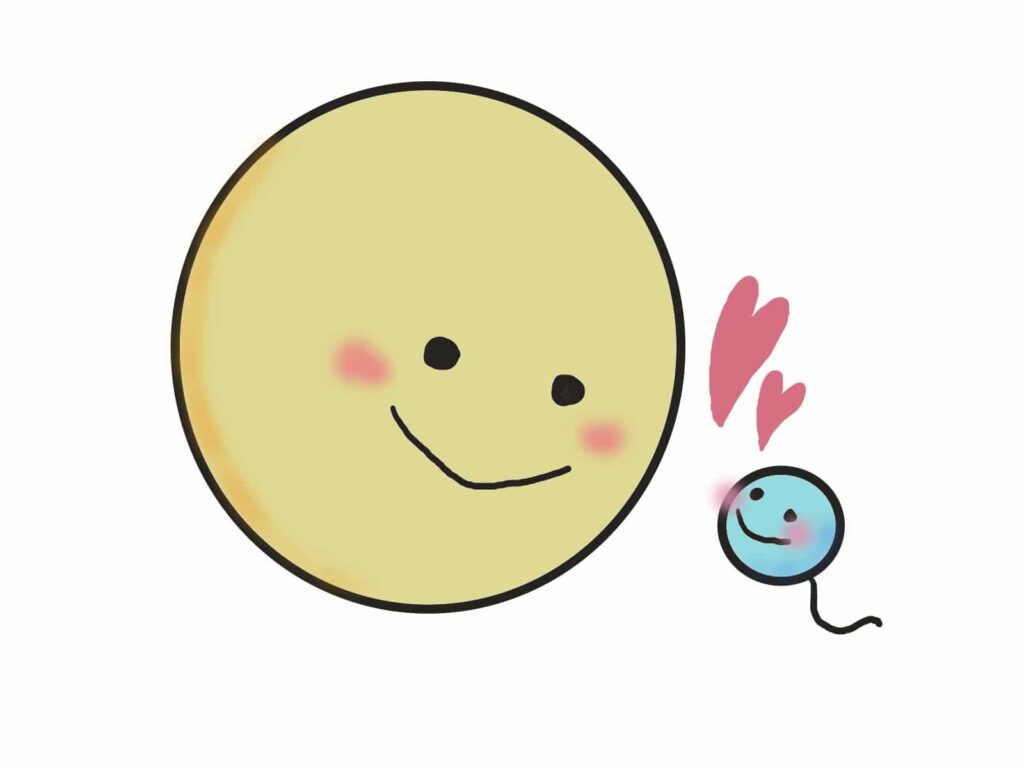
ハジメさんが提示した提供方法は主に2つ。「シリンジ法」と「タイミング法」です。
シリンジ法では、医療用カップに精液を入れて依頼者に渡し、依頼者自身が自宅で注入します。
一方のタイミング法は、排卵日に合わせて性交渉を行う方法です。どちらを選ぶかは依頼者の希望次第でした。
また、金銭の受け取りは一切せず、交通費など実費のみで対応していました。「営利目的にすると一気に意味が変わってしまう気がするんです。だから社会貢献として無償でやっています」と語ります。
依頼者が妊娠し、出産の報告を受けることが、彼にとって何よりのやりがいになっていました。
同性カップルやシングル女性からの依頼が増える背景
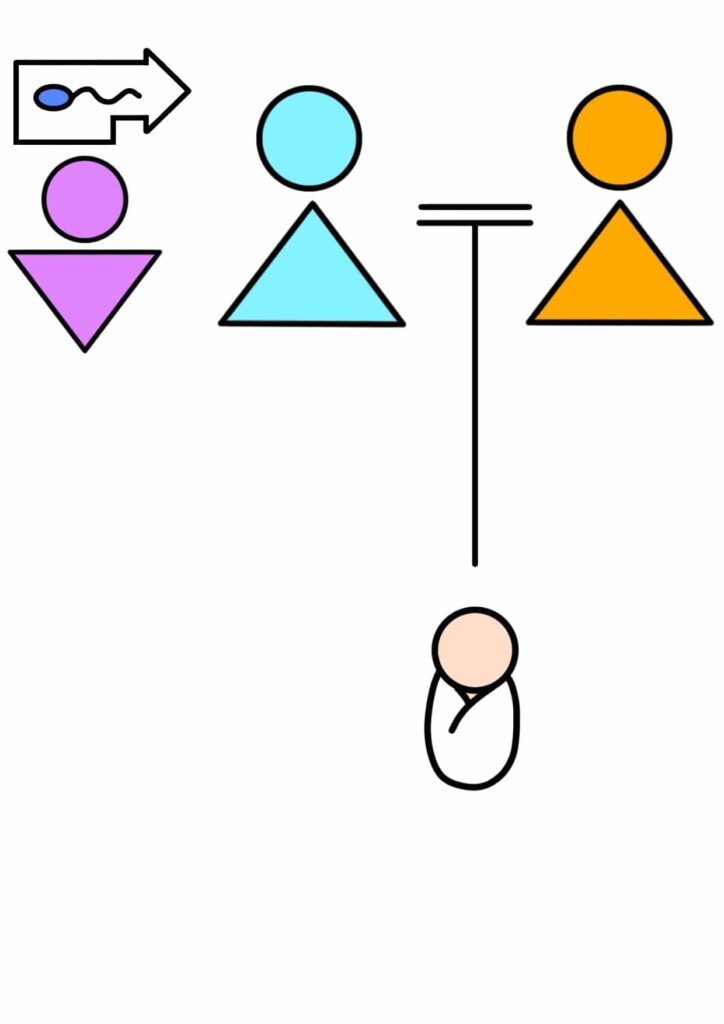
SNSでの活動を続けるうちに、ハジメさんが受ける依頼の傾向は変わっていきました。
最初は無精子症など医学的な事情を抱える夫婦が中心でしたが、次第に同性カップルや結婚を選ばないシングル女性からの相談が増えていったのです。
同性婚訴訟の広がりやLGBTQに対する社会的理解の進展が、子どもを持つことを望む同性カップルの増加につながりました。
また、「結婚はしないけど母親になりたい」というシングル女性にとっても、SNSを通じた個人間精子提供は選択肢のひとつとなっていました。
こうした背景が、ハジメさんの活動をさらに広げる大きな要因になったのです。
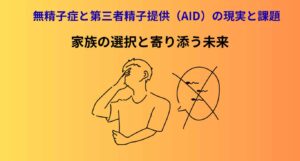
3.個人間精子提供に潜むリスクと法的課題
性被害や詐欺などのトラブルリスク
SNSを通じた個人間の精子提供には、見過ごせない危険が潜んでいます。
中には「タイミング法での提供」と称し、実際には性交渉目的で近づく男性も存在します。また、精子提供の見返りとして高額な金銭を要求するなど、詐欺まがいの手口も報告されています。
実際に、SNS経由で提供を受けた女性が「事前に約束した方法と違う行為を強要された」という被害を訴えたケースもありました。
匿名でやり取りできるSNSは便利ですが、同時に加害行為が表に出にくい環境でもあります。こうしたリスクを回避する仕組みは、現時点では十分に整っていません。
近親婚・感染症リスクと医師の警鐘
もう一つの大きな懸念は、感染症と遺伝的なリスクです。
医療機関で行われる精子提供では、HIVなどの感染症検査を半年以上かけて複数回実施し、遺伝性疾患の有無も確認します。
しかし、個人間での提供ではこうした厳格な検査が行われないことも多く、簡易検査だけでは完全な安全性を保証できません。
また、同じ提供者の精子から多数の子どもが生まれると、将来的に血縁関係を知らないまま結婚する「近親婚」の可能性が高まります。
海外では、一人の精子提供者から100人以上の子どもが生まれた事例もあり、日本産婦人科学会は「一人の提供者から生まれる子は10人まで」という指針を示しています。
獨協医科大学の岡田弘医師は「SNSを使った個人提供は、倫理面でも危険が多い」と警告しています。
法律未整備による課題とルールづくりの動き
現状、日本では個人間での精子提供を直接規制する法律は存在しません。
医療機関での提供は法律婚をした夫婦に限られており、同性カップルや独身女性は対象外となっています。そのため、SNSを利用した個人提供に頼る人が増えていますが、トラブル時に法的な保護を受けにくいのが現実です。
今年初めには、不妊治療のルールづくりを目的とする法案が提出されましたが、同性カップルや独身女性を対象外とした内容だったため、強い反発が起こり、結果として廃案となりました。
ハジメさんは「国がしっかり制度を整えれば、わざわざリスクのある個人取引を選ぶ必要はなくなる」と語っています。制度整備の遅れが、現場の混乱を生んでいると言えます。
まとめ
ハジメさんの経験は、個人間精子提供がどれだけ多様な背景を持つ人々の選択肢になっているかを示しています。
不妊症に悩む夫婦だけでなく、同性カップルや結婚を選ばないシングル女性にとっても、子どもを持つための一つの方法となっていました。
しかし、SNSを介した精子提供には、性被害や詐欺、感染症、さらには将来の近親婚リスクといった重大な課題が伴います。
これらは提供者と依頼者双方にとって深刻な問題になり得ます。医療機関での提供と違い、検査やルールが十分に整っていない現状では、善意の提供であっても大きなリスクを背負うことになります。
法整備が追いつかない現状の中で、個人が自己判断で動くしかない状況は、非常に脆弱で不安定です。
ハジメさんが語った「国がしっかりしていれば、こういう取引はなくなる」という言葉は、制度整備の重要性を物語っています。個人の善意や社会貢献の思いを尊重しつつ、安全と倫理を確保できる仕組み作りが求められています。
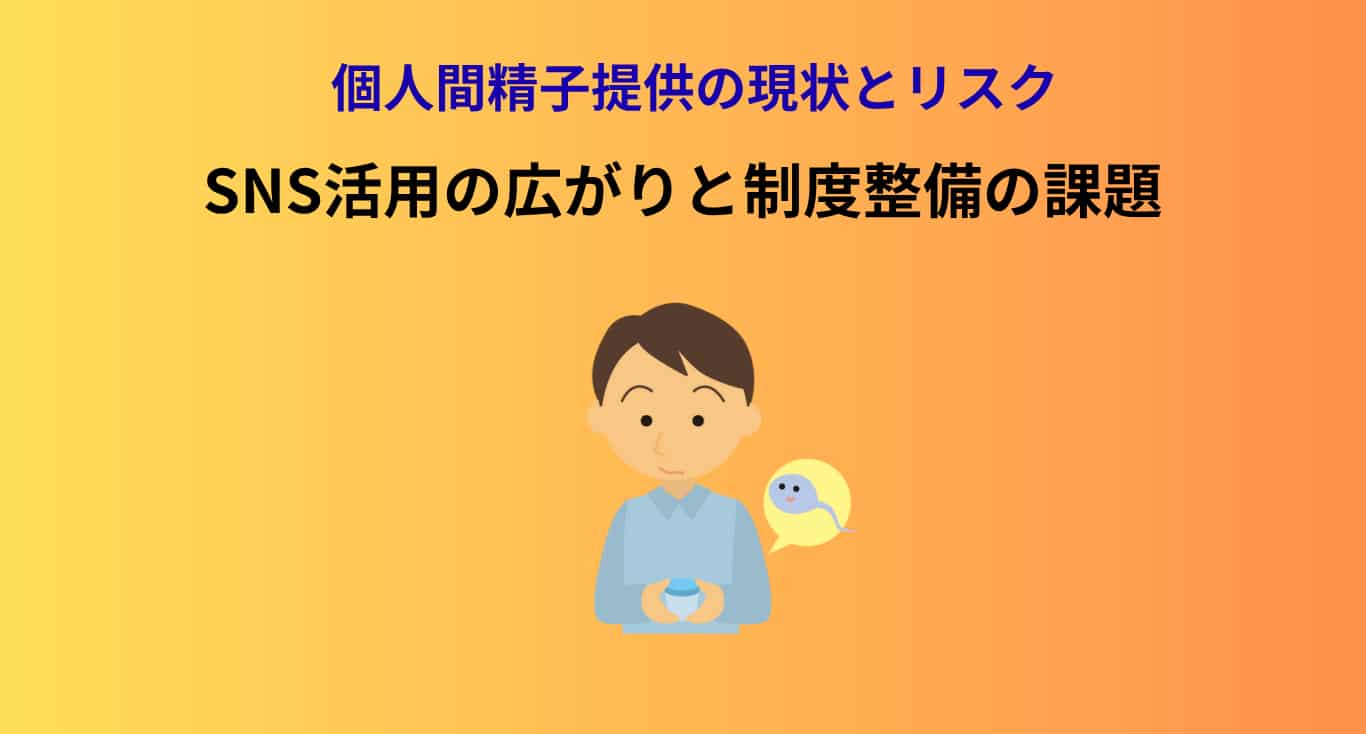
コメント