2025年7月31日をもって、長年使われてきた紙の保険証が原則として使えなくなることをご存じでしょうか。
これに伴い、マイナンバーカードを健康保険証として使う「マイナ保険証」への移行が本格化しています。
しかし、「資格確認書が届かない」「準備が間に合わない」といった声も広がっており、制度変更に戸惑う人も少なくありません。
本記事では、紙の保険証廃止の背景や、資格確認書の役割、移行の際に注意したいポイントをわかりやすく解説します。
はじめに
最近とても話題になっている「紙の保険証がもうすぐ使えなくなる!」というニュースについて、私自身の目線でまとめてみました。
ちょっと難しそうに見える制度変更ですが、暮らしに直結する話題なので、ぜひ最後まで読んでいただけるとうれしいです。
紙の保険証廃止の背景
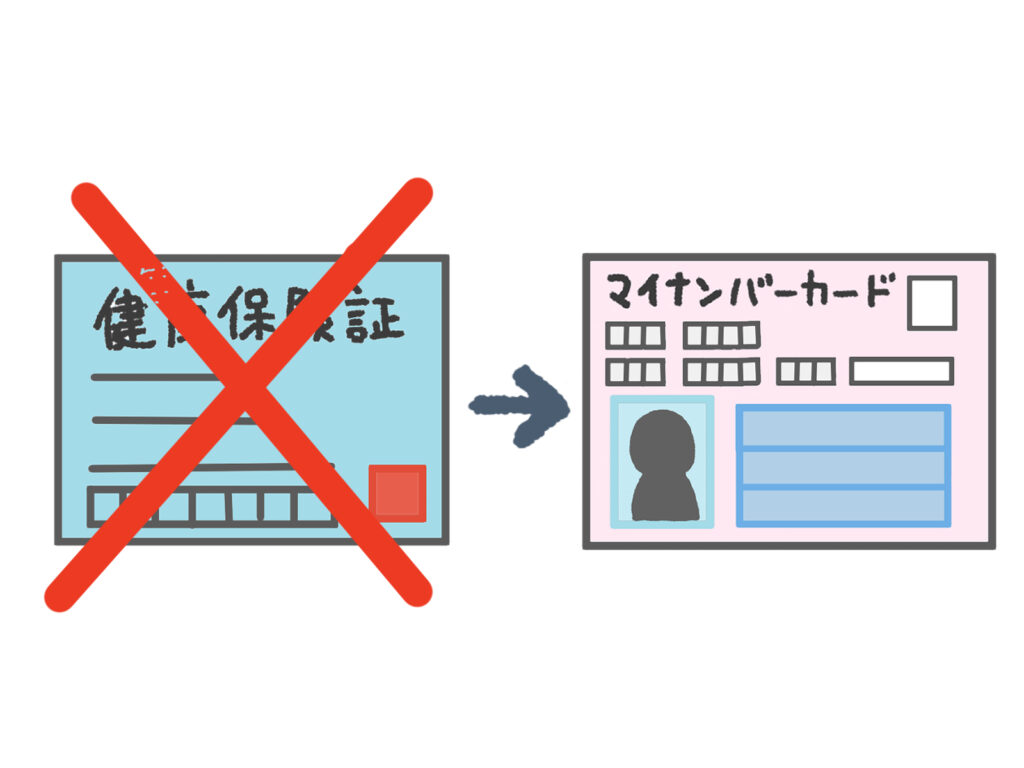
これまで医療機関で使われてきた紙の保険証は、2025年7月31日で原則として利用できなくなります。
背景には、国が進めている「マイナ保険証(マイナンバーカードと健康保険証の一体化)」の本格運用があります。
紙の保険証は誰もが使いやすい反面、紛失時のリスクや事務手続きの負担が課題とされてきました。
マイナ保険証はこうした課題を解決し、医療情報をスムーズに管理する目的で導入されています。
しかし、突然の期限設定により「手続きが間に合わない」「制度が分かりにくい」という声が街中やSNSで目立つようになっています。
私の周りでも「え?紙の保険証ってもう使えなくなるの?」と驚いている人が多い印象です。
マイナ保険証への移行が進まない現状
マイナンバーカードを持つ人の8割以上がマイナ保険証に登録済みとされていますが、実際に医療現場で利用されている割合は30%ほどにとどまっています。
理由として「カードリーダーが設置されていない医療機関がある」「紐付けや設定が難しい」といった声が多く聞かれます。
さらに、高齢者の中には「マイナカードを作ったことがない」「機械が苦手」という理由で、いまだ紙の保険証を使用している人も少なくありません。
今回の期限をきっかけに、こうした利用者に対して国が発行する「資格確認書」が注目を集めていますが、「届かない」という不安の声も広がっています。
1.紙の保険証が使えなくなるのはいつ?
有効期限の具体的な日付と影響
紙の健康保険証は、2025年7月31日で原則として利用できなくなります。
これは、国が進めている「マイナ保険証」の普及促進策の一環です。8月1日以降は、病院やクリニックで診察を受ける際に、従来の紙の保険証を提示しても無効扱いとなる場合があります。
たとえば、これまで家族ぐるみで同じ病院に通っていた70代の方は「急に使えなくなるのは不安。知らずに病院へ行ってしまいそう」と話しています。こうした突然の変化に戸惑う声はSNSでも多数見られます。
8月1日以降の医療機関での対応
8月以降に医療機関で診察を受ける場合は、マイナ保険証を提示するか、資格確認書を持参する必要があります。
資格確認書は、マイナ保険証をまだ作っていない人や、やむを得ない理由で取得できない人に発行されるものです。
ただし、医療機関の中にはカードリーダーの設置が遅れているところもあり、「結局、紙の保険証を見せたらどうなるの?」という疑問も出ています。
厚労省はこうした混乱を避けるため、医療機関に対し対応方法を周知していますが、現場では「当日になって患者に説明するのは大変」という声も聞かれます。
暫定措置としての10割負担回避
厚労省は、混乱を防ぐために暫定措置を設けています。
来年3月末までは、有効期限を過ぎた紙の保険証しか持っていない場合でも、その場で資格確認ができれば10割負担(全額自己負担)を求めないよう医療機関に通知しています。
この措置により、たとえば高齢の一人暮らしの方や、資格確認書の到着が遅れている人も、しばらくは安心して受診できます。
しかし、この猶予期間を過ぎると完全にマイナ保険証か資格確認書が必須となるため、今から準備しておくことが重要です。
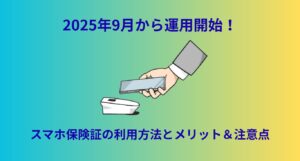
2.資格確認書とは何か?

資格確認書の役割と対象者
資格確認書は、マイナ保険証を持っていない人が医療機関を受診する際に必要となる書類です。
これを提示すれば、これまでの紙の保険証と同じように保険診療を受けることができます。対象となるのは、マイナンバーカードをまだ作っていない人や、作ったけれども健康保険との紐付け手続きが完了していない人です。
特に後期高齢者医療制度の対象となる75歳以上の方や、国民健康保険加入者でカードを持っていない人が主な交付対象です。
ある80代の女性は「マイナカードは作ったことがないし、手続きも面倒。でも資格確認書が届いてホッとした」と話していました。
資格確認書は、医療機関でのスムーズな受診を支える“保険証の代わり”として重要な役割を担っています。
発送遅延とSNSでの不安の声
しかし、この資格確認書の発送が間に合わず、不安の声がSNSにあふれています。
「親は届いたのに自分にはまだ来ない」「あと一週間で紙の保険証が使えなくなるのにどうすればいいの?」といった書き込みが多く見られました。
実際、ある70代の男性は「市役所に問い合わせたら『今週中には届く予定です』と言われたが、ギリギリになってしまうのは落ち着かない」と話しています。
発送時期は自治体ごとに異なり、同じ地域内でも届くタイミングに差があることから、この不安がさらに広がっているのです。
自治体ごとの発送対応状況
自治体も急ピッチで対応を進めています。たとえば東京・大田区では、対象となる約2万4,000人に対し、先週末までに発送を完了したとしています。
新宿区も「すでに送付済み」と回答し、千代田区では28日までに送付を完了すると発表しました。
一方で、引っ越しをした人や住所変更の手続きをしていない人には届かないケースもあり、その場合は自分で市区町村の窓口に出向いて申請する必要があります。
専門家は「有効期限が自治体ごとに異なるため、届かないと感じた場合は早めに役所へ確認を」と呼びかけています。
このように資格確認書は、紙の保険証廃止に伴う“安心材料”である一方、手続きや発送時期の違いが混乱の一因となっています。
3.マイナ保険証の普及と課題

利用率30%台にとどまる理由
マイナンバーカードを持っている人の8割以上が健康保険証としての利用登録を済ませていますが、実際に医療現場で使用している割合は30%ほどにとどまっています。
その理由として、まず医療機関側の準備不足が挙げられます。カードリーダーの導入が間に合っていない病院や診療所もあり、患者がカードを提示しても手入力で対応しているケースがあるのです。
また、利用者側の心理的なハードルも大きいといえます。「機械の操作が不安」「カードを失くしたらどうしよう」という声や、「暗証番号を忘れてしまったら困る」という懸念もあり、特に高齢者を中心に紙の保険証を使い続けてきた背景があります。
高齢者や地方住民の対応状況
高齢者や地方在住の人々にとって、マイナ保険証への移行は容易ではありません。
都市部と比べ、役所へのアクセスが不便な地域や、サポート人員が不足している地域では、手続きに時間がかかる傾向があります。
実際、ある地方都市に住む80代の女性は「市役所まで片道1時間かかるので行くのが大変。息子に頼んでようやく申請できた」と話していました。
また、高齢者施設に入所している人の中には、本人確認や代理申請の準備に手間がかかり、資格確認書に頼らざるを得ない状況が多く見られます。
このように、地域ごとにサポート体制の差が大きく、移行をスムーズに進めるためには現場の声を取り入れた支援が必要です。
今後の課題と解決策の方向性
今後の課題としては、マイナ保険証の利便性を実感できる仕組みづくりと、利用者への丁寧なサポート体制の強化が求められます。
たとえば、医療機関での受付時間短縮や処方データの共有など、実際に使って「便利」と感じられる機能を広めることが重要です。
また、地方自治体や医療機関が協力し、高齢者やデジタル機器に不慣れな人向けのサポート窓口や出張相談会を増やすといった対策も効果的です。
すでに一部自治体では、役所職員が地域の集会所でマイナ保険証の登録支援を行う取り組みが始まっています。
マイナ保険証の普及は時間をかけて進める必要があり、今回の紙の保険証廃止をきっかけに、誰もが安心して医療を受けられる環境を整えることが大きな目標となっています。
まとめ
紙の保険証が使えなくなることで、多くの人が「知らなかった」「どうしたらいいのか不安」という声をあげています。
今回の移行は医療のデジタル化を進める大きな一歩ですが、その一方で、準備が整っていない医療機関や手続きに慣れていない高齢者への影響が目立っています。
資格確認書はこうした人々を支える重要な仕組みですが、発送の遅れや自治体ごとの対応の違いが混乱を招きました。SNSには「届かない」という不安の声があふれ、一時的なパニック状態になった地域もあります。
それでも、厚労省が暫定措置を設け、資格確認さえできれば10割負担を求めない方針を示したことは、安心材料となっています。
今後は、マイナ保険証を実際に使いやすいと感じてもらえるような利便性の向上と、デジタルに不慣れな人への支援体制の充実が欠かせません。
今回の制度変更は、ただの保険証の切り替えにとどまらず、日本の医療のあり方を見直すきっかけにもなっています。これを機に、自分や家族の保険証の状況を確認し、安心して医療を受けられる準備を進めていきましょう。
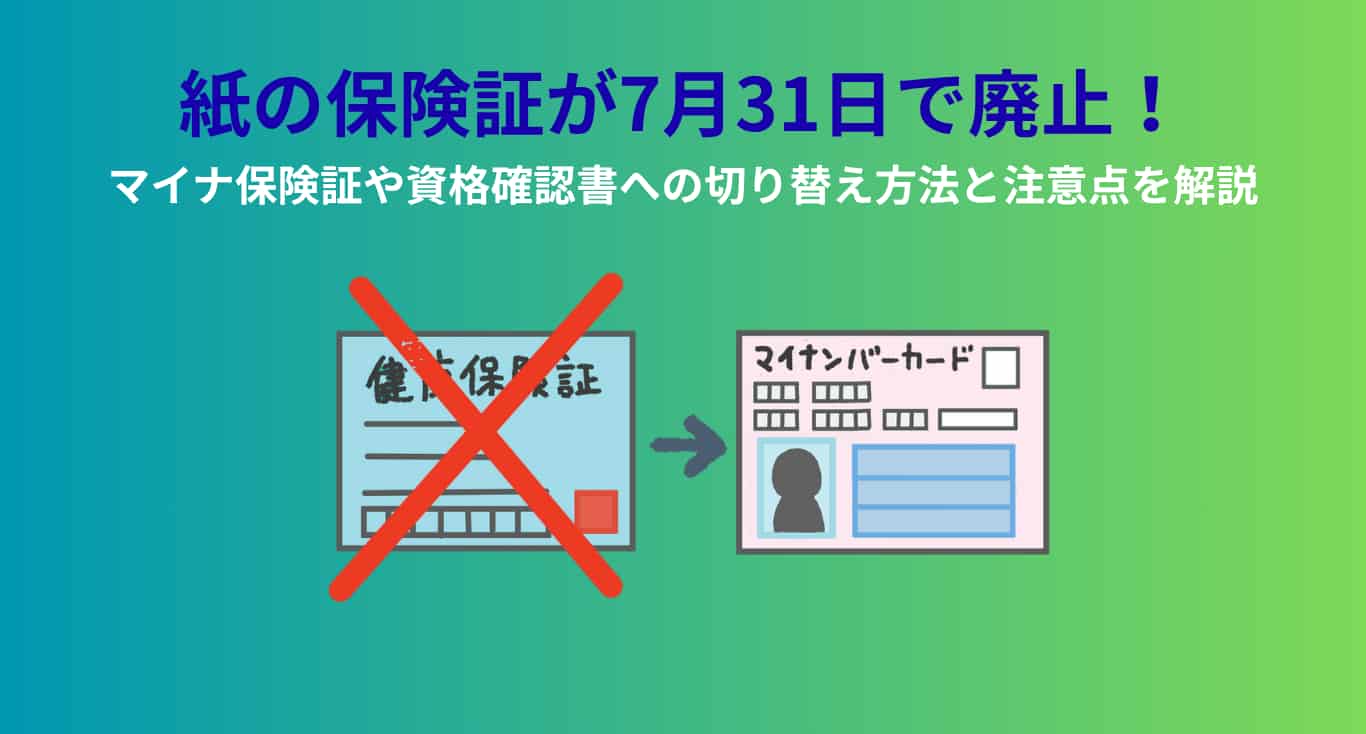
コメント