2025年7月、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」に出演した元外務大臣・田中真紀子氏が、現職議員の質の低下や議員定数の見直し、企業団体献金の廃止など、国会改革について鋭く切り込んだ発言が話題を呼んでいます。
参議院選挙で与党が過半数を割ったタイミングで飛び出した「真紀子節」は、政治不信が高まる中で多くの視聴者の共感を集めました。
本記事では、田中氏の提言内容をわかりやすく整理し、なぜ今このような“国会改革”が求められているのかを読み解きます。
はじめに

田中真紀子氏が語る「国会の劣化」とは
2025年7月21日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」に生出演した元外相・田中真紀子氏が、かつてないほどストレートに“今の国会のレベルの低さ”を語りました。
「今の議員たちは、本当に質が悪い」と言い切った田中氏。国会における質問の質、議員の態度、そして政策議論の深さなど、現場での経験に基づく言葉には説得力がありました。
とくに「筆記試験を導入すべき」「有権者がもっと厳しく見て落とすべき」など、具体的かつ大胆な改革提案は、視聴者の間でも大きな反響を呼びました。
発言の背景にある参院選の与党敗北
田中氏のこうした発言は、直前に行われた参院選の結果とも深く関係しています。
自民・公明の与党が非改選を含めても過半数に届かず、全体で47議席にとどまったことが、その象徴的な出来事です。
敗北を受けて会見を開いた石破茂首相は「国難の中で政治の停滞は許されない」として続投を表明しましたが、国民の間では「そもそも誰を選べばいいのか分からない」といった政治不信が高まっています。
こうしたタイミングで田中氏が問題提起した「議員の質」や「国会改革」は、まさに的を射たものであり、いま私たちが考えるべきテーマと言えるでしょう。
1.田中真紀子氏が提案する「議員の質」の見極め方
有権者による“立ち会い演説会”とテスト導入の提案
田中真紀子氏がまず提案したのは、候補者を見極めるための「立ち会い演説会」の義務化です。
現在、多くの選挙区では候補者同士が正面から政策を論じ合う機会が限られており、選挙カーの連呼や街頭演説だけで投票判断をすることが一般的です。
田中氏はこれに異を唱え、「候補者本人に直接質問できる場をもっと増やすべき」と訴えました。
例えば、「教育の現場に何が必要だと思うか?」「防災にどんな優先順位で予算を振り分けるか?」といった具体的な質問を市民がぶつけ、その受け答えから政策への理解度や本気度を図る──そんな“テスト”のような場が必要だとしています。
これにより、ただ肩書きや知名度で選ばれるのではなく、言葉の中身で判断する土壌が生まれるはずです。
国会質疑の「常時テレビチェック」制度とは
選挙で選ばれた後も、「本当にちゃんと仕事をしているか」を見極める仕組みが必要だと田中氏は言います。
その一つが、国会質疑の内容を常時テレビなどでチェックできるようにすること。
つまり、国民がいつでも議員の発言や質問内容を確認できるような「見える政治」を目指すという提案です。
たとえば、地元選出の議員が国会でどんなテーマを取り上げているのか、無言で座っているだけではないか――こうした実態を日常的に知ることができれば、「次の選挙でこの人に投票していいのか?」という判断材料になります。
政治家が国民に対して「言葉で説明する」姿勢を持ち続けることが、信頼の回復にもつながるといえるでしょう。
議員にも「筆記試験」を——選ぶ責任の再考
さらに田中氏は、「議員になる人にも筆記試験を課すべき」と語りました。
これは、少なくとも日本国憲法の基本的な内容や、財政・外交・福祉といった政策分野について最低限の知識があるかを問うための試験です。
もちろん、「学歴」や「資格」がすべてではありませんが、国家の制度を動かす立場にある以上、一定の理解力と判断力は必要です。
実際、「何を聞かれてもはぐらかす議員」「官僚に任せきりの答弁しかしない議員」に対する国民の不信は根強くあります。
筆記試験という仕組みは、それを少しでも減らすための“見える化”の一つとして、検討に値する案なのかもしれません。
2.議員数と歳費の実態にメス
「713人」も必要か?過剰な議員定数への疑問
田中真紀子氏が番組内で真っ先に問題視したのは、衆議院と参議院あわせて「713人」にものぼる国会議員の多さです。
人口減少が続く日本において、これほど多くの議員が本当に必要なのか──という問いかけは、多くの視聴者にとっても共感を呼ぶものでした。
たとえば、同じ先進国でも議員数は日本より少ない国があります。
イギリスの下院は650人、フランスの国民議会は577人です。人口に対して議員数が多すぎる日本は、地方の声を届けるためとはいえ、その人数に比例した「成果」が国民に実感されにくいのが現状です。
「数」ではなく「質」で政治を評価すべきだという、田中氏のメッセージがここにも現れています。
年収3400万円超!国会議員の収入内訳を公開
さらに田中氏は、議員の“お給料”の中身を驚くほど明確に語りました。
月130万円の歳費(いわゆる基本給)に加え、年2回のボーナスが約600万円、さらに「文書通信交通滞在費」などで年間1200万円。
これらを合わせると、1人あたり年間3400万円もの公費が支払われているというのです。
この金額には議員宿舎の家賃補助や新幹線の無料パスなども含まれておらず、実質的な手当はもっと手厚いという見方もあります。
田中氏は「これだけの報酬をもらう人が700人以上もいて、本当に必要ですか?」と問いかけ、国民の代表としての“コスト意識”を促しました。
議員自身が、今の日本の財政状況を真剣に受け止めているのか――という視点も、見逃せません。
借金国家・日本にふさわしい議員の在り方とは
日本は今、国の借金が1000兆円を超えるといわれています。
にもかかわらず、議員の数も報酬も「削減の対象」として踏み込まれてこなかったのが現実です。
田中氏は「借金財政の国にふさわしい、引き締まった政治をするには、まず議員の数を減らすべき」と断言しました。
この発言の裏には、国民にばかり負担を強いて、政治家自身が痛みを引き受けない構図への強い批判があります。
少子高齢化や災害対策、教育や医療など、財源が求められる分野は多岐にわたるなか、「まずは政治家が身を切る」姿勢が、信頼回復の第一歩になるのかもしれません。
3.企業献金・世襲議員・古参議員に鋭く切り込む
企業団体献金廃止で「ひも付き政治」脱却へ
田中真紀子氏が訴えたもう一つの大きな改革が、「企業団体献金の全面廃止」です。
現在の制度では、企業や業界団体が政治家個人や政党に対して献金を行うことが合法であり、それが「見返り」を期待させる構造を生み出しています。
たとえば、建設業界から多額の献金を受けている議員が、その業界に有利な政策を推進する──こうした“ひも付き政治”の構造は、国民からの信頼を大きく損なっています。
田中氏は「企業や団体が金を出せば、政治家はその期待に応えようとする。これはもう癒着です」とバッサリ。
実際、過去には献金をめぐって汚職事件に発展したケースも少なくありません。
政治の独立性と透明性を守るためには、「お金の流れ」を断ち切る覚悟が必要です。
市民からの少額寄付を中心にした「クリーンな選挙」が定着することこそが、未来志向の政治につながるのではないでしょうか。
親の選挙区は禁止?世襲政治への大胆提言
田中氏は自身が2世議員であることを認めた上で、「私のような世襲議員こそ、親の地盤から出るのをやめるべき」と自戒を込めて発言しました。
たとえば「親が新潟なら子は東京から」「北海道の家系なら沖縄から出馬する」といった“選挙区シャッフル案”を提示し、スタジオはざわつきました。
日本の政治における世襲比率は高く、親や祖父母が築いた支持基盤を引き継いで立候補する例が後を絶ちません。
田中氏はそれを「無条件に受け継ぐことは甘えであり、民主主義の健全性を損なう」と批判します。
実力ではなく“家柄”で国会議員になることが当然視される風潮は、若者の政治参加意欲すら奪いかねません。選挙区の移動というアイデアは、一石を投じる提案と言えるでしょう。
麻生氏・岸田氏にも苦言「もうやめたほうがいい」
番組中、田中氏は麻生太郎氏や岸田文雄氏といった自民党の大物議員にも言及。
「もう辞めたほうがいい」「後ろで綱引きしている人がいる限り、前には進まない」と、遠慮のない発言でスタジオを沸かせました。
麻生氏の映像が流れた際には、「仲良しだけど、もうこの顔見ても若い人は響かない」と、かつての盟友にすら厳しい言葉を投げかけました。
この発言の根底にあるのは、“いつまでも同じ顔ぶれ”への国民の閉塞感です。
新しいアイデアや柔軟な感性が必要とされる時代に、政治の現場だけがアップデートされていないという現実。
田中氏の言葉は、ただの個人攻撃ではなく、「政治に新陳代謝を」という根本的な問題提起だったのではないでしょうか。
まとめ
田中真紀子氏が「ミヤネ屋」で語った国会改革の提案は、単なる批判にとどまらず、具体的で実現可能性のある内容が多く含まれていました。
議員の資質を見極めるための演説会や筆記試験、常時チェック体制の導入。過剰な議員数と高すぎる報酬への疑問、そして企業献金・世襲・古参政治家といった旧来の体制への切り込み。
どれもが「政治を国民の手に取り戻す」ための視点を持っています。
「ただ投票するだけ」では、もうこの時代の政治には対応できないという現実。
田中氏の提言は、私たち一人ひとりが「この人に託す価値があるのか」を真剣に考えるきっかけを与えてくれます。
今の政治に不満があるなら、まずは政治に関心を持ち、自分の言葉で声を上げること。それこそが、真の改革への第一歩なのかもしれません。
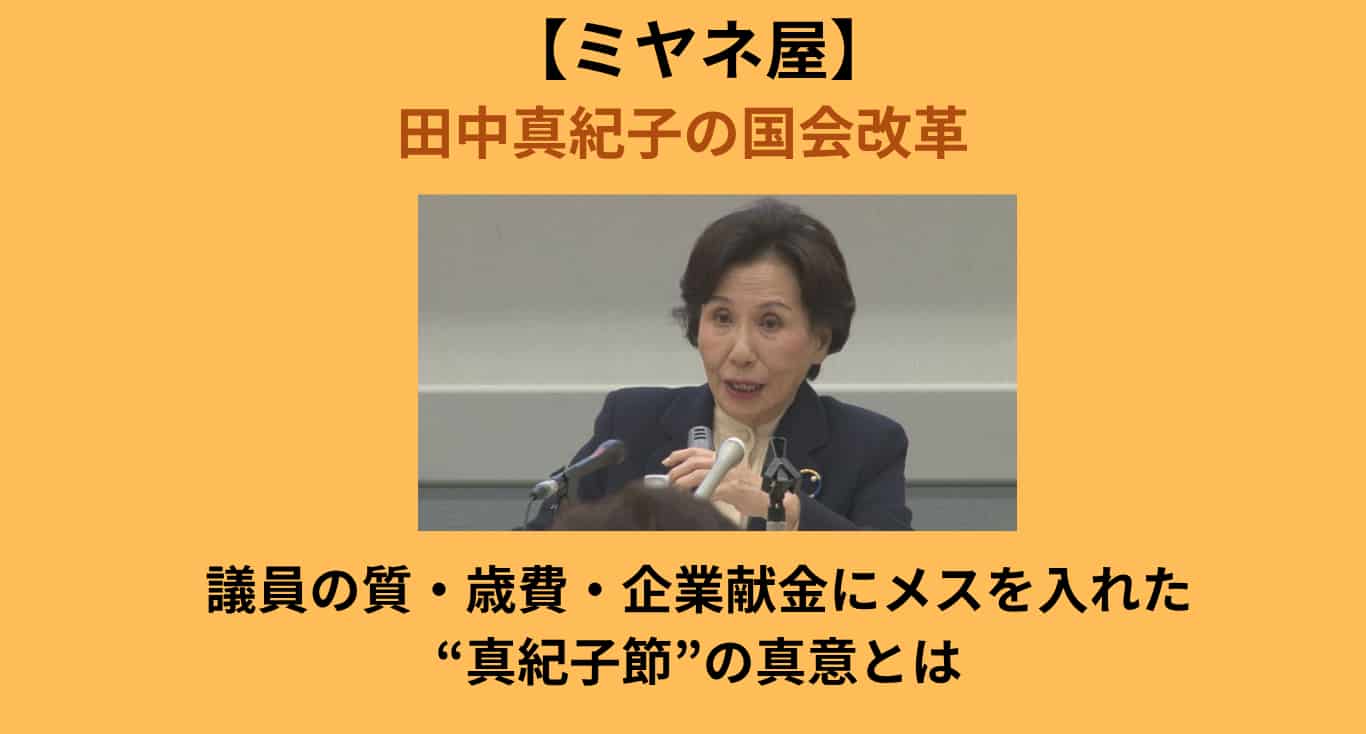
コメント