2025年7月20日投開票の参議院選挙で、自民・公明の与党は目標としていた50議席に届かず、過半数割れが確実となりました。
これを受けて、自民党内では石破茂首相の退陣を求める声が急速に高まっています。
特に、麻生太郎最高顧問が「続投は認めない」と周囲に伝え、石破おろしの動きが加速していることが、テレビ朝日の選挙特番でも報じられました。
この記事では、石破政権の現状と与党敗北の背景、政権内で広がる退陣論、そしてポスト石破をめぐる権力争いの最新情勢を、有権者としての視点でわかりやすくまとめています。
永田町の動きが次の日本の進路を左右する、緊迫した今こそ注視が必要です。
はじめに
与党過半数割れの衝撃と永田町の関心
2025年7月、参議院選挙の結果が出そろい、自民・公明の与党は過半数の50議席に届かないという厳しい情勢が明らかになりました。
とくに注目されるのは、就任からわずか半年余りの石破首相の政権が、衆院選・参院選と連続して国政選挙に敗北したという点です。
国政選挙での連敗は、政権の正当性や党内求心力を大きく損なう出来事であり、永田町では「このまま石破首相が続投できるのか?」という声が渦巻いています。
現場では、自民党本部での選挙情勢会議の空気も重苦しいものでした。
関係者によれば、配布された情勢資料には自民党にとって厳しい数字が並び、出席者たちは沈黙のままページをめくっていたといいます。選挙結果以上に、政局の先行きを見据えた動きが既に始まっているのです。
石破首相の去就をめぐる緊張感と政局のうねり
注目されるのは、石破首相が「国難」を理由に退陣を先送りする可能性です。アメリカとの関税交渉や、安全保障問題など、難しい課題が山積するなかで「今、政権を手放すのは無責任だ」とする声も党内に存在します。
一方で、高市早苗・前経済安全保障相が「もう一度、自民党の背骨を入れ直す」と明言するなど、“石破おろし”の動きも水面下で進行中です。
このように、選挙の敗北が単なる結果にとどまらず、自民党内部の力学を大きく揺るがしはじめています。
退陣か続投か、それとも第3の選択肢があるのか――石破首相の決断が、日本の政治地図を大きく塗り替える可能性があります。
1.石破政権の黄昏と「石破おろし」の兆し
参院選敗北で揺らぐ続投の正当性
石破首相が掲げた「与党で50議席以上」という目標は、あえなく崩れ去りました。
これは、就任直後の衆院選での敗北に続く2連敗であり、政権の求心力を大きく損ねる結果です。
歴代の自民党総裁の中で、2度の国政選挙に敗れて続投を選んだケースはありません。実際、自民党内でも「これ以上続けるのは党への背信だ」との声が漏れ聞こえています。
政権内の関係者によると、石破首相自身も今回の結果に強いショックを受けており、周囲との会話では「責任の重さを痛感している」と語っているといいます。
ただし、本人が公式に続投・退陣どちらかを表明するまでには至っておらず、判断を先送りしている状況が続いています。
「国難」を理由に続投を模索する思惑
一方で、石破首相の周辺では「いま退けば、国を危うくする」との声が強まっています。
背景にあるのは、アメリカとの間で続く関税交渉や、中国との外交摩擦、国内経済の停滞など、多くの懸案事項が重なっているためです。
「ここで指導者が変わること自体がリスクだ」という理屈は、かつて民主党政権時代の首相交代劇を想起させます。
実際、ある党幹部は「野党にも石破続投に一定の理解を示す者はいる」と述べ、危機対応の中での“政局休戦”に期待を寄せているようです。
ただし、これはあくまでも一部の見方にすぎず、多くの党員・議員は「続投の大義名分として『国難』を利用しているだけでは」と冷ややかです。
高市氏の発言に見える党内の不満と対立
選挙期間中、注目を集めたのが高市早苗・前経済安全保障相の発言でした。
彼女は応援演説の場で「私なりに腹をくくった。自民党の背骨を入れ直すために戦う」と語り、事実上、石破首相に退陣を求めた形です。
これは単なる個人の意見ではなく、保守派や旧安倍派など党内右派グループの意向を代弁しているとみられています。
さらに、党内では「森山幹事長の動きが鈍いのは石破体制の限界を示している」という批判もあり、地方議員や若手の一部からも公然と不満の声が出始めています。
「次の総裁を決める総裁選の準備に入るべきだ」という声が日に日に大きくなる中で、“石破おろし”は水面下からじわじわと表面化しつつあるのです。
麻生氏が“続投否定”明言か?参院選敗北で石破退陣論に現実味
選挙特番「選挙ステーション2025」(テレビ朝日系)では、麻生太郎・自民党最高顧問が、石破茂首相の退陣を周囲に強く促す意向を示していると報じられました。
石破政権のもとで、昨秋の衆院選に続く参院選での敗北が確実視され、与党過半数割れという結果に党内の緊張は一気に高まりました。
番組キャスターの大下容子アナウンサーも「石破総理の退陣論が自民党内で強まっています」と明言。麻生派の中堅・若手が集まり、情報分析を進めている状況も伝えられています。
石破首相自身は、選挙前の報道番組で「結果責任は厳粛に受け止める」と語っていたものの、続投の姿勢を保ちたい思惑もあり、判断を保留したまま。
しかし、麻生氏が「続投は認めない」と明確に伝えたことで、「石破おろし」がいよいよ現実味を帯びてきました。党内力学は、ついに決定的な局面を迎えようとしています。
2.ポスト石破をめぐる権力闘争
再登板が囁かれる岸田文雄の存在感
石破首相の進退が不透明な中、永田町では「次は誰が総理の椅子に座るのか」という話題が急速に熱を帯びています。
その中心にいるのが、前首相の岸田文雄氏です。2024年の総選挙敗北を受けて表舞台から一時退いた岸田氏ですが、今も派閥を維持し、麻生太郎元首相の支援も受ける形で党内に強い影響力を残しています。
岸田氏の再登板を推す声は、党内の中堅・若手からも上がっています。「石破政権の路線は安定感に欠ける。いま必要なのは、外交にも精通し、調整力のある岸田さんだ」という声もあり、再び「岸田カラー」のリーダーシップを求める流れが出てきています。
年齢的にもまだ67歳と若く、国際舞台での経験も豊富であることから、国内外に安心感を与える人材としての評価が再び高まっています。
旧派閥を軸とした合従連衡の行方
ポスト石破をめぐる動きは、個人の人気だけでなく、旧来の派閥構造も大きく関係しています。
たとえば麻生派は岸田氏への支持を明言しておらず、水面下で複数の候補者を天秤にかけているとみられます。一方、安倍派の残党勢力や高市氏を支持する保守系グループは、「今度こそ真正面から路線転換を図るべきだ」と強硬な姿勢を見せており、路線対立も含んだ複雑な構図となっています。
また、林芳正官房長官や加藤勝信財務相といった他のポスト石破候補も存在感を増しており、旧竹下派の動向がカギを握るとも言われています。
これらのグループがどの候補に集まるかによって、総裁選の構図が一変する可能性があります。派閥の駆け引きと政策の綱引きが、次期リーダー選びに大きな影響を与える局面に入ってきました。
総裁選実施と臨時国会の見通し
仮に石破首相が退陣の意向を示せば、自民党は直ちに総裁選の準備に入ることになります。
日程としては、臨時国会が8月1日に召集される予定ですが、その前後に党総裁選を実施し、新総理を選出、そのまま国会で首相指名選挙へという流れが想定されています。
ただし、石破首相が態度を明確にしないまま「国難対応」を理由に粘る場合、党内のスケジュール調整は混乱を極めることになりかねません。
仮に党内での反発が高まり、「臨時国会冒頭で不信任案提出」という流れになれば、事態はさらに複雑化するでしょう。
このように、次のリーダー選びは単なる“人気投票”ではなく、国の舵取りと与党内バランスの維持をどう図るかが問われる極めて重要なプロセスとなります。政局の行方は、まさに一寸先は闇です。
3.連立政権再編の可能性と“玉木首相”構想
維新との連携が難しい理由
自民党が連立与党としての安定多数を維持するためには、他党との協力が不可欠ですが、現在のところ日本維新の会との連携は現実的ではないようです。
代表である吉村洋文大阪府知事は、読売新聞のインタビューで「与党の連立に加わる考えはない」と明言し、政権与党との距離を明確にしています。
維新は地方自治体での独自路線を重視し、特に自民党との違いを強調することで支持を集めてきたため、連立を組むことはイメージ戦略上もマイナスに働く可能性が高いのです。
また、今回の参院選でも維新は苦戦を強いられており、党内に連立参加を歓迎する雰囲気が乏しいことも背景にあります。
現実問題として、政策面でも安全保障や原発再稼働をめぐって維新と自民党には食い違いが多く、選挙後すぐに歩み寄る可能性は低いと見られています。
国民民主党との連立と村山内閣の再来案
一方で、現実味を帯びているのが国民民主党との連立案です。
同党は中道よりの現実路線を掲げ、政策面で自民党と一定の接点があり、政権運営に柔軟な姿勢を見せてきました。とくに注目されているのが、「玉木首相」構想です。
これは、国民民主党代表の玉木雄一郎氏を首相に擁立し、自民・公明・国民民主の「自公国」連立を組むという大胆な再編案です。
この構想は、1994年に村山富市社会党委員長を自民党が首相に担ぎ、社会党・自民党・新党さきがけによる「自社さ連立政権」が誕生した歴史と重なります。
当時も「自民党が首相ポストを他党に譲る」という大胆な選択が政局打開のカギとなりました。今回も似たような政界再編のシナリオが語られるのは、それだけ永田町における緊張感が高まっている証拠です。
「玉木首相」構想の現実味とキーパーソンたちの動き
玉木氏本人も、政権交代後の展望について「今の政党の枠組みがそのまま残るとは思えない」と述べており、自身の首相就任に意欲を見せています。
彼の姿勢は、あくまで「政権の安定と政策実行を優先する」という建前のもとにあり、石破政権の後継として受け入れられる素地も整いつつあります。
この構想を支えるキーパーソンには、自民党の森山幹事長や麻生元首相、さらには岸田前首相の影もちらつきます。
特に麻生氏と玉木氏は水面下で接触があったとされ、一部報道では「連立交渉の布石として既に動いている」とも噂されています。
さらに、連立交渉が進む過程で、国民民主党に対する政策的譲歩やポスト配分も重要な交渉材料となるでしょう。
連立に参加する代わりにどのポジションが与えられるのか、またその過程で誰が調整役を担うのか――永田町の緊張はますます高まりつつあります。
今後の焦点は、石破首相の退陣表明のタイミングと、それに続く「誰が新しい政権の顔になるのか」という一点に絞られていきます。
その中で「玉木首相」は、突飛な構想ではなく、現実的なオプションとしてにわかに注目されているのです。
まとめ
参院選で与党が過半数を割り込んだことにより、石破首相の進退と今後の政権運営をめぐって、永田町はまさに「嵐の前の静けさ」といった様相を呈しています。
石破政権の続投に対しては党内外で賛否が分かれ、「石破おろし」やポスト石破を巡る駆け引きが水面下で活発化しています。
岸田前首相の再登板をはじめ、旧派閥を軸とした合従連衡が加速するなか、政権の枠組みそのものが大きく変わる可能性も浮上しています。
なかでも、「玉木首相」構想に象徴されるように、国民民主党を取り込んだ新たな連立政権が誕生するシナリオは、現実味を帯びつつあります。
自民党内の内紛だけでなく、連立拡大の行方や、臨時国会に向けた総裁選のタイミング、野党側の動きも含め、日本の政治地図は今まさに大きな変動期に差しかかっています。
これからの数週間、永田町での一挙手一投足が、次の総理と政権の未来を左右することになりそうです。
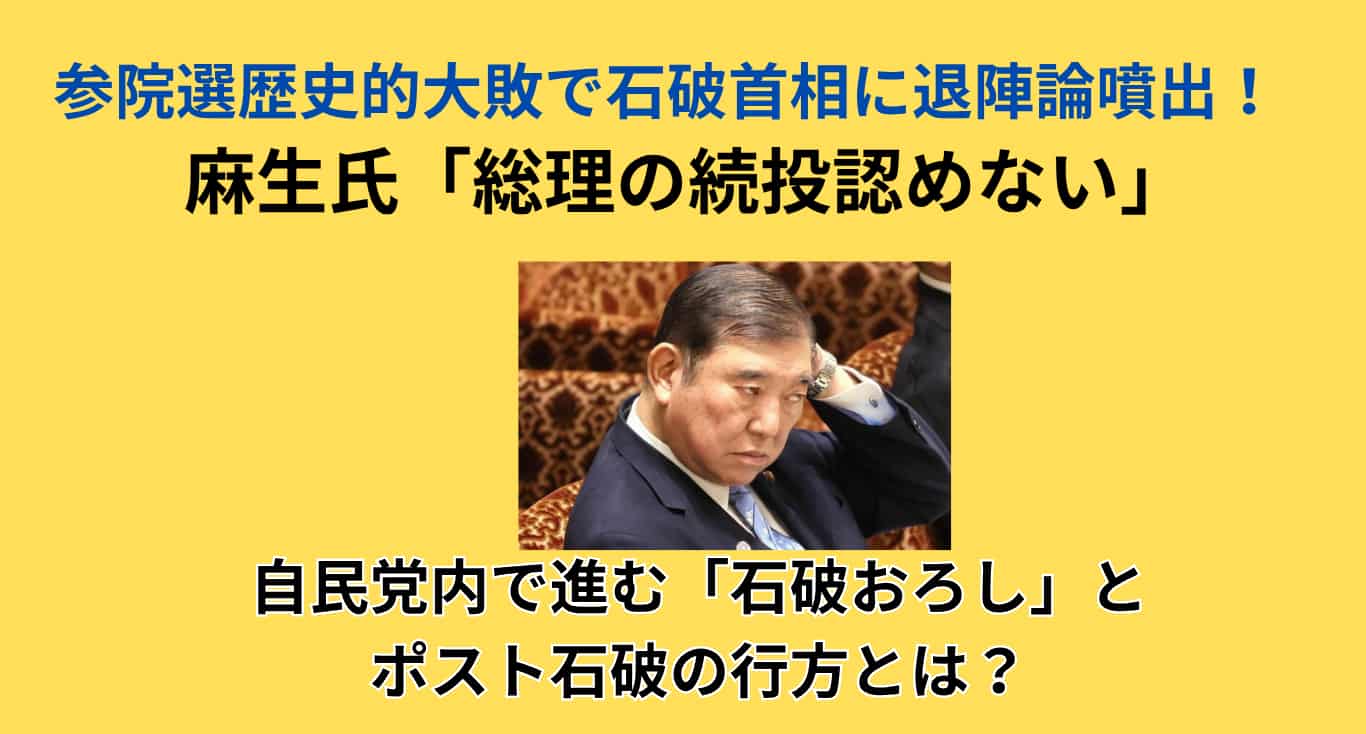
コメント