2025年7月に公開された起業家・溝口勇児さんの新プロジェクト「NoBorder」が、わずか数日でYouTubeチャンネルごとBAN(削除)されたことが話題になっています。安倍元首相暗殺の真相など、タブー視されるテーマに切り込んだ内容が「陰謀論」とも受け取られ、SNSでは「言論弾圧だ」と擁護する声とともに、「自作自演では?」という疑念も浮上しました。
この記事では、ひとりの視聴者としてこの出来事を丁寧に振り返りながら、なぜBANされたのか、どんな動画内容だったのか、そして本当に“表現の自由”が脅かされているのかを考えてみたいと思います。
はじめに
なぜ「NoBorder」は突然バンされたのか?
2025年7月8日にスタートした溝口勇児氏の新プロジェクト「NoBorder」は、その開始からわずか数日でYouTubeチャンネルが削除(通称「バン」)され、投稿されていたすべての動画が消去されるという衝撃的な展開を迎えました。
特に問題となったのは、安倍元首相の暗殺事件に切り込むというセンシティブな内容。世間的には「陰謀論」とも捉えられるそのテーマに正面から挑んだことで、プラットフォーム側からの規制を受けた可能性があると考えられています。
SNSでは「表現の自由への圧力ではないか?」という声も上がり、賛否が分かれる状況となっています。
溝口勇児という人物の背景と影響力
溝口勇児氏は、格闘技イベント「BreakingDown」の運営責任者(COO)として知られ、これまでに数々のベンチャー企業を立ち上げてきた起業家でもあります。
最近では、格闘家の朝倉未来氏とともに同イベントを仕切るほか、自ら選手としても出場し、全勝という記録を持つ異色の実業家です。
また2023年末には、自身のこれまでの経験を綴った著書『持たざる者の逆襲』を出版し、若者を中心に支持を集めました。そんな彼が立ち上げた「NoBorder」は、単なる動画プロジェクトではなく、彼自身の信念や問題意識が強く反映された社会的挑戦でもあったのです。
1.NoBorder立ち上げの経緯と目的
安倍元首相の命日に込めた挑戦の意味
「NoBorder」が公開されたのは、2025年7月8日――これは、安倍晋三元首相が銃撃され命を落とした日と同じです。
この日をあえて選んだことについて、溝口氏は「人生最大のリスクを伴う挑戦」と表現し、明確な決意をにじませました。ただの偶然ではなく、時代の転換点を象徴する日に、自らの信念と覚悟を重ね合わせたのです。
政治的なメッセージを直接的に語ることは避けながらも、溝口氏はこの日を「タブーに切り込む番組」の出発点と位置づけました。
安倍元首相の死の真相に迫るというセンシティブなテーマに対し、あえて“沈黙しない”姿勢を取ることで、現代日本のメディア環境や表現の自由の限界に対する挑戦でもあったといえます。
タブーに切り込む番組構想とその意義
「NoBorder」が掲げたのは、いわゆる“陰謀論”として扱われがちなトピックを、あえて正面から取り上げるという姿勢です。
安倍元首相暗殺事件のほか、政界やメディアに関する根深い疑問や、社会が見て見ぬふりをしてきた問題を扱い、その「境界線」を越えて語るというのが番組の基本方針でした。
もちろん、こうした内容は視聴者を選び、賛否を呼びやすいテーマでもあります。しかし、表向きの「自由社会」であっても、言及を避けられている話題は少なくありません。
溝口氏はその“避けて通る道”を選ばず、「どうせやるなら突き抜けたい」と自身のXで明言しています。これはYouTubeという一般的なプラットフォームをあえて選び、多くの人の目に届く場所で、あらゆる制限に挑んでみせたとも言えるでしょう。
BreakingDownからの転身と新たな挑戦
格闘技イベント「BreakingDown」で注目を集めた溝口氏ですが、彼にとって“戦う場所”はリングの上だけではありませんでした。
「NoBorder」は、情報の壁や偏見、権力との摩擦といった“見えない相手”に挑む場として立ち上げられたのです。
彼自身、BreakingDownでは主催者でありながら5度も試合に出場し、すべてに勝利しています。この「言葉と行動の一致」が、多くのファンの信頼を得る理由でもありました。
ビジネス界での成功だけでなく、社会的発信にも強い影響力を持つ溝口氏が、今度は自身の身を危険に晒してまで語ろうとする姿勢には、一種の“リアルな格闘”ともいえる覚悟がにじんでいます。
このように「NoBorder」は、BreakingDownでの戦いとは別の形で、彼の人生と信念を賭けたもう一つの舞台だったのです。
2.YouTubeチャンネルBANの顛末
第1弾~第4弾までの動画内容と反響
「NoBorder」のYouTubeチャンネルでは、公開から約10日間の間に4本の動画がアップされていました。
その第1弾は、安倍晋三元首相の銃撃事件の真相に迫る内容で、SNS上でも賛否両論が巻き起こりました
。視聴者の一部は「よくここまで言及した」「勇気ある試み」と称賛する一方、「不確かな情報を拡散するな」といった否定的な意見も見られました。
第2弾以降では、テレビや新聞が取り上げないようなテーマ――政府の情報管理や、大手メディアと政権の関係性などに踏み込む内容が続き、YouTube内でも視聴回数が急速に伸びていたことが確認されています。
コメント欄には「考えさせられた」「ここでしか見られない視点」といった声が並び、潜在的な需要の高さも感じさせるものでした。
「いきなりバン」の理由と可能性
ところが、そんな動きを止めるように突如起きたのが、チャンネルの“BAN”――すなわち、動画とアカウントの全面削除です。
溝口氏はこの件について、「何の警告もなく」「いきなり全部消えた」とXで語っており、その背景にはYouTubeのガイドラインに違反した可能性があると見られています。
ただし、YouTube側からは正式な理由説明が現時点で公開されておらず、「政治的に敏感な内容が自動的にAIに弾かれたのでは?」という推測もネット上で広まっています。
また、陰謀論的な表現や過度に扇動的と見なされる言葉遣いが、YouTubeのコンテンツポリシーに抵触した可能性もあります。
昨今、YouTubeでは「誤情報対策」の一環として、特定の政治的・社会的テーマに対し厳格な審査が行われており、公共性や視点の多様性よりも安全性が優先される傾向が強まっていることも一因といえるでしょう。
溝口氏の抗議と今後の対応
BANの直後、溝口氏は怒りと悔しさをにじませながらも冷静に現状を受け止め、X上で「抗議しまくります」と投稿しました。
YouTubeの窓口に直接連絡を取るだけでなく、知人を通じてGoogleの内部関係者にも状況説明を依頼するなど、多方面への働きかけを続けているとのことです。
さらに彼は、「おれがトランプぐらい影響力があれば、独自プラットフォームを作る」と投稿しており、今後の展開としては、より自由度の高い発信環境を自ら構築していく可能性も示唆しています。
すでにクラウド型のサーバー運用や、分散型ネットワークを活用した配信手段に関心を寄せているという情報もあり、「NoBorder」は一時的な挫折では終わらない、次なる動きへと向かっていることがうかがえます。
3.言論の自由とインフルエンサーの限界
陰謀論とされる情報に挑む覚悟
「陰謀論」という言葉には、事実かどうかにかかわらず“信用できない話”というイメージが付きまといます。
しかし溝口氏は、世の中で「語ってはいけない」とされてきたテーマ――それがたとえ陰謀論と呼ばれようと――に対して、あえて踏み込む覚悟を示しました。
たとえば、安倍元首相暗殺にまつわる報道の偏りや、事件の背後にある可能性への疑問提起は、既存メディアが避けがちな領域です。
こうした姿勢は、一部から「勇気ある発信」と賞賛される一方、「無責任な拡散」「扇動的だ」と非難されることもあります。
けれども、情報が均一化しがちな現代において、異なる視点を提示する存在が必要であることもまた事実です。溝口氏のように、誤解されるリスクを承知で「語ること」を選んだ姿勢は、表現の自由の本質を問い直すきっかけにもなり得ます。
独自プラットフォームへの思いと現実
YouTubeという巨大なプラットフォームを舞台にしながら、その限界にも直面した溝口氏は、「自分がトランプくらいの影響力を持っていれば、独自のプラットフォームを作る」と心情を吐露しました。
これは、単なる愚痴ではなく、現実に彼が情報発信の自由を確保しようと模索している証でもあります。
現代では、動画配信サイトやSNSが“公共の広場”のような役割を果たす一方で、その運営はあくまで民間企業のルールに従っています。
投稿者が自由に見えても、その実、言論空間はアルゴリズムやガイドラインによって制限されているのです。溝口氏は、その構造に直面した当事者として、いかにして“自分のメディア”を持つかを模索しています。
現実的には、独自サーバーやアプリの開発、サブスクリプション方式の導入といった選択肢がありますが、それらには資金力・技術力・継続的な運営力が求められます。
社会的影響力と規制のジレンマ
インフルエンサーとして一定の影響力を持つ溝口氏の発信は、ファン層への波及力が強い反面、社会的な責任も伴います。
「影響力があるからこそ発言を控えるべき」という声もありますが、それは時として「沈黙を強制する圧力」として機能する危険性をはらんでいます。
たとえば、医療や政治、事件の真相といったテーマは、多くの人が関心を寄せる分野である一方、誤解や誤情報を招きやすい領域でもあります。
プラットフォーム側の規制強化も、こうした“リスク回避”の一環と考えられますが、それが結果的に自由な言論や問題提起の芽を摘んでしまっては、本末転倒です。
溝口氏の試みは、今後の言論環境において「どこまでが自由で、どこからが規制されるべきか」という根本的な問いを私たちに突きつけているように感じられます。
一部で囁かれる“自作自演”疑惑について
今回のBAN騒動については、「話題作りのための自作自演じゃないの?」という声もSNSなどで見かけました。たしかに、チャンネルが急に注目を集め、その後すぐに削除され…という流れは、演出のようにも見えなくはありませんよね。
でも、私個人としては、その可能性はあまり高くないように思います。なぜなら、溝口さん自身がこの件について相当な悔しさや怒りを投稿で表現していたからです。
「本当に無力な自分が情けない」「徹底的に抗議する」とまで言っていたあの姿勢が、単なるパフォーマンスだとは感じられませんでした。
とはいえ、視聴者としては、すべてを鵜呑みにせず、いろんな視点から冷静に見ていくことも大事だと思っています。
「自作自演なのか?」「本当にBANされたのか?」という問いも含めて、まずは情報をじっくり見極めることが大切なのかもしれません。
まとめ
「NoBorder」は単なるYouTube番組のひとつではなく、溝口勇児氏の生き様と社会への問いかけが詰まった挑戦でした。
安倍元首相の命日にあえて始動し、表現のタブーとされる領域に切り込んだその姿勢には、現代の“語られないこと”への強い問題意識が表れています。
しかし、その挑戦は開始からわずか10日で“BAN”という壁に直面します。
理由の明示もないまま動画は削除され、発信の場を一瞬で奪われた彼の姿は、私たちが当たり前に享受している「自由」の脆さを浮き彫りにしました。
言論の自由とは何か、どこまでが許容されるのか──その曖昧な境界線の中で、発信者とプラットフォームはこれからもせめぎ合っていくことでしょう。
溝口氏が訴えた悔しさや、あきらめずに「次」を模索する姿勢は、同じ時代を生きる私たちに、「沈黙しないこと」の大切さを静かに伝えているのかもしれません。
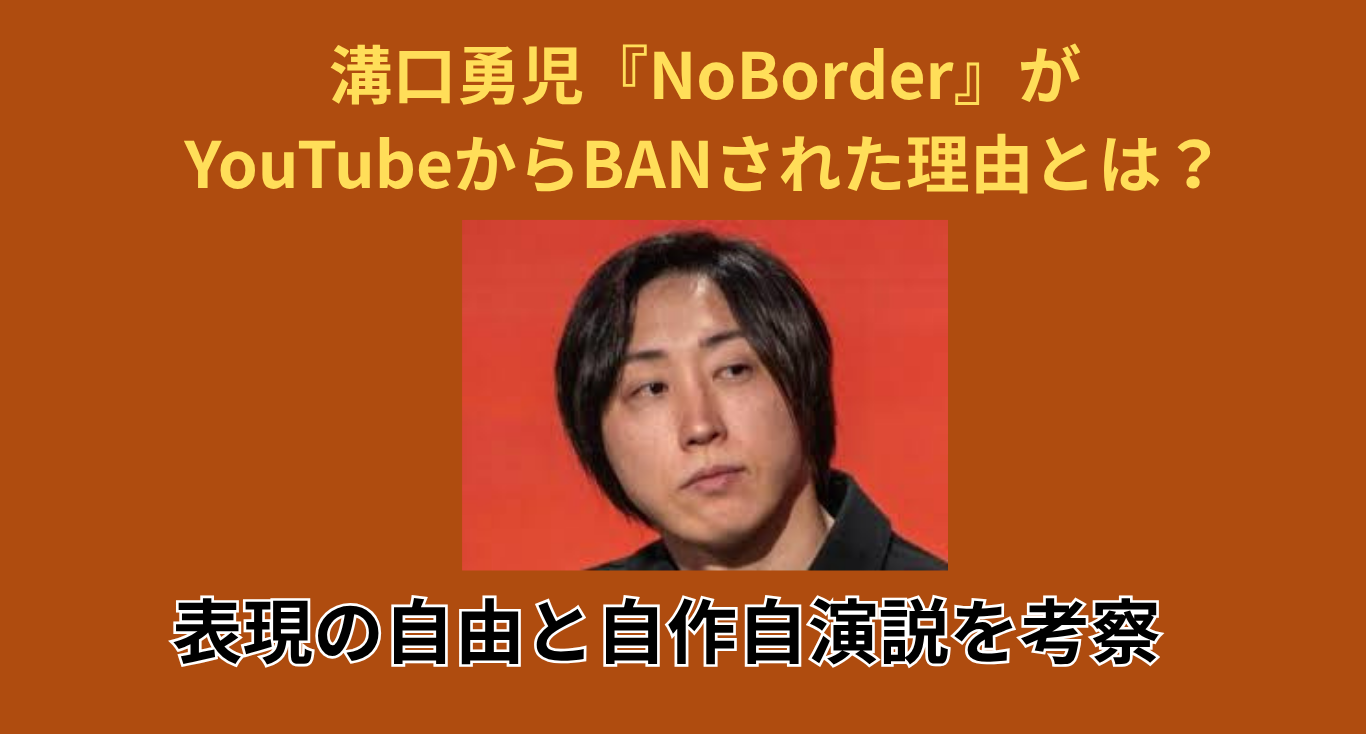
コメント