2025年7月、人気アーティストのキタニタツヤさんがX(旧Twitter)で投稿した「ショボくとも作り手であれ」という言葉が、ネット上で大きな話題となりました。
この一言が、なぜこれほどまでに多くの人の心を動かし、時に怒りや戸惑いをも引き起こしたのでしょうか?
本記事では、キタニさんの発言の背景と真意、そこに寄せられた共感や批判の声を、一般視聴者の立場からやさしい言葉で解説していきます。
SNS時代の「作り手と受け手」の関係について、いま改めて考えてみませんか?
はじめに
「ショボくとも作り手たれ」──キタニタツヤの問題提起
2025年7月13日、人気ミュージシャンのキタニタツヤがX(旧Twitter)に投稿したひとつの言葉が、大きな議論を巻き起こしました。
彼の言葉はこうです。「全ての人は『物知りな批評家』より『ショボい(ショボくとも)作り手』であってほしい」。一見すると控えめで謙虚な表現にも聞こえますが、実際には「誰もが創作者であるべき」という強いメッセージが込められており、音楽ファンやクリエイター、消費者の間で賛否が真っ二つに分かれました。
キタニは、自身の創作体験をもとに「手を動かして初めてわかることがある」と語ります。
イラスト制作ソフト「クリップスタジオペイント」を例に出し、実際に描いてみなければ線一本すら満足に引けない現実を、ユーモラスかつ切実に伝えました。
これは単なる愚痴ではなく、“消費者である前に、少しでも「作る側」に立ってみてほしい”という提案でもあります。
賛否を呼んだ発言の背景とSNSでの広がり
この投稿はSNS上で大きな反響を呼び、数日でインプレッションは650万件を超え、リポストも1万件以上にのぼりました。
肯定的な声は「たった一言で心が折れることもある」「作り手の気持ちがわかる社会になってほしい」といった共感のコメントが多く寄せられました。
一方で、「創作者が偉いという特権意識を感じる」「すべての人が作り手になるべき、という発想は危うい」といった批判も相次ぎました。
特に議論の中心となったのは、「創作者 vs 純粋な消費者」という構図そのものです。
キタニの投稿は、一部からは「消費者を見下しているように見える」という声すら上がりました。
ネット社会では誰もが気軽に感想や批評を発信できる今、「作り手と受け手」の関係性がどこまで対等であるべきか、改めて問い直される機会となったのです。
1.キタニタツヤの主張とその意図
“純粋な消費者”に対する提言の意味
キタニタツヤが投げかけた「ショボくとも作り手であれ」という提言は、単なる創作のすすめではありません。
それは、“ただ受け取るだけの存在”である「純粋な消費者」に対する静かな挑戦でもあります。
彼の言葉の背景には、作品を「無料で楽しむことが当然」と捉える風潮や、創作者への容赦ない批評が日常化したネット社会への違和感があります。
彼は、「たとえ不格好でも、手を動かして何かを作ってみることで、他者の創作に対する見方が変わるはずだ」と信じています。
これは、音楽でも絵でも文章でも構わない。「やってみたら難しさがわかる」という、ごく当たり前だけど忘れがちな気づきを、彼なりの言葉で投げかけたのです。
クリエイター視点からの「努力」への共感要求
キタニの発言の根底には、「作る」という行為がどれほど労力と時間、そして精神力を要するかを知ってほしいという切実な願いがあります。
彼が例に出した「CLIP STUDIO PAINTを3時間触るだけで綺麗な線も引けない」という話は、イラストを描いたことのない人にも伝わりやすい例えでした。
音楽制作もまた、短時間で成果が出るものではなく、地味な繰り返しと失敗の積み重ねです。
にもかかわらず、SNSやレビュー欄には「もっとこうすればよかった」「前作よりイマイチ」など、時に一方的とも言える評価が並びます。
もちろん感想を述べる自由はありますが、その中には無自覚に創作意欲を削ぐような言葉も少なくありません。キタニは、そうした消費者の側にも「想像力」や「共感」が必要だと感じているのです。
「DESK TOP MUSICファイター」としての自己告白
さらに彼は、自らを「DESK TOP MUSICファイター」と称して、正直な葛藤も明かしています。
「作り手様はそんなに偉いんか!」と反発されることを想定しながらも、それでも“作り手であること”への矜持を手放せない自身の性格を「性格の悪い可哀想な奴」と自嘲しました。
飲み会で孤立するような極端な意見を持ちながら、それでもそれを貫いてしまう――。
キタニのこの率直さは、単なる上から目線ではなく、「他者との共感のズレに悩む一人の人間」の姿として、多くの共感を集めた理由のひとつかもしれません。
つまり彼の提言は、誰かを叩くためのものではなく、「わかりあえないことへの諦めと、それでも伝えたい気持ち」がにじむ、ある種の独白だったのです。
2.共感を寄せる声──作り手を知るということ
「一度でも創作してみたらわかる」派の主張
キタニの発言に深く共感した人々は、「一度でも何かを作ってみれば、どれほど大変かわかる」と口を揃えます。
実際に、イラストを描こうとして思い通りの線が引けなかったり、文章を書いても言いたいことがうまくまとまらなかったりする経験は、多くの人にとって心当たりのあるものです。
たとえば、「子どもの頃に漫画を描いてみたけど1ページで挫折した」といったエピソードがX(旧Twitter)上で数多く共有されており、それが「作るって、こんなに難しいんだ…」という素直な気づきにつながっています。
このような体験から、少しでも“作る側”を理解しようとする姿勢が生まれ、「言葉の選び方ひとつで、誰かの背中を押すことも、折ってしまうこともある」という意識が高まっているのです。
批評の裏にある無自覚な暴力性
SNS時代の現在、誰もが「感想」を発信できる一方で、「批判」と「攻撃」の境界が曖昧になりがちです。
「この曲、前のより微妙」といった何気ない一言でも、クリエイターにとっては大きな痛手になることがあります。キタニが訴えたのは、そうした言葉の無神経さに対する警鐘でした。
共感を寄せる人々は、創作の裏にある見えない苦労を想像できるからこそ、言葉を選ぶようになります。
たとえば、「この作品は好みじゃないけれど、試行錯誤が感じられて興味深かった」といった表現に変えることで、同じ“感想”でも伝え方の質が大きく変わります。
キタニの投稿が突きつけたのは、作り手の苦悩を想像することの重要性でした。
そしてそれは、単にクリエイターへの優しさだけでなく、自分の発信が持つ影響力を見直すきっかけにもなっています。
「優しさが生まれる社会」を目指して
「一人ひとりが、少しでも“作る側”の痛みを知っていたら、もっと優しい世界になるのでは?」という声が、キタニの投稿以後、多くの共感を集めています。
たとえば、学生時代に自主映画を撮った経験のある人が「たった10分の映像を作るのに何十時間もかかった。それが誰にも見られないまま終わるつらさを知ってる」と投稿し、「だからこそ誰かが見てくれるだけで救われる」と続けていました。
このように、“創作の現場”に一度でも立ったことがある人たちは、他人の努力や葛藤を想像しやすくなります。
キタニの呼びかけは、単に「作ってみてよ」と軽く促すものではなく、「誰かの心を削って生まれた表現に、もう少しだけ思いを馳せてみようよ」という優しさの提案でもあったのです。
3.批判する声──特権意識と表現の危うさ

「創作者が偉い」という上下構造への違和感
キタニタツヤの「ショボくとも作り手であれ」というメッセージに対しては、「創作者のほうが消費者よりも優れている、という上下関係を感じる」という声も少なくありませんでした。
特に、「非創作者より創作者のほうが偉い」という印象を受けた人々からは、「トップミュージシャンが消費者を殴っているように見える」といった厳しい批判も寄せられました。
確かに、作り手の苦労や技術を知ってもらいたいという意図は理解できる一方で、「創作者にならない者は未熟だ」と捉えられる発信は、受け手に対するマウンティングとも受け取られかねません。
すべての人が表現者であることを求めるメッセージは、無意識に“価値ある人間像”を限定してしまう危うさをはらんでいます。
「誰もが作り手たれ」は成立するか
キタニが投稿で強調した「誰もがショボくとも作り手であってほしい」という理想は、響く人には強く響く一方で、「現実的ではない」と感じる人も多くいました。
現代社会では、時間的・精神的な余裕がなければ創作活動に手を出すことすら難しいという現実があります。日々の生活に追われながら、娯楽として作品を楽しむだけの人もいて当然です。
また、「純粋な消費者でも、創作者に敬意を払うことはできる」「創作者であっても、他人の表現を攻撃する人もいる」といった指摘もありました。
つまり、「創作をするか否か」で人の在り方を二分する考え方そのものに、違和感を覚えた人が多かったのです。
トップアーティストとしての影響力と発信の責任
キタニは紅白歌合戦にも出場し、若者を中心に強い影響力を持つアーティストです。
その発言ひとつひとつが、大きな意味を持つことも自覚しているようで、「スマセン、そう思っちゃってます…」と控えめな言い回しも投稿内に見られました。
とはいえ、立場のある人間が発信する言葉には、慎重さと配慮が求められます。
特に、ネット上では断片的に言葉だけが拡散され、意図とは異なる解釈をされることも多々あります。
今回の騒動でも、「自分とは関係のない人間にまで“作り手であれ”と押しつけているように見えた」という声が多く見られました。
つまり、キタニのように社会的影響力を持つ人物が自己の思想を語るとき、その言葉が誰を励まし、誰を傷つけるかという“発信の責任”が常につきまとうということを、私たち自身も再認識する必要があるのかもしれません。
まとめ
キタニタツヤの「ショボくとも作り手であれ」という言葉は、多くの人の心を揺さぶる一方で、強い反発も招きました。
その背景には、現代のネット社会における「批評と創作」の関係性や、「消費者とクリエイター」の力学が複雑に絡んでいます。
共感を寄せた人たちは、「一度でも作ってみれば、作品の裏にある努力や葛藤がわかる」とし、批判的な言葉を発する前に“想像力”を持つことの大切さを訴えました。
一方で、反対の立場からは、「すべての人に創作を求めるのは暴力的ではないか」「創作者が優位に立つという特権意識が透けて見える」といった声がありました。
キタニの真意がどこにあるかは本人にしかわかりませんが、少なくともこの投稿は「表現する側と受け取る側」のあり方を多くの人に考えさせる契機となりました。
そして私たちもまた、作品に触れるとき、その背後にある“誰かの手間や思い”に、ほんの少しでも思いを寄せることができれば、それだけで社会は少し優しくなるのかもしれません。
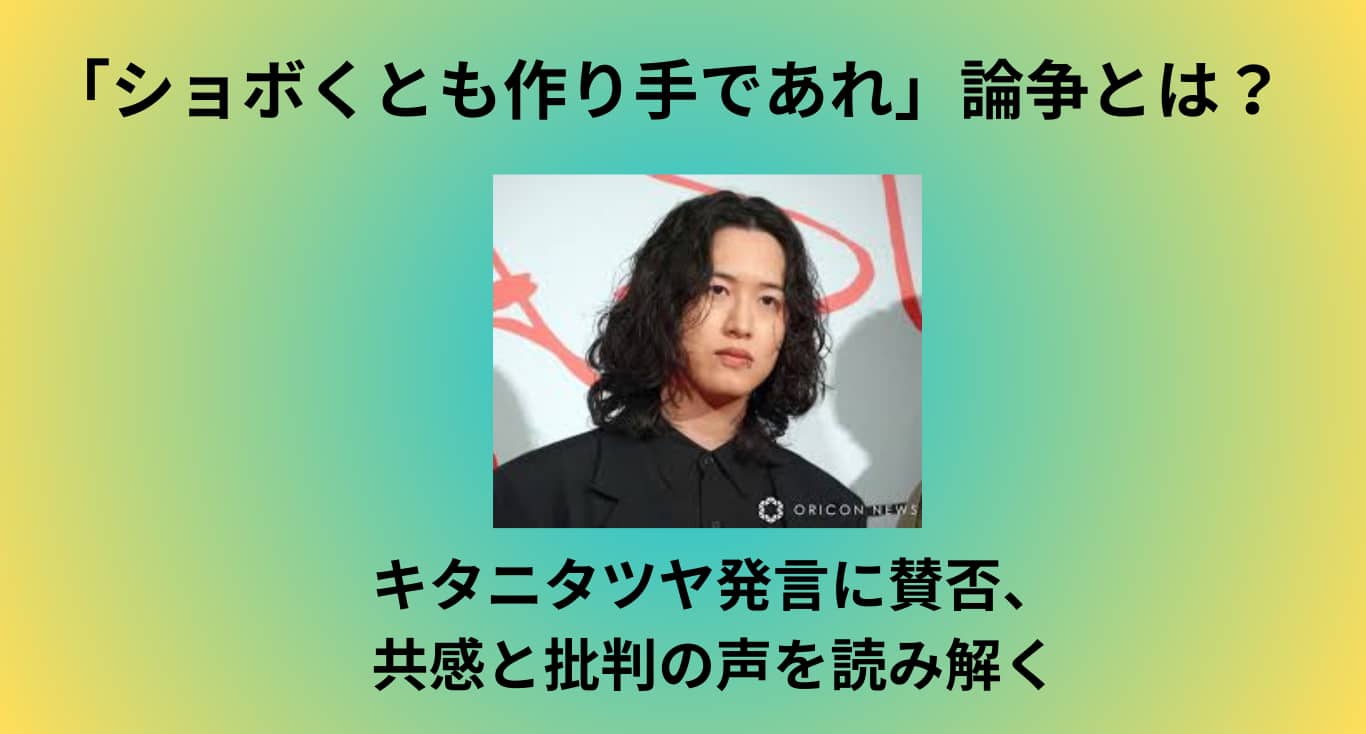
コメント