2025年7月14日放送のNHK「あさイチ」で取り上げられた“選挙特集”が、思わぬかたちで話題を呼んでいます。
番組内では「白票も意思表示のひとつ」という視点から、視聴者投稿を紹介。
しかし放送後、SNSでは「白票を肯定するのは無責任では?」といった厳しい意見が噴出し、一部では“炎上”状態に。
この記事では、白票をめぐる制度的な位置づけや、視聴者・ネット上の反応、さらには私たち有権者ができる具体的な行動までを、ひとりの生活者の視点で丁寧に掘り下げてみました。
選挙のたびに「投票すべきか、白票か」と迷う方こそ、ぜひ読んでみてください。
はじめに
あさイチが取り上げた「選挙特集」とは
2025年7月14日、NHKの朝の情報番組「あさイチ」で放送された「選挙特集」が、思わぬ波紋を呼んでいます。
番組の後半では、視聴者から寄せられた「白票に関する体験談」が取り上げられました。
投稿者は「白票も政治への意思表示だと思って投票したのに、投票所で立会人に止められた」と訴え、スタジオではこれに対し、白票は無効票とされつつも「候補者にふさわしい人がいないというメッセージになる場合もある」と紹介されました。
選挙制度や投票行動の意味について考える機会として、公共放送がこうしたテーマを扱うことには意義があります。
しかし今回、番組内の表現や伝え方が「白票を肯定しているように聞こえる」として、放送直後からSNSでは批判の声が広がりました。
なぜネットで炎上したのか、その背景
一見、選挙参加を促す意図にも見えるこの特集ですが、「白票にも意味がある」といった紹介の仕方に違和感を覚える視聴者が少なくなかったようです。
実際、「白票は結果的に現職を有利にするだけ」「無効票を投じても何も変わらない」という意見が多く、ネット上では「NHKが白票を勧めているように見える」との誤解や怒りも噴出しました。
政治への不信が根強く残る中で、有権者の「投票しない」「白票を投じる」といった選択がどんな意味を持つのかは、社会的にも繊細な話題です。
今回の「あさイチ」の取り上げ方は、その「ニュアンスの難しさ」を象徴するものとなりました。
1.番組内で紹介された「白票」投稿とは

投稿者の主張:「白票も意思表示」
「あさイチ」の「選挙特集」で注目を集めたのは、ある視聴者からの投稿でした。
その内容は、「政治に不信があっても投票には行きたい。だから自分はあえて白票を入れた」というもの。投稿者は、「白票も、誰にも投票したくないという“明確な意思”だ」と語っており、これは多くの有権者が感じているモヤモヤを代弁しているようにも受け取れました。
しかし、投稿の中には「白票を入れようとしたら投票所で止められた」というエピソードも含まれていました。
これが視聴者のあいだで「そんなことがあるのか?」と驚きと不安を呼び起こした要因でもあります。
実際には白票そのものは認められており、記入せずに投票箱に入れる行為は可能です。だとすれば、投票所での対応が不適切だった可能性も否定できません。
番組側の対応と解説
この投稿を受けて、番組のアナウンサーは「白票は無効票にはなります」と明言。
そのうえで、過去の選挙で白票を含む無効票が20万票を超えた事例を挙げ、「それも一つの有権者の意思として受け取られた」というような解説を加えました。
一見、中立的な説明に見えますが、「白票が意味ある行動として取り上げられた」と感じた視聴者が多かったのも事実です。
なかには、「NHKが白票を推奨しているように聞こえた」と憤る人もいました。
公共放送としてどこまで“意思表示”の一つとして紹介するか、そのバランスの取り方が問われる内容だったといえるでしょう。
白票を巡る過去の事例とその意味づけ
番組内でも紹介されたように、過去の選挙でも白票や無効票が話題になったことはあります。
たとえば2014年の衆院選では、無効票数が全国で180万票を超えたことが報じられ、「投票先がない」という有権者の声の表れとする報道もありました。
ただし、白票が政治的メッセージとして正式に扱われることは制度上ありません。
有権者の「不満」や「選択肢のなさ」を象徴する行為として社会的に語られることはあっても、選挙結果には何の影響も与えないのが現実です。
こうした過去の経緯と意味を踏まえると、白票の紹介はより慎重に行うべきだったとの声が上がるのも理解できます。
2.ネット上の反応と批判の声
「白票肯定」に対する厳しい意見
番組放送後、最も目立ったのは「白票に意味がある」という表現に対する厳しい声でした。
SNS上では、「白票を入れることで現状が変わるわけではない」「白票が無効票である以上、それを肯定するのは無責任」といった投稿が多く見られました。中には、「こんな報道を公共放送でやるなんて信じられない」「NHKが投票棄権を促すような内容を流すなんて」と強い口調で非難する意見もありました。
また、「白票は現職を利するだけ」「実質的には現状維持の票だ」と指摘する声も目立ちました。
特に選挙の結果が僅差である場合、無効票が多ければ多いほど投票された候補者の相対的な価値が上がることを懸念する人が多かったようです。
SNSで広がった誤解や懸念
SNSでは、番組の内容が一部切り取られた状態で拡散され、「NHKが白票を勧めている」「白票投票を礼賛している」といった誤解が生まれました。
短い動画やスクリーンショットに反応するかたちで、番組全体の文脈を知らずに批判する投稿も多く見受けられました。
このように一部の情報だけが独り歩きしてしまう現象は、今回に限ったことではありません。
たとえば、以前も政治家の発言が部分的に拡散され、「実際とは異なる意図で受け取られた」として問題になった例が複数あります。
今回のケースも、「白票=意思表示」という部分が一人歩きし、賛否が過熱する結果となりました。
放送内容に対する信頼の揺らぎ
今回の炎上を受け、NHKという公共放送に対する信頼にも揺らぎが生じています。
「中立であるべきNHKが、特定の考え方を支持しているように見える」という批判は、特に政治に敏感な層から強く上がりました。
「受信料を払ってまでこんな報道を見たくない」といった不満もあり、視聴者との距離感が改めて問われる結果となりました。
このような反応は、単に「白票」というテーマだけでなく、報道のあり方や伝え方、そしてメディアの責任に対する疑念も反映しているように感じられます。
誤解を招かない丁寧な報道と説明が、いまほど求められている時代はないかもしれません。
3.白票の法的・政治的な位置づけ
白票=無効票の扱いとは
日本の選挙制度では、「白票」は法律上「無効票」として扱われます。
つまり、選挙管理委員会が開票作業を行う際、候補者名や政党名が書かれていない票は、どれほどきれいに投票用紙が記入されていても“カウントされない票”として処理されるのです。
たとえば、投票用紙を白紙で投函したり、「誰にも投票したくない」といったメッセージを書いた場合も、制度上はすべて無効票です。
政治的な意思表示だとしても、開票作業では機械的に省かれるため、結果に反映されることはありません。
これが、「白票に意味があるのか?」という議論を生む大きな理由のひとつでもあります。
白票が示す意思と限界
一方で、白票を投じる人の中には、「誰にも投票したくない」「現状の選択肢に納得できない」という、れっきとした問題意識を持って行動している人もいます。
これは確かに“無関心”とは異なります。しかし、現実として白票は「誰にも投票しない」という結果しか残らず、その意図や背景が選挙結果に具体的に反映されることはありません。
たとえば、地方選挙で白票を含む無効票が非常に多かったケースでも、それが再選挙や制度改革につながることはほとんどありませんでした。
結局、白票は「問題提起」にはなっても「変化を起こす票」にはなりにくいという限界があります。
有権者が取れる他の行動は何か
では、「誰にも投票したくない」と感じたとき、有権者にはどんな選択肢があるのでしょうか。
一つは、地域の候補者や政党に意見を届けること。SNSや市民活動を通じて声を上げることも、意思表示の手段です。また、投票前に候補者の公開討論やマニフェストをじっくり比較し、「少しでも納得できる」選択肢を探す努力も重要です。
さらに、無所属の新人候補や少数政党の存在を見直すきっかけにもなります。
「どれも同じ」と思っていても、細かく調べていけば、わずかな違いが大きな変化を生む可能性を秘めている場合もあります。
白票という選択には一定の意味があるとはいえ、それが社会を動かす力として機能しにくいこともまた事実です。
だからこそ、投票のたびに「自分の声をどこに託すか」を考える姿勢が、民主主義を支える一歩となるのではないでしょうか。
まとめ
NHK「あさイチ」の「選挙特集」で取り上げられた白票投票をめぐる話題は、視聴者のあいだでさまざまな議論を巻き起こしました。
番組内では「白票も意思表示のひとつ」と紹介されましたが、その伝え方が「白票を肯定している」と受け取られ、ネット上では批判が殺到。白票に対する見方や、公共放送の報道のあり方にまで波紋が広がりました。
白票はたしかに「現状への不満」や「選択肢がない」という声の表れではありますが、制度上は無効票として扱われ、選挙結果には反映されません。
つまり、意思表示としての意味は持ちつつも、政治を変える力としては限界があるのが現実です。
そのうえで私たち有権者ができることは、情報を深く知り、自分の考えに近い候補者を見つける努力を惜しまないこと。
白票を入れるという“消極的な選択”ではなく、“小さくても前向きな一票”をどう見つけるかが、これからの選挙を変えていく鍵になるのではないでしょうか。
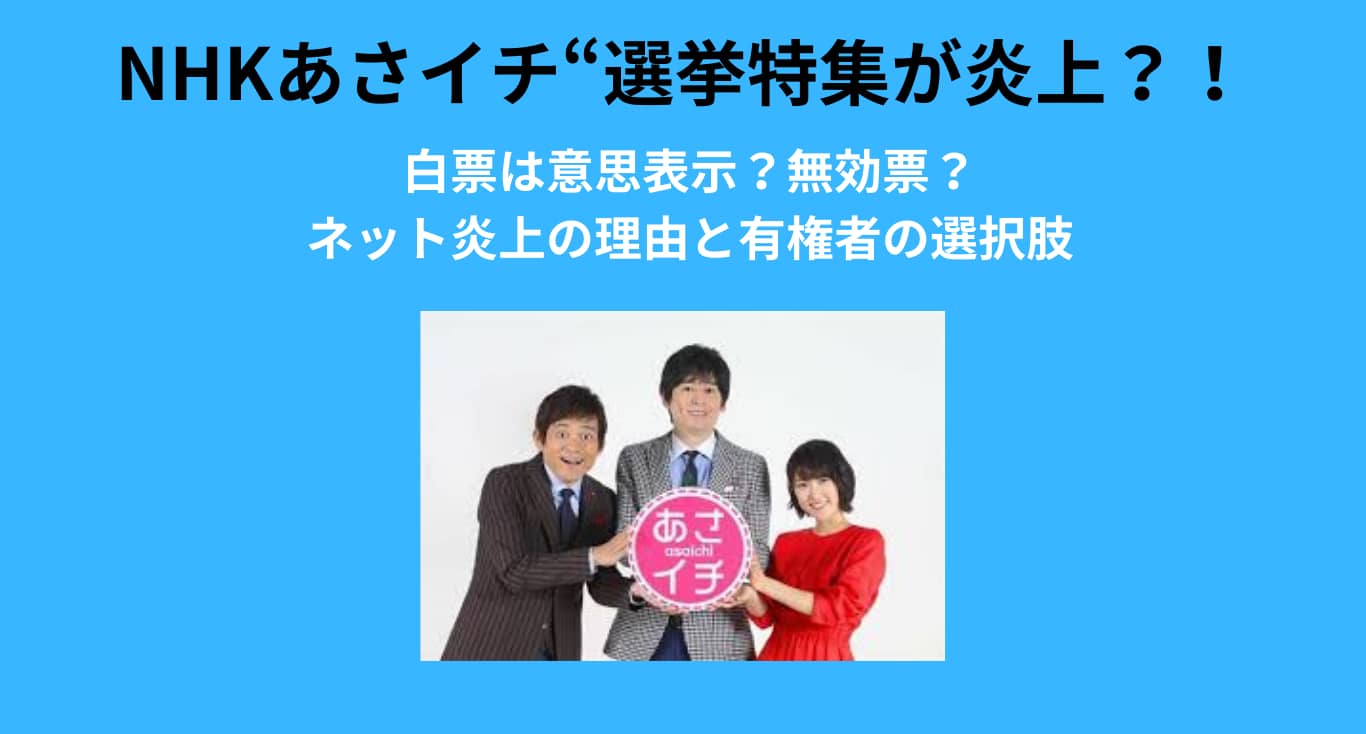
コメント