最近、東京都内の公園で「セミの幼虫の乱獲」が大きな問題になっています。特に深夜の時間帯に、外国人とみられるグループが大量に採集するケースが相次ぎ、公園管理者は中国語や韓国語、英語など多言語による「採取禁止」の張り紙で対応せざるを得ない状況です。
この記事では、一市民として実際に寄せられた住民の声や現場の対応、条例との関係、そして子どもたちへの影響などをわかりやすく紹介します。セミの幼虫を守ることは、ただのマナーの話ではなく、地域と自然を次世代へ引き継ぐための大切な課題です。
はじめに
都内の公園で起きている「セミの幼虫乱獲」問題
夏の風物詩ともいえるセミの鳴き声。その前段階である「幼虫」は、木の根元からはい出して、静かに羽化の準備をしているんです。
でも最近、東京都内の公園で、そのセミの幼虫が大量に採られてしまうという事態が相次いでいると聞いて、びっくりしました。
深夜になると、ライトもつけずに木の周りを探し回る人たちがいて、それを目撃した地域の方々が不安の声をあげているそうです。
実際、公園の管理者さんたちも「セミの幼虫を採らないでください」と書かれた張り紙を急いで出すほど、深刻な状況になっているんだとか…。
なぜ今、外国人による採集が注目されているのか
この問題が大きく取り上げられている背景には、採集している人の多くが外国の方と見られている点もあるそうです。
現場で声をかけても「日本語がわかりません」と返されるケースもあるそうで、張り紙も中国語・韓国語・英語など、いろんな言語で掲示されるようになっています。
文化の違いや食べ物の習慣など、事情がいろいろあるのはわかるのですが…一度に何十匹も採ってしまうような行為には「さすがにやりすぎでは?」という声が挙がるのも当然ですよね。
自然と触れ合う場である公園が、こんな風に荒らされてしまうのは、本当に悲しいです…。
1.深刻化するセミ幼虫の乱獲被害
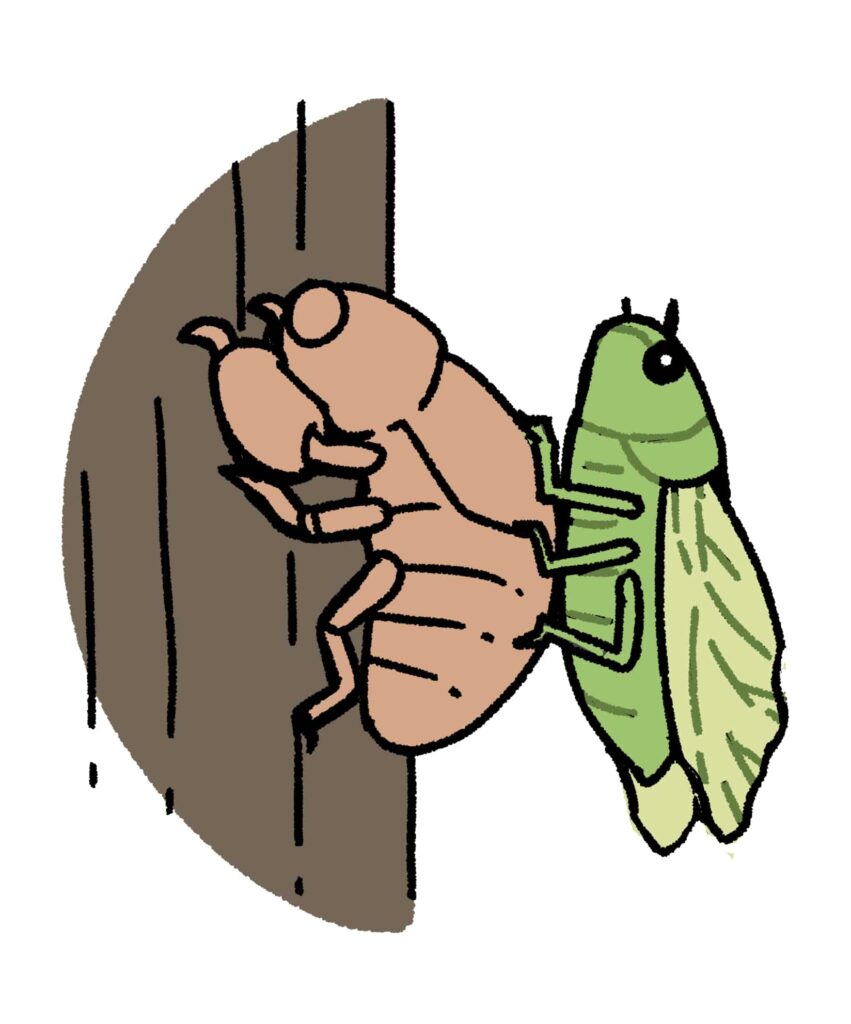
夜間に繰り返される大量採集の実態
セミの幼虫が地面から出てくるのは、夜から深夜にかけての時間帯。普段は静かなその時間帯に、人目を避けるように動く人たちの姿が公園でよく見られているそうです。
ある警備員さんは、巡回中に一晩で何十匹もの幼虫が採られていた現場を目撃したと話していました。
しかも、素手で木の根元を探ったり、木に登ったり、落ち葉をかき分けたりして…明かりも使わずに作業するので、突然出くわした近所の方が悲鳴を上げたこともあったとか!
夜の公園でそんな場面に遭遇したら、誰だってびっくりしますよね…。
目撃情報と住民の不安の声
「暗闇の中で何人もが木を物色していた」「あれでは安心して子どもと遊びに行けない」といった声が住民の間で多くあがっているそうです。
特に小さなお子さんを持つご家庭では、「セミを探すのを楽しみにしていたのに、全部採られていた…」なんて声も聞かれています。
私も子どもと一緒に、夏の公園でセミの抜け殻を見つけたりするのが大好きなので…この話を聞いたときには、すごく残念な気持ちになりました。
管理者による張り紙とその多言語対応
こうした状況を受けて、公園の管理者さんたちは「セミの幼虫を採らないでください」という張り紙をたくさん掲示するようになったそうです。
江東区の猿江恩賜公園では、日本語だけでなく、中国語、韓国語、英語などでも表示されています。
張り紙には、「子どもたちが楽しみにしています」といった、やさしい言葉も添えられていて…単にルールを押しつけるのではなく、思いやりの気持ちが込められていることが伝わってきます。
今年は羽化のシーズン前から、30枚も張り紙が用意されたということで、現場の深刻さがうかがえますね。
2.採集者の背景と「目的不明」の現実
中国語・韓国語の掲示が意味するもの
多言語での張り紙は、まさに現場の対応の工夫のひとつです。
実際、採集をしていた人に注意しても「日本語が通じない」と言われてしまう場面も少なくないようで…文化や言語の違いって、本当に難しい問題だと思います。
たとえば猿江恩賜公園の張り紙には、日本語の下に中国語や韓国語で「セミの幼虫を採らないでください」とやさしい表現で書かれていて、ただ禁止するだけじゃなくて、マナーの共有を目指している感じが伝わってきますね。
食用目的の疑惑と過去の対応事例
一部では、「セミの幼虫は食べるために採っているのでは?」という疑問の声もあがっているそうです。
日本ではちょっと考えにくいことかもしれませんが、昆虫を食べる文化のある国もあるので、実際にそういう目的で採っている人がいるのかもしれません。
過去には埼玉県川口市や杉並区などでも、同じような問題が起きていて、「食用目的での採取禁止」の張り紙が掲示されたこともあるそうです。「販売してるんじゃないか」と疑われた事例もあったとか…。
でも、実際に「何のために採ってるの?」と尋ねても、言葉が通じなかったり、「なぜダメなのか分からない」と言われてしまうそうで…本当の目的を確認するのはとても難しいみたいです。
管理側が感じる限界と困惑の声
現場で巡回している管理会社や警備員さんたちも、「どう対応していいか分からない」と悩んでいるようです。
子どもが虫かごに1~2匹入れているくらいなら問題ないけれど、大人が袋に何十匹も入れて持ち帰ろうとするとなると、やっぱり注意せざるを得ないとのこと。
でも、注意しても「日本語が分かりません」と言われてしまうと、それ以上何も言えないし、条例違反でもその場で取り締まる権限がない…。現場の皆さん、本当に苦労されているんだなと感じました。
3.公園のルールと環境保全の観点から
都条例で禁止されている動植物の採取行為
実は、都内の公園では植物や動物を勝手に採ってはいけないって、きちんとルールで決められているんです。これは東京都の公園条例に基づいたもので、公園の自然を守るための大切な取り決めです。
でも正直、私もこうして記事を書くまで、そこまで明確にルールがあるって知りませんでした…。外国人の方にとってはなおさら、「木にいる虫を取ってはダメ」という考え方自体が伝わりづらいのかもしれませんね。
他地域でも広がる「採取禁止」対応
この問題は、東京だけじゃなくて、近隣の市や町でも起きているみたいです。たとえば埼玉県川口市や千葉県松戸市などでも、注意喚起のポスターが出されたり、チラシを配ったりしているそうです。
中には、学校と協力して子どもたちに生き物観察のマナーを教える自然観察教室を開いている地域もあるんだとか!これってすごくいい取り組みだと思います。
頭ごなしに「ダメ!」じゃなくて、「なぜ大切なのか」を伝えるって、子どもだけじゃなく大人にも響きますよね。
最近では、罰則のことばかり書くのではなく、「子どもたちの体験を守るため」など、共感を呼びかけるメッセージが増えてきているそうです。みんなで守るという意識が大事ですよね。
子どもたちの自然体験への影響
一番かわいそうなのは、やっぱり子どもたちです。
夏休みの自由研究でセミの羽化を観察したり、朝早く起きてセミの声を聞いたり…そんな貴重な体験が、乱獲のせいでできなくなってしまうなんて、本当に残念です。
「セミの抜け殻が全然なかった」「虫かごを持っていっても、誰かに『もういないよ』と言われた」といった話も耳にします。せっかく楽しみにしていたのに、それを大人の事情で奪ってしまうなんて…切ないですよね。
自然とのふれあいって、子どもの感性や想像力を育てるとっても大切な時間だと思います。それを壊してしまわないように、大人たちがルールを守って、ちゃんと次の世代に引き継いでいけたらいいなと思います。
まとめ
都内の公園で起きているセミの幼虫の乱獲問題。これは単なる「マナーの悪さ」では済まされない、とても深刻な課題です。
夜中にこっそりと繰り返される大量採集、言葉が通じないもどかしさ、文化の違い…いろんなことが複雑に絡み合っています。
でも、だからこそ大事なのは「どうやってみんなでこの場所を守っていくか」ということ。いろんな国の人が暮らす中で、お互いの文化を理解しながら、ルールを共有していくことが大切だと感じました。
セミの声が響く夏の朝、子どもたちがワクワクしながら自然とふれあっている…そんな風景をこれからも守っていけるように、大人として、地域の一員として、私もできることをしていきたいと思います。
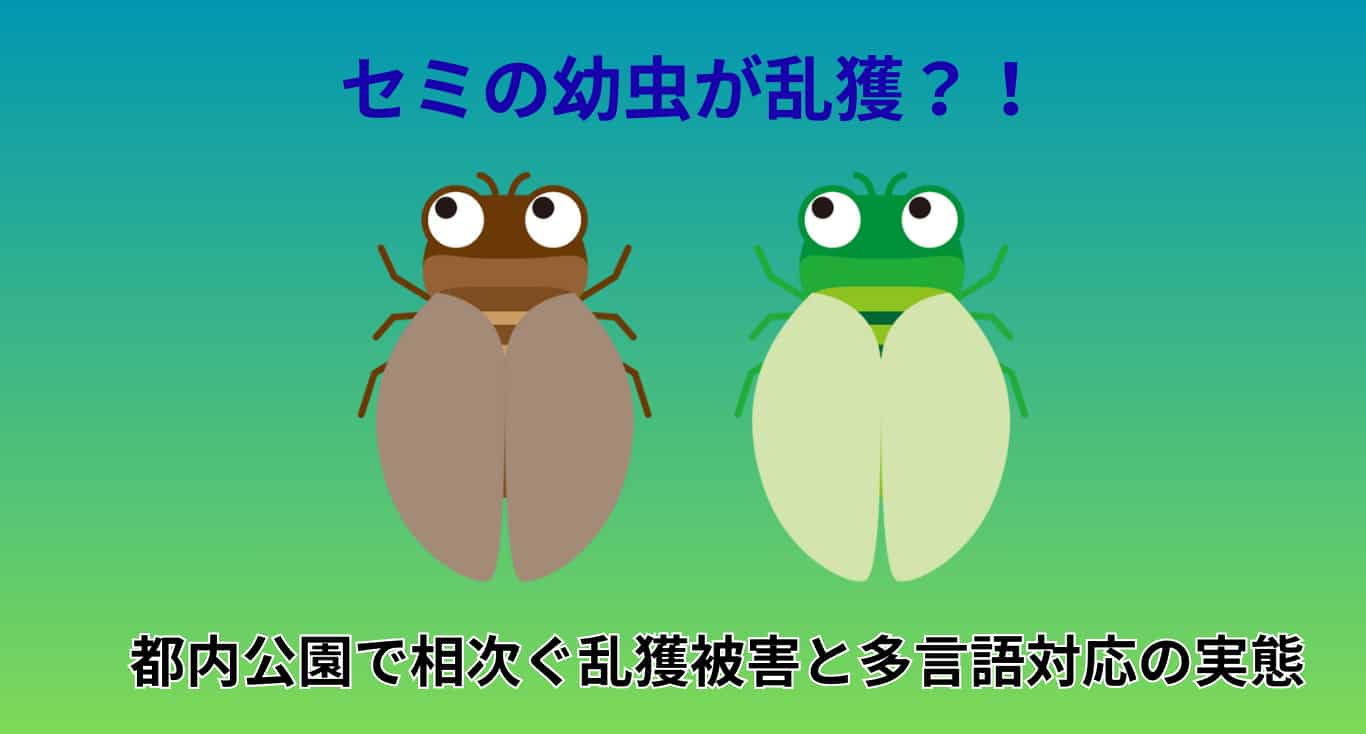
コメント