「政府が50年ぶりに“減反政策”を見直し、米の増産へと方針転換しました。でも本当に今、農家は米を増やせるのでしょうか?――」
ウクライナ情勢や気候変動によるコメ不足、食料安全保障の問題を背景に、2024年春、国はコメの生産量を増やす政策を打ち出しました。しかし、現場の米農家からは「もう無理だ」「現実が見えていない」と不満の声が上がっています。
この記事では、米農政の大転換の理由と背景、そして現場の農家が直面している厳しい現実を、一般消費者の視点でわかりやすくお伝えします。
はじめに
米農政が大転換、「減反」から「増産」へ
2024年春、政府は長年続けてきた「減反政策」に終止符を打ち、米の増産に舵を切る方針を打ち出しました。これは、食料安全保障の観点からも大きな転換とされています。これまでの「作りすぎないように」という方針から、「もっと作ってほしい」へ──その方針転換は、多くの農家にとってまさに青天の霹靂でした。
たとえば、福島県天栄村の米農家・吉成邦市さんは、「今さら増産と言われても、機械も土地も人手も足りない」と憤ります。彼のように、農政の現場を知る農家ほど、この転換がいかに現実離れしているかを痛感しているのです。
現場の農家からは不安と戸惑いの声が噴出
農家の多くは高齢化が進んでおり、個人経営の米農家の平均年齢はすでに70歳を超えています。
新たな設備投資や作付面積の拡大は、もはや夢物語のような話。特に小規模農家にとって、トラクターや田植え機、コンバインなどの農機具を買い換える余力はなく、「農機が壊れたら引退」という現実が待っています。
さらに、農地の確保や水の管理といった、表には見えにくい課題も山積しています。
全国の耕地面積の4割を占める中山間地域では、水争いすら起きるほど水資源の管理が難しいのが実情です。
政府の「増産せよ」という掛け声の裏側には、現場を知らないままの理想論が横たわっており、当事者の不安と現実とのギャップは深まるばかりです。
こうした現状を踏まえ、政府もただの「号令」ではなく、さまざまな支援策を打ち出しています。
たとえば、米農家向けには「収入保険制度」や「水田活用の直接支払交付金」などがあり、減収リスクや転作収入の不足を一定程度補う仕組みが整備されています。また、2025年度からは中小農家への所得補償を強化する方向で制度見直しが進んでいます。
さらに、スマート農業の導入支援や機械リース制度の拡充など、大規模経営でなくとも生産性を高められる環境整備も図られています。ただし、これらの制度が実際に現場で機能するかどうか、そしてどこまで小規模農家が恩恵を受けられるかは、今後の運用次第です。
1.なぜいま「米の増産」なのか

食料安全保障と政府の狙い
近年、世界的に異常気象や紛争が続く中、日本でも「食料安全保障」という言葉が注目を集めています。
特にロシアによるウクライナ侵攻以降、小麦やトウモロコシといった輸入穀物の価格が高騰し、「国産の食料をもっと確保すべきではないか」という議論が強まってきました。
こうした背景を受けて、政府は2024年4月、「食料・農業・農村基本計画」を新たに策定。コメの生産量を2030年までに増やす方針を打ち出しました。
減反政策によって一度は「作りすぎない」方向へと進んできた日本の農政が、50年ぶりに「もっと作る」方向に舵を切ったのです。
石破茂首相は「米は日本の主食であり、安定供給こそが国の柱」と強調。米を例外扱いする時代は終わり、戦略物資としてのコメを再評価する動きが広がっています。
令和のコメ不足はなぜ起きたのか
ここ数年、スーパーやコンビニでは「新米の品切れ」や「価格上昇」といった現象が見られるようになりました。
背景には、気候変動による不作や、食の多様化による需要の変化、そして高齢化による農家の減少が重なっています。
実際、2023年のコメの生産量は791万トンと、需要と比べてもギリギリのラインでした。
一方で、外食や中食(テイクアウトなど)での米需要が予想以上に回復し、流通業界では「思ったより米が足りない」という事態が起きたのです。
特に業務用米の在庫不足は深刻で、飲食店からの「米が仕入れられない」という声も多く上がりました。
この“コメ不足”の状況が、政府をして増産への政策転換を決断させた直接のきっかけになったのです。
増産方針の背景にある政策転換
増産方針の裏には、「儲かる農業」を掲げる国の新戦略があります。かつては生産調整によって価格を保ち、過剰な在庫を避けるという仕組みがとられてきましたが、今では「自立した農業経営」こそが目指される姿となりました。
つまり、国は補助金や制限で農家を守るのではなく、競争力を持った農業へとシフトさせようとしているのです。たとえば、農業法人化の推進や、スマート農業への補助、輸出向け高品質米の育成といった政策がその一例です。
ただし、こうした政策の恩恵を受けられるのは、ある程度の規模と資金力を持つ大規模農家や法人が中心です。一方で、地方で細々と続けてきた小規模農家には、その変化に乗り切る体力がありません。
「現場の声を聞かず、政策だけが先に走っている」。福島の吉成さんをはじめ、多くの農家が口をそろえてそう話すのも、無理はない現状なのです。
2.農家が直面する現実と限界
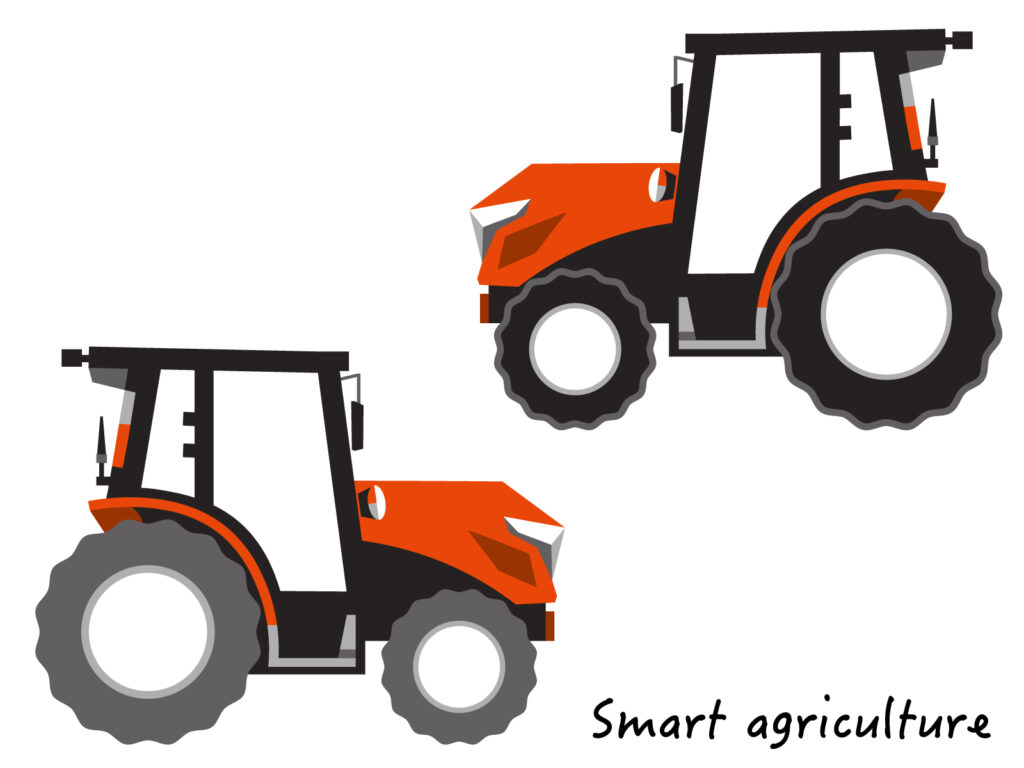
高齢化と設備投資のハードル
米を増やしたくても、そのために必要な体力と資金が、多くの農家には残されていません。
現在、米農家の平均年齢は70歳を超えており、定年後に農業に取り組んでいる人も少なくありません。増産のためには新たな農業機械の導入が不可欠ですが、トラクターや田植え機、コンバインをすべて揃えるには数千万円の投資が必要です。
福島県天栄村の吉成邦市さんは、退職後に2ヘクタールの米作りを始め、約3,000万円をかけて機械を一式そろえました。その減価償却費だけで年間300万円。年金生活に入る年代の農家にとって、これほどの設備投資は大きなリスクです。
「いまさら新しい機械なんて買えない。壊れたら終わり」。そう口をそろえる農家が多いのが現実です。
小規模農家の赤字経営と作付けの限界
さらに深刻なのが、米作りが儲からないという現実です。現在、全国の米農家のうち81%が2ヘクタール未満の小規模経営。
そうした農家では、60キロあたりの生産コストが約1万6千円にもなる一方で、2023年の売値は1万5千円程度と、そもそも赤字であることが多いのです。
吉成さんによれば、損益分岐点となる作付面積は3ヘクタール以上。それ以下では、農薬代や燃料代を差し引くとほとんど利益が残らず、自家消費分を確保して終わりというケースも珍しくありません。
アンケート調査でも、米農家の9割が「経営が苦しい」と答え、「廃業を考えるほど」という回答も1割以上にのぼりました。収入を得るために働くはずの農業が、むしろ生活を圧迫しているというのが今の日本の農村の姿です。
水田管理の過酷さと中山間地の実情
農業が大変なのは、資金や収支の問題だけではありません。たとえば、福島のような中山間地域では、水の確保すら一筋縄ではいきません。
関東平野では蛇口をひねれば水が出るような農業用水の設備が整っていますが、天栄村ではいまでも土のうを積んで水路の流れを変え、水を手作業で田んぼに引き込まなければなりません。
また、こうした地域では「我田引水」という言葉が生きていて、水をめぐるトラブルも少なくありません。吉成さんの話では、かつて水争いが原因で殺人事件まで起きたほどだといいます。
このように、全国の耕地面積の約4割を占める中山間地域では、物理的にも精神的にも大きな負担を抱えながら米が作られています。東京からは見えない山あいの田んぼで、毎年ぎりぎりのやりくりと努力によって、私たちの食卓が支えられているのです。
制度があっても“使えない”現実
政府は「増産を後押しする制度」として、過去には戸別所得補償制度を導入し、現在も多面的機能支払や収入保険といった支援策を打ち出しています。
しかし、実際に制度を“使いこなせる”農家は限られています。
たとえば、収入保険に加入するには正確な帳簿が必要で、スマート農業の導入には機械だけでなく、ITリテラシーも求められます。
「年金生活で、スマホの操作もままならない」と語る高齢農家にとって、最新の政策はまるで別世界の話。
農業法人化の推進なども掲げられていますが、小さな村の家族経営では法人化そのものが高いハードルとなります。
国の制度と、農村のリアルとの間には、いまだ大きなギャップが横たわっているのです。
3.後継者不足と新規就農の壁
若手が参入できない構造的問題
米作りの未来を語る上で避けて通れないのが、「担い手」の問題です。今、日本の米農家の多くが70代に突入し、現役を退く時期を迎えています。
しかし、その後を引き継ぐ若い世代が、圧倒的に足りていません。
若者が稲作に参入しない背景には、いくつかの構造的な壁があります。まず、米作りで生計を立てるには、まとまった面積の水田が必要です。
しかし、水田の多くは代々受け継がれてきたものであり、「知らない人」にはなかなか貸してもらえません。
また、米農家として生きていくには、高額な農業機械をそろえなければならず、新規参入者が初期投資をまかなうのは非常に困難です。結果として、「やりたいと思っても始められない」──それが、今の新規就農の現実なのです。
土地が借りられないという「目に見えない障壁」
土地の問題は、農業の新規参入者にとって最大のハードルです。表向きには「農地バンク」や「担い手マッチング」といった制度もありますが、実際には地域の信頼関係がなければ成り立たないのが現実です。
天栄村の吉成さんも、長年地域に根ざしてきたからこそ、他の農家がリタイアした際に水田を譲ってもらえました。いくらやる気があっても、土地を貸してくれる「信用」がなければ始まらない──この“目に見えない壁”が、多くの若手の参入を阻んでいるのです。
しかも、農地が遠くに分散していると、それだけで管理や移動のコストがかかり、経営が成り立たなくなるという現実もあります。
だからこそ、「やれる人」にだけ土地が集中してしまい、そこに若手が入り込む余地はほとんどありません。
団塊世代の引退で加速する農業人口の減少
2025年には、いわゆる団塊の世代がすべて75歳以上となり、農業人口の高齢化はいよいよ限界を迎えます。
これまで何とか米作りを支えてきた世代が一斉に引退すれば、日本の稲作の基盤そのものが崩れかねません。
吉成さんの住む天栄村では、20年前に600軒ほどあった米農家が、いまでは350軒にまで減少。
そのうち、稲作で生計を立てている「主業農家」はわずか10軒。その中で後継者がいる農家は、たったの3、4軒だといいます。
「米作りをやめたら、田んぼは草むらになり、村の景色が変わってしまう」と吉成さんは語ります。
農業はただの生産活動ではなく、地域の暮らしや風景を支える営みです。その担い手がいなくなるということは、食だけでなく、地域の未来そのものが揺らぐということなのです。
4.政策と制度の課題
所得補償制度の限界と収入保険の実情
政府は米の増産を推進するにあたり、小規模農家への支援策として「水田活用の直接支払交付金」や「収入保険制度」を挙げています。
前者は主に飼料用米や麦・大豆などの作付けに対する支援であり、主食用米を対象とした所得補償は限定的です。
また、収入保険制度は過去の収入実績に基づいて補償される仕組みのため、安定的な収入のない新規就農者や赤字経営が続く小規模農家には実質的な恩恵が届きにくいという問題があります。
スマート農業と大規模経営への偏重
さらに注目されるのが、政府が推進するスマート農業の導入支援です。ICTやドローン、自動運転トラクターといった最新技術の導入には補助が出ますが、それらを扱える技術力と初期投資の資金が求められます。
結果として、これらの制度は一定の経営体力を持つ大規模農家や農業法人向けに偏りがちです。多くの中山間地域の小規模農家にとっては、「絵に描いた餅」となってしまうことも少なくありません。
制度設計の不整合と地方の現実
政府は農業支援にさまざまな制度を用意していますが、それぞれの制度が分断され、全体の整合性に欠けるという指摘もあります。
たとえば、新規就農者に対する資金支援制度と、農地の集積・集約を進める政策がかみ合っておらず、土地が借りられないという構造的問題は依然として残っています。
また、制度の申請や実施に時間がかかり、手続きが煩雑なことも、中小規模の農家にとっては大きな負担となっています。
現実性の乏しさと政策の再設計の必要性
こうした中で、「増産せよ」とだけ言われても、実際の現場では踏み出せない農家が多数存在します。
政策の現実性を担保するためには、所得補償の対象拡充や柔軟な収入保険制度の設計、そして小規模農家にも実行可能なスマート農業導入支援の仕組みが不可欠です。
また、地域の農業者が自発的に協力・連携できる環境を整える「地域農政」的アプローチも再評価されるべき時期に来ているのではないでしょうか。
まとめ
コメ不足を受けて、政府は50年ぶりに「減反」から「増産」へと農政の大転換を図りました。
だが、現場の実情は、掛け声だけではどうにもならないほど深刻です。米農家の高齢化は進み、設備投資も困難、小規模農家の大半は赤字経営。農地の確保や水管理といった地域特有の課題も山積しています。
そして、最大の問題は「次の世代」が育っていないこと。若者が新たに米作りを始めたくても、必要な農地は簡単に借りられず、信用と地域との関係が前提となります。
加えて、機械投資や遠方に散らばる水田の管理など、想像以上のコストと労力がのしかかります。
このままでは、団塊世代の引退とともに稲作そのものが成り立たなくなる地域が急増しかねません。
政府の「増産」政策が本当に実を結ぶためには、数字や目標だけでなく、現場の声に耳を傾け、小規模農家や新規就農者が持続的に稲作に関われるような支援と環境整備が不可欠です。
「水田は村の景色をつくっている」。吉成さんのこの言葉に、日本の農業が持つ社会的価値と、それを支える人びとの覚悟が込められています。
米の生産量をただ増やすだけではなく、その「どう作るか」「誰が作るか」こそが、今こそ問われているのです。
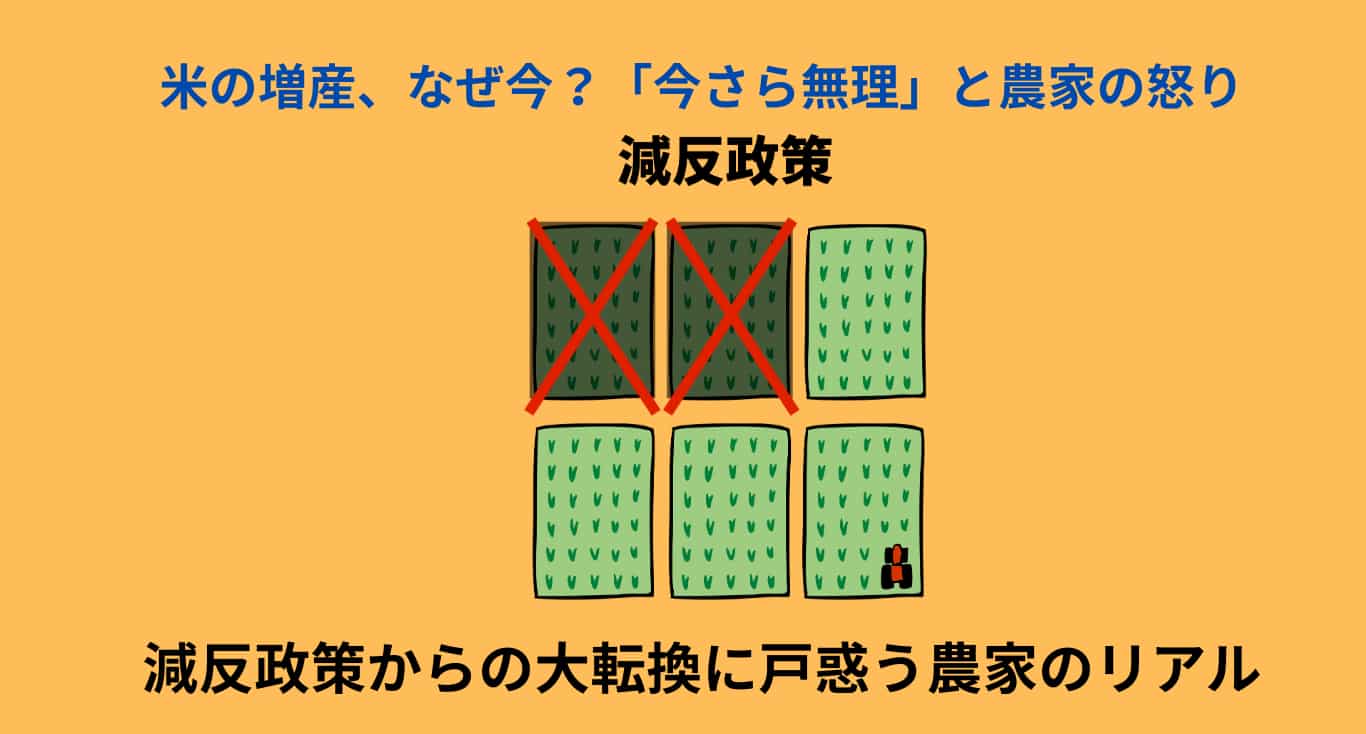
コメント