2026年度から始まる「私立高校授業料の実質無償化」。政府は「経済状況に関係なく、すべての子どもに進学の選択肢を」と理想を掲げています。
しかし、秋田県に住む田中広太さん(仮名・15)のように、制度の対象であってもなお「夢を諦める」高校生がいます。
通学費や生活費、そして地方ならではの交通の不便さ…。制度が整っても、その恩恵が届かない家庭は少なくありません。
この記事では、田中さんの体験をもとに、「私立無償化の理想と現実」「地方に残る教育格差の問題」について考えていきます。
はじめに
地方の生徒が抱える「進学の壁」
「やりたいことが見つかったのに、そこへ進む道が見えない」——そんな声を、地方に住む高校生から聞く機会が増えました。
秋田県の田中広太さん(仮名・15)もそのひとりです。
中学時代、憧れの陸上選手と出会い、彼と同じ私立高校へ進学したいと強く思うようになりました。
しかし、田中さんの家庭は母親が一人で家計を支える状況。私立高校の授業料が無償になる制度があるにもかかわらず、それ以外の通学費や生活費の壁が立ちはだかり、夢を追う道を断念せざるを得ませんでした。
このように、制度の「無償化」という言葉だけでは覆いきれない経済的・地理的な課題が、地方の生徒たちの進路選択を大きく制限しています。
都市部であれば通学の利便性や支援制度の恩恵を受けやすい一方で、地方では通学距離の長さや交通手段の少なさがネックとなり、同じ制度のもとでもまったく異なる現実が広がっています。
私立無償化の理想と現実

政府は「どんな家庭の子でも、希望する進路をあきらめずに済むように」という理想を掲げ、2026年度から私立高校の授業料を実質無償化する方針を打ち出しました。
制度の改正により、年収制限が撤廃され、多くの家庭が対象になることが期待されています。
しかし、実際には支援の恩恵は首都圏に偏っており、教育格差がさらに広がるのではないかという懸念も強まっています。
たとえば、文部科学省の試算によると、追加予算の約4割が東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3県に集中するとのこと。私立高校が都市部に多く立地している構造自体が格差の一因であり、制度の設計そのものが「地方の声」を置き去りにしている可能性があります。
無償化の理想は否定すべきではありません。しかし、現場で何が起きているのかを見つめ直すことは必要です。田中さんのような地方の生徒たちが、自分の夢を「経済事情」で諦めなければならない社会のままで、本当にいいのでしょうか。
1.田中広太さんの選択と葛藤
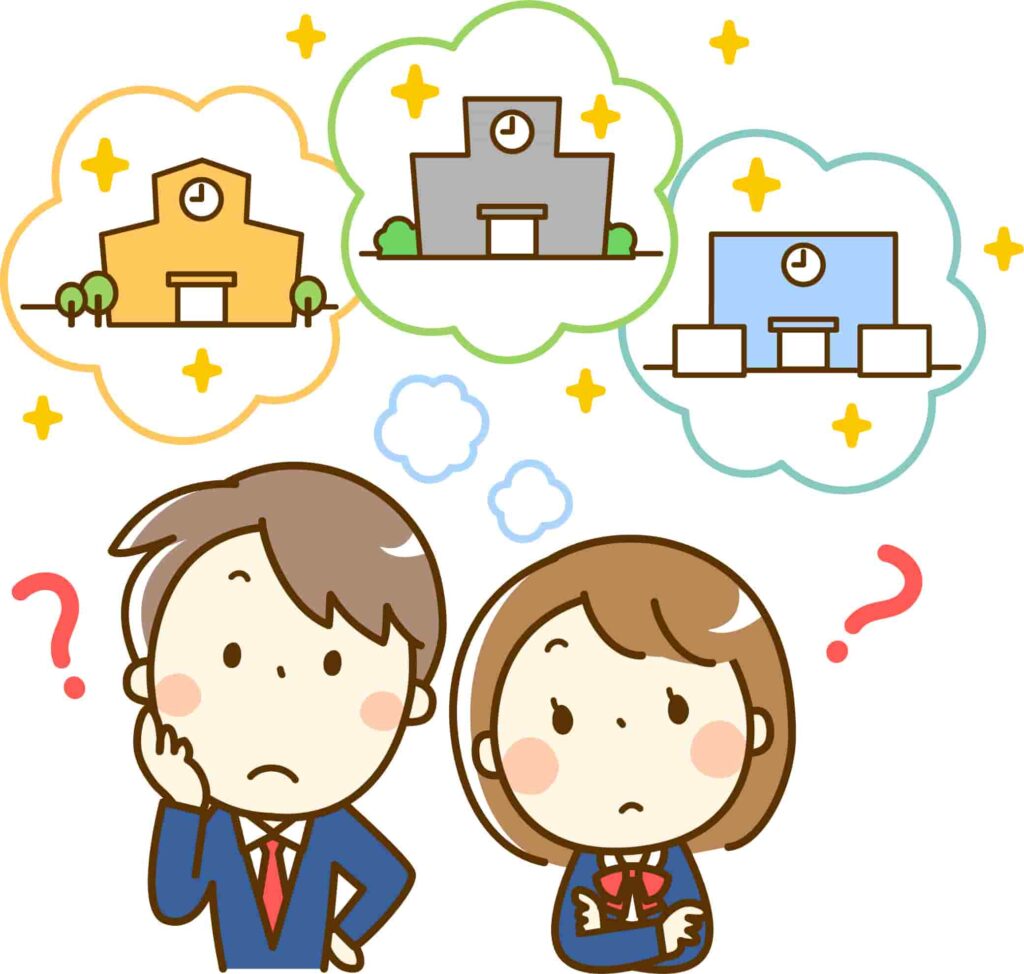
憧れの選手を追って私立高を志望
中学2年の夏、田中広太さんはある陸上合宿で、3歳年上の先輩選手に出会いました。
その選手は秋田市内の私立高校に通う短距離選手で、東北大会や全国大会の常連。ハードルを跳ぶフォームは驚くほど滑らかで、田中さんの目には「別世界の存在」と映ったといいます。
「自分も、あの人みたいになりたい」——その想いから、田中さんはその私立高校への進学を志すようになりました。大会の成績をチェックし、フォームや走り方をまねるうちに、髪型までそっくりになっていったといいます。
冬場の厳しい雪に閉ざされた地元から、母の車で1時間以上かけて体育館へ通う日々も苦ではありませんでした。それほどまでに、彼の心は夢中だったのです。
経済的負担と生活の現実
しかし、私立高校への進学には大きな壁が立ちはだかりました。母ひとりで家計を支える田中家は、祖父母・弟を含めた5人暮らし。
生活費を切り詰める日々で、食材は「半額セール」を狙ってまとめ買い、入浴時間も短縮するなど、日々の節約が当たり前のようになっていました。
制度上、田中さんの家庭は授業料の実質無償化対象にあたるとされていました。しかし、実際には「施設費」「教材費」「交通費」など、授業料以外の出費が多くのしかかります。
自宅から高校までの通学には片道1時間半以上、早朝の部活動に対応するには始発の電車に乗らなければならず、場合によっては下宿やアパートも検討しなければならない。母は「授業料がゼロでも、通わせるのは現実的じゃない」と苦渋の表情を浮かべました。
さらに、その高校が進学や就職に強いという評判がなかったことも、不安の一因でした。「夢を追うことと、将来を考えること」——この二つのあいだで揺れ動く母と息子のあいだには、いつしか言葉にできない温度差が生まれていました。
地元公立高への進学という決断
最終的に、田中さんが選んだのは地元の公立高校。中学3年の秋、彼は母に「公立に行く」と自分から切り出しました。強がるように「こっちの方が安心だから」と笑ってみせたものの、本心では「夢をあきらめた」と感じた瞬間でもありました。
進学後も陸上を続けていますが、心のどこかで「あの私立に行けていたら、何かが変わっていたかもしれない」と思うことがあるといいます。
夢を諦めたのではなく、現実に折り合いをつけただけ。そんな田中さんの選択には、多くの地方の高校生たちが重ねる想いがあるのではないでしょうか。
2.制度と数字が語る地域格差

私立無償化の恩恵が集中する都市部
私立高校の授業料無償化は、「すべての子どもに進学の機会を」という理念のもとに始まりました。
しかし、その恩恵は全国に均等に届いているのでしょうか。
文部科学省が試算したデータによれば、2026年度から始まる制度による追加経費約3938億円のうち、35.7%にあたる約1405億円が東京・神奈川・埼玉・千葉の1都3県に集中するとされています。
この数字は何を意味するのでしょうか。1都3県に住む高校生の割合は全国の約25.9%。
つまり、生徒の分布に比して、無償化の予算が都市部に偏って配分されている現実が浮かび上がります。
これは、私立高校自体が都市部に多く集中しているという構造的な背景があり、進学率も高いため、どうしても首都圏に予算が集中してしまう仕組みになっているのです。
制度の設計上やむを得ないとはいえ、「税金を払っているのは地方も同じなのに、なぜ都市部ばかりが得をするのか」と感じる地方在住の保護者や生徒は少なくありません。
田中さんの母も、テレビのニュースで制度拡充を知ったとき「結局、金持ちは金持ちになり続けるだけ」とため息をついていました。
地方への恩恵の薄さと制度の限界
授業料そのものは無償になっても、それ以外の費用、たとえば施設使用料や通学交通費、部活動費などは支援の対象外です。
とくに地方では、私立高校への通学が物理的に困難であるケースも多く、電車やバスが1時間に1本、あるいは乗り継ぎが必要で早朝や夜間の移動が難しいといった事情が現実としてあります。
加えて、学校数そのものが少なく、希望する部活動や専門コースがある私立高が近隣に存在しないという問題もあります。
そうなると、通学に時間がかかるうえに下宿やアパート暮らしを強いられ、家計への負担は跳ね上がります。
制度上「授業料は無償です」と言われても、それだけでは夢を実現できないという壁が、地方の家庭には確実に存在しているのです。
支援の公平性を問う声
こうした不公平感を訴える声は、当事者である高校生からも上がり始めています。
長野県の公立高校に通う森栗之介さんは、仲間たちとともに「一律の私立無償化ではなく、まずは公教育の底上げを」と署名活動を行い、文部科学省へ3万6000筆を超える署名を提出しました。
森さんは「制度がこのまま進めば、地方の生徒は静かに消されていく。自分たちの未来の選択肢が、経済格差や地域格差で狭められていることに気づいてほしい」と訴えます。
支援制度の本来の目的は、すべての子どもが平等に教育を受けられる環境を整えることのはずです。その理想に近づくためには、支援を「都市型」に偏らせず、地方の実情に即した制度設計への見直しが求められています。
3.公教育の現場からの叫び
教員の多忙と教育環境の老朽化
地方の公立高校では、教員の負担が限界に達している現実があります。たとえば、長野県の屋代高校に通う森栗之介さんが目の当たりにしたのは、「明日で27連勤」とつぶやく教員の姿。
学級担任を務めながら、複数の部活動の顧問として週末も休みなく大会に帯同するなど、まさに“休む間もない”状態が続いていました。
こうした教員の過労は、教育の質にも影響を及ぼします。森さんの中学時代の先生のひとりは「先生にはならない方がいい、なるなら覚悟してこいよ」と口にしていたそうです。
生徒が質問をしようにも、職員室に先生が不在なことも多く、相談しづらい空気が常に漂っていました。
また、設備面の老朽化も深刻です。たとえば、森さんの中学校では夏場、エアコンの使用をためらう声がありました。「電気代がかかるから、すぐ切って」と言われるのが日常だったといいます。
高校でも、Wi-Fiの電波が教室まで届かず、1人1台配布された端末に教材をダウンロードできない教室が存在するなど、「ICT教育」以前の問題を抱えているのが実情です。
トイレが和式しかない、暖房器具が古くて友人がやけどをした……。こうした細かな現実のひとつひとつが、「学ぶ環境」としての公教育の脆弱さを物語っています。
生徒たちが体感する「学びの格差」
制度の話を離れても、生徒たちは日々、肌で「格差」を感じています。田中さんが私立高を断念したのは授業料そのものの問題ではなく、そこに付随する“環境”の差でした。
強豪校の整った施設、経験豊富な指導者、遠征費や道具購入へのサポート体制。どれも、地方の公立校では到底手が届かないものでした。
また、公立校では人手不足ゆえに、部活動が成り立たなくなるケースも少なくありません。
指導者がいないために、練習が自主的なものに限られたり、大会への参加を諦めたりする部も出てきています。一方、私立では外部指導者の確保や設備投資が積極的に行われ、生徒たちの可能性を伸ばす環境が整っています。
「頑張っても、自分の力だけでは越えられない壁がある」——これは、田中さんだけの実感ではありません。地方の多くの生徒が、日常のなかで無意識に感じている“進路格差”の一端なのです。
一律無償化では解決しない課題とは
私立高校の一律無償化によって、制度上は「すべての生徒が平等に進学できるようになる」とうたわれています。しかし、現場からの声はそれに反します。
多くの生徒・保護者・教育関係者が口にするのは、「支援が制度だけで完結してしまっている」という違和感です。
授業料の無償化だけでは、通学や生活、学習の質に直結する要素まではカバーできません。
特に地方では、私立へのアクセスが難しいこと、そして何より公立の教育水準が支援の手薄さで置き去りにされていることが深刻です。
森さんが行った署名活動では、「一律無償化が進めば進むほど、地方の公立校が衰退する」という声が数多く寄せられました。
制度の理想と現実のギャップを埋めるためには、私立無償化だけでなく、地方の公教育に対する根本的な支援の強化が必要です。
「教育の公平」とは何か。単なる“お金の話”だけでは済まされない、地方の学びの現場の叫びが、今、制度に問いかけています。
まとめ
「私立無償化」が掲げる理想は、「どの子どもも学力と意思さえあれば、経済的な理由に関係なく希望する進路を選べる社会をつくること」です。
しかし、田中広太さんのように、制度の網目からこぼれ落ちてしまう生徒がいるのも事実です。
制度の対象となる授業料は無償化されても、地方に暮らす生徒たちは通学費、生活費、施設利用料など、見落とされがちな“見えない負担”に日々直面しています。
また、そもそも私立高校が地域に少ない、アクセスが悪い、情報が不足しているなど、制度を活用する以前の壁も多く存在しています。
公教育の現場では、教員不足と環境の老朽化という課題が深刻化し、子どもたちが本来持つ可能性を広げられない状況もあります。
一律の私立無償化が進めば進むほど、公立高校の存在意義が相対的に薄れ、地方の生徒たちにとっての「選択肢」が狭まっていくという声は、決して見過ごすべきではありません。
教育は、未来への投資です。そしてその未来とは、都市部だけでなく、地方に暮らすすべての子どもたちを含んだものです。
制度を支える私たち有権者一人ひとりが、誰のための、どんな教育制度を求めるのか。その問いを、今こそ真剣に考えるべき時ではないでしょうか。

コメント