2025年7月、参政党の神谷宗幣代表が「高齢女性は子どもが産めない」と街頭演説で語ったことで、大きな議論が巻き起こりました。SNSでは賛否が分かれ、「科学的事実だ」と擁護する声もある一方で、「言い方がひどい」「心が傷ついた」とする投稿も多く見られました。
確かに、高齢出産にはリスクが伴い、年齢による妊孕力の変化は医学的に証明されています。
でも近年では、有名人をはじめ多くの人が妊活についてオープンに語るようになり、男性側の生殖能力の低下にも注目が集まっています。
こうした現実がある中で、「若い女性=出産」というように短絡的に紐づけるような発言は、あまりに配慮を欠いているのではないでしょうか。
このブログでは、発言の内容と背景、それに対する社会の声を紹介しながら、「政治家の言葉のあり方」について、ひとりの有権者として考えてみたいと思います。
はじめに
発言が注目を集めた背景
2025年7月、参政党の神谷宗幣代表が街頭演説で語った「高齢女性は子どもが産めない」という発言が、SNSを中心に大きな議論を呼びました。
この言葉をめぐって、「科学的には事実だ」という声と、「発言の仕方に配慮が足りない」という反発が真っ二つに分かれ、関連ワードは「子供を産めない」「出産適齢期」なども含めて続々とトレンド入りしました。
きっかけとなったのは、参院選の公示日当日に都内で行われた神谷氏の演説。その内容が報道されるや否や、ネット上での反応は加速し、今なお波紋が広がり続けています。
社会的な文脈と感情的な波紋
この問題がここまで注目された背景には、少子化や女性の生き方をめぐる社会的な緊張感が横たわっています。現代では35歳を過ぎると「高齢出産」とされる一方、不妊治療やキャリア形成を経て妊娠・出産を目指す女性も多くいます。
また最近では、有名人たちも妊活を公表し、社会全体で出産や不妊に関する理解が進んできました。さらに、科学的には男性の生殖能力も加齢とともに低下するという研究もあります。
そんな中、「子どもが産めない」という一言が、ただの事実としてではなく、まるで「若い女性=出産」と決めつけるような響きを持って多くの人に届いてしまったのです。
俳優の毬谷友子さんが「怒りで震えている」と投稿したように、受け手側の心に強く響いたこの発言。政治家の言葉が社会に与える影響の大きさが、改めて問われることになりました。
1.神谷宗幣氏の発言内容とその意図
街頭演説での具体的な発言
問題の発言が飛び出したのは、参議院選挙の公示日である7月3日、東京都内で行われた神谷宗幣代表の街頭演説の場でした。
「子どもを産めるのも若い女性しかいない」「男性や、申し訳ないけど高齢の女性は子どもが産めない」といった発言がその中心です。
さらに神谷氏は、日本の少子化を憂慮する立場から「若い女性に子どもを産みたいと思ってもらえるような社会をつくるべきだ」と語り、「今の日本は『働け!働け!』とやりすぎてしまった」とも指摘しました。
このような発言は、出生率の低下に危機感を持つ層には一定の理解を得た一方で、言葉の選び方が不適切だとして多くの反発を呼びました。
「申し訳ないけど」という前置きや、「高齢女性は子どもが産めない」と名指しする表現が、個人の尊厳を軽視していると受け取られたのです。
「現実を語っただけ」とする主張
神谷氏は、自身の発言について「科学的事実を述べただけ」「感情ではなく、現実を見てほしい」と主張しています。
確かに、医学的には妊娠・出産には年齢的な限界があることは広く知られています。35歳を超えると妊娠の確率は下がり、40歳を過ぎるとさらに難しくなるというデータもあります。ですが、それは「だから若い女性に子どもを産ませよう」と短絡的に繋げるべき話なのでしょうか?
実際には、年齢によらずさまざまな事情で妊娠に悩む人がいます。不妊治療を続ける方、パートナーとの関係、経済的な不安など、背景は人によって違います。
事実をもとに語るのであればこそ、なおさら言葉の選び方と伝え方には丁寧さが必要だと私は思います。
「若い女性に子どもを」との提案の背景
神谷氏の発言には、人口減少という社会課題への対策として、「出産可能年齢の女性にもっと子どもを産んでほしい」という意図がありました。
その背景には、出生数の減少、少子高齢化、労働人口の縮小といった複雑な問題が横たわっています。
とはいえ、「子どもを産むのは若い女性の責任」というような響きがあったことも否めません。
女性のキャリア、結婚観、経済的な事情など、出産にはさまざまな要因が絡んでいます。
「若い女性が産めばいい」という単純な言い方では、かえってプレッシャーを与えてしまうこともあるのです。出産や育児の支援環境の整備、パートナーとの協働、安心して妊娠・出産ができる社会制度づくりなど、もっと包括的な視点が必要とされていることを、今回の件は浮き彫りにしています。
2.ネット上の反応──賛否両論
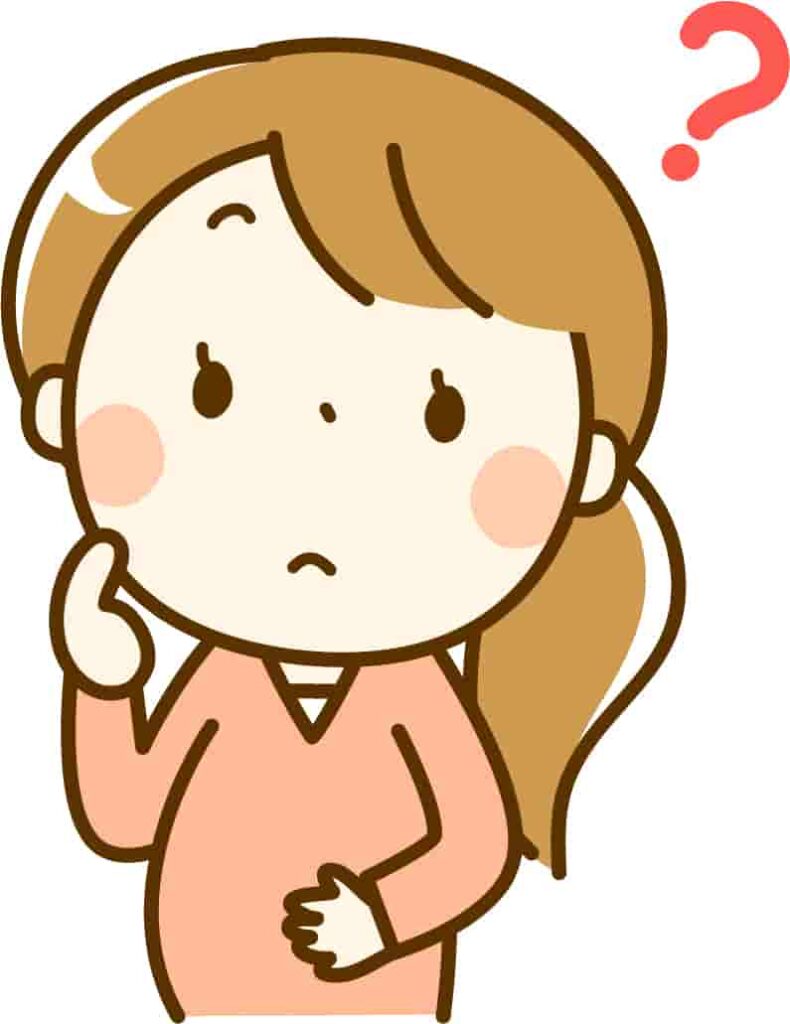
科学的事実として肯定する声
神谷氏の発言に対して、「それは科学的に正しい」「事実を言っただけで批判されるのはおかしい」といった肯定的な意見も少なくありませんでした。
X(旧Twitter)では、「高齢女性が子どもを産めないのは誰もが知ってること」「1ミリも間違ってない事実でしょ?」というような投稿が多く見られました。
彼らにとっては、社会課題を直視するうえで、政治家が“耳の痛い現実”を語るのはむしろ当然だという受け止め方です。
また、少子化対策の議論を進めるためには、避けて通れないテーマであるとの認識もあり、「タブーにせず議論することが必要だ」「感情で封じることの方が問題」という声も上がりました。
発言の是非よりも、その背後にある現実と向き合おうという姿勢が見られます。
傷ついたと感じる当事者の声
一方で、言葉に傷ついたという声も非常に多くありました。
特に不妊治療の経験がある女性や、さまざまな事情で出産できなかった人たちからは、「また心の傷がえぐられたようだ」「出産できなかったことを責められている気がする」といった投稿が相次ぎました。
「高齢女性」という表現でひとくくりにされたことに対しても、「高齢って何歳から?」「35歳から高齢出産と言われるのに、それ以前に産めなかった人はどうすればいいの?」といった疑問や怒りが噴出しました。
年齢や体の状態に限らず、妊娠や出産にまつわる悩みは人それぞれであるという現実が、改めて浮き彫りになったのです。
言葉の選び方を問う中立的意見
また、極端な賛否に分かれる中で、発言そのものよりも「言葉の選び方」に注目する中立的な意見も目立ちました。
漫画家の倉田真由美さんは、「内容は正しいけど言い方でニュアンスが変わる」「『申し訳ないが』という表現は余計」と指摘しました。これは、事実であってもその伝え方次第で、相手を傷つけたり、誤解を生む可能性があるという視点です。
SNS上でも、「発言の内容を否定するつもりはないけど、あの言い方では傷つく人が出るのは当然」とする声が多く見られました。
「出産できない=劣っている」と受け取られかねない構造になってしまったことが、今回の炎上の大きな原因の一つだとする指摘もあります。
このように、神谷氏の発言をめぐる反応は、単なる“正しいか間違っているか”の二元論にとどまらず、人々がどれほど出産や人生にまつわるテーマに敏感で、多様な価値観を持っているかを浮き彫りにする結果となりました。
3.著名人や政治家の反応
八幡愛議員の立場とメッセージ
れいわ新選組の八幡愛衆院議員は、自身のX(旧Twitter)で神谷氏の発言に対する明確な懸念を表明しました。
彼女は「高齢者は子どもを産めないという当たり前のことを言って何が悪い」といった主張に対し、出産には年齢だけでなく、個々の事情があることを訴えました。
「出産において高齢とは35歳から。若くても授かれない人はたくさんいる。適齢期に焦ったり、諦めたり、辛い思いをしている人もいる」と投稿し、政治家の言葉が人に与える影響力の大きさに警鐘を鳴らしました。
彼女の投稿には、「共感した」「この視点がなかった」「ありがとう」という声が多く寄せられ、当事者の心に寄り添う姿勢が評価されました。
毬谷友子の怒りと共感の広がり
元宝塚歌劇団出身の俳優・毬谷友子さんは、「怒りで震えているんですけど」と短いながらも強い言葉で反応。
彼女の投稿は拡散され、同様の感情を抱いた多くの人の共感を呼びました。
特に、「なぜあのような言葉を公の場で使えるのか」「心が切り裂かれる思いだった」というコメントが続き、芸能界や表現者としての立場から、発言の“届き方”への鋭い指摘となりました。
このような感情的な反応が注目された背景には、毬谷さん自身が発信に慎重なタイプとして知られていたこともあります。そんな彼女が「震えるほど怒っている」と表明したことは、多くの人にとって「感情を代弁してくれた」と感じられたようです。
倉田真由美の冷静な言葉選び批判
一方、漫画家の倉田真由美さんは冷静に言葉の選び方に注目しました。「内容は正しいけど言い方ひとつでニュアンスは変わる」「『申し訳ないが』という言葉が余計だった」と、事実を伝えるうえでの表現の工夫についてコメント。
彼女の意見は、発言の是非を決めつけるものではなく、コミュニケーションとしての配慮を重視する立場からの発言でした。
このように、炎上する要素は“内容”よりも“伝え方”に起因することが多いという現代的な視点が、多くのユーザーの納得を得ています。
倉田さんの発言は、過剰な反応にも冷静な視点を促すバランス感覚を提供し、議論が感情論だけに流れないようにする貴重な意見として注目されました。
まとめ
神谷宗幣氏の「高齢女性は子どもが産めない」という発言は、事実に基づいているとされながらも、社会に大きな波紋を広げました。
科学的に正しいからといって、誰もが同じように受け止めるわけではありません。このテーマには、年齢、性別、過去の経験、妊娠・出産への想いといった、個々に異なる事情が複雑に絡み合っています。
ネット上では賛否が真っ二つに分かれ、感情的な批判もあれば、冷静な言葉選びを求める声も目立ちました。
八幡愛議員のように「政治家の言葉の重み」を意識する人もいれば、毬谷友子さんのように直感的な怒りを共有する声も多くありました。そして、倉田真由美さんのように“正しさ”より“伝え方”に注目する冷静な視点も、今回の議論をより深いものにしています。
この出来事は、少子化や出産適齢期といった社会課題を考えるうえで、単に「誰が正しいか」ではなく、「どう語るか」がどれほど重要かを示しています
。今後、政治家や社会的な影響力を持つ人が言葉を発するとき、事実の背景にある人々の思いにまで心を配る必要があるということを、改めて私たちに教えてくれた出来事だったのではないでしょうか。
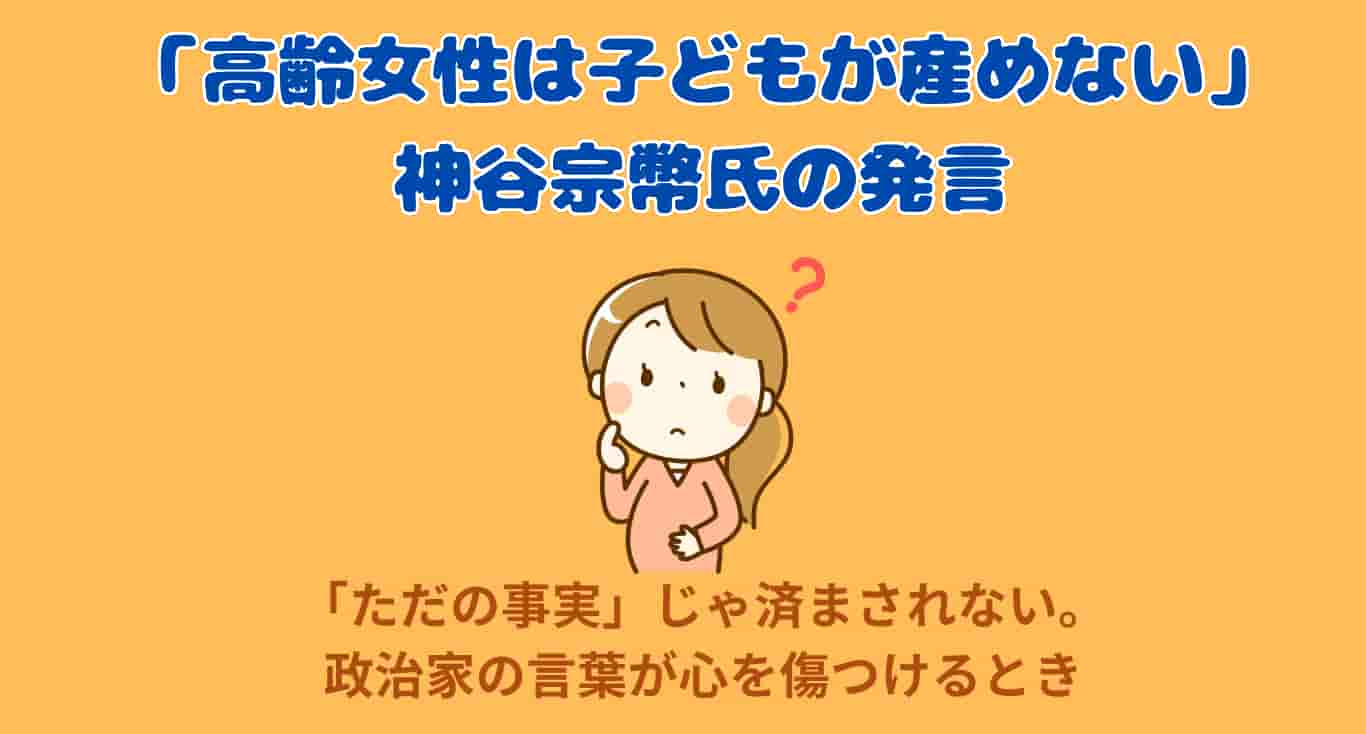
コメント