バラエティ番組って、ただ笑って楽しむもの…そう思っていた私たち。
でも、2025年6月30日放送の『しゃべくり007』では、お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘さんが娘さんの目の前でビンタされる演出が放送され、「これは笑えない」「子どもがかわいそう」とSNSで議論が巻き起こりました。
芸人さんは“笑い”のプロとして演出を受け入れているけれど、それを見た視聴者がどう受け取るかはまた別の話。
なぜ今、私たちはバラエティをこんなにも真剣に見てしまうのでしょうか?
視聴者の共感、SNSの影響、そして“見る側”としての責任について感じたことを綴ります。
はじめに
SNSで物議を醸した『しゃべくり007』6月30日放送回
2024年6月30日に放送されたバラエティ番組『しゃべくり007』では、お笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘さんが愛娘と共演し、話題を集めました。
番組の中で、尾形さんが娘の前でくりぃむしちゅー・上田晋也さんからビンタを受けるという演出がありましたが、それを見た一部の視聴者からは「笑えない」「子どもの前でやることではないのでは?」といった声が上がり、SNS上で議論が巻き起こりました。
娘の前でビンタ、視聴者の「真剣」な反応とは
尾形さん本人はその後、X(旧Twitter)で「バラエティーは真剣に見ないでください」「バラエティーは娯楽です」と投稿し、笑いを提供する場としての番組の意図を強調しました。
けれども視聴者の中には、子どもの前で親が叩かれる姿に心を痛める人も多く、「見ていられなかった」「子どもの気持ちを考えると切なくなった」という意見も少なくありませんでした。
こうした反応は、ただの一過性の「炎上」とは異なり、視聴者の中にある“親子の関係性への共感”や“子どもに与える影響”といった真面目な問題意識が背景にあるように感じられます。
今やテレビはただの娯楽ではなく、多くの人が「現実とのつながり」を意識しながら視聴する時代。その変化が、バラエティに対しても“真剣に見る”という視点を生み出しているのかもしれません。
1.視聴者がバラエティを「真剣に見る」理由

子どもの心情への共感が増えている
かつてのテレビ番組では、子どもが親の出る番組を見ても「テレビだから」と割り切る空気がありました。
しかし現在、多くの視聴者が「子どもがどう感じるか」という視点を持つようになってきています。
今回の『しゃべくり007』での尾形さんのビンタ場面も、「娘の前で父親が叩かれるなんて、心に傷が残らないだろうか」といった声が多数あがりました。
これは、親子関係に対する視聴者の意識が高まり、家庭の中での「尊厳」や「信頼」を、バラエティの演出と結びつけて考える人が増えたことを示しています。
親が子どもに叱られる場面、逆に子どもが大人の事情で気まずい思いをするシーンなどが放送されると、その背景にある「感情」までも想像してしまう。
そういった共感力の強まりが、番組を単なる“お笑い”として見るのではなく、ひとつの「現実の延長線上」として捉える傾向を強めているのです。
コンプライアンス意識の高まりとその影響
近年、テレビ業界では「コンプライアンス」が強く意識されるようになりました。暴力的な演出やセクハラ的な表現はもちろん、誰かが不快に感じる可能性のある内容そのものが問題視されることが増えています。
こうした流れのなかで、視聴者も自然と“番組の倫理性”に敏感になってきているのです。
かつては「笑って済ませた」ような演出も、今では「これは問題では?」と立ち止まって考える視聴者が多数います。
とくに子どもが関わる場面では、「教育上よくない」「真似されると困る」といった意見がすぐに飛び交います。今回のビンタのシーンも、「笑いのためとはいえ、子どもがいる場で親を叩くのは適切か」という真剣な問いを呼び起こしました。
SNSによる感情共有が「真剣さ」を加速させる
SNSの存在も、視聴者がバラエティを「真剣に見る」きっかけのひとつとなっています。
番組を見ながらリアルタイムで感想を投稿したり、他人の投稿に共感したりするなかで、感情がどんどん増幅していく構造があります。
たとえば今回の放送直後にも、「娘の前で叩かれてるの見て、泣きそうになった」「私ならショックでトラウマになるかも」など、強い感情を含んだ投稿がX上に次々とあらわれました。
これらが共感されて拡散されることで、「やっぱりこれはおかしいのでは?」という意見が多数派に見えるようになり、結果的に“バラエティに対して真剣になる空気”を作り出していきます。
つまり、視聴者一人ひとりの感じたことがSNSという場で共有され、それが新たな“世論”として形を持ち始める。
その流れのなかで、娯楽番組であるはずのバラエティが、思いのほか真面目に、そして重たく受け止められるようになっているのです。
2.娯楽と倫理のはざまで揺れるバラエティ演出

「叩く」演出は笑いか、暴力か
テレビのバラエティ番組では、「叩く」「転ばせる」「水をかぶる」といった体を張ったリアクション芸が昔から使われてきました。
それを見て笑う文化は長く続いてきたものの、時代が変わり、そこに疑問を持つ人も増えてきました。
たとえば今回の『しゃべくり007』では、尾形さんが娘の前でビンタされるという場面がありました。
これに対してSNSでは「笑えなかった」「暴力を正当化しているように見えた」といった声も見られ、賛否が分かれました。
一方で、「演出だと分かっている」「本人が納得してるのだから問題ない」という声もあり、視点によって印象は大きく異なります。
問題は、その“叩く”行為が本当に笑えるものとして成立しているのか、それとも単に「暴力的な場面」として捉えられてしまっているのか。
視聴者がどう受け取るかによって、同じ演出でもまったく別の意味を持ってしまうのが、今のテレビの難しさでもあります。
模倣によるいじめの懸念と放送倫理
「叩くのは演出」と大人は分かっていても、子どもはそうとは限りません。
テレビで繰り返し流れる“暴力的”な演出を真似して、学校で同じことをしてしまう──そんな事例は過去にもいくつか報道されています。
NHK放送文化研究所の指摘にもあるように、「模倣していじめに発展する危険性」も無視できない問題です。
たとえば、「笑いのためなら相手を叩いてもいい」という価値観が無意識に刷り込まれてしまえば、それは教育上も社会的にも大きな影響を及ぼす可能性があります。
今回のケースでは、尾形さんが父親として出演していたという点がより問題を複雑にしています。
子どもにとっては、テレビの中とはいえ「自分のパパが叩かれた」という体験になるわけで、それが笑いになるのか、トラウマになるのかはとても繊細な問題です。
だからこそ、演出側も「子どもに見られること」を意識した倫理的な判断が求められる時代になってきています。
芸人の尊厳と子どもの目線から見た違和感
芸人が体を張って笑いを取るスタイルは、本人の意志や職業意識に基づくものであり、それ自体が悪いとは言えません。
しかし今回のように、芸人が親として出演している場合、そこにはもう一つの“視点”が生まれます。それは、「子どもが自分の親の姿をどう受け止めるか」という視点です。
ビンタを受けた尾形さんは、笑いのために体を張ったわけですが、それを見た娘さんが「これがパパの仕事なんだ」と素直に理解できる年齢なのかどうかは疑問が残ります。
ましてや、視聴者の中には「親が叩かれる姿なんて見たくなかった」「子どもが混乱するのでは」といった声も多く寄せられました。
つまり、バラエティの演出として成立していたものが、“親子の関係性”という軸で見たとき、違和感や疑問として浮かび上がってくる。
これは、従来の「芸人としての姿」だけではなく、「一人の親としての姿」も同時に求められる時代に入ったということなのかもしれません。
3.「バラエティを真剣に見るな」という呼びかけの真意

尾形貴弘のX投稿に込められた意図
放送後にSNSで話題になったのは、番組内容だけでなく、出演した尾形貴弘さん自身のX(旧Twitter)での投稿でした。
「バラエティーは真剣に見ないでください」「バラエティーは娯楽です」と、率直な言葉で視聴者に呼びかけたのです。この言葉には、芸人としての苦悩と、テレビの本質を守りたいという思いがにじんでいました。
尾形さんのように、笑いのために体を張る芸人たちは、「やらせ」や「仕込み」などの批判を受けつつも、視聴者を楽しませたい一心で仕事に臨んでいます。
そうした中で、自分の演出が「虐待的だ」「子どもの心に悪影響だ」と真剣に非難されてしまうのは、本意ではないのでしょう。
尾形さんの投稿は、演者としての立場から「娯楽には娯楽としての受け止め方がある」という“視点の切り替え”を求めたものだったのだと思います。
娯楽に求められる「軽さ」と視聴者の責任
テレビが娯楽である以上、視聴者には“笑って楽しむ”という前提も必要です。
もちろん、内容に対して疑問を持つのは悪いことではありませんが、行き過ぎた批判や感情的な反応が続くと、制作者や演者が萎縮し、自由な表現ができなくなる恐れもあります。
たとえば、以前放送されたあるバラエティ番組では、芸人が泥の中に落ちるという昔ながらの演出が「汚い」「子どもが真似する」と炎上したことがありました。
視聴者の一部は「面白かった」と評価していたにも関わらず、SNSでの否定的な反応が目立ち、結果的に番組がその演出を控えるようになったという例もあります。
「笑い」にも多様性があり、それをどう捉えるかは人それぞれですが、テレビの世界に“軽さ”がなくなってしまえば、それはもうバラエティとは言えません。
視聴者自身も、どこまで真剣に向き合うべきか、バランスを取る責任があるのではないでしょうか。
「一歩引いて見る」ことのすすめと社会的意義
過去のアニメ『ちびまる子ちゃん』では、まる子が祖父におねだりするエピソードが放送された際、ある60代の視聴者が「年金暮らしの中で小遣いをねだられるのがつらかった」とフジテレビに意見を寄せたことがあります。
このように、たとえフィクションであっても視聴者の心を大きく揺さぶることがあるのです。
しかし、そうした感情が起こったときにこそ大事なのは、“一歩引いて見る”という姿勢です。
「これは番組の演出として成立しているのか」「現実とどう線を引くか」といった視点を持つことは、番組をより深く理解するためにも役立ちます。
視聴者がすべての場面に感情移入しすぎてしまうと、バラエティだけでなく、ドラマやアニメといった他のジャンルでも、自由な表現が難しくなってしまいます。
もちろん、視聴者の感性や意見は大切ですが、それが行きすぎないためにも「これはテレビ」という枠を意識し、ある程度の距離を保って受け止めることも、今の時代には必要な態度なのかもしれません。
4.「叩く笑い」は日本だけ?海外のリアクション
韓国では頭を叩く笑いはNG
今回の『しゃべくり007』を見ていてふと思ったのが、「このビンタの笑い、日本以外ではどう見えるんだろう?」ということです。実は、お隣・韓国では頭を叩く行為自体がとても失礼とされていて、バラエティでもNGとされることが多いそうです。
韓国は儒教の価値観が強く、「目上の人を叩くなんてとんでもない」という文化。そのため、笑いの中でもツッコミで“頭をパシッ”とやるような場面は、かなり控えられているんだとか。代わりに、言葉や表情でのユーモアが主流です。
日本では昔から「シバキ漫才」や「ツッコミ芸」が当たり前でしたが、これって実は海外ではあまり通用しないスタイルなのかもしれませんね…。
世界ではどう見られている?“叩く”ツッコミの賛否
欧米ではどうかというと、こちらもかなり否定的な意見が多いそうです。特にアメリカでは、「暴力的な演出」として放送コードに引っかかってしまうこともあるほど。たとえ演出であっても、「叩く=暴力」と受け取られてしまうんですね。
一方で、中国や台湾などアジア圏の若い世代には、日本のお笑いファンも一定数いて、「あれが日本流なんだ」と受け入れられることもあります。でもやはり、「真似しよう」とまではいかず、あくまで“日本独特のスタイル”として見られているのが現状です。
つまり、私たちが自然に笑っている“ビンタ芸”や“叩きツッコミ”は、世界的に見ると「えっ、それって大丈夫なの?」と心配される可能性が高いということです。
「日本の笑い」も見方を工夫する時代に
今や、笑いもグローバルな時代。だからこそ、視聴者である私たちも「この笑いはどこからきているのか?」を少し立ち止まって考えてみることが大事なのかもしれません。
たとえば今回の尾形さんのビンタも、日本では「定番ネタ」として受け入れられていても、文化が違えば大きな誤解を生む可能性があるということ。それに気づくだけでも、見方はぐっと変わってくる気がします。
テレビを見るときは、「これは日本の文脈で作られてる笑いなんだな」と一歩引いて見る視点を持つことで、違和感よりも「なるほど」が増えるかもしれません。
まとめ
『しゃべくり007』の一場面から始まった今回の議論は、単なるバラエティ番組の是非を超えて、テレビという娯楽のあり方や視聴者の向き合い方そのものにまで広がっていきました。
視聴者の感受性が高まり、コンプライアンスが求められる時代において、「叩く」「怒鳴る」といった古典的な笑いの演出も見直しの対象となっています。
しかしその一方で、演者たちは真剣に“娯楽”を届けようとしています。
尾形貴弘さんの「バラエティーは真剣に見ないでください」という言葉には、芸人としての誇りと、視聴者へのお願いの両方が込められていました。笑いは軽さや寛容さのなかに生まれるものです。
それを受け取る私たちも、「真剣に見すぎてしまうこと」が生み出す軋轢について、少し立ち止まって考えてみる必要があるのかもしれません。
バラエティに限らず、あらゆる表現に「正しさ」ばかりを求めすぎれば、やがて表現の自由そのものが失われてしまうかもしれません。
私たちにできることは、作品に込められた意図や文脈を想像し、必要以上に過敏になりすぎず、時には「一歩引いて見る」視点を持つこと。そうした成熟した見方こそが、テレビも視聴者もより豊かにしていくのではないでしょうか。
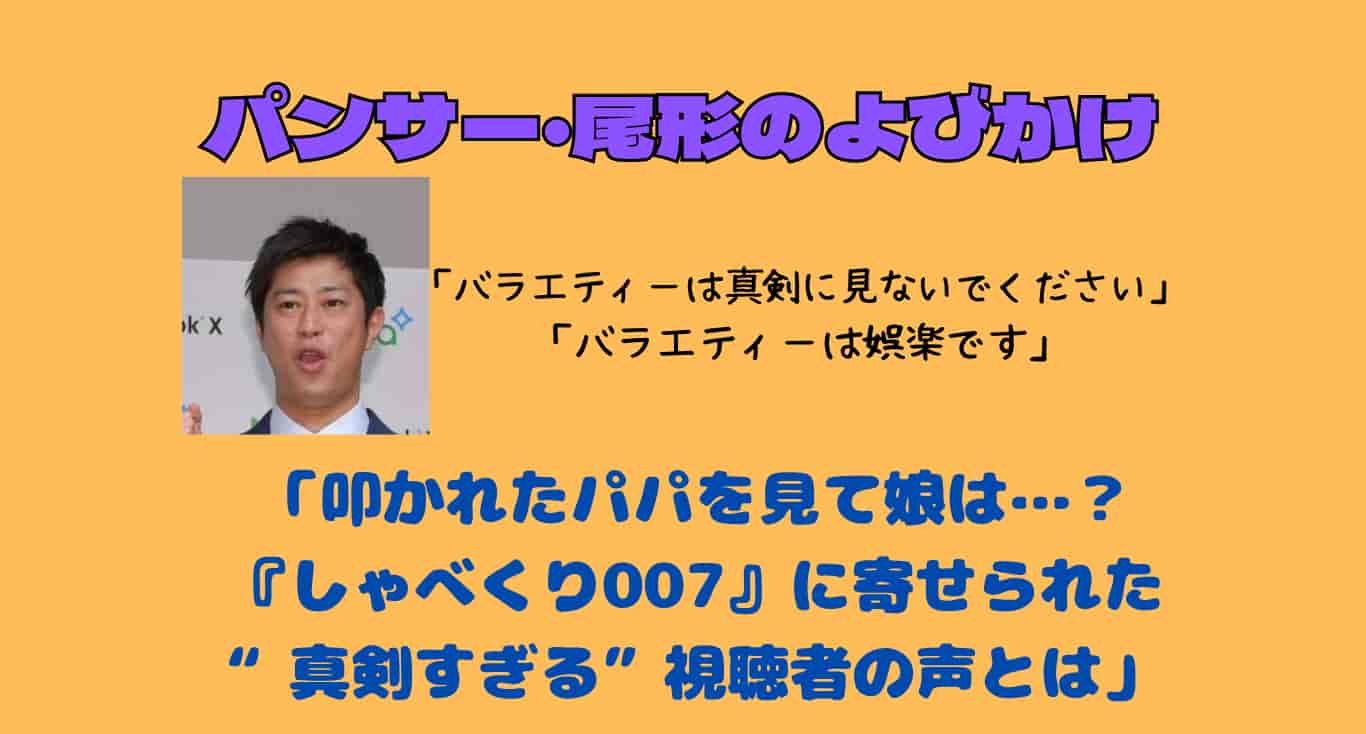
コメント