名古屋市で起きた小学校教員による女子児童の盗撮事件は、ただの“ニュース”として片付けられない深刻な問題をはらんでいます。
撮影された画像がSNSのグループチャットで共有されていたという事実は、「見ただけ」「送ってないから関係ない」といったこれまでの認識を覆すものです。
この記事では、一市民としてこの事件に強いショックを受けた私の視点から、「撮影罪」や「送信罪」といった新しい法律の内容、そしてグループチャット参加者にまで及ぶ可能性のある捜査について、できるだけわかりやすく整理しました。
子どもたちを守るために、今私たちにできることを一緒に考えてみませんか。
1.盗撮と共有行為に問われる罪とは

「撮影罪」とはどんな法律か
「撮影罪」は、2023年に新しく設けられた法律で、相手の同意なく性的な意味合いをもった姿態を撮影した場合に適用されます。従来の「迷惑防止条例」と違い、全国共通のルールとして明文化されたことで、より厳しい罰則が科されるようになりました。
たとえば、駅の階段でスカートの中をスマートフォンで盗撮した場合、以前は都道府県ごとに対応が異なり、罰金もまちまちでした。
しかし今では、こうした行為は「撮影罪」として処罰され、最長3年の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます。つまり、罪の重さがぐっと増したのです。
今回の事件でも、教員が女子児童の下着を撮影していたという事実が確認されれば、この「撮影罪」が適用されます。
しかも、被害者が未成年であり、加害者が教員という立場であることから、社会的な影響も無視できません。
撮影した画像の送信行為と「送信罪」の関係
さらに注目すべきは、「撮影した画像を他人に送る行為」もまた処罰の対象になる点です。この行為には「送信罪」という別の罪が適用されます。
たとえば、盗撮した画像をLINEやSNSのグループチャットで共有した場合、それ自体が送信罪に該当する可能性が高くなります。この送信罪は、最大で5年の拘禁刑または500万円以下の罰金という、撮影罪以上に重い罰則が設けられています。
今回の事件では、加害者が撮影した画像を複数の人物に送信していたとされ、まさにこの送信罪が問われることになります。悪質なケースでは、撮影と送信の両方に問われ、併せて処罰される「併科」という扱いも考えられます。
グループチャット参加者も捜査対象になり得る理由
では、グループチャットにいただけの人はどうなるのでしょうか。実は、ただ参加していたというだけでは罪に問われない可能性が高いとされています。ですが、警察の捜査対象になることは十分ありえます。
たとえば、送られてきた画像を保存していた場合や、コメントで加担していたような証拠があれば、その人物も事件に関与したと判断されることがあります。また、家宅捜索が行われ、スマートフォンの中身が調べられる可能性もあります。
今回のケースでは、10人ほどがグループチャットに参加していたと報じられていますが、その中には実際に画像を保存したり、拡散した人物が含まれているかもしれません。そうなれば、単なる「閲覧者」から「共犯者」へと立場が変わることになります。
つまり、「見ただけだから」「自分は送っていないから」と安心はできない時代になっているのです。
2.「撮影罪」施行から2年の変化
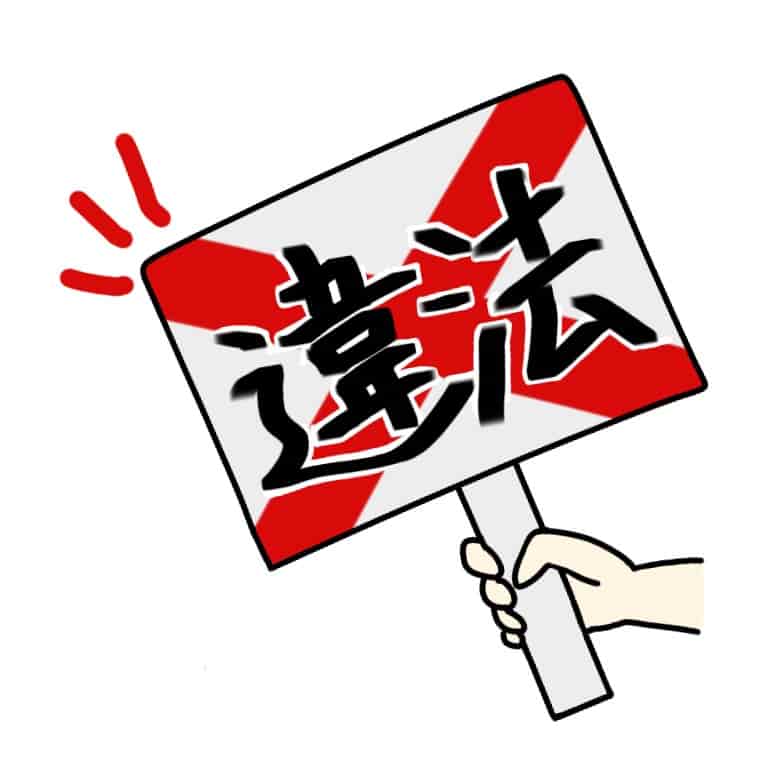
迷惑防止条例との違いと処罰の厳罰化
「撮影罪」が創設される前、盗撮行為は各都道府県の「迷惑防止条例」に基づいて処罰されていました。しかし条例によって罰則にばらつきがあり、「初犯なら数万円の罰金で済む」といったケースも多く、抑止力としては不十分でした。
それに対して、「撮影罪」は全国一律で、懲役刑を含む厳しい内容になっています。
罰金の上限額も条例の50万〜100万円に対し、撮影罪では最大300万円と3倍以上。さらに拘禁刑(いわゆる懲役)も最大3年と、条例の1〜2年より長くなっています。
今回のように、小学校教員が児童の下着を盗撮したようなケースでは、立場の悪質性も考慮され、より重い処罰が下される可能性が高いといえるでしょう。
初犯でも正式起訴されるケースが増加
以前の運用では、盗撮が初犯であれば略式起訴となり、罰金だけで済むことが多くありました。
ですが、最近ではスマートフォンに複数の盗撮画像が保存されているなど「余罪」が確認されるケースも増えており、初犯であっても「正式起訴=公判請求」されることが少なくありません。
実際、今回の事件でも教員のスマートフォンから他の被害児童の画像が見つかれば、単なる一件の盗撮では済まされず、複数の罪が積み上がる可能性もあります。
こうした場合、検察は略式ではなく、公の場で裁かれる正式裁判を選ぶ傾向にあるのです。
つまり、「初めてだから」「軽い気持ちでやった」では済まされないという状況が現実となっています。
法定刑の引き上げがもたらした影響
法定刑の引き上げは、裁判所の量刑判断にも影響を与えています。これまでの罰金額の相場は30万円程度でしたが、現在は50万円以上になることも珍しくありません。
たとえば、駅構内で女性を盗撮した男性が、初犯にもかかわらず60万円の罰金を科された例も報告されています。
また、罰金ではなく拘禁刑が選ばれるケースもあります。とくに、職業や立場によって社会的影響が大きい場合、たとえば教員や医師、公務員が犯した場合には、実刑判決が下されることもあるのです。
このように、「撮影罪」が施行されたことで、社会全体としても「盗撮は重罪である」という認識が広まりつつあります。それでもなお事件が続く現状は、さらに一歩踏み込んだ対策の必要性を示しています。
3.事件が示す社会的課題と今後の対策
教員による性犯罪と教育現場への信頼の喪失
教員が児童の下着を盗撮するという行為は、単なる犯罪行為にとどまらず、教育現場全体の信頼を大きく揺るがす出来事です。
保護者にとって、学校は子どもを安心して送り出せる「安全な場所」であるはずです。しかし、その内部で子どもが被害にあうという現実は、「誰を信じればいいのか」という深い不安を生みます。
とくに今回のように、加害者が普段から児童と接する立場にあったこと、そしてその信頼を利用して行為に及んでいた可能性があることは、道徳や教育の根本を揺るがす問題です。
教員の採用や研修のあり方、日常の監督体制、そして不審行動への早期対応の仕組みなど、教育委員会や学校単位での見直しが求められています。
SNS時代における「共有」の法的責任
今回の事件では、撮影された画像がSNSのグループチャットで共有されたことも大きな問題です。
画像を送った側が悪いのは当然ですが、「ただ受け取っただけ」「見ただけ」という人たちも、今や捜査対象になる時代です。
SNSは便利である反面、情報が一瞬で広まり、悪意ある画像や動画が半永久的にネット上に残ってしまいます。今回のような事件では、関与しているのが仲間内だけだったとしても、第三者に拡散されることで、被害者の名誉や心を深く傷つける二次被害が生じかねません。
たとえば、「笑い話」として画像を保存していた場合や、「これはひどいね」と言いながらも画像を友人に転送してしまった場合、それも送信罪にあたる可能性があります。
法的責任だけでなく、モラルや倫理の観点からも「見て見ぬふり」は通用しないという意識が必要です。
保護者・学校・社会が果たすべき役割
このような事件を防ぐためには、家庭・学校・社会それぞれが果たすべき役割を自覚し、連携することが不可欠です。
まず保護者は、子どもとの日常会話の中で、「学校で何か気になることはなかったか」など、小さな異変を見逃さないようにすることが大切です。
子どもが違和感や不安を感じていたとしても、それを言葉にするのは難しいことがあります。安心して話せる雰囲気をつくることが第一歩です。
学校側もまた、教員同士の相互監視や、外部の目が入る制度の整備が求められます。例えば、防犯カメラの活用や、匿名で通報できる仕組みなどが有効です。
また、教員向けの性教育や倫理研修も定期的に実施する必要があります。
そして社会全体として、性犯罪に対する認識を高め、加害者の立場に甘い目を向けるような風潮を改めていくべきです。
子どもたちを守るためには、ひとりひとりが「関係ない」と目をそらさず、社会全体で危機感を共有していくことが求められています。
まとめ
名古屋市の小学校教員による盗撮・画像共有事件は、「学校」という本来安心できるはずの場所で、信頼を裏切る行為が行われたという点で、多くの人に強い衝撃を与えました。
この事件を通して明らかになったのは、法律の整備だけでは犯罪を完全に防ぐことができないという現実と、SNSを介した画像の拡散が新たな加害の形になっているという事実です。
「撮影罪」や「送信罪」といった新しい法律ができたことで、盗撮やその拡散行為に対する罰則は強化されました。
しかし、社会全体がこの問題に真剣に向き合い、教育現場・家庭・インターネット利用者のそれぞれが自分の立場で行動を見直さなければ、同様の事件は繰り返されてしまうでしょう。
子どもたちが安心して学び、成長できる社会をつくるために――。この事件を他人事とせず、私たち一人ひとりが「今、自分にできることは何か」を考えるきっかけにしたいものです。
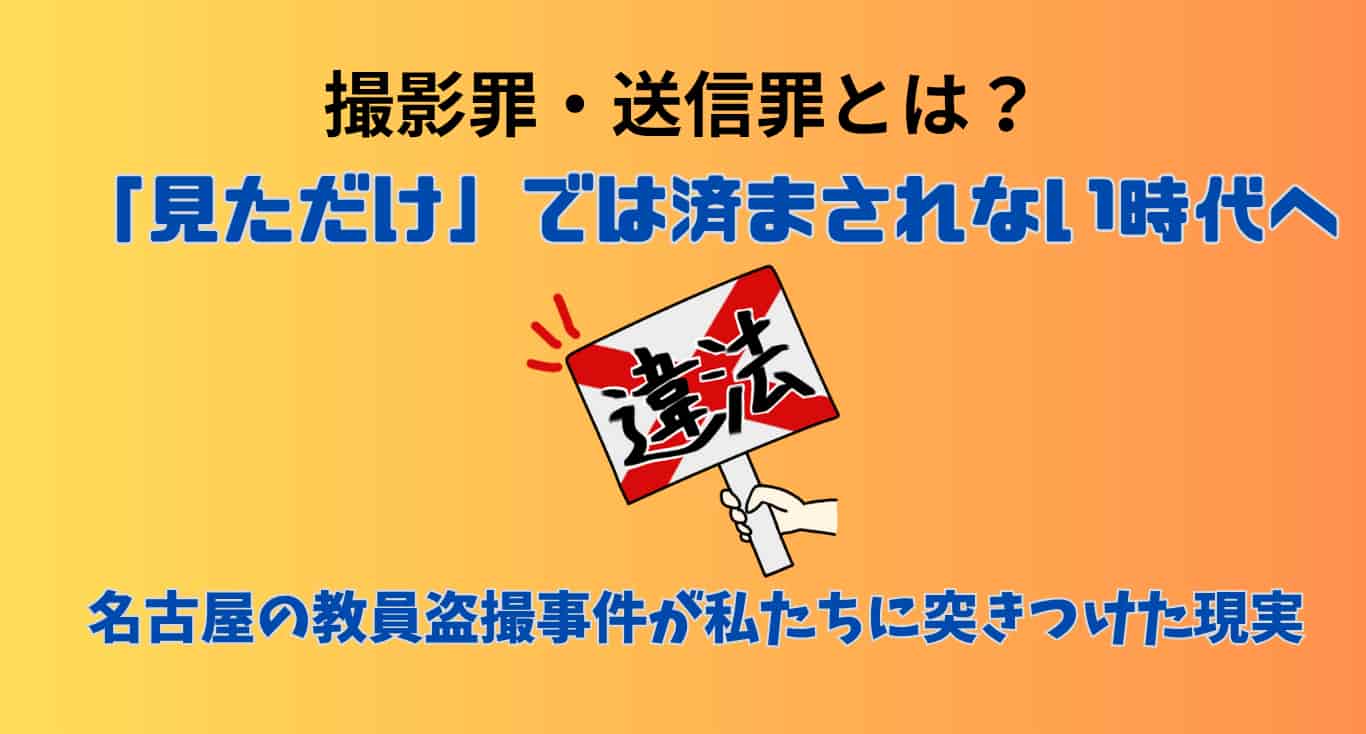
コメント