転売で一時話題になった“おじさんトレカ”──サイdo男カード。
けれどその根底にあるのは「まちの人を好きになる」仕組みでした。
本記事では、販売休止の背景・転売の実態・今後の再発行/アーカイブの可能性まで、地域PRの視点で整理します。
サイdo男カードとは?目的と効果
福岡県香春町・採銅所(さいどうしょ)地区で生まれた「サイdo男カード」は、地域のおじさんを“ヒーロー”に見立て、子どもとの交流を生むためのまちおこしトレカです。
3枚100円・6枚500円(キラ確定)という手に取りやすい価格で、地域イベントでの販売や配布を通じ、世代間交流・ボランティア参加のきっかけを作りました。
JUST IN!! 新着記事
— RKB毎日放送NEWS📺 (@rkbnews4ch) October 28, 2025
⠀ //
🗣”普通のおじさん”がトレカのキャラクターに 「サインください!」子供たちも熱狂、外国からも訪れる人気「サイdo男カード」を生んだのはコンビニない人口1700人の町 福岡
\\
もっと見る 👇👇
📰https://t.co/GjIUPVATSl… pic.twitter.com/ysKQcTeT0d
制作背景・目的・実施効果
制作背景
- サイdo男カード(「サイドメンカード」とも)は、福岡県香春町・採銅所地区にて、地域の“おじさん・中高年男性”をカード化したもので、地域のおじさんたちと子ども・若い世代の接点をつくる目的で企画されました。
- 制作者(採銅所地域コミュニティ協議会)の事務局長・宮原絵理さんは、「地域のおじさんたちには素晴らしいスキル・経験があるのに、子どもたちが知らないのはもったいない」「もっと身近なヒーローになってほしい」との思いから企画をスタート。
- 地域課題として、人口減少・高齢化・世代間交流の希薄化が指摘される中、子どもたちが地域の大人を「知らない人」ではなく「知ってる人」「ヒーロー」に感じられるようにする工夫としてカード化されたようです。
実施内容と効果
- カードの仕様:3枚100円/6枚500円(キラカード1枚確定)という価格設定。
- 収録カード数は当初20~30種程度、その後40種前後・47種まで増えたという報告もあります。
- 効果として、子どもたちの地域活動参加(掃除・ボランティア等)が増えたという声があります。たとえば、「カードのおじさんに会える」という理由で地域活動に参加する子が増えたという記事も。
- また、モデルとなった“おじさん”側も「子どもに会える」「カードになった」という実感から、地域活動に積極的になる方が出たというインタビューあり。
まとめ
この取り組みは「地域づくり×遊び」という構成で、一見ユニークですが実は社会課題と直結する設計。子ども・地域住民・地域活動者をつなぐ“遊びの器”として機能していました。
転売の実態と販売休止の背景
販売休止の趣旨
本来の目的(交流・学び)から外れ、収集・売買中心に注目が移ったため、一時的に販売を休止。
有効な転売対策が見出せない限り再開しない方針が共有されました。
メディア露出とSNS拡散で人気が急騰し、レア(キラ)単品が数千円で取引される例も。
ただし、この値動きは短期的な話題プレミアの色合いが強く、理念と市場の齟齬が顕在化しました。
色んな番組で取り上げられてたサイドメンカード、販売中止だって😱
— peri (@kaname_mochi) September 9, 2025
サイdo男カードは、福岡県 北九州市 香春町 採銅所地区の地域おこしとして始めたカードゲーム💳️
仕組みが面白くて、スキルを持つオジサン達も格好良かったのに、転売ヤーのせいで残念な流れだ。#NHK #てれふく #サイdo男カード https://t.co/UXzYQDcjoX
転売・相場の実態
- 人気が出るにつれ、メディア取材・SNS拡散が相次ぎ、県外・海外の問い合わせも出てきたとの報告。
- 特に「キラカード(レア仕様)」について、フリマサイト等で1枚4,000円近い値がついたという報道があります。
- また、カードそのものだけでなく、「新聞記事の切り抜き」などが転売サイトに出品されたという記述も。
販売休止に至る経緯
- 協議会側としては、転売によって本来の目的(子どもと地域のおじさんのつながり・遊びとしてのカード)が変質しつつあると判断。
- 2025年6月13日の役員会で「販売休止」を決定。再開は「有効な転売対策を見いだせない限り行わない」とコメントされています。
- 制作者たちは、「報道が“面白いカード”という側面ばかりを切り取って伝えてしまい、取り組みの本質(地域のつながり)に触れられないまま外部に広がってしまった」と振り返っています。
問題点・論点
- カードという“商品”として希少価値がつき、市場的に「転売可能な資産」化してしまった点。
- 地域限定・少量生産という仕様が、プレミアム化・投機対象化を誘発した可能性。
- 制作者/地域側のコントロールが難しい領域(インターネット・SNS・転売マーケット)で急拡大したため対応が追い付かなかった。
- 「遊び・地域コミュニティつながり」という目的と「収集・売買」という市場機能が相反する構造になってしまった。
補足:ユーザー・SNS上の反応
SNS上にも以下のような声が見られます:
“サイdo男カード どうしたら転売が起きないのか 大量に生産はできない 価格を変えるべきか 諦めるしかないのか 考えてもキリないけど 転売するくらいなら返して欲しい” X (formerly Twitter)
このように、地域側・ユーザー側双方で「転売化への懸念」が浮上していたのが実状です。
転売価格の目安(横スクロール表)
※あくまで報道・ネット上の記録をもとにした「目安」です。公式の取引記録ではありません。
| カード名/仕様 | 定価(販売時) | 確認された転売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常パック(3枚入り) | 100円 | — | イベント等で販売 |
| キラ確定パック(6枚入り) | 500円 | — | キラ1枚以上封入 |
| キラ単品(例) | — | 〜4,000円 台の出品例 | 一部フリマで高値化 |
ご当地トレカに資産価値はつく?──条件とリスク
- 短期的プレミア:SNS/報道で跳ねるが沈静化しやすい
- 長期的価値の条件:シリーズ継続、地域の物語性、適度な入手制限、コミュニティの定着、公式アーカイブ
- リスク:目的逸脱、炎上、供給過多、真贋・保存性の問題
価値が定着した事例 vs 消えた事例(横スクロール表)
| 分類 | 資産価値がつきやすい地域カード | 価値が消えた(定着しなかった)地域カード |
|---|---|---|
| ① 発行の継続性 | シリーズ化・年次更新あり(第○弾/限定版) | 単発イベントで終了 |
| ② 地域の物語性 | 人・産業・文化の背景が濃い(地域記録化) | デザイン先行で中身が薄い |
| ③ 希少性の質 | 地元限定/期間限定など“適度なハードル” | ネット販路拡大で供給過多 |
| ④ 市場形成 | ファンコミュニティ/交換文化が根付く | 一過性バズで終わる |
| ⑤ 制作者の理念 | 交流・学びを守る運営ポリシー | 目的が曖昧で炎上→価値下落 |
| ⑥ 外部評価 | 新聞・展示・学術評価=資料価値化 | SNS話題のみで埋没 |
サイdo男カードは復活する?──再発行・アーカイブ化の可能性
一時休止から再構築へ:理念の再定義がカギ
サイdo男カードは、2025年6月に販売休止となった際、運営側が明確に「目的と手段が乖離している」と発表しました。
しかしこの判断は、単なる中止ではなく「理念を守るための一時停止」でもあります。
地域協議会は、当初から「カードそのものを売るため」ではなく、「子どもと地域の大人をつなぐ遊び」として始めていました。
したがって、理念を再整理した上で再発行する余地は十分にあります。
再発行にあたって想定される方向性としては、以下のような案が考えられます。
| 再発行の方向性 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 地域内限定販売(販売先制限) | 町内イベント・学校・直販のみで配布 | 転売防止と地元参加の強化 |
| 地域体験型配布(スタンプラリー形式) | 採銅所を巡って集める方式 | 「人に会う」カード本来の価値を回復 |
| ストーリー連動版(第2弾) | 初期モデルのおじさん達の“その後”を描く | 地域記録・人間関係の継承 |
| オンライン展示/デジタルアーカイブ | 実物は配布停止、Webで記録化 | 転売対策と文化保存の両立 |
「ふるさと納税」や「アーカイブ活用」で文化資産へ
最近では、地域限定カードを「ふるさと納税返礼品」として再活用する例が増えています。
サイdo男カードも以下のような形で再評価される可能性があります。
- 🎁 ふるさと納税返礼品としての復活
→ 転売防止の仕組みを維持しつつ、限定数量で公式流通化。
→ “支援者だけが得られる地域アートカード”として再ブランディング可能。 - 🗂 郷土資料としてのアーカイブ化
→ 採銅所コミュニティセンターや香春町の公民館で「地域の記録」として展示。
→ 子どもたちに「この人たちが町を支えた」という学びを残す形。 - 🌐 オンラインアーカイブ+NFT連携(将来的試み)
→ 実物を発行せず、地域限定アクセスでカード情報を保管する形も考えられます。
→ 転売防止+文化保存のハイブリッド手段として注目されています。
自治体PR視点から見る再発行の意義
自治体にとって、こうした「まちのおじさんをヒーローにする」カードは、次のようなPR効果をもたらします。
| 効果の種類 | 内容 |
|---|---|
| ① 認知拡大効果 | “普通のおじさん”を取り上げたことで、地域の温かみが全国ニュース化 |
| ② 関係人口創出 | SNSで知った人が実際に採銅所を訪れる“トレカ観光”を誘発 |
| ③ 世代間交流の継続 | 子どもが「カードに登場したおじさん」に会いに行く行動変化が生まれた |
| ④ 自治体ブランディング | “人が主役のまちおこし”という独自ブランドとして定着の可能性 |
特に香春町は、銅の採掘文化・炭鉱遺産・里山コミュニティなど、地域固有の文化資源が豊富。
「人×文化×物語」の三層構造を守れば、単なるトレカから地域文化メディアへと進化することができます。
将来の展望:一過性の話題から“地域の記録資産”へ
再発行やアーカイブ化が進めば、サイdo男カードは単なる「プレミア商品」ではなく、「2020年代の日本の地域づくりを象徴する資料」として、後世に残る可能性があります。
- 🔹 短期:転売・流通問題の整理(2025〜2026)
- 🔹 中期:地域内再展開・教育連携(2026〜2028)
- 🔹 長期:全国的モデルケースとして研究・展示(2030年以降)
つまり、“売れた”カードから“語り継がれる”カードへ。
地域の人が主役である限り、サイdo男カードは次の形で生き続けるはずです。
転売で一時的に注目を集めたサイdo男カード。
けれど本当の価値は、“地元の人が自分の町を好きになるきっかけ”を作ったことだと思います。
もし次の世代に受け継がれる形で復活できたなら、それはもう「投機商品」ではなく、「地域の物語」そのものです。
結論:人と地域のつながりへ
サイdo男カードは「レア」ではなく「リアル」を映す取り組みでした。
転売で揺れた事実はあるものの、子どもが地域の大人を“知る”という価値は揺らぎません。
再発行やアーカイブ化が実現すれば、プレミア商品ではなく、日本の地域づくりを象徴する文化資産として語り継がれるはずです。
FAQ
Q. もう入手できないの?
一時休止のため新規販売は停止中。過去分の再配布や再発行は未定です。公式発表を待ちましょう。
Q. 資産価値は今後も上がる?
短期プレミアは変動が大きいです。長期的に残るには、シリーズ継続・アーカイブ・コミュニティ定着などの条件が重要です。
Q. 転売対策はある?
地域内限定/体験連動/ふるさと納税化/公式アーカイブなど、理念を守りつつ正規流通を限定する手法が有効です。
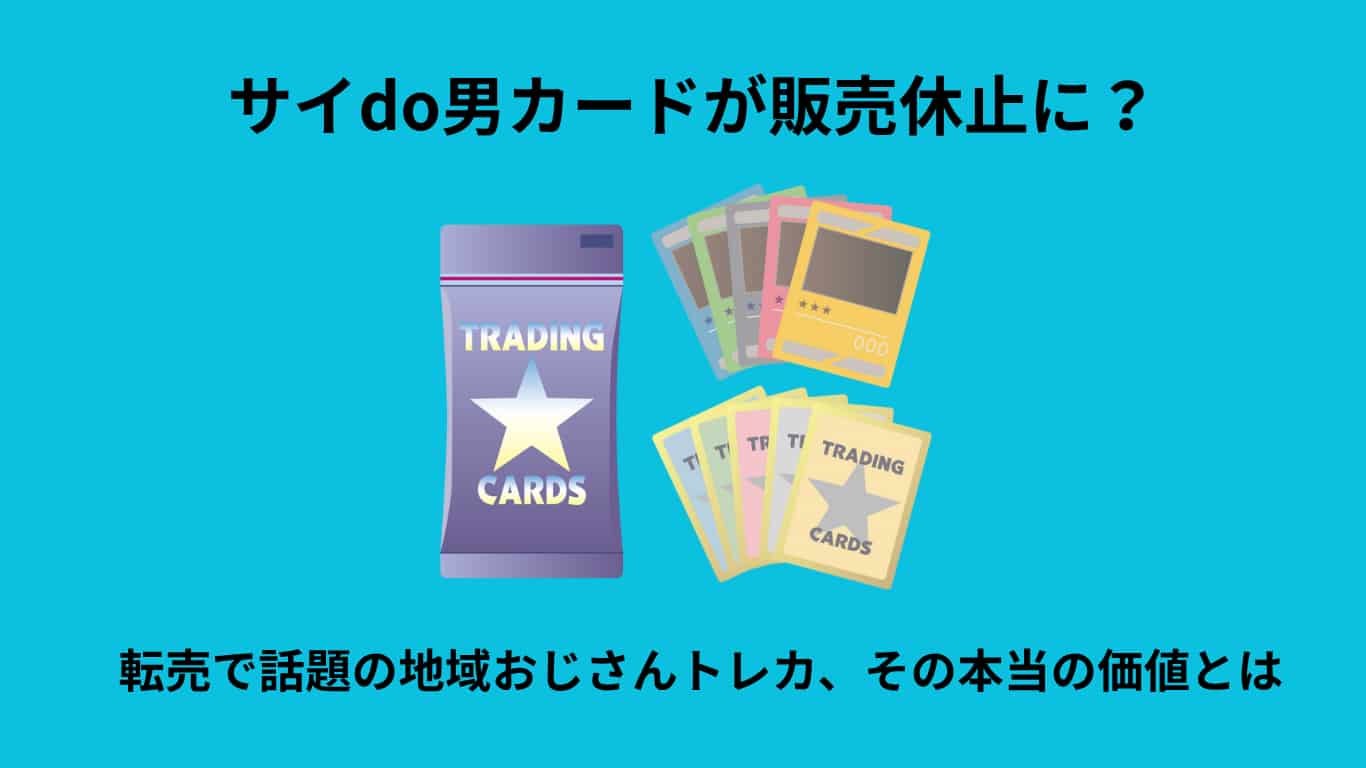
コメント