横浜アリーナで行われた「山田裕貴のオールナイトニッポン」のイベントに、ネプチューンがサプライズ登場して会場を大盛り上がりにしました!
しかし一方で、巴投げや股間ネタなど“ホリケン暴走芸”に賛否の声が相次いでいます。
俳優・山田裕貴さんとネプチューンの強い信頼関係があるからこその「愛あるイジり」なのか、それとも今の時代には問題がある行為なのか……。
SNSでも議論が巻き起こる今回の出来事を、一般視聴者の目線で分かりやすくまとめました!
はじめに
ネプチューンが横浜アリーナにサプライズ登場
26日夜、横浜アリーナで行われた「山田裕貴のオールナイトニッポン ドラゴンフェニックス甲子園」のエンディングに、ネプチューンが突然登場しました。

原田泰造さんが山田裕貴さんに豪快な“巴投げ”を決め、堀内健さんは「ジャングルパニック」と叫びながら股間をつかむしぐさを連発。
会場は驚きと笑いでざわつき、ゲストの赤楚衛二さん、勝地涼さん、SUPER BEAVERの渋谷龍太さんにも連続ムチャぶり。
ステージは一時“混乱”しましたが、最後は出演者全員で「なかま」を合唱し、イベントらしい一体感で締めくくられました。
具体的な場面としては、
- 泰造さんの一回転気味の投げで観客がどよめく
- ホリケンさんが山田さんとの距離をゼロに詰めて一気に笑いを取りにいく
- 渋谷さんが「やってもらいたかったのでうれしい」と笑顔で受け止める
といった“現場の空気”が続き、予定調和ではないライブの勢いが前面に出た時間でした。
視聴者から賛否が巻き起こった理由とは
盛り上がる一方で、今回の“股間ネタ”や過度な接触に対しては意見が分かれました。
肯定派は「これぞホリケン」「サプライズだからこその熱量」と評価。
山田さんやゲストが笑顔で受け止め、最後に“なかま”で締めたことで「信頼関係の上に成り立つお祭り」と見る声がありました。
一方、否定派は「股間いじりは今は笑えない」「俳優相手に触れるのはヒヤヒヤする」と指摘。ケガの心配や、見ている側が気まずくなるという感想も少なくありません。
賛否が分かれた背景には、次のような“今”の空気があります。
- 身体に触れる笑いに対する感度が上がっている
- 俳優やアーティストのイメージ保護を重視する視点が広がっている
- SNSで場面だけが切り取られ、文脈が伝わりにくい
つまり、ライブ感あふれる“愛ある暴走”が、見る人によっては“不安”に見える時代。
今回の記事では、この出来事を手がかりに「ネプチューンと山田裕貴の関係」「ホリケン芸の歴史」「股間ネタと放送倫理の変遷」を順に追い、なぜ賛否が生まれたのかを解きほぐしていきます。
1.ネプチューンと山田裕貴の深い関係

デビュー当時から続く信頼と交流

山田裕貴さんが『海賊戦隊ゴーカイジャー』で注目され始めた頃、バラエティの現場でネプチューンの3人と顔を合わせる機会が増えました。
収録の合間に泰造さんが気さくに話しかけてくれたり、名倉さんが楽屋で「本番は肩の力を抜いてええで」と声をかけてくれたり――そうした小さなやり取りの積み重ねが、山田さんにとって“頼れる先輩”としての安心感につながっていきます。
たとえば、緊張で言葉が詰まった若手時代、ホリケンさんが横から突飛なボケで空気をひっくり返し、山田さんが笑いながら乗っかることで、場がふっと軽くなる――そんな場面が何度もありました。
現場での「助け舟」が続いた結果、単発の共演ではなく“人”としてのつながりが続いていった、というわけです。
共演を重ねて育まれた“仲間意識”
今回の横浜アリーナでも、それははっきり表れました。
泰造さんの豪快な巴投げに山田さんが笑顔で受け身を取り、ホリケンさんの“ゼロ距離のムチャぶり”にも臆せず反応する。
舞台袖から見ていた共演者が次々に巻き込まれ、最後は全員で「なかま」を合唱――この流れは、台本にない“信頼の連鎖”がないと成立しません。
ポイントは、無茶ぶりが「一方的なイジり」ではなく、相手の顔や空気を見て強弱をつける“暗黙の合図”で動いていること。
ホリケンさんが距離を詰める瞬間、山田さんの表情や体の向きが“OKサイン”になり、名倉さんや泰造さんがフォローの位置に回る――そうした呼吸が、観客には「大騒ぎ」に見えつつも、実は安全と笑いが両立する形で回っています。
だからこそ、俳優・アーティスト相手でも成立する。受け止める側の覚悟と、投げる側の観察眼。その両方が重なったところに、“仲間だからできる”瞬間が生まれるのです。
2.ホリケン芸の歴史と評価
予測不能な暴走芸の特徴
ホリケンさんの笑いは、いきなり距離を詰める“ゼロ距離ボケ”と、その場の空気を一気に裏返す“設定崩し”が核です。
たとえば、静かなトークの最中に突然立ち上がって奇妙なポーズを取り、共演者の肩や背中にぴたりと寄ってツッコミを誘う。小道具があれば勝手に持ち出し、ないなら自分の体を小道具にしてしまう。
さらに、相手の表情を見ながら加減を調整し、一瞬で「困惑→笑い」へと着地させるのが持ち味です。
今回の横浜アリーナでも、巴投げの豪快さや“ゼロ距離ムチャぶり”はまさにホリケン流。
予定調和を壊して観客の視線を一身に集め、直後に相手の反応を見て強さを弱めたり、別の出演者にふって場を回す――この“暴れる→回す→収める”の三拍子で、ライブの温度を上げていきました。
予測不能に見えて、実は相手の顔色と安全を常に観察している点が、長く第一線で通用している理由です。
バラエティ黄金期を支えた存在と「天才」と呼ばれる理由
90〜2000年代のバラエティは、「体を張る」「空気をひっくり返す」タイプの芸が主流でした。
ホリケンさんはその中心にいて、台本にない瞬間の“事故寸前の笑い”を、怪我なく不快なく笑いに変える変換器として機能してきました。
収録現場では、重くなった空気を感じると誰より先に動き、最初の一発で観客の注意を奪い、次の一手で共演者にバトンを戻す。
これにより、MCや俳優、アーティストが自然にリアクションを取りやすくなり、番組全体の流れが軽くなるのです。
同業の芸人から「天才」と評されるのは、突拍子もない行動そのものより、秒で状況判断し、暴走とケアを同時にやれる“両利き”だから。勢いだけで押さず、最後は必ず「笑いの芯」に着地させる。
今回のサプライズでも、巴投げ→周囲を巻き込み→全員で「なかま」へ、という流れにより、会場全体を“お祭り”のムードで包みました。
結果として、予定外の騒ぎがイベントのハイライトに昇華された――これが、長年ホリケンさんが現場で重宝されるゆえんです。
3.股間ネタと放送倫理の変遷
昔は許容された“男同士のノリ”
2000年代前後のバラエティでは、男同士のスキンシップを誇張したボケが「お約束」の一つでした。
たとえば、舞台袖で突っつく、肩を組んだ勢いで転がす、相手の反応を見て“股間付近を誇張して指さす”――といった、痛くはないけれど距離が近い笑いです。
収録ではスタッフや先輩が様子を見ており、危ないと判断すればすぐ止める前提で進行。
観客も「ノリ」「勢い」として受け取り、終わったあとに当事者同士で軽口を交わして“和了(あが)り”にするのが定型でした。
今回の横浜アリーナでも、その空気感は一部残っていました。
泰造さんの豪快な巴投げに山田さんが笑顔で受け身、ホリケンさんのゼロ距離ムチャぶりに周囲が即座にフォロー――“勢い→笑い→ケア”という昔ながらの回し方があったからこそ、会場はお祭りの熱量を保てたのです。
現代ではハラスメント認識が強まる
一方、今は「触れる=同意が必要」という考え方が浸透しています。
特に俳優やアーティストは、体そのものがイメージの一部。たとえ仲間内のノリでも、観客席やSNSからは「本当に大丈夫?」と見えることが増えました。
具体的には――
- 映像が短い切り抜きで拡散され、文脈(合意や関係性、アフターケア)が伝わりにくい
- 視聴者の側に「見ていてヒヤヒヤする」「相手が無理して笑っていないか」という感覚が根づいた
- スポンサーやイベント主催も「安全第一」を明確に打ち出すようになった
この結果、同じ振る舞いでも評価が真逆になりやすい。舞台上の当事者には“仲間の悪ふざけ”でも、受け手の一部には“境界線を越えた接触”に映る。
だからこそ現場には、
- 触れずに笑いを作る代替案(言葉・間・距離の使い分け)、
- 観客に伝わる合図(安全の見える化)、
- 終演後の言葉でのフォロー(舞台裏の合意を短く共有)、
といった「今の基準」に合わせた工夫が求められます。
今回のケースでも、最後に全員で「なかま」を歌い、笑顔で肩を並べた締めは、“信頼関係が前提だった”ことを観客に伝えるサインになっていました。
昔の勢いを活かしつつ、現代の感覚に寄り添う――その折り合いが、これからのライブ・バラエティには欠かせません。
まとめ
横浜アリーナのサプライズは、ネプチューンと山田裕貴さんの長年の信頼があるからこそ成立した“お祭りの瞬間”でした。
泰造さんの巴投げに山田さんが笑顔で受け身、ホリケンさんのゼロ距離のムチャぶりに周囲が即フォロー、最後は全員で「なかま」――勢い→笑い→ケアの流れがはっきり見えました。
一方で、今は「触れる笑い」に厳しい目が向く時代。
俳優やアーティストのイメージ保護、SNSでの切り取り拡散、同意の見える化などの理由から、同じ芸でも評価が割れるのは自然なことです。
これからのライブやバラエティに求められるのは、①触れずに笑いを作る代替(言葉・間・距離)、②観客にも伝わる“安全の合図”、③終演後の一言フォロー、といった今の基準に合わせた工夫。
今回の出来事は、「仲間の悪ふざけ」をどう現代の感覚にアップデートしていくかを示す好例でした。
視聴者としては、当事者の関係性とその場の合図を汲みつつ、気になる点は言葉で議論する――そんな楽しみ方と向き合い方の両立が、これからのエンタメを豊かにしていきます。
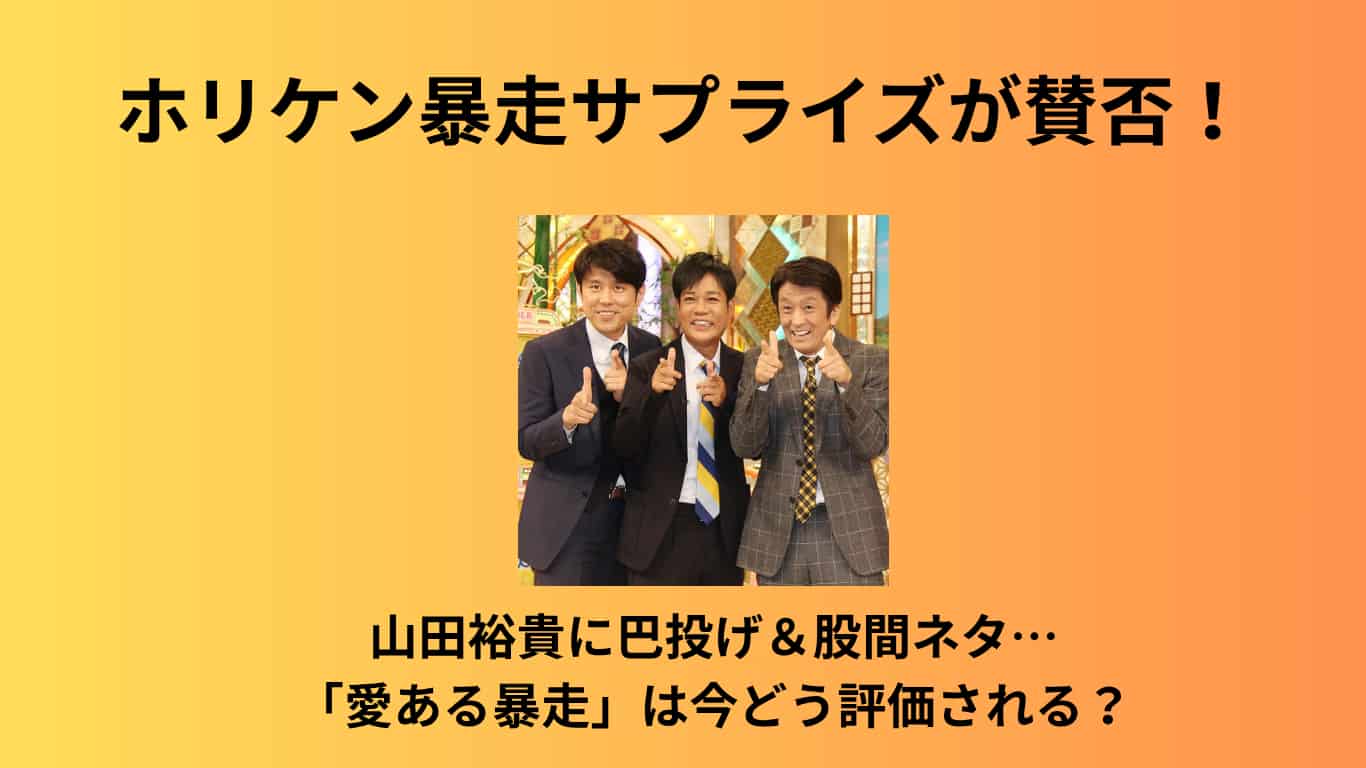
コメント