ランサムウェアは「クリック一つ」で会社の受発注や出荷を止め、取引先やお客さまにまで影響を広げます。
2025年10月に報じられたアスクルのシステム障害は、その現実を私たちに強く示しました。
本記事では、ランサムウェアの基本、アスクル事例で見えた実害とサプライチェーンへの波及、そして明日から実践できるバックアップ・メール対策・多要素認証などの具体策を、専門用語を避けて丁寧に説明します。
まずは「感染しにくくする」「止まっても早く立ち上がる」ための準備から始めましょう。
はじめに
ランサムウェアとは何かを理解する重要性
ランサムウェアは、パソコンやサーバーのデータを人質に取り「元に戻してほしければお金を払え」と迫るサイバー犯罪です。難しい仕組みを知らなくても、被害の姿は想像しやすいですよね。
たとえば、会社の受発注データが突然開けなくなり、見積書も請求書も出せない——それだけで日々の仕事は止まってしまいます。個人でも、家族の写真や家計簿が開けなくなるだけで大きな痛手です…。
私が強く感じるのは、「クリック一つ」で起きるという身近さです。宅配の不在通知を装ったメール、会議資料に見せかけた添付ファイル、無料ソフトの偽サイトなど、入り口は日常に紛れています。
専門部署がない中小企業や、テレワークで社外から接続する働き方ほど影響は大きくなりがちです。つまり、IT担当だけの問題ではなく、私たち一人ひとりが基本の注意を知っておく価値があるのだと思います。
アスクルのシステム障害が示した社会的影響
2025年10月に報じられたアスクルの障害は、ランサムウェアが「一社のトラブル」にとどまらないことを具体的に示しました。
受注や出荷が止まると、オフィス用品が届かない企業が増え、現場の仕事が遅れます。自社だけでなく、仕入れ先・配送会社・販売先といった“つながる相手”にも影響が広がり、結果として私たちの生活の細部——プリンター用紙が切れる、梱包資材が手に入らない——といった形で不便が表面化します。
この出来事から見えるポイントは二つです。
ひとつ目は、EC(ネット販売)と物流が止まると、業界をまたいで連鎖すること。
二つ目は、復旧には時間がかかり、その間の注文キャンセルや遅延対応、問い合わせ増加など、現場の負担が大きくなることです。
つまり、ランサムウェア対策は「被害を受けないため」だけでなく、「もし止まっても動きを最小限に保つため」の準備——代替手段や連絡体制、在庫の持ち方——まで含めて考える必要がある、ということだと感じました。
1.ランサムウェアの基本知識

定義と仕組み
ランサムウェアとは、パソコンやサーバーの中にあるデータを勝手に暗号化し、使えなくしてしまう悪質なプログラムです。
犯人は「元に戻したければお金を払え」と要求します。つまり、データを“人質”にして金銭を取ろうとする犯罪です。
仕組みはシンプルですが非常に巧妙です。感染したコンピューターの中のファイルを特殊な鍵で暗号化し、解除するための鍵を持っているのは攻撃者だけ。
その鍵と引き換えに「暗号を解くツールを売ってやる」と連絡してくるのです。ところが、支払いをしてもデータが戻らないケースも多く、結局泣き寝入りになる被害者が後を絶ちません。怖いですね…。
たとえば、ある中小企業では、社員の一人が開いた請求書メールの添付ファイルから感染し、社内サーバーがすべて暗号化されました。
バックアップも同じネットワークに置いていたため復元できず、結果的に数日間、受注・発送が完全に止まりました。こうした事例は、決して大企業だけの話ではないのです。
主な感染経路と攻撃手法
感染のきっかけで最も多いのは「メール」です。請求書や荷物の通知を装った添付ファイルを開いた瞬間に感染するパターンがよくあります。
また、偽のWebサイトにアクセスさせ、気づかないうちにウイルスをダウンロードさせる「ドライブ・バイ・ダウンロード」型も増えています。
最近では、リモートアクセスのパスワードを総当たりで破るなど、直接システムに侵入する手口も使われています。
さらに恐ろしいのは、感染後の「広がり方」です。攻撃者は一台のパソコンを足がかりに、社内ネットワーク全体を探り、他の端末やサーバーへと次々に感染を広げていきます。
最初の一人のミスが、会社全体のシステム停止につながる——まさに“ドミノ倒し”のような構造です。私たち一人の注意が、会社全体を守る力になると実感します。
二重脅迫型ランサムウェアの登場
近年、特に増えているのが「二重脅迫型」と呼ばれるタイプです。
従来のランサムウェアはデータを暗号化するだけでしたが、最近は暗号化の前にデータを盗み出し、「お金を払わないなら情報を公開する」と脅すのです。
この手口によって、単なる業務停止だけでなく、顧客情報や取引情報が流出するリスクも加わりました。
たとえば2023年に報じられた国内メーカーの被害では、工場の設計図面や取引先リストが盗まれ、一部がダークウェブ上に公開されたとされています。企業にとっては信用を失うだけでなく、取引停止や損害賠償に発展するケースもあるのです。
こうした背景から、ランサムウェアは「支払えば解決する」問題ではなく、「いかに感染を防ぐか」「被害を最小限に抑えるか」を考える時代に変わってきています。
私も家庭のパソコンで、見知らぬ添付は開かない・ソフトは正規のサイトから入れる…など、できることから続けています!
2.アスクルのランサムウェア被害
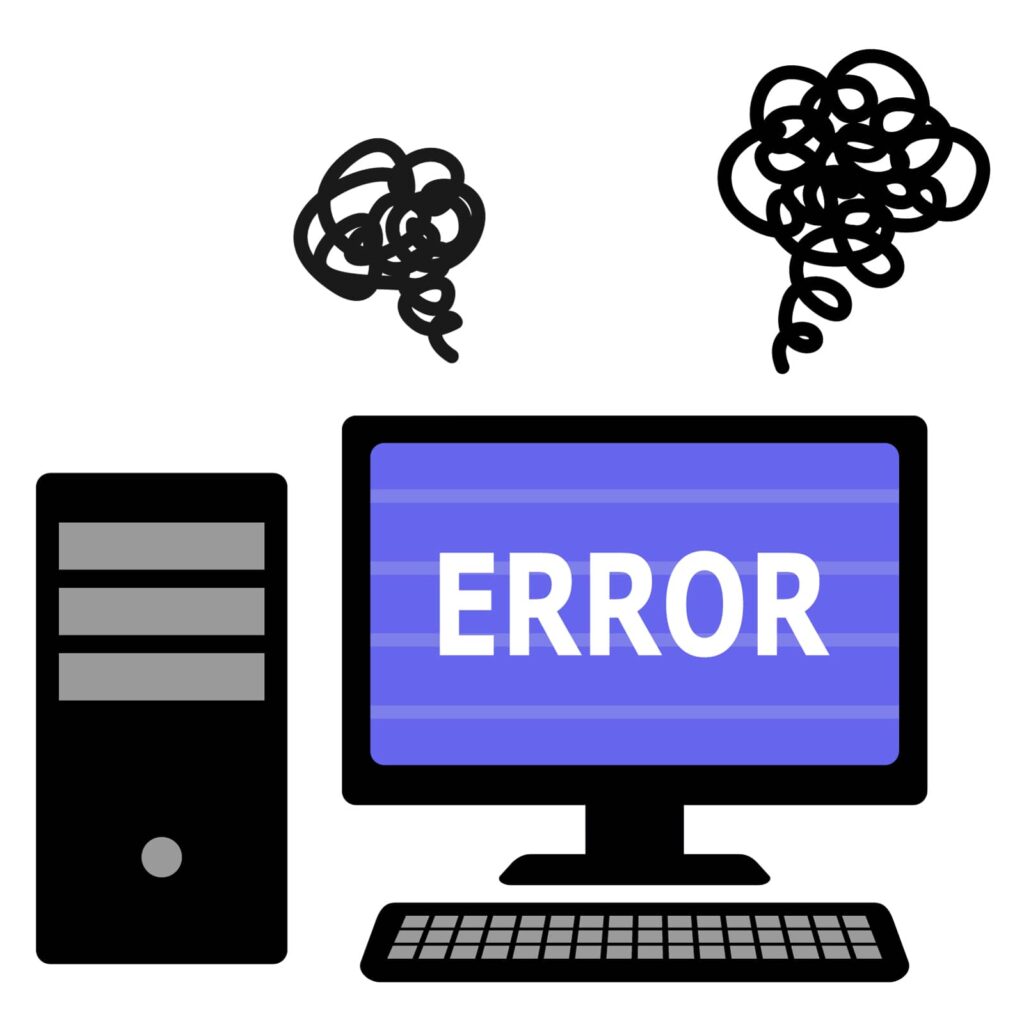
発生経緯と影響範囲
2025年10月、アスクルは基幹システムがランサムウェアに感染したことを公表しました。
最初に表れたのは「カートに商品が入らない」「注文確定でエラーになる」といった、ユーザー側の不具合です。
社内では、受注データの参照や印刷ができず、倉庫システムとの連携も止まりました。
対象は法人向けの「ASKUL」、個人向けの「LOHACO」、企業のまとめ買いを支える購買サイトなど幅広く、注文・出荷・返品の多くの機能が影響を受けました。
実際の現場では、次のような困りごとが同時に起きます。
・受注担当:注文一覧が読み込めず、受注の確認電話やメールが滞る
・出荷担当:ピッキングリストが出力できず、倉庫が手作業で状況確認
・カスタマーサポート:問い合わせが急増し、待ち時間が長期化
一見すると「一時的なサイト不具合」に見えますが、裏側では会社全体の仕事が止まっている状態です。利用者としても不安になりますし、現場のご苦労を思うと胸が痛みます。
受注・出荷停止がもたらした実害
受注と出荷が止まると、売上が出ないだけでなく、日常の業務まで崩れます。
たとえば、オフィスのコピー用紙やプリンタのトナー、衛生用品、梱包資材など「いつもの消耗品」が届かない。
結果として、見積書の印刷ができず、出荷物の梱包も遅れ、社内会議の資料も間に合わない——小さな遅れが積み重なって、会社全体の動きが鈍ります。
さらに、既に受け付けていた注文がキャンセルになれば、顧客対応の負担も増えます。「急ぎで必要だったのに」「代替品はあるのか」といった電話やメールが集中し、担当者は在庫の再確認や返金処理、別ルートの手配に追われます。
倉庫側も、止まっていた分の出荷を再開する際、ラベルの再発行や棚卸しのやり直しが必要になり、復旧後もしばらく混乱が続きます。想像するだけで大変さが伝わってきます…。
サプライチェーン全体への波及
今回のポイントは、影響がアスクル1社にとどまらないことです。
アスクルの物流やECの仕組みを一部活用している小売ブランドや取引先にも、欠品や発送遅延が波及しました。
たとえば、店舗の在庫補充が遅れて陳列がスカスカになる、オンライン注文が一時停止になる、配送ステータスが表示できない——こうした“周辺の困りごと”が連鎖的に起こります。
さらに、仕入れ元のメーカーや一次卸にも影響が広がります。出荷が止まると、工場の生産計画は見直しを迫られ、在庫回転が悪化します。
逆に、復旧直後は“止まっていた分”の注文が一気に戻り、倉庫と配送がパンクしやすい。ドライバーの手配、臨時スタッフの確保、深夜出荷の増加など、現場は短期間での“急ブレーキと急アクセル”に耐えなければなりません。
このように、ランサムウェアは「ITの問題」ではなく、購買・物流・販売・サポートまで巻き込む“全社的な業務停止”を引き起こします。
サプライチェーンでつながる相手が多いほど、影響は大きく、復旧にも時間と体力が必要になるのです。私たち利用者も、状況を理解して落ち着いて対応したいですね。
3.他事例との比較と企業の備え
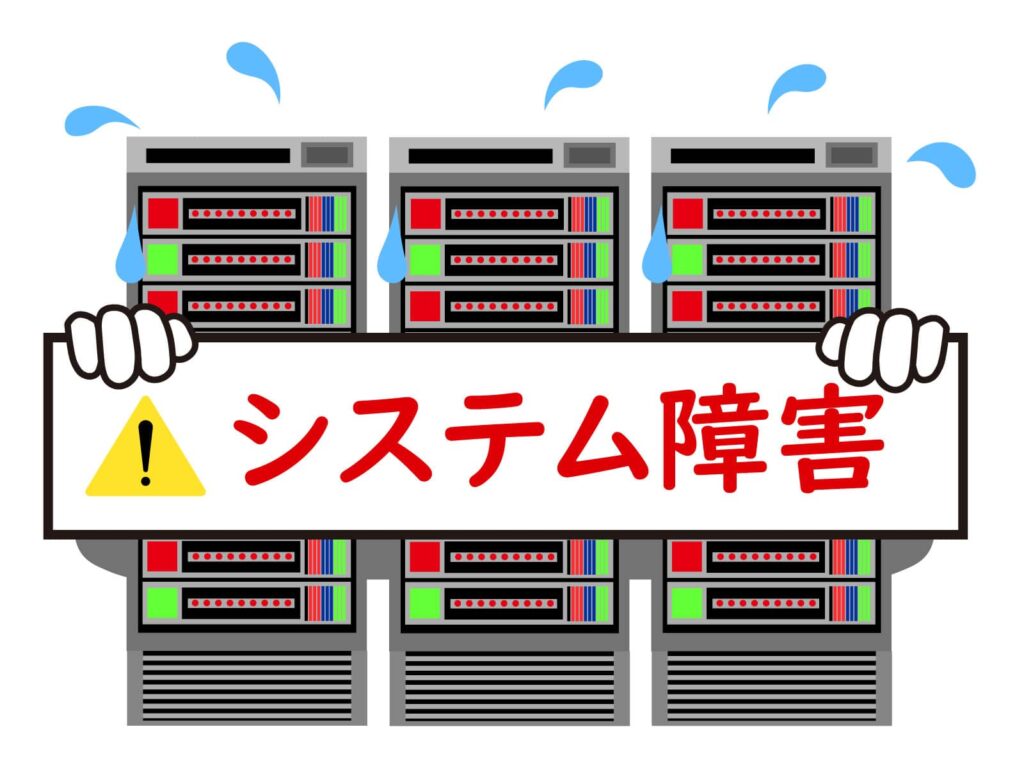
名古屋港・Colonial Pipelineなど過去の事例
ランサムウェアは国や業種を問わず、重要な現場を止めてきました。
たとえば、日本の名古屋港ではコンテナの出入りを管理する仕組みが止まり、トラックの列ができました。荷主は「いつ引き取れるのか」が読めず、倉庫や工場の予定がズレ込んだと伝えられています。
アメリカの燃料パイプライン会社(Colonial Pipeline)では、ガソリンの供給が滞り、一部の地域でスタンドに長い列ができました。会社の内部だけの問題でなく、一般の生活にまで影響が及んだ典型例です。
医療分野でも、アイルランドの公的医療機関では予約や検査が相次いで延期されました。病院のITが止まると、患者の情報確認や検査結果の共有ができず、安全な診療に支障が出ます。
これらに共通するのは、「ITは裏方」でも、止まれば目に見える形で社会の動きが止まる、という点です。日々の暮らしは、見えないところの仕組みに支えられているのだと改めて感じます。
共通点とアスクル事案の特異性
共通点は大きく三つあります。
1つ目は、最初は小さなトラブルに見えても、実際は会社の心臓部(受発注、在庫、配送、予約など)が止まっていること。
2つ目は、取引先や利用者など“周りの人”にも迷惑が広がること。
3つ目は、復旧しても「止まっていた分の処理」が一気に押し寄せ、しばらく混乱が続くことです。
そのうえで、アスクルには特有のポイントがあります。
アスクルは「EC(ネット販売)」と「物流」の両方を自社で大きく担い、さらに他社のECの裏側も支えています。つまり、自社のサイトが止まるだけでなく、パートナーの販売や在庫補充にも波及しやすい構造です。
名古屋港や医療機関が“社会インフラとしての大きさ”で広がったのに対して、アスクルは“商流の結節点としての広がり”が目立つと言えます。生活に近い分、影響の実感も強いですね。
企業が取るべきセキュリティ対策
明日から取り組める、効果の高い順でまとめます。
- バックアップは「離して・試す」
重要データは本番ネットワークから離して保存(オフラインや別クラウド)。四半期に一度は「実際に戻せるか」演習を行う。 - メール対策は“添付をそのまま開かない”の習慣化
宛先不明・不自然な日本語・圧縮ファイル・マクロ付き文書は要注意。疑わしい添付は開かず、IT担当に転送するルールを紙1枚で周知。 - リモート接続は必ず多要素認証(MFA)
社外から社内に入る入口には「パスワード+ワンタイムコード」。使っていないリモート機能は止め、使う人も必要時だけ許可する。 - 社内の“横移動”をさせない
部署ごとにネットワークを分け、不要な共有フォルダを整理。管理者権限のアカウントは常用しない。ログは一か所に集めて異常を見つけやすく。 - 止まっても動ける“手順書”
受注・出荷・問い合わせ対応の「代替フロー」を用意。たとえば、優先度の高い商品だけ手作業で出荷する、連絡先を一覧化して一斉メールで案内する等。印刷して現場に置く。 - 取引先と“もしも”を事前に話す
委託先や主要パートナーと、停止時の連絡窓口、優先順位、代替ルート(別倉庫・別配送)を取り決め、年に一度は共同訓練。 - 広報と法務の準備
公式サイトやSNSに掲出する定型文、Q&A、問い合わせフォームをテンプレ化。個人情報が関係する可能性がある場合の連絡手順も決めておく。 - “払えば解決”にしない社内方針
原則として身代金は支払わない方針を明文化し、例外があり得る場合の判断手順(経営・法務・警察との連携)もあらかじめ決めておく。
どれも特別な道具がなくても始められる内容です。ランサムウェアはゼロにはできませんが、「感染しにくくする」「止まっても早く立ち上がる」準備で、被害を大きく減らすことができます。
私たちの小さな一歩が、会社や家庭を守る大きな力になります!
まとめ
ランサムウェアは「クリック一つ」で会社の心臓部を止め、取引先やお客さま、そして私たちの暮らしまで巻き込む厄介な脅威です。
アスクルの事例は、ECと物流という身近なサービスが止まると、現場の仕事・在庫・配送・問い合わせ対応が一斉に揺れることをはっきり教えてくれました。だからこそ、特別な技術よりもまず「基本」を固めることが近道です。
- データは離して保つ(オフライン/別環境にバックアップ)+戻せる練習を定期的に。
- メールや添付は即開かない。迷ったらIT担当へ転送する“合言葉”を浸透させる。
- 社外からの接続は多要素認証を必須にし、使わない入口は閉じる。
- ネットワークは分ける、管理者権限は常用しない、ログは一か所に集める。
- 止まっても回せる代替フロー(受注・出荷・案内)を紙1枚にして現場に常備。
- 主要パートナーと「もしも連絡網」と優先順位を取り決め、年1回は一緒に訓練。
- 広報・法務の定型文とQ&Aを用意し、事実ベースで迅速に案内できる体制を。
完璧に防ぐことは難しくても、「感染しにくくする」「止まっても早く立ち上がる」準備は誰にでもできます。今日できる小さな一歩を積み重ね、明日の“もしも”に備えましょう。
ここまで読んでくださって、ありがとうございます!同じ生活者として、一緒に備えていきましょうね。
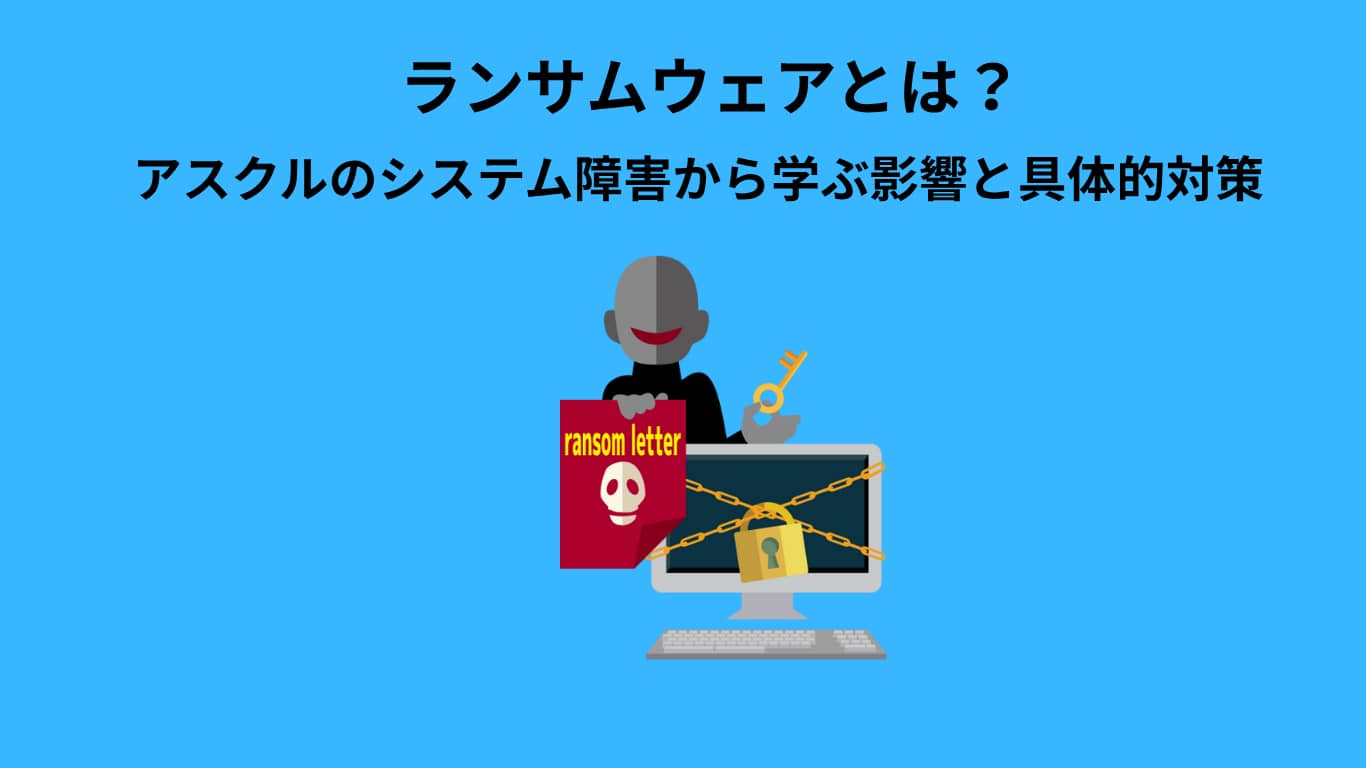
コメント