2025年、俳優・古川雄大さんが見せる二つの顔に注目が集まっています。
月10ドラマ『終幕のロンド』では、孤独を抱えたフリーライター・波多野祐輔を静かに演じ、NHK大河『べらぼう』では、江戸の文化を彩る絵師・北尾政演(山東京伝)として明るく華やかに躍動。
まるで“影”と“光”を行き来するような対照的な役柄で、俳優としての深みを見せています。
本記事では、古川雄大さんのプロフィールから、それぞれの作品での演技表現、そして二つの役の“陰と陽”の魅力までを詳しく掘り下げていきます。
はじめに
古川雄大という多才な俳優
古川雄大は、舞台とテレビの両方で存在感を放つ“歌って演じる”俳優です。
長野県出身、身長182cmというモデルのような体躯に、伸びやかな歌声と繊細な表情が合わさり、ミュージカルからドラマまで幅広い作品で起用が続いています。
たとえば、舞台では高い歌唱力とダンスで躍動感のある役を、ドラマでは静かな場面での視線や間で感情を伝える役を任されることが多く、同じ人物とは思えないほどの振り幅を見せます。
2025年は特に注目の年で、月10ドラマ「終幕のロンド」とNHK大河ドラマ「べらぼう」というタイプの異なる二作に同時期に出演。前者では“影”を感じさせる人物像、後者では“光”をまとった文化人というコントラストが際立ちます。
ファンはもちろん、初めて彼を知る読者にも、その多面性が一目で伝わるラインナップです。
二つのドラマで見せる“陰と陽”の演技対比
「終幕のロンド」で古川が演じるのは、フリーライターの波多野祐輔。
遺品整理をめぐる人間模様の中で、企業の不正を追う一方、コミュニケーションが得意でない面や“嗅覚障害”という弱さも抱えています。
派手な言動は少ないのに、場面が進むほど目が離せなくなる“静かな緊張”を生む役です。具体的には、情報を集める取材シーンでの低い声量や、答えを飲み込む仕草が、内面の孤独や葛藤をリアルに感じさせます。
一方の「べらぼう」では、江戸の絵師・戯作者として名を成す北尾政演(のちの山東京伝)を演じます。こちらは人の輪の中心に立ち、時に艶やかな色気も漂わせる“陽”の人物。
例えば、蔦屋重三郎に才能を見いだされる場面では、視線の明るさや身振りの軽やかさで、文化の渦の真ん中にいる高揚感を観客に伝えます。
同じ俳優が、片や囁くような台詞回しと伏し目がちの目線で“影”を、片や張りのある声と開いた身体で“光”を描き分ける—この二作並走の年は、古川雄大の表現の幅を確認する格好の機会になります。
1.古川雄大のプロフィールとキャリア
生年月日・出身・所属事務所などの基本情報
1987年7月9日生まれ、長野県出身。身長は182cm。すらりとした体型と柔らかな物腰が印象的で、画面でも舞台でも“立ち姿が絵になる”タイプです。
現在は大手事務所に所属し、俳優としての活動に加え、音楽活動や写真集・エッセイなど表現の場を広げています。
公式インタビューやイベントでも丁寧な言葉選びが目立ち、ファン層は10代から大人世代まで幅広いのが特徴です。
ミュージカルからドラマへ──演技と歌の両立

キャリアの土台はミュージカル。若い頃からダンスと歌で鍛えられ、ステップのキレやブレスの強さが舞台上での説得力につながっています。
たとえば、客席の最後列まで届くロングトーンや、ダンスで息が上がる場面でも崩れない発声は、テレビドラマの“静かな芝居”にも生きています。
具体例として、朝ドラ『エール』では“ミュージックティーチャー”として登場し、軽やかな所作と歌心のある台詞回しで人気に。ライブ感覚の舞台仕込みのテンポが、テレビのクローズアップでも違和感なく映えました。

2025年は、月10ドラマ『終幕のロンド』と大河『べらぼう』に同時期出演。前者では抑制の効いた低いトーン、後者では晴れやかな声色と堂々とした立ち居振る舞い、と作品ごとに“音色”から変えてくるのが見どころです。
素顔と人間味:インタビューで語る“頑張れる人間像”
インタビューでは「だらしないところもあるけれど、頑張れる人でいたい」という等身大の言葉をよく口にします。
撮影の合間に台本へ細かな付せんを貼り、場面の“空気”を書き込むなど、コツコツ型の準備が得意。
たとえば、取材シーンが多い『終幕のロンド』では、記者ノートの開き方やペンの持ち方、録音アプリの操作手つきまで事前に練習。
『べらぼう』では筆と扇子の扱い、座り姿勢の重心まで和装講師から学び、画面の端でも所作が崩れないよう整えています。
こうした積み重ねが“派手さ”だけに頼らない説得力を生み、静かな目線の動きやわずかな息づかいにも意味が宿ります。
結果として、舞台では大きく、ドラマでは繊細に――場に合わせて“見せ方”を切り替えられるのが、古川雄大という俳優の強みです。
2.「終幕のロンド」での役どころ:波多野祐輔
物語の概要と波多野祐輔の立ち位置
物語は、遺品整理を通して“残された想い”を拾い上げるヒューマンドラマ。
主人公・鳥飼樹が依頼を受けるたびに、故人と家族の間に埋もれた手紙や写真、ボイスメモなどの“痕跡”が現れます。
波多野祐輔は、その裏側で情報を集めるフリーライター。たとえば、依頼人の口からは出てこない企業名や、古い名刺に残った手書きメモを手掛かりに、事件と日常の狭間を静かに歩きます。
現場では、遺品のダンボールに貼られた宅配伝票の“差出元”や、古いUSBの中身、家計簿の余白にある走り書きなど、誰も気に留めない細部に目を凝らすのが彼のスタイル。
派手なアクションはないのに、視線の動きとページをめくる指先だけで“何かを掴んだ”ことが伝わる――そんな“静かな推進力”で物語の裏筋を明らかにしていきます。
フリーライターとしての探求心と孤独――嗅覚障害が象徴する“内面の静けさ”
波多野は、人と距離を置きがちで、会話も必要最小限。取材のアポイントもメッセージで済ませ、面会は短時間で切り上げるタイプです。
その分、机に向かえば粘り強く、夜明け前まで資料を照らすデスクライトとキーボードの打鍵音だけが部屋に響きます。
特徴的なのが“嗅覚障害”の設定。たとえば、孤独死の現場でも彼は“におい”を感じません。これは弱点であると同時に、仕事の武器にもなります。
通常なら足がすくむ場でも冷静さを保てるため、他の人間が気づけない“視覚の手掛かり”を拾えるのです。
壁紙の色ムラ、換気扇の油汚れ、冷蔵庫の霜のつき方――においの代わりに目と耳で情報を補う彼は、五感のバランスを自分なりに組み替えながら真実へ近づいていく。
一方で、その静けさは孤独も伴います。差し出されたコーヒーの香りに反応できない自分を悟られまいと、カップをそっと置く場面。
取材相手が発した“ため息の重さ”だけで、言葉にされない後悔を読み取る場面。
声を荒げることはないのに、内側の熱は確かにある――古川雄大は、低いトーンの台詞回しと伏し目がちの目線、指先の小さな動きで、その“揺れ”を丁寧に描き出します。
3.「べらぼう」での役どころ:北尾政演(山東京伝)

江戸文化を担う青年──浮世絵師としての政演
「べらぼう」で古川雄大が演じる北尾政演は、のちに“山東京伝”として名を残す若き才能です。
画材屋の店先で紙の手触りを確かめたり、版木の彫り跡に指を滑らせて出来を見抜いたり――職人の町で呼吸するように生きる青年として描かれます。
たとえば、師匠の屋敷で下絵を重ねる小さな所作。筆を紙に置く前の“ひと呼吸”や、墨の濃淡を試す筆先の微かな揺れが、絵師としての集中と自負を伝えます。
蔦屋重三郎に見いだされる場面でも、古川の身体づかいが効きます。
褒め言葉を受けた瞬間、背筋が自然に伸びて視線が前へ出る。言葉少なでも、胸の奥で火が灯る高揚が伝わるのは、舞台仕込みの“間”の扱いが生きているから。
町人のざわめき、行燈の明かり、版元の掛け声――江戸の音の中で、政演は文化の渦に巻き込まれ、中心へと歩を進めていきます。
明るさと色気が映える“陽キャ”な演技──初の大河で見せる華
政演は、人の輪に自分から飛び込み、場の空気を明るく変えるタイプ。
茶屋での雑談でも、扇子を軽くはたいて冗談を添え、周囲の緊張をほどく。祭り囃子が聴こえると、足取りが弾み、袖口がふわりと広がる――そんな“陽”のムードを、古川は笑みの出し入れやテンポの良い相づちで体現します。
色気の出し方も軽やかです。帯を結び直すさりげない仕草、絵を見せるときに相手へ半歩近づく距離感。声は一段高く張り、言い切りで締める。
仕事の場ではきっぱり、友と語るときはやわらかく――声の“明暗”で人物の表と裏を切り替えます。
初の大河という大舞台でも、所作・発声・視線の三点をきっちり整えることで、華やかさが独りよがりにならず、物語の推進力として機能。政演が登場すると場が明るくなり、次の展開への期待が自然と高まる――そんな“光の役”を、古川雄大は確かな説得力で引き受けています。
補足:「古川雄大 結婚」が検索上位にある理由
最近、「古川雄大 結婚」というキーワードが検索の上位に上がっています。
しかし、これは本人の私生活の話ではなく、出演中の大河ドラマ『べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~』のストーリー展開が影響していると考えられます。
ドラマの次回予告で、古川雄大さん演じる北尾政演(のちの山東京伝)が“馴染みの遊女と結婚する”という描写があり、その印象的な場面が視聴者の関心を集めたようです。
政演は、明るく社交的で人を惹きつける魅力を持つ人物。
その恋愛模様がリアルに描かれているため、SNSでは「本当に結婚したの!?」と話題になりました。
こうした“役柄の結婚”が、検索トレンドで「古川雄大 結婚」として注目されている要因です。
実際には、古川雄大さん本人が結婚しているという公式発表はなく、所属事務所(研音)や本人のSNSでもそのような報告は出ていません。
つまり、今回の“結婚”はあくまで作品内の出来事。
それだけ、古川さんの演技が自然で、視聴者の心に響いている証拠とも言えるでしょう。
まとめ
古川雄大の“静”と“陽”は、同じ一年に放送される二作でくっきりと分かれて描かれます。
『終幕のロンド』の波多野祐輔では、メモの走り書きやUSBの中身を手掛かりに真実へ近づく“視線と指先”の芝居が核。コーヒーの香りに反応できずカップをそっと置く――そんな小さな所作が、嗅覚障害と孤独を物語ります
。一方『べらぼう』の北尾政演(山東京伝)は、扇子を軽くはたく仕草や半歩近づく距離感、張りのある言い切りの声で周囲を明るくし、江戸の熱気を引き寄せます。
つまり、低い声量と伏し目で温度を下げる“影の演技”、笑みとテンポで空気を上げる“光の演技”――対極の表現を同時期に見比べられるのが今年の醍醐味。
視聴のポイントは三つだけ。①『ロンド』では手の動きと間(ま)に注目、②『べらぼう』では所作と声の“明暗”に注目、③どちらも一度音声をオフにして観て、表情と身体だけで伝わる情報量を確かめること。これらを意識するだけで、古川雄大の“多面体”が一段と立体的に見えてきます。
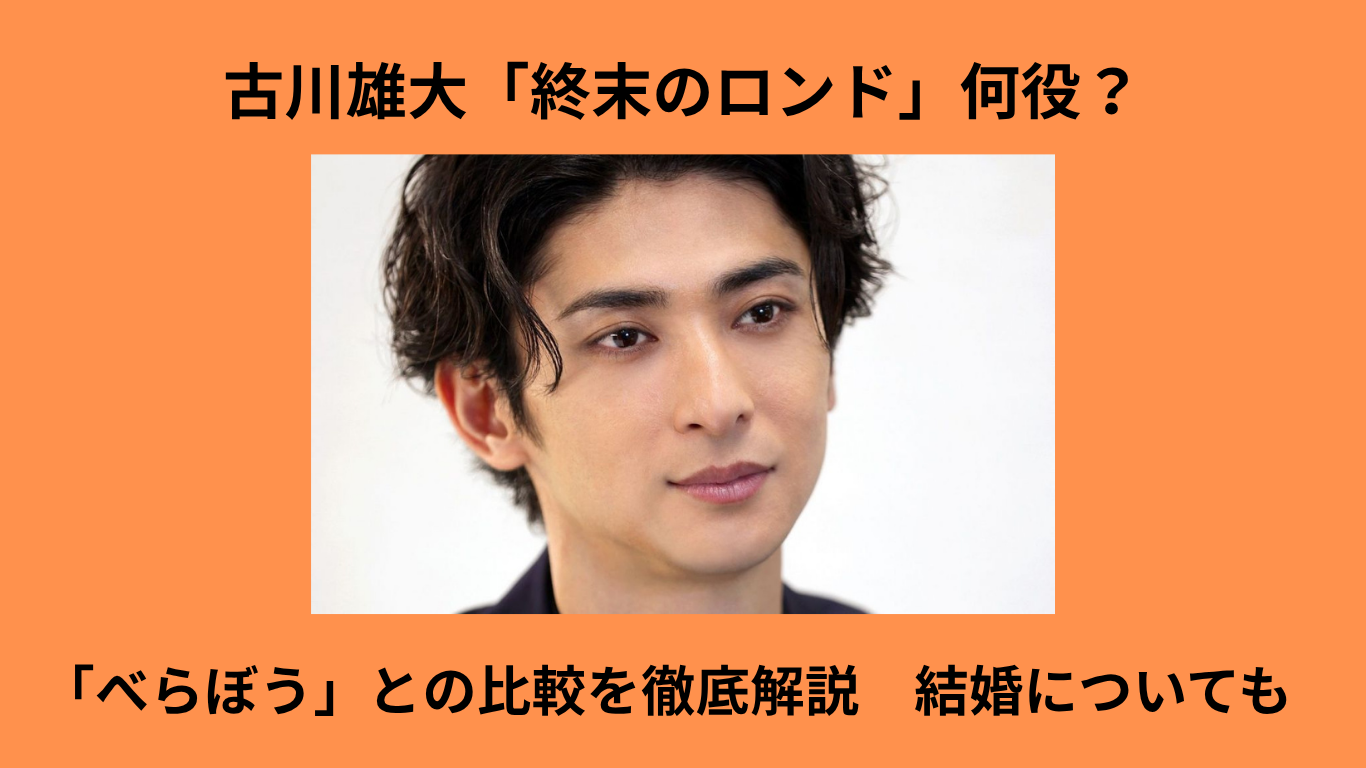
コメント