2024年は賞レース連覇、チャート独占、ライブ映画も大ヒット――Mrs. GREEN APPLEは“時代の顔”になりました。
一方で2025年に入り、「フェーズ2完結」「活動休止?」という報道や憶測が増え、ファンの間では「理由は?」「いつ休むの?」「再開はある?」という声が高まっています。
本記事では、10周年という節目、表現の拡張(個人活動)、そして過密スケジュールという3つの視点から活動休止の可能性を整理。
さらに、最有力の再始動シナリオ(フェーズ3)、想定される時期や合図、ファンが今できる準備まで、わかりやすく解説します。
先に結論だけ知りたい方は「まとめ」へ、流れから理解したい方は「これまでの経緯」からどうぞ。
はじめに
10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEの現在地
2024年、Mrs. GREEN APPLEはデビュー10周年という大きな節目を迎えました。
彼らの音楽は年々進化を続け、「青春」「希望」「再生」といったテーマを軸に、多くのリスナーの心をつかみ続けています。
この年はまさに快進撃といえる活躍ぶりで、日本レコード大賞2年連続受賞、Billboard JAPAN年間アーティスト1位、ライブ映画の興行収入18億円突破など、数々の記録を更新しました。
その一方で、ファンの間では「これまで以上に多忙では」「しばらく休んでほしい」という声も増えています。
10周年という節目は祝福ムードに包まれながらも、バンドにとって新たな転換期を迎えるタイミングでもありました。
音楽シーンの最前線で走り続けてきたMrs. GREEN APPLEが、これからどんな選択をするのか──注目が集まっています。
活動休止の噂とファンの注目
2025年に入り、「フェーズ2完結」「活動休止か」という報道が相次ぎました。
一部メディアでは「10周年アルバム『10』をもって一区切りにする」との関係者コメントも伝えられ、ファンの間では様々な憶測が飛び交っています。
SNSでは「またフェーズが変わるのかも」「静かな期間を経て新章に入るのでは」といった声が多く見られ、前向きに受け止めるファンが多いのも印象的です。
過去にも“Phase 1完結”を宣言して活動を止めたあと、劇的な進化を遂げて“Phase 2”として再出発した彼ら。
今回の噂も、単なる終わりではなく、新しい始まりの予兆として受け止めるファンが少なくありません。
音楽、映像、演技と表現の幅を広げ続けるMrs. GREEN APPLE。
10年の歩みを経た今、彼らが次に見せる景色とは――。
1.これまでの経緯──フェーズ制が描く再生の物語
Phase 1完結から再出発までの流れ
Mrs. GREEN APPLEは、2020年に「Phase 1完結」を宣言し、突然の活動休止に入りました。
当時はファンの間に驚きと戸惑いが広がりましたが、彼らにとってそれは“終わり”ではなく、“再生への準備期間”でした。
その年にリリースされたベストアルバム『5』は、これまでの活動の集大成でありながら、どこか“区切り”を意識させる内容でした。
活動を止めた理由について、ボーカルの大森元貴さんは後のインタビューで「自分たちの音楽を見つめ直し、次の形を探したかった」と語っています。
そして、約2年の沈黙を経た2022年。Mrs. GREEN APPLEは“Phase 2”として活動を再開。
復帰第1弾となる楽曲「ダンスホール」は、これまでのイメージを一新するポップで開放的なサウンドで、多くのリスナーに衝撃を与えました。
MVではカラフルな演出や軽快なダンスが印象的で、再出発の象徴として話題を呼びました。

メンバー脱退と体制の再構築
Phase 1完結後の大きな変化として、2021年にはドラムの山中綾華さんとベースの髙野清宗さんが脱退。
デビュー当時から支えてきたメンバーの離脱は大きなニュースとなり、ファンの間では「グループとして大丈夫なのか」と心配の声も上がりました。
しかし残った大森元貴さん、若井滉斗さん、藤澤涼架さんの3人は、新体制での活動を選択。
大森さんが作詞作曲を担い、若井さんがギターサウンドで支え、藤澤さんがキーボードで世界観を広げる──そんな役割分担がより明確になりました。
結果として、グループは少数精鋭となり、表現の幅がむしろ広がっていったのです。
この時期、彼らはクリエイティブチーム「Project-MGA」を立ち上げ、制作やビジュアルの方向性を自らコントロールするようになりました。
外部スタッフとのコラボも積極的に行い、音楽性と表現の自由度を格段に高めたのです。

フェーズ制に込められた意味と戦略
Mrs. GREEN APPLEの“フェーズ制”とは、単なる活動の区切りではありません。
それは「常に変化し続けるための仕組み」として設計された独自の戦略です。
Phase 1では“青春の衝動”をテーマに、等身大の若者の心情を描いた楽曲が多く見られました。
たとえば「インフェルノ」や「青と夏」など、疾走感と情熱を感じさせるナンバーは、彼らの代名詞として世代を超えて愛されています。
一方、Phase 2では“成熟と再生”がキーワード。
「ダンスホール」や「ケセラセラ」に見られるように、前向きなメッセージ性と洗練されたアレンジが特徴的です。
音楽的にはポップスの枠を超え、R&Bやエレクトロの要素も融合。海外の音楽トレンドを意識したサウンドづくりが際立ちました。
つまり、このフェーズ制は音楽的リブランディングのサイクルであり、一度立ち止まり、殻を破り、新しい自分たちを再定義するプロセスなのです。
その柔軟さこそが、Mrs. GREEN APPLEを“変化できるバンド”として際立たせる最大の強みといえるでしょう。
2.2024年の快進撃──成功の裏にあった過密スケジュール
チャート・賞レースを総なめにした一年
2024年のMrs. GREEN APPLEは、まさに“数字が語る”一年でした。
年末の音楽賞では「ライラック」で大賞を手にし、主要テレビ番組の年間ランキングでも上位を独占。カラオケの年間ランキングでは「ダンスホール」「ケセラセラ」「青と夏」など過去曲までが再浮上し、世代を超えて歌われました。
配信でも強さは顕著で、新曲が出るたびにストリーミングの急上昇に入り、YouTubeの急上昇音楽でも常連に。ベスト盤『10』は“入門書”として新規ファンを呼び込み、ライブ映画はスクリーンでの動員記録を伸ばしました。
結果として、テレビ・ラジオ・街中・カラオケのどこにいても曲が流れる“国民的ヒット”の状態が続き、名実ともにその年の主役になったのです。
メディア・ライブ活動の拡大と負荷
一方で、その裏側は超過密。
たとえば、新曲リリースのたびにテレビ収録、ラジオ生出演、雑誌・ウェブの取材が連日続きます。
並行してMV撮影、アートワークの撮影、ダンスやバンドセットのリハーサル、タイアップ先との打ち合わせも入ってきます。
大型フェスやアリーナ公演が重なる時期は、前日深夜まで地方でライブ→早朝移動→昼にテレビ収録→夜は別会場で本番、という“移動と本番の繰り返し”になりがちです。
さらに、音楽番組では生演奏用のショートアレンジを準備し、ライブではフル尺の構成を組み直す必要があるため、演奏面の準備も二重三重。
衣装・照明・映像演出の確認まで含めると、制作とプロモーションが常に同時進行でした。
この“多方面同時対応”ができたからこそ広がった一方で、心身の負担は確実に積み重なっていきます。
ファンが感じ取った“働きすぎ”の兆候
ファンはその変化を敏感に受け取りました。
SNSには「告知が毎週のようにある」「出演情報を追い切れない」「体調だけは大事にしてほしい」といった声が並び、ライブ後のインタビューで見せるわずかな疲労感や、短い休養告知にも即座に反応。
「このペースは長く続けなくていい」「少し止まっても待てる」という“守りの応援”へと空気が変わっていきます。
過去に“Phase 1完結→充電→再始動”を経験しているからこそ、「区切って進化するのがこのバンド」という理解がすでに共有されており、休むことへの肯定が広がりました。
“もっと見たい”よりも“長く続けてほしい”。2024年の終盤には、そんな成熟した応援スタイルが目立つようになったのです。
3.活動休止の可能性と今後の展望
報道に見えるフェーズ2完結の予兆
ここ最近の報道では、「10周年ベスト『10』を一区切りにする」「フェーズ2完結を協議」という言葉が並びました。
実際、アーティスト側の公式コメントは出ていない一方で、メディア露出や告知のトーンに“総括”を思わせる表現が増えたのは確かです。
たとえば、ベスト盤の特設ページやインタビューで「これまでの歩み」「第2章の収穫」といった振り返りの言い回しが目立ちました。
また、スケジュール面でも予兆は読み取れます。
年末から年度始めにかけ、通常ならアリーナや夏フェスへ向けた大規模ツアーのアナウンスが続く時期に、次の大型プロジェクトの解禁が控えめになると、ファンの間で「一度止めるのでは?」という見方が強まります。
SNSでも「発表の間隔が少し空いた」「“区切り”を示すビジュアル多め」といった観測が相次ぎ、噂の燃料になりました。
「なぜ今なのか」—節目・表現拡張・疲労の三要因
① 節目(10周年)
10周年は、音楽活動の“棚卸し”に最適なタイミングです。ベスト盤のリリースや記念企画が整った今は、次の10年へ向けて方向性を整える区切りとして申し分ありません。
具体例として、周年タイミングで一度立ち止まり、編成や制作体制を見直したバンドは少なくありません。結果として、その後の作品の色合いがガラッと変わるケースも多いです。
② 表現拡張(個人活動の広がり)
ボーカルの大森元貴さんは音楽に加え、映像・演技のフィールドでも注目を集めています。
撮影や番宣、主題歌制作など、“音楽×映像”の越境案件が増えるほど、グループの年間計画は複雑になります。
この状況でフェーズを切り替えると、個々の挑戦を尊重しつつ、次の章のサウンドや物語を落ち着いて作り込めます。
③ 疲労(過密スケジュールの蓄積)
2024年は“リリース→プロモーション→ツアー→映像企画”がノンストップ。現場では、番組用のショートアレンジやフェス用のセット組み替えなど、細かな準備が重なります。
ファンの間でも「追い切れないほど告知が多い」「まずは休んでほしい」という声が定着。“守る応援”が広がった今、戦略的な休息はむしろ歓迎される空気になっています。
フェーズ3構想と三つのシナリオ
A:フェーズ2完結 → 一時休止 → フェーズ3へ(最有力)
数か月~1年程度の“静かな期間”を置き、サウンド・ビジュアル・ライブ演出を再設計。再開時は、新しいキービジュアルやコンセプト曲を先行公開し、“物語の第3章”を強く打ち出す。
具体例: 再始動初週にティザー映像→翌週に新曲先行配信→翌月に短期ホールツアー告知、のような段階的解禁。
B:活動継続+個人活動拡大(高確度代替案)
グループ名義は維持しつつ、新曲は年2~3本に絞って“点で当てる”運用。並行してメンバー個々の企画を前面に押し出す。
具体例: 配信シングルは大型タイアップを狙い撃ち、ライブは季節限定のシティ型フェスや周年イベントに集中参加。空いた時間を個人の撮影・コラボに充てる。
C:長期休止に近い静養・ソロ専念(低確度)
グループ活動を大きく絞り、個人名義の作品づくりへ。解散ではないものの、復帰時期は未定。
具体例: 大森さんが映像作品の主演・主題歌を兼任、他メンバーは作曲提供やプロデュースワークを強化。再合流は“特別公演”から小規模に始める。
—
いずれの道でも、鍵は“フェーズ3の最初の一手”です。
一曲目のコンセプト、最初に見せるビジュアル、最初のステージの作り方——この三点が揃えば、物語は自然と前へ転がります。ファンはもう“変化するバンド”に慣れています。だからこそ、勇気ある区切りと強い第一歩が、次の10年のスタンダードを決めていくはずです。
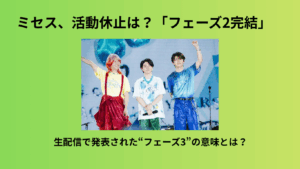
まとめ
Mrs. GREEN APPLEの10年は、「区切って、見直し、もう一度飛ぶ」という物語でした。
2024年は賞レースやチャートで“結果”を示し、同時に過密さという“代償”も抱えた年。ファンはその走りを間近で見てきたからこそ、「少し止まっても待てる」という成熟した応援へと変わりました。
活動休止の噂が強まる背景には、①10周年という節目、②音楽以外へ広がる表現の挑戦、③積み重なった疲労――という三つの要因があります。どれも“終わり”ではなく“次の章をより良く始めるための準備”として筋が通っています。
今後の現実的な道筋は、フェーズ2完結 → 一時休止 → フェーズ3の始動。再開の初手は、1曲目のコンセプト、最初に見せるビジュアル、初ステージの設計――この三点が鍵になります。段階的にティザー→先行配信→短期ツアーと積み上げれば、物語は自然に前へ転がります。
ファンにできることはシンプルです。音源や映像を“今のうちに”もう一度味わい、ライブの記憶を言葉に残し、静かな期間は各メンバーの挑戦を見守ること。
そして、フェーズ3の最初の光が見えたら、最初の一歩をいっしょに踏み出す準備をしておきましょう。終わりではなく、静かな始まり――その瞬間を迎えるために。

コメント