2025年、京都大学の北川進特別教授がノーベル化学賞を受賞しました。
受賞理由は、世界のエネルギー問題や環境課題を解決へと導く「金属有機構造体(MOF)」の開発。
しかし注目を集めたのは、その功績だけではありません。
記者会見で語られた「つらいこともいっぱいあるが、30年以上楽しんできた」という言葉――
その穏やかな語り口に、多くの人が“心を動かされた”のです。
本記事では、北川さんの研究と人柄、そして“人を惹きつける語りの技術”をわかりやすく紹介します。
科学だけでなく、仕事や人生に通じる「伝える力」のヒントがきっと見つかるはずです。
ノーベル化学賞・北川進さんとは
2025年、京都大学の北川進特別教授がノーベル化学賞を受賞しました。
受賞理由は、環境やエネルギー問題の解決につながる革新的な新素材「金属有機構造体(MOF)」の開発です。
しかし注目されたのは、その研究成果だけではありません。穏やかで温かみのある語り口、そしてどんな質問にも笑顔で答える人柄が、多くの人の心をつかみました。
会見では「勧誘電話かと思った」とユーモラスに語り、笑いを誘う場面も。科学という難しい分野を身近に感じさせるその姿は、研究者でありながら“伝える力”を持つ稀有な人物として人々に印象づけられました。
「研究は楽しむもの」に込められた思い
会見の中で北川さんが語った言葉の中でも、多くの人の胸に残ったのが「つらいこともいっぱいあるが、30年以上楽しんできた」という一言です。
研究の世界は、結果が出るまでに長い時間を要する忍耐の連続です。思うように進まない日々や、失敗の積み重ねの中で心が折れそうになることもあるでしょう。そんな中で「楽しむ」という姿勢を貫けるのは、好奇心と情熱を失わなかった証でもあります。
北川さんの“楽しむ研究”という姿勢は、ただの楽観ではなく、「挑戦そのものを面白がる」生き方を意味しています。
どんな苦労も未来につながる経験として受け止める。その柔らかい強さが、北川さんの語る言葉をより深く響かせているのです。
このブログでは、そんな北川さんの人柄や語りの魅力、そして研究者としての哲学を通じて、私たちの日常にも通じる“伝える力”“楽しむ心”を探っていきます。
1.研究と人柄に表れる北川さんの哲学
30年以上楽しんできた──挑戦を喜びに変える力
北川進さんが語った「30年以上楽しんできた」という言葉には、研究に対する真摯な姿勢と、挑戦を恐れない強さが込められています。
研究は成功よりも失敗のほうが多く、思い通りにならないことの連続です。それでも北川さんは、「未知の現象と出会うたびにワクワクする」と語り、困難を前向きに受け止めてきました。
たとえば、金属有機構造体(MOF)の研究初期には、世界中の科学者が「そんな材料は安定しない」と否定的でした。
しかし北川さんは、分子の“つながり方”にこだわり、何度も試行錯誤を重ねる中で、ついに安定した構造を生み出しました。
この粘り強さと楽しむ姿勢が、今日の革新的な成果へとつながっています。失敗を恐れず、未知の世界に挑み続ける北川さんの姿は、まさに「研究を楽しむ」という言葉を体現しているといえるでしょう。
「また変な勧誘かと思った」──ユーモアが生む親しみ
ノーベル賞受賞の知らせを受けた際、北川さんは「最近、変な勧誘の電話が多いので、またかと思って不機嫌に出たら、アカデミーの委員長でした」と会見で語り、会場を笑いに包みました。
その場の空気を一瞬で和ませる軽やかなユーモア。これは、長年の研究生活の中で培われた“人との距離の取り方”でもあります。
学生たちからも「先生はいつも優しくて、冗談を交えながら教えてくれる」との声が多く聞かれます。
難しいテーマの議論中でも笑顔を絶やさず、時には「実験は料理と同じ。手を動かさないと味が出ないよ」と例えることもあったそうです。
この親しみやすい語り口が、厳しい研究の場でも学生たちのやる気を引き出す力となっていました。北川さんのユーモアは、単なる笑いではなく、人の心を前向きにする“エネルギー”のようなものなのです。
支えてくれた家族と仲間への感謝の言葉
北川さんが受賞会見で何度も口にしたのは、家族や仲間への感謝でした。
「同僚や学生の皆さん、海外の博士研究員、そして家族に感謝します」と語る姿からは、どれほど周囲の支えを大切にしてきたかが伝わります。
長年、海外との共同研究や学会出張が続く生活の中で、家族は陰ながら支え続けてきました。
奥様も「研究に没頭する夫を見守るのが私の役割」と語っており、その支えがあったからこそ、北川さんは安心して挑戦を続けることができたのです。
また、研究室では「失敗したら一緒に考えよう」「結果が出たらみんなの力だ」と常にチーム全体を尊重してきました。
個人ではなく“仲間と共に進む研究”を貫く姿勢が、北川さんの温かい人柄そのものです。成功を独り占めせず、支えてくれた人々と分かち合う──その姿が、受賞の喜びをさらに深いものにしているのです。
2.穏やかで人を惹きつける語りの技術
難しい話ほどやさしく伝える表現力
北川進さんは、専門的な内容でも「身近な比喩」に置き換えて説明します。たとえば、MOFを語るときに「分子の間に空気の入る余地をつくる発想」と表現します。これなら、化学に詳しくない人でも“スカスカのスポンジ”を思い浮かべられます。
会見でも、数字や専門語を並べる代わりに「ためる・選ぶ・反応させる」と三つの動詞でまとめ、聞き手の頭に“動き”として残るように工夫していました。
あなたが話すときも、専門語は一度かみ砕いてから出し、たとえば「触媒」なら「反応を手伝う助っ人」、「吸着」なら「ペタッと貼り付けて離さないイメージ」と置き換えると、相手の理解が一気に進みます。
感謝と共感で締めくくる話し方
北川さんは、話の冒頭や結びに必ず「支えてくれた家族や仲間への感謝」を置きます。これは、場の空気を柔らかくし、聞き手の“受け取る姿勢”を整える効果があります。
たとえば発表の最後に「この成果は実験を支えてくれた学生と、家で背中を押してくれた家族のおかげです」と一言添えるだけで、内容が“自分ごと”として届きやすくなります。
実務の場でも応用できます。会議の冒頭で「準備に協力してくれた皆さん、ありがとうございます」、締めに「今日の議論を明日からの小さな改善につなげましょう」と結ぶだけで、対立よりも共創を生む空気が育ちます。
ユーモア・間・問い──聴く人を動かす3つの要素
北川さんのユーモアは“自分を少し下げる”タイプです。受賞連絡を「勧誘電話かと思った」と語ることで、会場全体がほっと笑いました。
自慢話ではなく、肩の力が抜ける笑いは、すべての人を同じ土俵に乗せてくれます。
次に「間」。北川さんは早口にならず、要所で数秒の沈黙を置きます。新しい概念を言った直後に一拍置くだけで、聞き手は頭の中で“絵にする時間”を得ます。あなたも重要語の後に息を吸うだけで、伝わり方が変わります。
最後に「問い」。北川さんは「出会いを大切にすると花開く」と述べた後、断定せず余白を残します。
あなたの現場なら「この方針、現場に持ち帰るとしたら最初の一歩は何でしょう?」と投げかけて終えると、聞き手の足が自然に前へ出ます。
3.MOF研究と受賞の背景
金属有機構造体(MOF)とは何か
MOFは、金属の“点”と有機分子の“棒”を組み合わせて作る、目に見えない骨組みのような素材です。骨組みの中には、無数の小さな空洞(トンネルや部屋のような空間)が広がっています。
この空洞があるおかげで、MOFは「ためる」「選ぶ」「運ぶ」が得意です。
たとえば工場の煙に含まれる二酸化炭素だけを“選んでつかまえる”、水素ガスを“ギュッとためる”、薬の成分を“必要な場所まで運ぶ”など、暮らしや環境に直結する使い道が考えられています。
イメージとしては、超軽量で高性能な“分子サイズのマンション”。部屋の大きさや入り口の形を自由に変えられるので、入居(=取り込み)させたい分子に合わせて設計できるのが強みです。
北川さんの貢献と世界的評価
MOFの考え方が広がる前、研究者の間では「壊れやすいのでは?」という見方もありました。北川さんは、金属と有機分子の“つなぎ方”を工夫し、壊れにくく目的に合ったMOFを次々と作り出しました。
たとえば、
- 発電所や工場から出る排ガスの中から二酸化炭素だけを効率よく吸い取る設計
- 水素バスや燃料電池向けに、より多くの水素をためられる仕組み
- 台所の消臭や有害物質の除去につながる“におい”や“毒”を選んで捕まえる仕掛け
といった、生活・産業のど真ん中で役に立つ例を実験で確かめ、応用の扉を開きました。
「作って終わり」ではなく、「どう使えるか」まで丁寧に見せたことが、世界的な評価につながり、ノーベル化学賞という形で結実しました。
1.プロフィールと基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 氏名 | 北川 進(きたがわ すすむ) |
| 生年月日 | 1951年7月4日(74歳) |
| 出身地 | 三重県四日市市 |
| 学歴 | 京都大学工学部 卒業(1975年) 京都大学大学院工学研究科 博士課程修了(1980年) |
| 職歴 | 京都大学教授 → 高等研究院 特別教授(現職) 理事・副学長を歴任 |
| 専門 | 物質化学・無機化学・多孔性材料化学 |
| 主な受賞歴 | 日本化学会賞、フンボルト賞、クラリベイト引用栄誉賞など多数 |
2.家族と生活のエピソード
北川さんはプライベートでは家族を非常に大切にする研究者として知られています。
会見でも次のように語りました。
「同僚や学生、海外の博士研究員の皆さんに感謝しています。そして理解して支えてくれた家族にも感謝しています。」
研究に没頭しながらも、家庭では穏やかでユーモアのある性格だと周囲は語ります。
奥様も研究者ではありませんが、長年にわたり「家族の支え」として京都で生活をともにしてきたと報じられています。
また、お子さんは成人しており、科学とは別の道を歩んでいるとみられています。
北川さんの温かい笑顔や、電話勧誘と間違えたノーベル賞受賞連絡のエピソードも、
人柄をよく表していますね。
3.研究者としての歩み
● 若き日の京都大学時代
1970年代、京都大学では「化学構造の新しい可能性を探る」研究が盛んでした。
北川さんは当時から、“分子の間の空間”に注目する独自の発想を持っていたと言われています。
「物質の中に“空気の入る余地”を作れないか」
― この発想が後のMOF(多孔性金属有機構造体)へとつながります。
指導教官は当時、結晶化学の権威であった江口清助教授(京都大学)。
博士課程では、金属錯体化学や配位子設計に関する基礎を学びました。
● 教員としてのキャリア
- 京都大学で助手→助教授→教授と昇進し、2000年代に入ると国際共同研究に積極的に参加。
- アメリカ・バークレーのオマー・ヤギー教授(共同受賞者)とは、
1990年代後半から相互に論文引用・共同討論を重ねた仲です。 - 2007年には京都大学内に「iCeMS(アイセムス)」を設立し、
生命科学と物質科学の融合研究を推進。
この組織からは若手研究者が次々と世界へ巣立っています。
4.師弟関係と研究室文化
北川研究室は「静かな実験室」として知られ、
派手なパフォーマンスよりも粘り強く“観察と記録”を重ねる研究姿勢を重視してきました。
かつての教え子たちは次のように語っています。
「先生は怒ることがない。失敗しても“いい経験だったね”と笑ってくれる。」
「常に“面白いと思えることをやりなさい”と言われました。」
こうした研究室文化が、MOFのような創造的発想を生み出す土壌になったといわれています。
現在、彼の門下からは国内外の大学・企業に数十人の教授クラスが誕生しており、「北川スクール」と呼ばれるほどの影響力を持っています。
5.ノーベル賞受賞の意義と京都大学への影響
北川さんの受賞は、京都大学にとって山中伸弥氏以来の快挙です。
大学は以下のように声明を発表しています。
「北川教授の受賞は、京都大学が掲げる“自由の学風”の象徴であり、若手研究者に大きな勇気を与えた。」
この言葉どおり、北川さんは**「自由に考え、自由に失敗できる研究環境」**を守ってきた人でもあります。
日本の研究資金が厳しくなる中でも、
“成果を急がず、純粋に科学を楽しむ文化”を次世代へ伝えてきました。
まとめ
北川進さんの歩みは、「好きだから続けられる」「続けるから見えてくる」を体現していました。
失敗が続く日も、未知に出会うワクワクを手放さない。
難しい内容は身近なたとえで語り、要所では感謝とユーモアを添える――その積み重ねが、研究室の空気をやさしくし、周囲の力を自然と引き寄せました。
MOFという“分子サイズのマンション”は、二酸化炭素の回収や水素の貯蔵など、暮らしと地球に直結する可能性を広げています。
けれど、それを支えたのは最先端の装置だけではありません。日々の小さな挑戦を楽しむ心、仲間や家族への敬意、伝わる言葉選び――人としてのふるまいでした。
明日から私たちにできることはシンプルです。①難しい話ほどやさしい言葉に置き換える、②話の冒頭と最後に感謝と共感を添える、③大事な箇所で一拍置き、問いを残す。仕事でも学びでも、この三つを試すだけで、相手の表情と場の空気が変わります。
「つらいこともいっぱいあるが、楽しんできた」。この一言を胸に、私たちも目の前の一歩を面白がって進んでいきましょう。
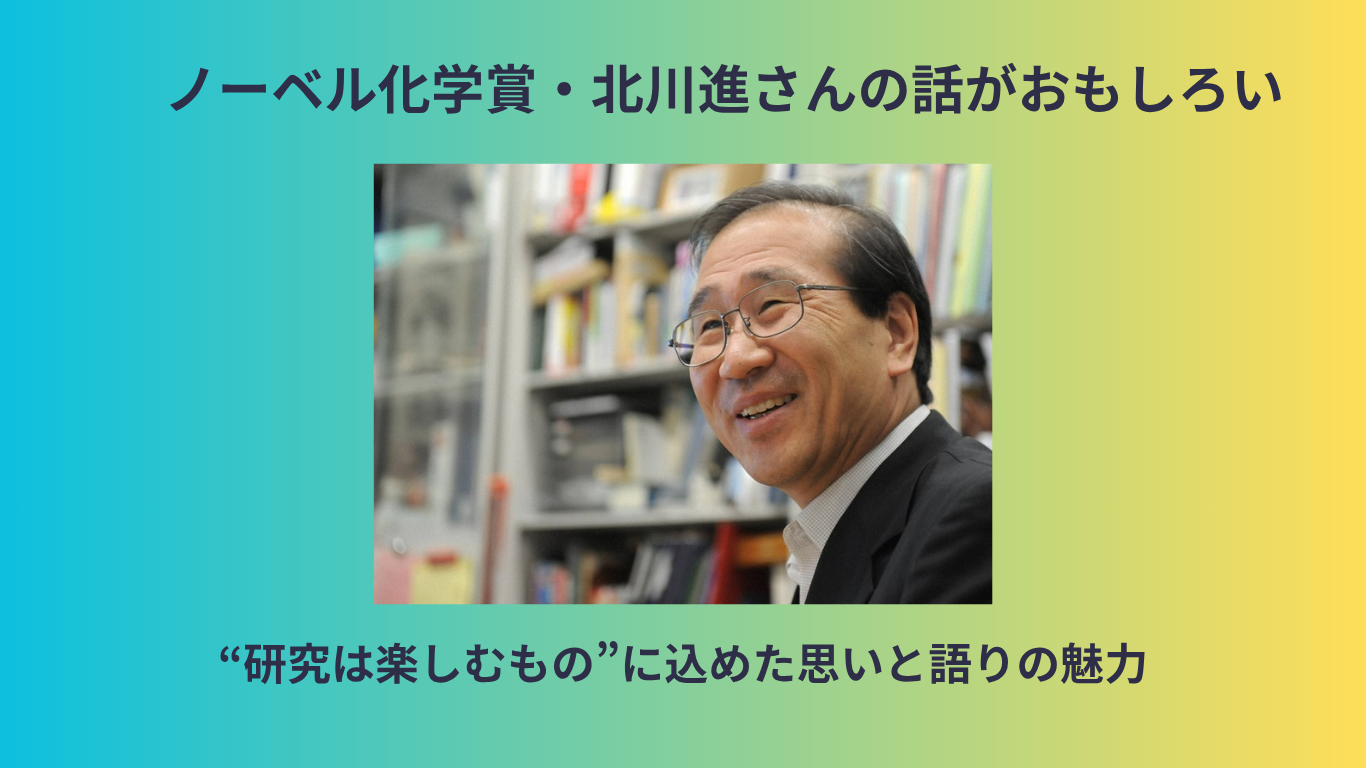
コメント