自民党総裁選をめぐる報道で、メディアへの不信感が一段と高まっています。
そのきっかけのひとつとなったのが、ある記者が会見前に発したとされる「支持率下げてやる」という言葉です。
日テレNEWSのライブ配信中に拾われたこの音声は、冗談交じりのものだった可能性が高いとされています。
しかし、視聴者の多くには「報道が世論を誘導しているのではないか」という印象を強く与え、結果的に“報道不信”に火をつける形となりました。
小泉進次郎氏「推し報道」への違和感
今回の総裁選では、テレビや新聞の多くが小泉進次郎氏に焦点を当て、連日ポジティブな論調で報じていました。
爽やかなイメージや発信力、若手らしさなどが繰り返し強調され、他候補に比べて“演出過多”と感じる声も少なくありませんでした。
SNSでは「また小泉劇場の再来か」「メディアが進次郎を“次のスター”にしたいだけでは」といった冷ややかな意見も見られました。
こうした報道姿勢の中で、記者の「支持率下げてやる」という発言が拾われたことで、「やっぱりメディアは最初から方向を決めている」という不信感が一気に広がったのです。
高市総裁囲み取材の現場と“発言者不明”の理由
「支持率さげてやる」発言は自民党 高市総裁 コメント 公明党幹部との会談をおえて ── 政治ニュースライブ(日テレNEWS LIVE)で、高市氏が登場するのを待っている記者たちの雑談が放送されてしまったものです。
この囲み取材には、自民党本部の記者クラブ(党本部記者会)に所属する主要メディアの政治部記者が一堂に会していました。
参加していたのは、NHK、日本テレビ、TBS、テレビ朝日、フジテレビ、共同通信、時事通信、読売、朝日、毎日、産経、日経など、全国紙とキー局の政治部を中心とする常駐記者たちです。
つまり、現場には複数社のマイクとカメラが並列に設置されており、拾われた声がどの記者のものかを、映像や音声のみで特定することは極めて困難です。
ライブ配信に使用された音声は、会場全体のマイク(ハウス集音)を通じてまとめられたものであり、「声が配信に乗った=日テレ記者の発言」という単純な構図ではありません。
現時点では、発言した記者の所属や個人名を確定できる一次情報は存在していません。
そのため、今回の問題は“誰の声か”よりも、“なぜその言葉が視聴者の不信を強めたのか”という点で捉える必要があります。
冗談のつもりが、世論の“象徴”に
報道現場では、待機中の雑談や軽口が交わされることも珍しくありません。
今回の発言も、そのような冗談の一環だった可能性があります。
しかし、政治報道に対して多くの国民が“偏り”や“意図”を感じている最中に発せられた言葉だけに、受け止め方はシビアでした。
ライブ配信という「生の現場」に偶然残った声が、視聴者の感情を刺激し、
「これが報道の本音ではないか」という疑念を呼び起こしたのです。
その後、配信された編集版の映像から該当部分が削除されていたことも、「隠したのでは」との憶測を呼びました。
一言の軽口が、メディアへの信頼を大きく揺るがすことになったのです。
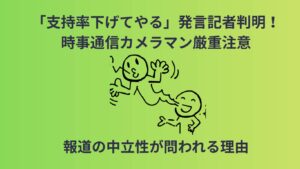
過去にもあった“報道への反発”

記者やメディア関係者の不用意な発言が批判を招くケースは、過去にも何度かありました。
たとえば、2017年には政治家への質問時に記者席からヤジのような声が入り、報道倫理が問われました。
2021年には東京五輪関連の取材で、ある報道スタッフが「もう出禁でいいだろ」と発言し、SNSで炎上。
2023年には、記者個人がSNS上で政権批判の投稿を行い、社内処分を受けた例もあります。
こうした事例はいずれも、「報道の中立性」「取材者としての節度」が問われたものであり、
視聴者が“報道の公平性”に敏感になっている現状を反映しています。
なぜ今、報道不信が強まっているのか
SNSの普及により、誰もが政治家の発言を直接視聴・共有できる時代になりました。
かつてはテレビや新聞が唯一の情報源でしたが、今ではライブ配信や個人発信が並列に存在します。
その結果、報道内容と実際の映像・文脈にズレを感じたとき、「メディアが都合よく切り取っているのでは?」という疑念が即座に生まれるのです。
報道は“正確さ”だけでなく、“透明性”を求められる時代に入りました。
どんな意図で映像を編集し、どんな言葉を見出しに選ぶのか、そのプロセスを説明しなければ、視聴者は納得しません。
視聴者が求めているのは「公平さ」と「説明」
国民が報道に求めているのは、特定の政治家を持ち上げたり、逆に貶めたりすることではありません。
誰の立場にも偏らず、事実を淡々と、正確に伝えてほしいというシンプルな願いです。
そして、もし編集や誤報があった場合には、隠すのではなく説明してほしい。
そんな“透明な報道姿勢”こそが、信頼を取り戻す唯一の道です。
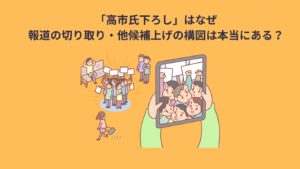
結びに
「支持率下げてやる」という一言は、発した本人にとっては何気ない冗談だったのかもしれません。
しかし、視聴者の心には“報道の本音が漏れた瞬間”として刻まれました。
メディアが自らの存在意義を問われる時代、一つひとつの言葉や編集判断が、信頼を築くか、壊すかを決めます。
いま必要なのは、政治家ではなく、報道そのものの“説明責任”なのかもしれません。
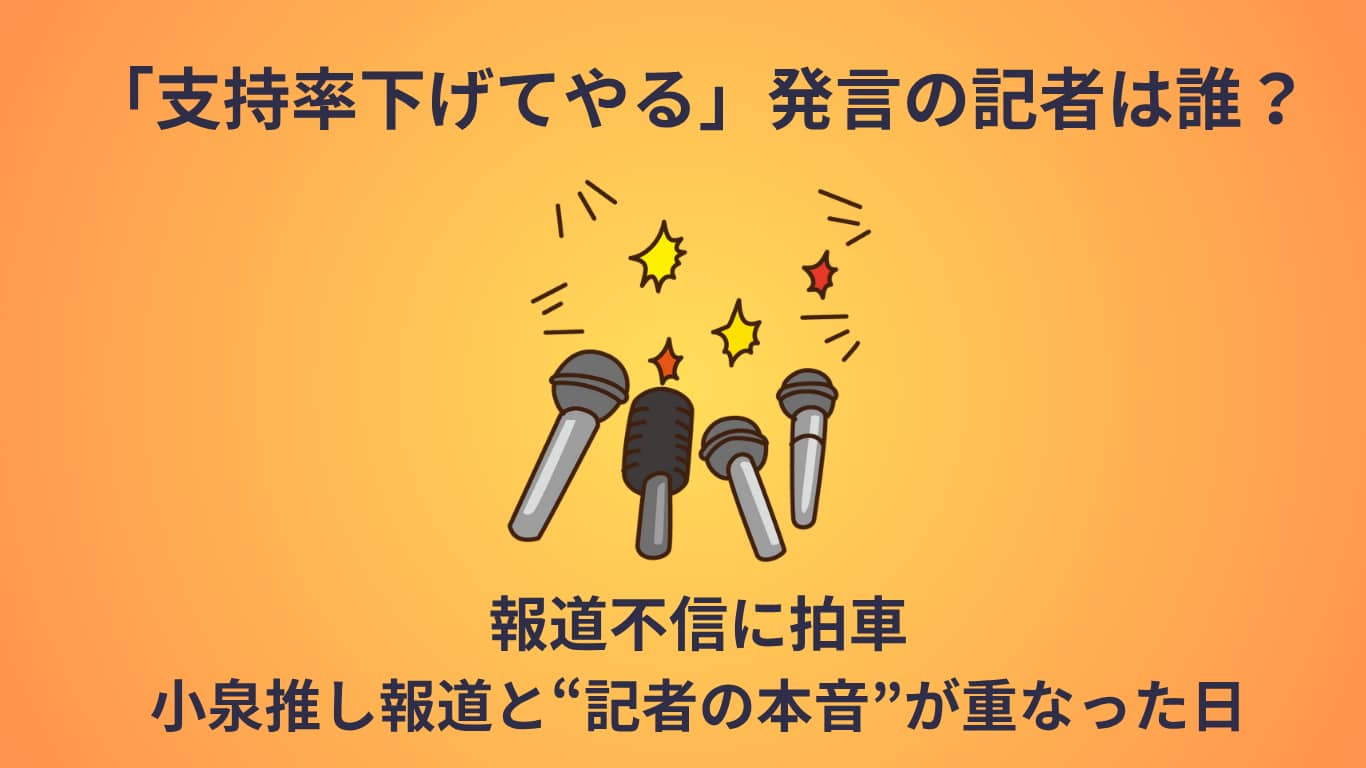
コメント