2025年10月6日、ノーベル生理学・医学賞を日本人研究者・坂口志文(さかぐちしもん)さんが受賞しました!
「免疫には攻撃だけでなくブレーキもある」という仕組みを解き明かし、花粉症や自己免疫疾患の治療法にもつながる画期的な発見として世界が注目しています。
この記事では、坂口さんの人柄や学歴、研究への姿勢、そしてノーベル賞に至るまでのストーリーを、難しい専門用語を使わずにやさしく紹介します。
はじめに
免疫の「ブレーキ」を見つけた日本人研究者・坂口志文とは
私たちの体には、細菌やウイルスと戦う“攻撃役”の免疫だけでなく、行きすぎを止める“ブレーキ役”もあります。そのブレーキ役の中心にいるのが「制御性T細胞(Treg)」という免疫細胞です。
坂口志文さんは、このTregの存在と働きを世界に示した研究者です。
たとえば、花粉症のように免疫が暴走してつらい症状が出るとき、もしブレーキがうまく効けば症状は軽く済みます。
逆に、1型糖尿病や関節リウマチのような自己免疫の病気は、このブレーキの不調が関係していると考えられています。
坂口さんの発見は、「なぜ自分の体を攻撃しないのか?」という長年の謎に、シンプルで力強い答えを与えました。
ノーベル賞に至る発見と評価の全体像
坂口さんの道のりは、一度の大発見で終わりません。まずTregという“ブレーキ役”の存在を示し、そのあと「どんな目印で見分けられるか」「本当にブレーキとして働くのか」を動物実験などで一つずつ確かめていきました。
結果として、自己免疫の病気だけでなく、アレルギー、臓器移植、さらには“がんとの戦い方”にまで発想が広がります(がんの周りではブレーキが強すぎて攻撃が弱まる、という見方です)。
こうした基礎から応用までの積み重ねが国際的に高く評価され、2025年10月6日にノーベル生理学・医学賞の受賞につながりました。
本記事では、この偉業を「基本情報」「主要業績」「受賞の歩み」「キャリア」「ノーベル賞までのストーリー」「家族・背景(公知範囲)」の順で、専門用語を避けながら整理していきます。私自身も「へえ、そうなんだ!」と驚いたポイントを、できるだけそのままの目線で書きました。
1.基本情報とプロフィール
生年月日・出身地・専門分野(1951年生まれ/滋賀県長浜市/免疫学・病理学)
1951年1月19日生まれ、滋賀県長浜市出身。専門は「免疫学」と「病理学」です。
免疫学は、体を守る仕組み(免疫)がどう働くかを解き明かす学問。病理学は、病気の“原因やメカニズム”を細胞や分子のレベルで探る分野です。
坂口さんは、この2つの視点を組み合わせ、免疫が暴走しないように働く“ブレーキ役”=制御性T細胞(Treg)に注目して研究を進めてきました。
花粉症や自己免疫の例をとると、なぜ症状が強く出る人と出ない人がいるのか——その差に「ブレーキの効き具合」が関わることを示した点が、一般の人にも分かりやすい功績です。私もここを知って「なるほど!」と腑に落ちました。
所属・肩書(大阪大学IFReCほか/名誉教授等)+人となりと研究姿勢
拠点は大阪大学・免疫学フロンティア研究センター(IFReC)。これまで京都大学などでも研究・教育を担い、現在は名誉教授の称号も有します。
肩書だけを見ると“雲の上”の研究者ですが、研究姿勢はとても現場主義です。たとえば、「免疫はなぜ自分を攻撃しないのか?」という素朴な疑問に、地道な実験を重ねて近づいていく——派手な結論を急がず、再現できる証拠を積み上げるタイプです。
臨床(医療の現場)との距離感も近く、Tregの知見を、自己免疫疾患のコントロールや移植医療、がん免疫の改善など“使える知識”に育てる視点を大切にしてきました。
読者目線で言えば、「難しいことを、具体的な病気の改善につなげる研究者」だと私は感じます。
坂口志文(Shimon Sakaguchi)とは — 基本情報・業績
名前・生年・出身地など
- 坂口 志文(さかぐち しもん / Shimon Sakaguchi)
- 生年月日:1951年1月19日
- 出身地:滋賀県長浜市(または滋賀県)
- 専門:免疫学、病理学
- 所属:大阪大学免疫学フロンティア研究センター(IFReC)など
主な業績・受賞
坂口先生は「制御性 T 細胞(Regulatory T cells, 通称 Treg)」を発見し、それらが免疫系の“抑制”や“自己寛容”(自分自身を攻撃しないように制御する機構)に果たす役割を明らかにしたことで知られています。
この発見は、自己免疫疾患、アレルギー、がんなど多くの疾患の理解・治療戦略に革命的な影響を与えるものと評価されてきました。
主な受賞歴には、以下のようなものがあります:
| 年 | 賞・栄誉 |
|---|---|
| 2004 | William B. Coley Award |
| 2008 | 慶應医学賞(Keio Medical Science Prize) |
| 2011 | 朝日賞(Asahi Prize) |
| 2015 | Gairdner 国際賞(Gairdner Foundation International Award) |
| 2017 | クラフォード賞(Crafoord Prize) |
| 2020 | ロベルト・コッホ賞(Robert Koch Prize)ほか |
| 2019 | 文化勲章受章 |
| 2025 | ノーベル生理学・医学賞受賞(本日発表) |
ノーベル賞の授与理由は、「末梢免疫寛容(Peripheral Immune Tolerance)」に関する発見、とりわけ過剰な免疫反応を抑える制御性 T 細胞の働きに関する知見であると報じられています。
学歴・キャリアの軌跡
以下は確認できている主な学歴・研究キャリアの流れです:
- 京都大学 医学部 卒業(M.D.取得、1976年)
- 京都大学 大学院(免疫学・病理学等)で Ph.D.取得(1982年)ポスドク研究:米国・ジョンズ・ホプキンス大学、スタンフォード大学などで免疫学・病理学を研究
- 1989年:Scripps 研究所 助教授 等のポジションを経験
- 日本帰国後、RIKEN、東京などで研究・教職に就任
- 1999年:京都大学 再生医科学研究所 教授就任(生体機能調節学分野など)
- 2007年:大阪大学免疫学フロンティア研究センター(IFReC)へ移籍、教員として免疫学研究を推進
- 大阪大学および京都大学で名誉教授・栄誉教授などの称号を得る
彼の研究は長年にわたり基礎から応用へと進み、制御性 T 細胞を操作することで自己免疫疾患を抑制したり、がん免疫療法の発展にも貢献する可能性があると期待されています。
家族・背景・プライベート情報(公開されている範囲で)
公開情報には限りがありますが、いくつか言及されている情報を以下に示します。ただし確証が薄いものも含まれるため、参考程度にとどめてください。
- 子どもがいるかどうか、また子どもの情報については明確には公表されていないようです。
- 坂口先生の家族構成で、父親は哲学を学んで高校教師をしていた、母親は江戸時代から医者を務めてきた家系出身、という伝聞がネット上で語られています。ただし、これらは信頼できる一次情報源での確認が不足していることに注意が必要です。
- 自宅は京都市内で二人暮らし。暇を見つけては鴨川の辺を散策している。
- また、弟さんが1型糖尿病を発症したという報道もあります(発症年齢19歳、54歳で逝去との記述あり)
- テレビのインタビューを、お兄さんが答えていました。3人兄弟。
妻・教子さんの存在
妻・坂口教子(さかぐち のりこ)(71歳)さんも同じ研究者で、今も同じ研究室で共同研究を続けてます。坂口研究室(ラボ)は計約30人の大所帯に。明るい性格の教子さんは「ラボママ」(坂口さん)として、多くの学生から慕われている。
受賞のインタビューで坂口さんは「家内と2人でやっていたようなもの。実験動物の世話や細胞の解析など、よくやってくれました」と感謝を述べています。

坂口さんのお母様は、ノーベル賞を受賞することを心待ちにしていたそうです。
以上のように、家族に関する公開情報は断片的かつ非公式なものが多いため、正確性は保証できません。
2.主要業績:制御性T細胞(Treg)の発見
何が「発見」だったのか(CD4⁺CD25⁺T細胞→Tregという概念の確立)
従来は「免疫は攻撃して守るもの」という見方が主流でした。
坂口さんは、CD4という目印を持つT細胞の中に、さらにCD25という目印で見分けられる“抑え役”の集団があることをつかみました。これが制御性T細胞(Treg)です。
ポイントは「単なるおとなしい細胞」ではなく、周りの免疫細胞の暴走を能動的に止める専門部隊だと示したこと!
たとえば、マウスからTregを取り除くと、体中で自己免疫反応が起こり、臓器に炎症が広がります。
逆にTregを戻す(増やす)と症状が収まる——この“入れる・抜く”で機能を証明したことが、概念を一気に確立させました。実験でスッと答えを出す感じが、すごく気持ちいいです。
免疫寛容・自己免疫・がんへのインパクト
Tregの働きは、私たちが自分の体を誤射しない「免疫寛容」の土台です。身近な例でいうと、
- 自己免疫疾患(1型糖尿病、関節リウマチなど)では、Tregの数や働きが足りない・質が落ちるとブレーキ不全が起きます。Tregを整える発想は、症状のコントロールに直結します。
- アレルギー(花粉症、食物アレルギーなど)でも、過剰反応を静める役としてTregが関与します。Tregが育つように誘導できれば、反応を和らげられる可能性があります。
- 臓器移植では、移植した臓器を“敵”と見なさない状態(免疫寛容)をつくる鍵として、Tregの利用が注目されています。
- がん免疫は少し逆で、腫瘍の周りにはTregが多く集まりがちで、免疫の攻撃を弱めてしまいます。ここではTregの“効きすぎ”をピンポイントで緩めると、からだ本来の抗がん力を引き出せる——という発想につながります。
このように、Tregは「足りなければ補う、強すぎればゆるめる」という双方向の調整で医療応用の扉を開きました。家庭のブレーキ調整みたいで、わかりやすいですよね。
代表論文・キーワード(FOXP3/末梢免疫寛容/転用可能性)
TregをTregたらしめる“設計図スイッチ”として知られるのがFOXP3(フォックスP3)という遺伝子です。
FOXP3がうまく働かないと、重い自己免疫症状が出ることが知られており、Tregの正体と重要性を裏づける強力な証拠になりました。関連キーワードは以下のとおりです。
- FOXP3:Tregの性質を決めるスイッチ(転写因子のことですが、ここでは“性格を決める合図”くらいの感覚でOKです)。
- 末梢免疫寛容:胸にある臓器(胸腺)の“選別”を抜けた後も、体のあちこち(末梢)で自己攻撃を抑える仕組み。Tregが主役です。
- 転用可能性(トランスレーショナル):自己免疫・アレルギー・移植・がん免疫など、病気の現場に橋渡しできる汎用性。
代表論文群は、CD25でTregを見分けた初期研究、Tregが炎症を抑えるしくみの解明、FOXP3の役割を遺伝の面から示した仕事へと段階的に発展しました。
難解な理屈を積み木のように積み上げ、最終的に「免疫にはブレーキ系がある」という、医療に役立つシンプルな地図を描ききったのが坂口さんの最大の功績だと、私は受け止めています。
3.受賞歴と評価の累積
国内外の主な賞(朝日賞/慶應医学賞/文化勲章 ほか)
坂口さんの研究は、専門家だけでなく一般社会からも高く評価されてきました。
たとえば朝日賞(2011年)は、社会や文化に大きく貢献した業績に贈られる日本の代表的な賞です。ニュースで目にすることも多いので、ご存じの方もいるはず!
医療現場の課題に直結するTregの発見が、学術を超えて社会的価値を持つと認められた証しです。
また慶應医学賞(2008年)は、医学分野の先駆的な研究に与えられる賞。基礎研究が将来の治療にどのように結び付くか——その“橋渡し力”が評価されました。
そして文化勲章(2019年)。これは日本の文化発展に特に功績のあった人に贈られる最高位の栄誉の一つです。難しい研究を、病気の理解や治療の発想にまで押し広げたことが、国の誇りとして認められたと言えます。一般市民としても、こういう受賞ニュースは本当にうれしいです。
国際的前哨戦と称される賞(Gairdner・Crafoord・Robert Koch)
科学の世界では、「この賞に選ばれると、将来ノーベル賞に近づく」と語られる国際賞があります。
代表がGairdner国際賞(2015年)。医学・生命科学の分野で影響力の大きい研究に贈られ、過去の受賞者から多数のノーベル賞受賞者が出ています。Tregという“免疫のブレーキ”の発見が、世界の医療の常識を変え始めているという強いサインでした。
Crafoord賞(2017年)はスウェーデン王立科学アカデミーが授与する賞で、ノーベル賞の対象外分野も広くカバーします。免疫の制御という難題に対し、理屈だけでなく実験で確かめる姿勢が国際的に評価されました。
さらにドイツのRobert Koch賞(2020年)。感染症や免疫の研究に与えられる権威ある賞で、基礎から応用へと広がる“使える発見”としてTreg研究が注目されたことを物語ります。
これらの国際賞は、坂口さんの仕事が“日本発の成果”から“世界の共通財産”へ育っていった過程を示しています。私もニュースの見出しを追いながら、ワクワクしていました。
2025年ノーベル生理学・医学賞の授与理由と意義
そして2025年10月6日、ついにノーベル生理学・医学賞が発表されました。
授与理由は簡単に言えば、「体が自分を攻撃しないための仕組みを解き明かした」こと。
具体的には、免疫の暴走を止める制御性T細胞(Treg)の存在と働きを示し、私たちが日々健康を保つ“見えないブレーキ”の実像に迫った点が高く評価されました。
この意義は、診断や治療の発想を根本から変えるところにあります。たとえば、
- 自己免疫の病気では「ブレーキを整える」治療へ、
- アレルギーでは「過剰反応を静める」工夫へ、
- 移植医療では「拒絶反応を起こしにくい体内環境」づくりへ、
- がんでは逆に「ブレーキの効きすぎを一時的にゆるめる」戦略へ。
“足りなければ補い、効きすぎなら和らげる”というシンプルな考え方で、病気ごとに最適な方向へ舵を切れる——それがTregの発見が持つ、だれにとっても分かりやすい価値です。こういう発想って、生活の知恵にも通じますよね!
まとめ
坂口志文さんの仕事は、「免疫には攻撃だけでなくブレーキがある」という、ごく当たり前でいて実は誰も説明できていなかった事実を、実験で一つずつ確かめて地図に描いた点に尽きます。
ブレーキ役=制御性T細胞(Treg)を見つけ、その見分け方と働きを示したことで、私たちは病気を“強く叩く”だけでなく、“ちょうどよく整える”という選択肢を手に入れました。
実生活へのイメージを挙げると――
- 自己免疫の病気:壊れたブレーキを直す(Tregを増やす・育てる)発想で、症状を和らげる道が開ける。
- アレルギー:花粉症の“過剰な反応”を、Tregを育てる工夫で静める可能性。
- 移植医療:拒絶を“押さえ込む薬を増やす”から、“からだの中の和解を促す”方向へ。
- がん:がんの近くで効きすぎるブレーキを一時的にゆるめ、からだ本来の攻撃力を取り戻す作戦へ。
今後の課題は、(1) 精密制御(どの臓器・どの場面でどれくらいブレーキを効かせるか)、(2) 安全性(感染症やがんのリスクを上げない工夫)、(3) 個別化(人それぞれの体質や病気の段階に合わせた調整)の3点。言い換えれば、“ブレーキの調律”です。
アクセルとブレーキのバランスを人ごと・病気ごとに最適化できたとき、医療はさらにやさしく、確かに前進します。私も家族の健康を思いながら、この視点を大切にしたいと思いました。
Tregの発見は、難解な免疫学を「体の中の交通ルール」にたとえられるほど身近にしました。
強すぎる信号は弱め、足りない信号は補う――その考え方は、自己免疫・アレルギー・移植・がんという違う領域を一本の線で結びます。
坂口さんのノーベル賞は、その線が世界の医療にとって共通言語になったことの証しと言えるでしょう。ここまで読んでくださって、ありがとうございました!
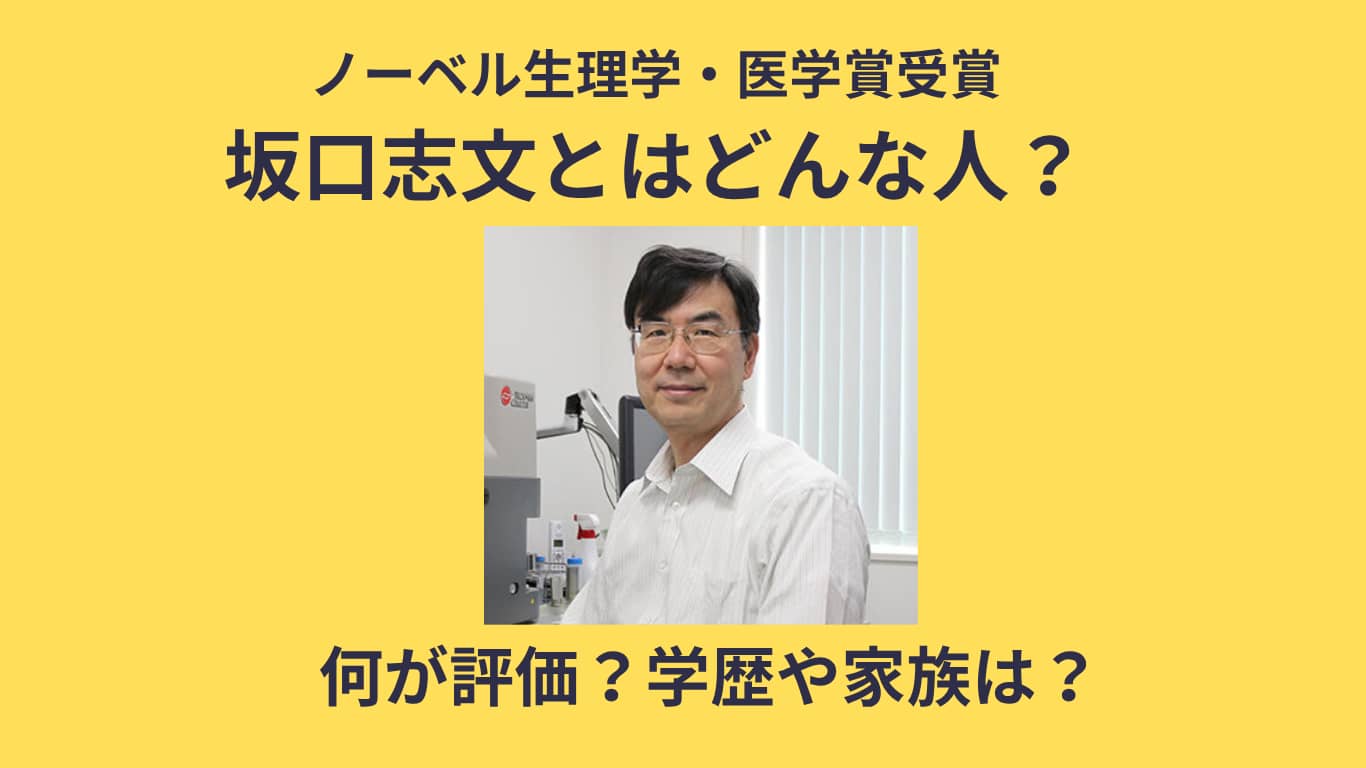
コメント