「笑いの演出」か「配慮不足」か──評価が割れたのが、萩本欽一さんによる女性審査員への強めのツッコミでした。
24時間テレビ2025のスタジオでは、進行の都合でコメントを短く求める場面が続き、受け取り方に差が出たようです。
本追記では、問題となったやり取りを時系列で振り返り、SNS反応の傾向、そして“テンポと配慮”を両立させる演出のヒントをまとめます。
※が義本欽一さんと24時間テレビの関係を語るうえで、欽ちゃんの人柄を表しているとして、以下のようなエピソードがネットでも投稿されています。
「初代司会のギャラを1億円まで釣り上げ、全額寄付して引き受けた」
2017年3月に読売テレビ『マヨなか芸人』で、萩本欽一さんの後輩である「ずん」飯尾和樹さんらが語った“伝説”紹介です。スポーツ紙がそれを記事化し、「初代総合司会のギャラは1億円で“全部チャリティーに回してくれ”と頼んだ」と伝えました。
以後、週刊系サイトなど複数メディアが同内容を“逸話”として再掲していますが、日本テレビや萩本さん本人の公式証言・文書は確認できません。したがって、裏取りの取れた史実というより“関係者の語りに基づく話”とみるのが妥当です。
はじめに

萩本欽一と『24時間テレビ』の長年の関わり
萩本欽一さんは『24時間テレビ』にとって欠かせない存在です。1978年の初回放送では総合司会を務め、番組のスタートダッシュを支えました。
2007年にはチャリティーマラソンに挑戦し、視聴者に感動を届けた経験もあります。長い年月の中で番組の顔ともいえる役割を果たし、「欽ちゃんがいるから24時間テレビを見てきた」という声も少なくありません。
まさに功労者といえる立場ですが、その一方で時代の変化とともに彼の芸風が注目される場面も増えてきました。
放送中に巻き起こった態度への批判
2025年の『24時間テレビ48』に出演した萩本さんの態度がSNSで物議を醸しました
。特に「全日本仮装大賞」の特別版で、審査員やゲストに対して「話が長い!」とツッコミを入れる姿が「威圧的」と受け取られたのです。
例えば、プロ卓球選手の伊藤美誠さんがコメントを始めた途端に遮ってしまう場面や、司会の上田晋也さんへの厳しい指摘が印象に残った人も多かったようです。
番組を盛り上げようとする意図があったとしても、視聴者の中には「見ていて不快」「時代に合っていない」と感じる人が多く、X(旧Twitter)では批判的な投稿が相次ぎました。功労者としての重みと、現代の感覚とのズレが浮き彫りになった瞬間でした。
1.萩本欽一の出演シーンと問題視された場面
「全日本仮装大賞」特別版でのやり取り
『24時間テレビ48』では、長年人気を博してきた「全日本仮装大賞」が特別版として登場しました。
萩本さんは司会席で進行を担当し、名物企画「ピンポン」の特別演出も披露されました。
会場には香取慎吾さんの姿もなく、萩本さん自身が中心となる形で進行しましたが、その際のコメントややり取りが大きな注目を集めました。
普段なら「欽ちゃん流の軽妙なツッコミ」として笑いに変わるやり取りが、この日ばかりはピリッとした空気を作ってしまったのです。
ゲストや審査員への厳しいツッコミ
審査員席には上田晋也さんや浜辺美波さん、アンミカさん、大久保佳代子さんら、豪華な顔ぶれが並んでいました。
ところが、萩本さんは「時間がないから」と前置きしつつ、審査員のコメントにすぐ「長い!」と突っ込みを入れるスタイルを徹底しました。
特に、卓球の伊藤美誠選手が真剣にコメントしようとした場面で話を遮ってしまったことは、視聴者に強い印象を残しました。
周囲の出演者も空気を察し、羽鳥慎一さんが慌ててフォローに回ったり、大久保さんが意識的にコメントを短くまとめたりする様子が映し出され、スタジオ全体に緊張感が漂いました。
SNSで広がった「威圧的」との指摘
こうした場面はすぐさまSNSで拡散されました。Xでは「威圧的で見ていて苦しくなる」「昔のノリがもう通じていない」といった声が続出しました。
中には「欽ちゃんだから許される空気ではなくなっている」と指摘する投稿もあり、番組全体の雰囲気を損なったと感じる人も多かったようです。
一方で、「笑いを作ろうとしただけ」「昔から変わらない欽ちゃんらしさ」と受け止める人もいましたが、批判的な声の方が目立ちました。この一件は、視聴者が求める笑いの形が変わりつつあることを浮き彫りにしたとも言えるでしょう。
2.功労者としての存在と時代の変化
『24時間テレビ』の歴史と欽ちゃんの貢献
萩本欽一さんは『24時間テレビ』の立ち上げから関わり、初回の総合司会として番組の方向性を作り上げました。
深夜帯を含む長時間の生放送をまとめる進行力や、視聴者の心をつかむコメント力は当時から高く評価されていました。
さらに2007年には60歳を超えてチャリティーマラソンに挑戦し、走り切る姿に多くの人が胸を打たれました。こうした実績から、萩本さんは番組の「功労者」として今も特別な存在感を放っています。
昔ながらの“イジり芸”と現在の視聴者感覚のギャップ
一方で、長年の代名詞ともいえる“イジり芸”が、現代では受け止められ方を変えています。かつては『スター誕生!』などで素人や新人を軽妙にいじり、場を盛り上げていました。
しかし現在の視聴者は「笑い」よりも「人への配慮」を重視する傾向が強まっています。
例えば、誰かが真剣に話している最中に「長い!」と遮る行為は、昔ならテンポのよいツッコミとして笑いに変わったかもしれませんが、今では「失礼」「威圧的」と受け止められやすいのです。
このギャップこそが、今回の批判につながった大きな要因といえるでしょう。
コンプライアンス時代における芸風のリスク
現在のテレビ業界はコンプライアンスへの意識が非常に高まっています。過度なイジりや人を傷つける発言は、視聴者やスポンサーから厳しくチェックされ、すぐに炎上につながるリスクを抱えています。
萩本さんの芸風は「相手を立てながら笑いを生む」スタイルでもありましたが、線引きが難しい場面では「不快」「威圧的」と映ってしまう危険性があります。
特にSNSが瞬時に反応を拡散させる現代では、ひとつの言葉が大きな波紋を広げることも珍しくありません。
長年の経験を持つ功労者だからこそ、その芸風が時代の変化とぶつかりやすい状況に置かれているのです。
3.世間の反応と多様な見方
SNSやヤフコメでの批判的意見
放送直後、X(旧Twitter)やポータルサイトのコメント欄には「見ていて息苦しい」「ゲストの話を遮るのは失礼」といった声が多く並びました。
具体的には、①伊藤美誠選手のコメントを遮った場面、②審査員の感想にすぐ「長い!」と返した場面、③司会の流れを止めるような強めの口調――この3点が「威圧的」と受け取られやすかったようです。
一方で、当日のスタジオの空気感を知らない視聴者には厳しめに映りやすい、という指摘もありました。
いずれにせよ、「笑いのための一言」が、受け手により「不快な一言」に変わりうることを、多くの投稿が示していました。
「芸風の問題ではなく企画や周囲の対応」という擁護の声
擁護側の意見で目立ったのは、「欽ちゃんは昔からあのテンポ。企画サイドが活かし方を誤ったのでは」という見方です。
たとえば、
- コメントを短く切る役回りを最初から“合いの手”として明示しておく
- ゲストが話すブロックと、欽ちゃんがテンポを上げるブロックを分ける
- ツッコミの直後にMCやナレーションで“フォローの一言”を重ねる
といった演出上の工夫があれば、同じ発言でも「トゲ」より「テンポ」として受け取られたのでは、という具体的な提案が複数見られました。つまり、個人の芸風よりも“見せ方の設計”に課題があった、という立場です。
高齢芸能人の立ち位置と今後への期待
今回の議論は、ベテランの“看板芸”と令和のテレビ空気のすれ違いを映し出しました。
たとえば、
- ベテランの持つ“スピード感のある仕切り”を、若手MCの穏やかな視界誘導で包む
- 「鋭い一言」の後に、相手の意図を汲む“補足のひと言”を必ず乗せる
- 生放送ではなくVTR主体にし、編集でテンポと配慮のバランスを整える
などの形で、経験と時代感覚を橋渡しする方法はあります。
視聴者が求めているのは、誰かを傷つける笑いではなく、場を温めるキレのよさ。長年テレビを支えてきた功労者の存在感を尊重しながら、演出や段取りで“やさしいテンポ”へ調整していく――それが、多くの読者が期待する「次の一歩」だと感じます。
まとめ
今回の騒動は、「功労者の看板芸」と「令和のテレビ空気」のすれ違いがはっきり見えた出来事でした。
萩本欽一さんは『24時間テレビ』の歴史を作ってきた存在であり、その瞬発力あるツッコミは長所でもあります。
一方で、ゲストの言葉を遮る・強い口調で畳みかける――といった“昔のテンポ”は、いまの視聴者には「不快」「威圧的」と受け取られやすい場面があることも事実です。
番組側ができる具体策はシンプルです。
①「短評役」と「じっくりコメント役」を最初から役割分担する、②ツッコミの直後にMCが“補足のひと言”で空気を和らげる、③生放送ではなくVTR構成を増やし編集で配慮を担保する、④ゲストが話すブロックは“遮らない”ルールを明示する――こうした見せ方の設計だけで、笑いのキレと人への配慮は両立できます。
視聴者が望むのは、誰かを傷つけないテンポのよさです。
ベテランの経験値を尊重しつつ、時代に合わせた“やさしいテンポ”へ。制作側の段取りと演出の工夫、そして出演者同士の思いやりがあれば、功労者の魅力は今後も十分に活きます。
次の『24時間テレビ』では、笑いも配慮もある「気持ちのいいテンポ」で、誰も置き去りにしない時間を期待したいところです。
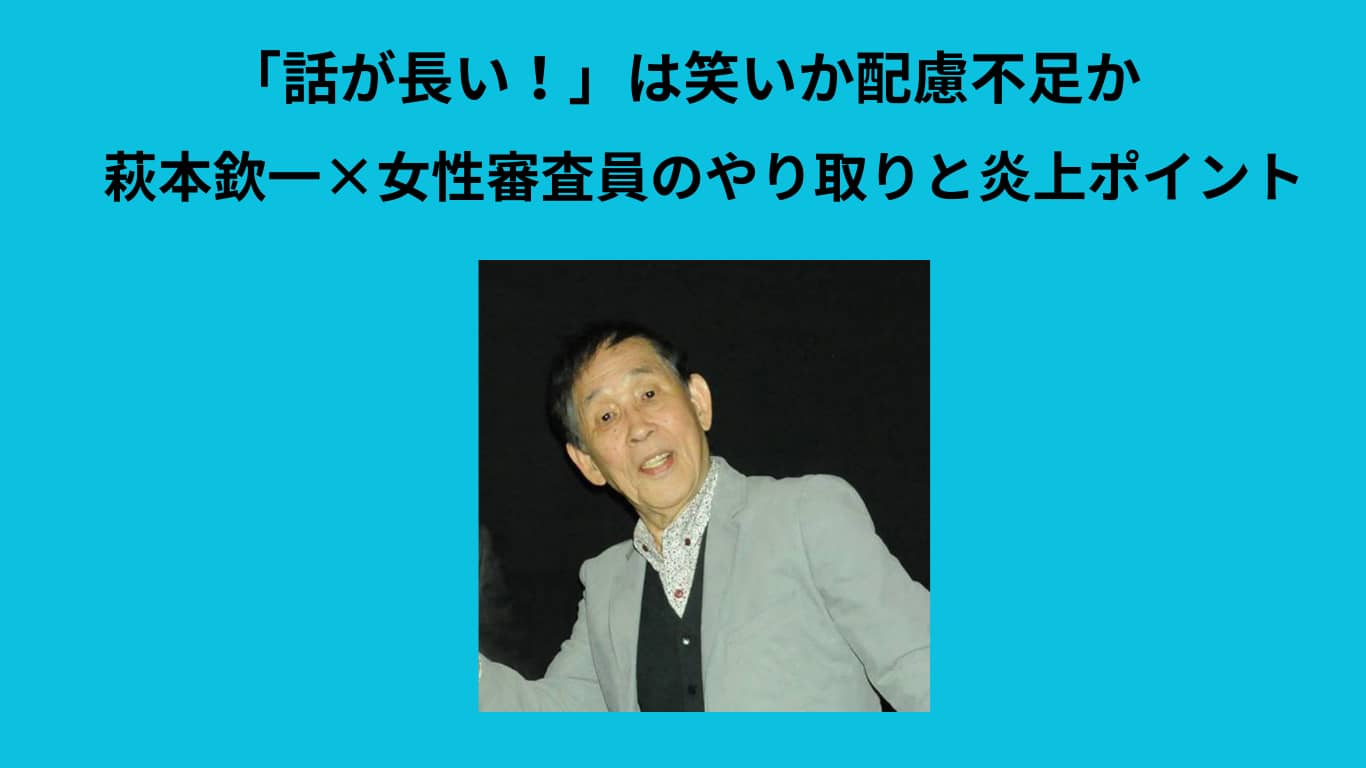
コメント