もし夫や妻を亡くしたら、あなたの生活はどうなりますか?
遺族厚生年金の制度が2028年4月から大きく変わります!
今回の改正は男女差を解消する大きな一歩ですが、一部の方にとっては受給期間が短縮されるなど影響もあります。特に「子どものいない30歳以上60歳未満の専業主婦(または夫)」は注意が必要です。
この記事では、改正の内容・専業主婦への影響・誤解しやすいポイントを、誰にでもわかるようにまとめました。
全国対応型:2028年4月からの遺族厚生年金改正とは?
2028年4月から、遺族厚生年金の制度が全国的に大きく変わります。
特に注目されているのは「子どものいない配偶者は5年で支給が終了する」という新ルールです。
これまで無期限で受給できていた方が、ある日突然「5年で終了」と聞けば、不安に感じてしまいますよね…。
今回の記事では、全国のどこにお住まいの方でも理解しやすいように、初心者向けにわかりやすく解説しています。
- 改正の背景と目的(男女差解消の視点)
- 誰がどんな影響を受けるのか(専業主婦・共働き世帯別)
- 誤解されやすい「子のいない」の定義と注意点
- 改正後に考えておきたい生活設計の見直しポイント
全国対応型で制度変更の全体像を理解できる記事になっていますので、ぜひ最後までお読みいただき、あなたやご家族の生活にどのような影響があるのかを確認してください。
| 区分 | 改正前 | 改正後(2028年4月〜) |
|---|---|---|
| 子のない30歳以上の妻 | 無期限で受給 | 5年で終了(有期給付) |
| 子のない55歳未満の夫 | 受給なし | 5年で開始(有期給付) |
| 子のいる配偶者 | 従来通り(長期受給) | 従来通り(長期受給) |
| 子のない60歳以上の妻・夫 | 従来通り(無期限受給) | 従来通り(無期限受給) |
※「子のいない」は18歳以下の子がいない場合を指します。成人した子どもは該当しません。
遺族厚生年金改正の背景
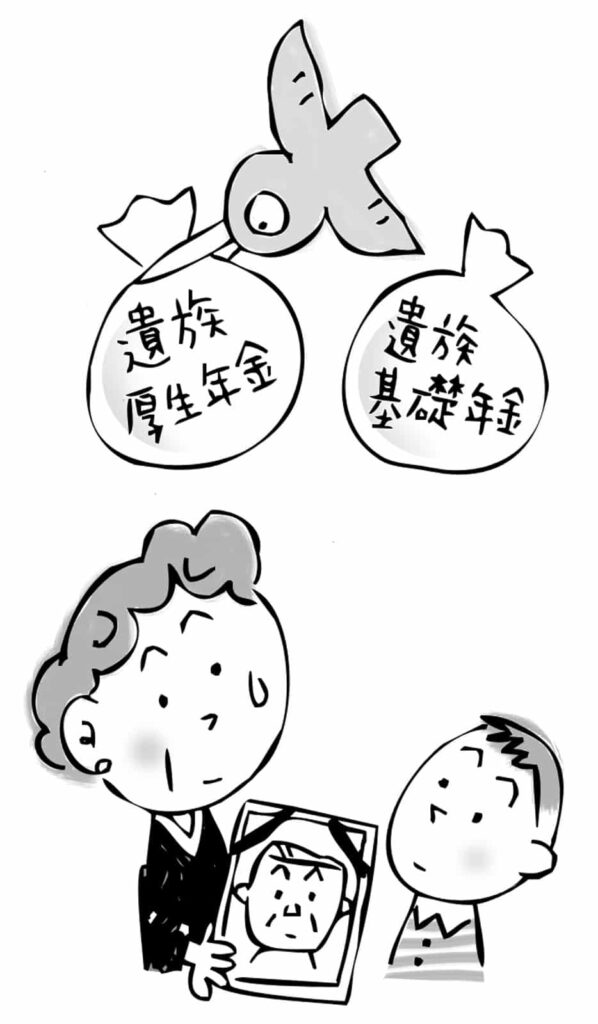
遺族厚生年金は、配偶者を亡くした方が生活の安定を維持するために支給される年金制度です。
これまでは「夫が亡くなった場合」と「妻が亡くなった場合」で受け取れる条件が大きく異なっていました。
例えば、夫を亡くした妻は年齢や子どもの有無によって無期限で受給できる場合が多かったのに対し、妻を亡くした夫は55歳未満だと1円も受け取れないというケースがありました。
こうした男女差に対する不公平感は、特に共働き世帯の増加や、妻の方が収入が多い家庭にとって大きな課題でした。
こうした背景を受けて、2028年4月から遺族厚生年金の受給条件が大きく変わる予定です。
今回の改正は、性別による条件の違いを解消し、男女平等の観点から制度を見直すことを目的としています。
改正により何が変わるのか
改正の大きなポイントは「子のない配偶者」への扱いです。
これまでは、30歳以上の妻であれば無期限に遺族厚生年金を受給できましたが、改正後は夫・妻ともに60歳未満であれば原則5年間だけの支給になります。
一方で、60歳以上であればこれまで通り無期限で受給できます。
さらに、これまであった「年収850万円未満」という収入要件は廃止され、受給できる人が増える見込みです。加えて、年金額の増額も行われるため、一定の条件に該当する人にとっては家計の助けになる場合もあります。
ただし、「子のない」という言葉は「18歳以下の未成年の子どもがいない」という意味であり、成人した子どもがいる場合は「子のない」に分類されるため注意が必要です。
このあたりの理解を誤ると「私は子どもを産んだのに対象外なの?」という誤解を招きやすいのです。こうした制度の細かな部分も含め、今回の改正が生活にどのような影響を与えるのかを丁寧に見ていきます。
1.遺族厚生年金はどう変わる?
男女差解消を目的とした改正内容
これまでの遺族厚生年金は、妻と夫で受け取れる条件に差がありました。例えば、夫を亡くした30歳以上の妻は無期限で遺族年金を受け取れる一方で、妻を亡くした55歳未満の夫は受給資格がなかったのです。
この差は「妻は専業主婦であることが多い」という前提で作られた制度でした。
しかし近年は、妻が正社員として働き、夫が家事や育児を担う家庭も増えています。こうした社会の変化を踏まえ、2028年4月からの改正では「男女で差をつけない」ことが重視されました。
具体的には、子どものいない配偶者が60歳未満の場合、妻であっても夫であっても原則5年間だけの受給に統一されます。一方で、60歳以上であれば無期限での受給が継続されます。
この改正により、従来「夫だから年金はもらえない」という不公平は解消されますが、同時に「無期限で年金を受け取れていた一部の妻」が有期に変更されるという影響も生じます。
子のない配偶者への影響
今回の改正で最も影響を受けるのは、「18歳以下の子どもがいない30歳以上60歳未満の配偶者」です。
たとえば、これまで夫を亡くした45歳の妻は無期限に年金を受給できましたが、改正後は5年で打ち切られる可能性があります。
ただし「5年で必ず打ち切り」というわけではなく、病気や障害がある場合、あるいは収入が極端に少ない場合など「配慮が必要なケース」では、5年目以降も継続して受け取れることがあります。
また、これまで受給資格がなかった55歳未満の夫も、5年間は受給できるようになります。
例えば、30代で妻を亡くした夫は従来ゼロ円でしたが、改正後は5年間だけでも支給されるようになるため、男女間の格差は縮まることになります。
その他の変更点(収入要件廃止・年金額増額)
今回の改正は、受給期間の見直しだけではありません。
これまで「有期給付を受け取るには年収850万円未満であること」という条件がありましたが、この条件が撤廃されます。つまり、比較的高収入の世帯であっても遺族年金を受け取れるようになります。
さらに、支給される年金額そのものも増額されます。
たとえば、月に15万円だった受給額が16万円になるなど、生活費の補填としての役割がより大きくなることが期待されます。このため、受給期間が5年に限定されても、その間の家計を助ける効果は高くなります。
このように、今回の改正は男女平等を実現する大きな一歩である一方、生活設計の見直しが必要になる家庭も出てくる可能性があります。
2.専業主婦への影響は?

年齢別・子の有無による違い
今回の改正は、特に専業主婦として家庭を支えてきた方に大きな影響を与える可能性があります。
たとえば、夫と死別した時に18歳以下の子どもがいる場合は、これまで通り長期間の受給が可能です。しかし、子どもがすでに成人している、あるいはもともと子どもがいない場合は注意が必要です。
30歳未満の専業主婦の場合、改正前後で受給条件に大きな違いはなく、5年間の受給が基本です。
一方で、これまで無期限で年金を受け取れていた30歳以上60歳未満の専業主婦は、原則として5年間に制限されます。
たとえば、夫を亡くした45歳の専業主婦は、これまで生活費を安定的に補っていた遺族年金が5年で終了することになります。
60歳以上であれば従来どおり無期限で受給できるため、年齢によって大きく条件が異なる点が特徴です。
5年有期給付化で影響を受けるケース
改正の影響を強く受けるのは、子どもがいない30歳以上60歳未満の方です。
これまで無期限で頼りにしていた年金が5年で終了することで、生活設計の見直しが必要になるでしょう。
たとえば、長年専業主婦として働いてこなかった方が急に収入を得るのは簡単ではありません。パートに出る、資格を取るなどの準備を早めに進める必要があります。
一方で、これまでまったく受給できなかった夫側には一定のプラス効果があります。
たとえば、55歳未満で妻を亡くした夫は以前なら受給ゼロでしたが、改正後は5年間の年金を受け取れるようになります。
男女差は解消されますが、受給期間が短縮される妻側にとっては痛手となるケースも少なくありません。
配慮措置と段階的実施のポイント
「5年で終わり」と聞くと不安になる方も多いですが、全員が一律に打ち切られるわけではありません。
病気や障害で働けない場合、あるいは生活に大きな困難がある場合は、5年目以降も支給が継続される「配慮措置」が設けられています。
たとえば、夫を亡くして体調を崩し、仕事に就けない状況にある場合は、この措置に該当する可能性があります。
また、この改正は2028年4月に開始されますが、一部の女性については20年かけて段階的に実施されます。
2028年度末時点で40歳以上になる女性(子のいない妻)は無期限受給のまま据え置かれるため、すぐに影響を受けるのは比較的若い世代に限られます。
このように、年齢や家族構成によって影響は大きく異なるため、自分がどの条件に該当するかを確認しておくことが重要です。
3.よくある誤解と注意点
「子のいない」とはどういう意味?
今回の改正内容でよく誤解されるのが、「子のいない配偶者」という表現です。
「私は子どもを産んでいるのに、なぜ『子のいない』に分類されるの?」と感じる方もいますが、制度上の「子」とは18歳以下の未成年の子どもを指します。すでに成人して独立している子どもがいる場合は、制度上は「子のいない」に該当します。
例えば、子育てを終えた50代の専業主婦が夫と死別した場合、子どもがすでに成人していれば制度上は「子のいない配偶者」とされ、今回の改正により原則5年間の有期給付となります。
この定義を誤解してしまうと、自分がどの区分に該当するのかを間違えて認識してしまう恐れがあります。
配慮が必要な場合とは?
「5年で打ち切り」というルールに不安を感じる方は少なくありませんが、すべての人が一律で終了するわけではありません。
配慮が必要な場合、5年目以降も年金を受け取り続けられる場合があります。たとえば、病気や障害で働けない方、または小さな子どもや要介護の家族を抱えていて就労が困難な場合がこれに該当する可能性があります。
ただし、配慮の基準は一律ではなく、具体的な判断はケースごとに行われます。そのため、該当する可能性があると感じた場合は、早めに年金事務所などに相談することが重要です。
改正で注意すべきポイントと生活設計への影響
今回の改正は、男女平等を実現するという大きな意味がありますが、同時に受給期間の短縮という現実的な影響も伴います。
特に「これまでは無期限に年金を受け取れる」と考えて生活設計を立てていた30歳以上60歳未満の専業主婦は、収入計画を見直す必要があります。
例えば、これまでは遺族年金を頼りにパートに出る必要がなかった方も、5年後には収入が途絶えることを想定して働き方を検討する必要があります。
また、改正の影響を受けない層(2028年度末時点で40歳以上になる女性)との間で「なぜ自分だけ有期なのか」と感じることもあるでしょう。こうした差を理解したうえで、早めにライフプランを考え直すことが大切です。
まとめ
2028年4月から始まる遺族厚生年金の改正は、男女間の不公平を解消する大きな一歩となる一方で、受給期間が短縮される世帯にとっては生活設計の見直しを迫られる内容でもあります。
特に、これまで無期限で支給されていた30歳以上60歳未満の「子のいない妻」が5年の有期給付となる点は大きな変化です。
一方で、これまで遺族年金を受給できなかった若い夫に新たな支給の道が開かれるなど、男女双方に影響があります。
また、「子のいない」という言葉が18歳以下の未成年の子どもを指していること、病気や障害など就労が難しい場合には継続受給できる配慮措置があることも押さえておくべきポイントです。
影響を受けるかどうかは年齢や家族構成により異なるため、自身の状況を確認したうえで、今後の生活設計を早めに立て直すことが大切です。
制度は変わりますが、理解を深めることで不安を減らし、必要な対策を講じることができます。今回の改正をきっかけに、もしもの時に備えたライフプランを考えてみてはいかがでしょうか。
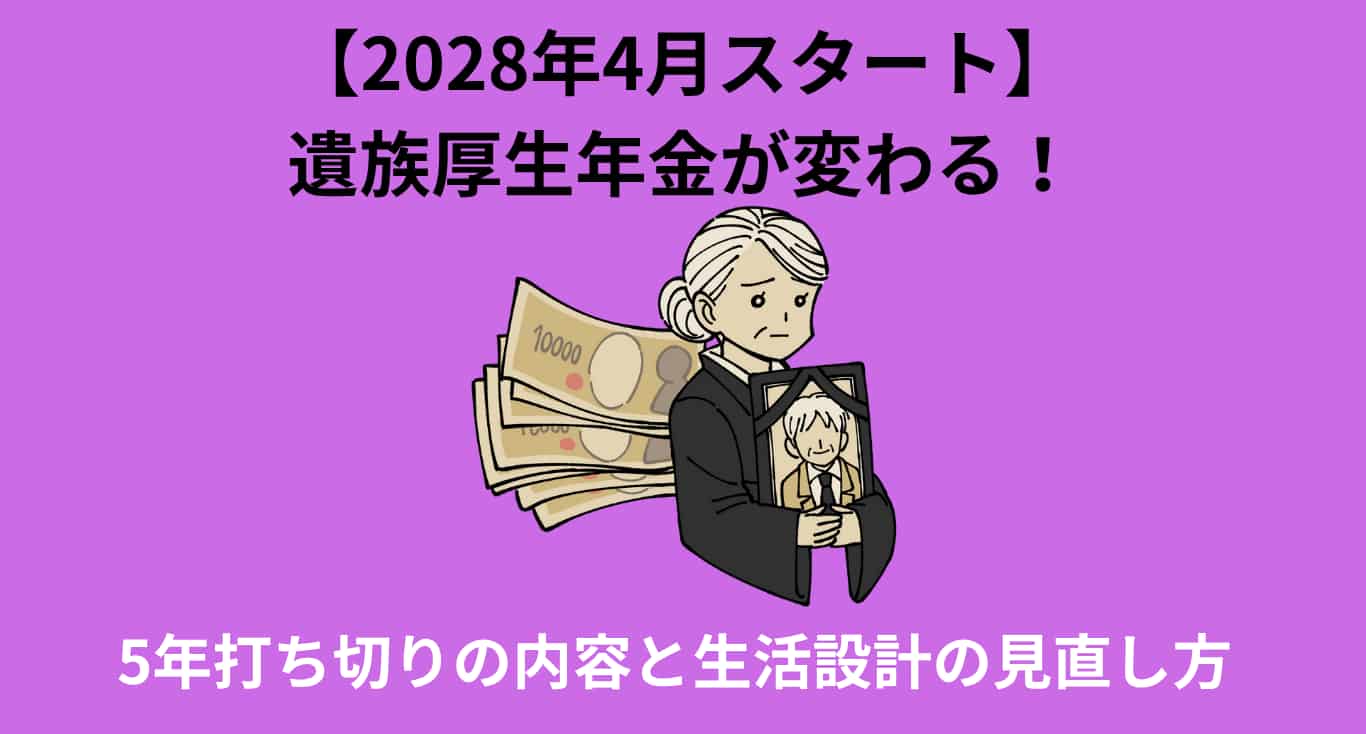
コメント