2024年度の国の税収が、ついに75兆円台に到達する見通しとなり、ニュースでも大きく取り上げられました。「そんなに税金が集まってるの?」「でもうちの生活は苦しいまま…」と思った方も多いのではないでしょうか。
今回のブログでは、なぜ税収がここまで伸びたのか、その理由を日常生活の目線でわかりやすくひもときながら、増えた税金がどう使われるのか、そして私たちの暮らしにどんな影響があるのかを、一般市民の視点で考えてみたいと思います。
はじめに
税収が過去最高を更新した背景とは
2024年度の国の一般会計における税収が、ついに75兆円台に達する見通しとなりました。
これは前年度の約72兆円からさらに伸び、5年連続で過去最高を更新するという異例の事態です。
特に注目されたのが、物価の上昇や賃上げの動きが、消費全体の金額を押し上げ、結果的に消費税収を増やした点です。
たとえば、日用品や光熱費、外食費などの価格が上がったことで、私たちが支払う税金の総額も自然と増えたわけです。
さらに、大手企業を中心に好業績が続いたことで法人税収も増え、全体の税収を支える結果となりました。
国の財政における税収の重要性
税収は、国の「お財布」の中身ともいえる存在です。道路や学校、病院といったインフラの整備から、年金・医療などの社会保障、そして防衛や外交まで、あらゆる政策の財源は基本的に税金からまかなわれています。
今回のように税収が上振れた場合、赤字国債の発行を抑えることができるだけでなく、防衛費の増額といった新たな政策への資金投入も可能になります。
たとえば、2023年度の上振れ分では、国債の返済や防衛費の財源として活用されました。
つまり、税収が好調かどうかは、国の将来を左右するほどの影響力を持っているのです。
1.2024年度の税収実績とその特徴

一般会計税収が75兆円台に達した理由
2024年度の国の一般会計税収は、最終的に75兆円台になる見込みと報じられました。
これは、政府が当初の見込みとしていた約73兆4,350億円を大きく上回る数字です。
その理由としてまず挙げられるのが、「物価高」と「賃上げ」の影響です。
たとえば、食料品や日用品、交通費など生活に密着したモノやサービスの値段が上がると、必然的にそれにかかる消費税額も増加します。
一方で、企業側では2025年3月期決算において電機メーカーや小売・サービス業などが好業績を記録しました。企業の利益が大きくなると、それに比例して納める法人税も増えるため、税収全体を底上げする要因となりました。
これら複数の要素が重なり合い、結果として税収は過去最高に達したのです。
前年度からの増加額と比較
2023年度の税収は、最終的に約72兆761億円でしたので、今回の見通しでは約3兆円の増加となります。
たった1年でこれほどの伸びを見せたのは、異例とも言えます。
しかも、2023年度の税収も当初の見込みから2.5兆円ほど上振れていたため、2年連続で「想定以上」の税収が得られている状況です。
たとえば昨年の例で言えば、補正予算を組んだ後に企業の決算結果が好調だったため、最終的に法人税が大きく上振れしました。
今年も同様に、3月決算企業の業績が想定を上回ったため、5月分までに納付された法人税が反映され、全体の税収額が押し上げられたと見られています。
財務省による決算見込みの内容
財務省は、この税収実績をもとに「決算見込み」を近く発表するとしています。
これは、国の一年間の収入と支出のバランスを示すもので、いわば「家計簿」の決算報告のようなものです。
決算見込みでは、実際にいくらの税金が集まり、それがどのように使われたかが明らかになります。
税収の上振れが確認されれば、その分、赤字国債の発行を減らしたり、防衛費や子育て支援などの政策に回す余地が広がるため、今後の予算編成にも影響を及ぼします。
特に、物価高対策や財政健全化の議論が続く中で、この「税収の使い道」は大きな注目を集めることになるでしょう。
2.税収を押し上げた要因の分析

消費税収増加の背景にある物価高と消費動向
今回、税収が大きく増えた背景には、日常生活に直結する「物価高」の影響があります。
たとえば、スーパーでの食品の値上げ、電気代やガス代の上昇、外食やレジャー施設の料金アップなど、私たちが普段支払っているものすべてに「消費税」がかかっています。
価格が高くなるということは、それに比例して税額も増えるということです。
さらに、2024年度は春の労使交渉(いわゆる春闘)で多くの企業が賃上げを実施したこともあり、消費者の財布のひもが緩みました。
給料が増えたことで、外食や旅行、家電の買い替えなど消費活動が活発になったのです。
こうした“値上げ+消費の活性化”のダブル効果が、消費税収を押し上げる結果につながりました。
法人税収を支えた企業の好決算
もうひとつの大きな要因が、「法人税収の増加」です。特に2025年3月期決算で、電機業界やサービス業、小売業界などが好業績をあげたことが大きく影響しました。
たとえば、半導体需要の回復や円安による輸出増、インバウンド(訪日観光客)の回復により、業績を伸ばした企業が目立ちました。
こうした企業が多くの利益を出すと、その分、法人税として国に納める金額も増加します。
中でも東京証券取引所に上場する大企業の決算が軒並み堅調だったことから、法人税収全体が前年を上回った形となりました。これは、企業の成長と税収がいかに密接につながっているかを示す良い例です。
上場企業の業績と税収の関係
税収を押し上げた法人税の中でも、特に上場企業の動向が注目されます。上場企業は一般的に利益規模が大きく、納税額も桁違いです。
たとえば、トヨタやソニーといった製造業の大手はもちろん、ユニクロを展開するファーストリテイリングのような小売業も、利益の伸びが税収に大きく貢献します。
また、最近ではオンラインサービスやIT業界の一部企業でも成長が見られ、これまで以上に多様な業種が税収を支える構図になってきています。
こうした企業群の好業績が重なったことで、法人税全体の底上げが実現したのです。
このように、物価高による消費税の増収と、企業の好決算による法人税の増収という2つの要因が、2024年度の税収を過去最高に導いた大きな柱となっています。
3.過去との比較と今後の見通し

近年の税収推移と過去最高の更新
ここ数年の税収は、コロナ禍による一時的な落ち込みを経て、急回復を遂げています。
2020年度は感染拡大の影響で経済が停滞し、税収も大きく減少しましたが、2021年度以降は回復基調に入り、2023年度には72兆円超、そして2024年度にはついに75兆円台へと達する見込みです。
このような急伸の背景には、単なる景気回復だけでなく、物価の持続的な上昇や企業収益の拡大といった構造的な変化があります。
かつては「税収の伸び=経済の成長」と単純に捉えられがちでしたが、現在は価格上昇による“名目経済”の拡大が大きく関わっています。
つまり、私たちの暮らしの負担感が増す一方で、国の税収が伸びているという“ねじれ”が生まれているのです。
上振れ分の活用事例(国債・防衛費など)
税収が予想よりも多く集まった場合、その「上振れ分」はどのように使われるのでしょうか。
2023年度には約2.5兆円の上振れがありましたが、そのうち一部は赤字国債の発行抑制に使われました。
つまり、本来なら借金でまかなう予定だった費用を、実際には追加の税収でまかなえた、ということです。
また、残りの財源は防衛費の増額や社会保障費の補填にも活用されました。
たとえば、年々高まる防衛ニーズに応えるための自衛隊装備の更新費用や、物価上昇に伴う医療・介護サービスへの支出補填などが挙げられます。
税収の上振れがあればあるほど、将来の借金を減らすことができるだけでなく、国民の安心につながる分野に予算を回す余裕が生まれるのです。
今後の経済動向と税収への影響
とはいえ、今後も同じように税収が増え続けるとは限りません。
たとえば、物価上昇が行き過ぎて消費者の購買意欲が冷え込めば、消費税収はかえって減る可能性もあります。また、企業の業績も円安・円高、海外経済の影響などに左右されやすく、特に輸出型企業では収益がブレやすいのが実情です。
さらに、2025年度以降は高齢化の加速や少子化の影響で、労働人口の減少が懸念されています。
働く人が減れば、所得税や法人税の伸びも抑えられるかもしれません。
国としては、こうした変化を見据えながら、景気の腰折れを防ぐ経済対策と、持続的な税収確保のバランスを取っていく必要があります。
今後の税収を見通すには、経済の成長だけでなく、消費者の心理、企業の収益、そして物価や賃金の動向など、複合的な要因を丁寧に見極めていくことが求められます。
4.消費税の逆進性と見直しの必要性
消費税は本当に“公平”な税なのでしょうか
消費税は、物を買うたびに一律で課される税金です。そのため「みんなが同じように払っている」と思われがちですが、実は収入の少ない人ほど負担が重い、いわゆる“逆進性”のある税金なのです。
たとえば、年収100万円の人が生活費として年間90万円を使えば、その大半に消費税がかかります。
つまりほぼすべての収入に税金がかかっているようなものです。一方で、年収1,000万円の人が同じ90万円を使っても、残り910万円は非課税です。これでは、所得に対する税負担のバランスが大きく崩れてしまいます。
「消費税は公平」だと言われる一方で、生きていくために不可欠な支出にまで課税されている現実は、やはり不公平と言わざるを得ません。
物価高の中で生活必需品に税がかかる不条理
最近は、食料品や日用品、光熱費など、私たちが暮らしの中でどうしても必要とするものの価格が上がり続けています。そのうえ消費税までかかってくると、「買うたびにじわじわと効いてくる…」という感覚、ありませんか?
しかも、収入がなかなか上がらない中で物価だけが上がっている今のような状況では、消費税の負担がより重く感じられるのは当然です。
一部では「高所得者のほうが消費額が多いから減税しても得をするのはお金持ちだけ」といった意見もありますが、それは金額ベースの話。低所得の家庭にとっては、数千円でも生活のゆとりに直結する重要な支援です。
消費税の減税・廃止という選択肢
このように考えると、今こそ消費税の在り方そのものを見直す時期ではないでしょうか。
たとえば、
- 消費税を5%程度に一時的に引き下げる
- 食品や生活必需品だけでも非課税にする
- いっそのこと、消費税を廃止して別の税収構造を検討する
といった方法も、現実的に議論されるべきだと思います。私たちの毎日の暮らしが苦しいときにこそ、「消費すればするほど苦しくなる税制度」は、見直されるべきではないでしょうか。
財源は「どこから取るか」ではなく「誰がどれだけ負担すべきか」
よく言われるのが「じゃあ減税したら財源はどうするの?」という声。でも、本当に今のままの税の取り方が“最適”でしょうか?
たとえば、
- 巨額の内部留保を抱える大企業
- 株式や金融商品で得た高額所得に対する優遇税制
- 防衛費や大型公共事業の見直し
こういった分野にこそ、見直す余地があると思います。家計が苦しい人たちからまず取るのではなく、余裕のあるところから適正に負担してもらう仕組みこそ、今の時代にふさわしいのではないでしょうか。
※この「第4章」は、これまでの分析・データを踏まえた「生活者の声」や提言として、まとめ記事の前に差し込むことで自然につながります。ご希望に応じて、見出しや段落の調整も対応可能です。
5.高所得者への課税と「出ていく論」の真実
富裕層を増税すると海外に逃げてしまうのか?
消費税の見直しを求める声が上がる一方で、「高所得者にもっと税金を」と言うと必ず出てくるのが、「じゃあお金持ちは日本から出ていくよ」という意見です。でも、本当にそうなのでしょうか?
たしかに一部の人は海外移住を検討するかもしれません。しかし、実際に行動に移す人はごく一部にとどまっています。なぜなら、
- 家族の生活や子どもの教育環境
- 日本の医療・治安・インフラの良さ
- 日本で築いたビジネスや人脈
…こうした要素を手放してまで国外に移るというのは、思っているほど簡単ではないからです。つまり、「出ていくから増税できない」というのは、少し大げさに語られている印象もあります。
世界の富裕層課税の実情
実は、日本だけが高所得者に厳しいわけではありません。むしろ、欧米の先進国では日本より厳しい課税が当たり前になっています。
たとえば…
- アメリカでは、年収6,000万円以上の人に連邦税だけで約37%
- イギリスやドイツ、フランスでは、年収2,000万円超で45%程度の所得税
- スウェーデンに至っては、50%を超える国民も多くいます
日本では、所得税が最大45%、住民税と合わせて55%が最高ですが、実際にそこに達する人は一部だけ。しかも、株の売却益や配当には約20%の一律税率が適用されていて、働いて得た収入よりも税負担が軽くなるという、逆転現象も起きています。
まず、世界の主要国では、高所得者に対する「累進課税」(収入が多いほど税率が高くなる仕組み)が常識です。
| 国名 | 所得税の最高税率(概算) | 適用の所得帯域(目安) |
|---|---|---|
| 日本 | 45% + 住民税10% | 約4,000万円超〜 |
| アメリカ | 約37%(連邦税のみ) | 約6,000万円超〜 |
| イギリス | 45% | 約2,000万円超〜 |
| フランス | 45% | 約2,000万円超〜 |
| ドイツ | 約45% | 約3,000万円超〜 |
| スウェーデン | 約52% | 約1,000万円超〜 |
※各国によって課税方式(地方税含むか、控除の計算など)が違うため単純比較はできませんが、日本の税率は国際的に見ても特別に高いわけではありません。
「取りやすいところから取る」ではなく「適正に負担する社会」へ
日本の税制は、「働く人」には厳しく、「資産を持つ人」には優しいという構造になっています。これでは、真面目に働く人が損をしているように感じてしまいますよね…。
高所得者や大企業が、きちんとその力に応じた負担をすることで、
- 生活に苦しむ人の支援
- 教育・医療・介護などの社会保障
- 子育て家庭への手厚い政策
こうしたことにも予算が回せるようになります。
「お金持ちが逃げないように…」と気を使いすぎるよりも、みんなが「ここにいたい」と思える社会にするほうが、結果的に人も税も集まってくるのではないでしょうか。
まとめ
2024年度の国の一般会計税収が75兆円台に達するという見通しは、私たちの暮らしや企業活動、そして国の政策運営が密接につながっていることを改めて感じさせるニュースでした。
物価の上昇によって日常の買い物にかかる消費税が増えたこと、企業が好業績を上げて法人税が増えたこと、こうした要素が合わさって税収を押し上げたのです。
過去と比べても、ここ数年の税収の伸びは著しく、その使い道にも注目が集まります。
上振れた税収が国債の発行抑制や防衛費、社会保障に使われることで、国の財政を少しでも健全な方向に導く力になるのは確かです。
ただし、今後もこの調子で増収が続くかどうかは不透明です。
物価高による消費の冷え込みや、企業業績の変動、少子高齢化による労働力不足など、多くの課題が控えています。今後の税収を持続的に確保するためには、経済全体のバランスを見極めつつ、国民生活と国の成長を両立させる政策がますます求められるでしょう。
そして何よりも忘れてはならないのは、消費税が逆進的な性格を持つ税であるということです。
生きていくために必要な支出にまで課税される現状は、生活が苦しい人ほど負担が重くなってしまいます。
この不公平さを和らげるためにも、一時的な消費税の減税や、生活必需品の非課税化といった選択肢を真剣に考える必要があるのではないでしょうか。
同時に、高所得者や資産家に対する課税の在り方も見直すべき時期に来ています。
「出ていくから増税できない」ではなく、公平で納得感のある税制度こそが、人もお金も日本にとどめる力になると感じます。
いま求められているのは、「誰がどれだけ負担すべきか」という視点で、税のあり方を国民全体で見直していくこと。
日々の買い物のたびに感じる小さな不満や疑問こそが、社会を少しずつ動かすきっかけになると信じています。
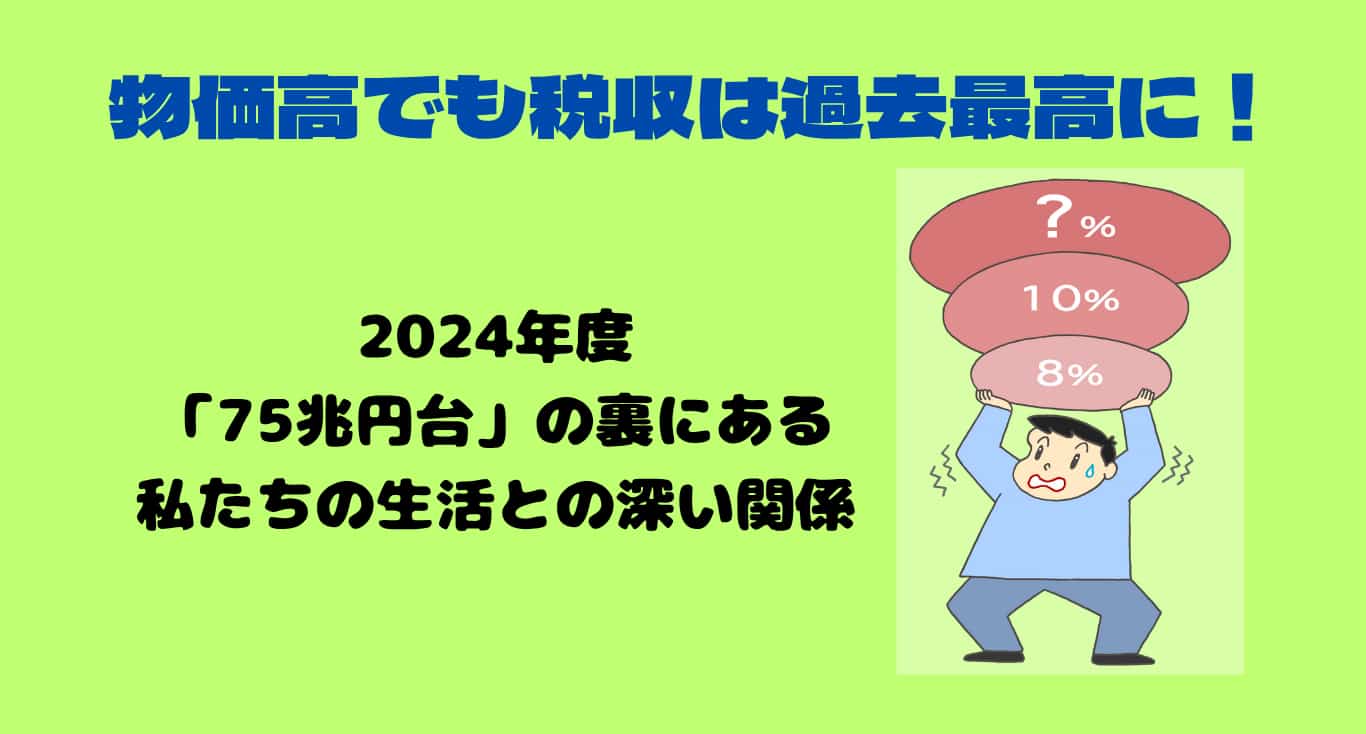
コメント